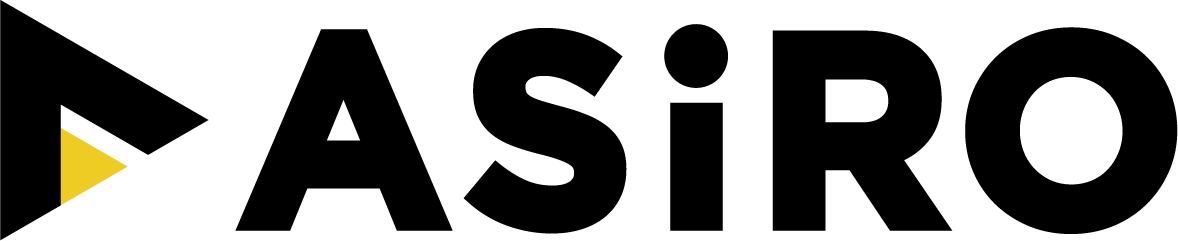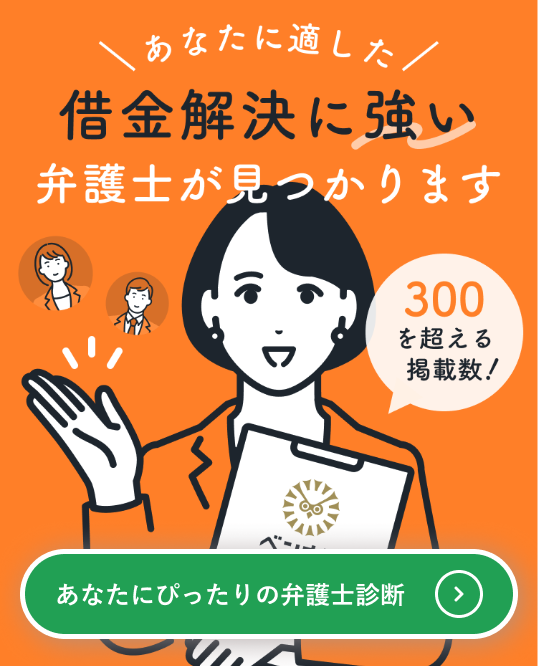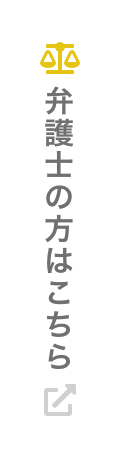消費者金融からの借入が長期間返済できていない場合、「この借金は時効で消えるのでは?」「時効までなんとかやり過ごせないかな?」と考える方も多いでしょう。
消費者金融などからの借金は、最後の返済日から5年が経過すると時効が成立する可能性があります。
しかし、時効が成立するには厳密な条件があり、ただ放置しているだけでは借金が消えることはありません。
また、借金の時効が成立する条件が整っていたとしても、誤った対応をすると時効がリセットされ、返済義務が継続してしまうリスクもあります。
本記事では、消費者金融の借金が時効で消滅するための具体的な条件や、時効を目指すうえで注意すべきポイントを詳しく解説します。
時効を狙って借金を放置するリスクや、時効となる前に借金問題を解決できる手続きである「債務整理」についても簡単に紹介します。
返済に追われる日々から解放されるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
消費者金融からの借金の消滅時効は5年
アコムやプロミス、アイフルなどの消費者金融からの借金は、民法第166条に基づいて、最後に返済した日から5年間が経過すると消滅時効が成立します。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
なお、お金の貸し借りがあった場合では、債権者は当然お金を回収する権利があることを知っているといえます。
そのため、借入先にかかわらず基本的に民法166条の1項が該当し、最後の返済期日から5年間で借金は消滅時効となります。
まずは、借金に関する消滅時効という考え方や、借金の時効が成立する詳しい条件について見ていきましょう。
時効とは?成立させるための条件
消滅時効とは、一定の期間にわたって権利が行使されない場合に、その権利自体を消滅させる仕組みのことです。
基本的に、消費者金融などのお金を貸している側は、契約に基づいて「お金を回収する権利(債権)」を持っていますが、「権利をいつまでも行使しない者は法律上保護する必要はない」という考えから、債権は5年間で消滅時効が成立することになっています。
ただし、5年間という期間はあくまで消滅時効の条件のうちの一つです。
実際に借金の消滅時効を成立させて返済義務から逃れるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 借金の最終返済日から5年間が経過する
- 時効が更新・中断される事由が存在しない
- 消滅時効の成立を債権者に対して主張する(時効援用)
5年間が経過すれば自動で消滅時効が成立するわけではない点に注意が必要です。
時効の起算日は最終返済日
起算日とは、借金の消滅時効までのカウントが開始する日を指します。
そして、消費者金融の消滅時効の起算日は、最終返済日です。
最終返済日とは、基本的に「支払いを怠った最後の返済期日」を指し、滞納後に支払いをおこなったことがある場合は「最後に返済をした日」となります。
民法の改正と借金の時効について
2020年4月の民法改正以前は、借金が時効となるまでの期間が、借入先によって異なっていました。
信用組合や信用金庫などの営利目的でない団体から借りた場合は10年間、銀行や消費者金融などから借りた場合は5年間などと細かく決められていたのです。
なお、現在残っている借金についても、2020年3月以前の契約については、改正前の民法が適用されるため、借入先によって時効期間が異なります。
一方、2020年4月以降の契約については、借入先にかかわらず時効までの期間が5年間に統一されているので注意しましょう。
消費者金融からの借金の時効を成立させる方法
消費者金融からの借金は、最後の返済日から5年間が経過すれば消滅時効が成立する可能性があります。
しかし、何もせず放置していただけでは時効は成立しません。
消費者金融からの借金の時効を成立させるためには、以下の2つの手続きを踏む必要があります。
- まずは時効期間が経過し、時効が完成しているか確認
- 消費者金融に対して時効の援用を主張する
それぞれについて、具体的に解説します。
1.まずは時効期間が経過し、時効が完成しているか確認
消費者金融の借金が時効で消滅するためには、消滅時効期間が経過している必要があります。
消費者金融からの借金の場合、原則として最後に返済した日、または最終的な返済の督促があった日から5年が経過していることが時効の条件です。
しかし、単に5年が経過しただけで時効が自動的に成立するわけではありません。
時効までの5年間のあいだに、債権者からの催告書が届いたり、電話で借金返済に関する相談などがあったりした場合は、それが時効期間のリセットにつながる可能性があります。
一度でも借入先から催促されている場合は、時効期間がリセットされている可能性があるので注意しましょう。
また、時効が成立しているかを確認するには、時効の起算点がいつなのかを返済履歴などの書類をもとに正確に把握することが重要です。
不明な点がある場合は、弁護士などに相談することで正確な状況を把握しましょう。
2.消費者金融に対して時効の援用を主張する
時効期間が経過していたとしても、それを債権者に正式に伝えなければ時効は成立しません。
「借金が時効を迎えたのでもう返済しません」と、債権者に対して時効を主張する行為を「時効の援用」と呼びます。
時効援用をするには、単に電話やメールなどで伝えるだけでは不十分で、債権者に対して書面で通知することが必要です。
時効援用の通知には、内容証明郵便を用いるのが一般的です。
内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を記録できる郵便方法で、裁判における証拠としても使用できます。
内容証明郵便で時効援用をすることにより、消費者金融側に通知を送った事実と内容を正式な証拠として残すことが可能です。
時効援用を通知する文書には、法律で決まった形式などはありませんが、基本的には「消滅時効が完成しているため、今後一切の支払い義務はない」という旨を明記し、契約番号や債務の金額など、時効成立のために必要な内容を盛り込む必要があります。
不適切な表現や記載漏れがあると、時効の援用が認められないケースもあるため、事前に専門家へ相談しながら進めるのが安心です。
消費者金融の時効が更新・猶予されてしまう4つのケース
通常、消費者金融からの借金は最終返済日から5年間が経過すれば消滅時効が成立します。
しかし、以下のいずれかのケースに当てはまる場合は、時効までのカウントが更新・猶予されてしまい、5年間では時効が成立しない可能性があります。
- 少額でも弁済した場合
- 返済の意思を示す行動をした場合
- 消費者金融から支払いを督促された場合
- 消費者金融から裁判を起こされた場合
それぞれ、時効が更新されてしまう根拠や、具体的にどのような行動が当てはまるのかなどを紹介します。
1.少額でも弁済した場合
消費者金融の借金が時効になるためには、債務者が借金自体を「認めない」ことが重要です。
借金を一部でも返済をすると、債務の存在を認めたこととみなされ、時効が中断される要因となります。
たとえ1円であっても、滞納分を支払ってしまうと、その時点で時効までのカウントがリセットされ、返済した日から新たに5年間の経過を待つ必要があるのです。
「一時的に支払っておけば安心だろう」と考えたり、「消費者金融側に柔軟に対応してもらえるかもしれない」と期待したりして、少しだけ返済してしまうケースもありますが、時効を目指すうえではおすすめできません。
消費者金融は、借金回収のプロでもあるため、消滅時効が完成しそうな顧客に対して、少額でもいいから支払うように促してくる可能性もあります。
安易に督促に応じてしまうと、せっかく時効が成立しそうな場合でも、再度返済義務が発生するので注意しましょう。
時効が完成間近の場合や、すでに完成している可能性がある場合は、債権者からの督促には応じず、すぐに専門家に相談し、適切に行動することが重要です。
2.返済の意思を示す行動をした場合
借金に関して明確な返済の意思を示す行動をすると、時効が更新する可能性があります。
たとえば、消費者金融に対して「分割払いの計画を相談した」「支払い方法を問い合わせた」などの行為は、法律上「債務の承認」とみなされる可能性が高いです。
債務の承認が発生すると、それまで経過していた時効の期間はリセットされてしまいます。
時効の完成を目指している場合は、消費者金融からの連絡に対して返済の意思を示す前に、必ず専門家に相談しましょう。
3.消費者金融から支払いを督促された場合
消費者金融からの支払い督促も、時効の完成に影響を与える要因の一つです。
とくに、内容証明郵便で催告書が送付された場合や、裁判所を通じて支払い督促が送られた場合、6ヵ月間にわたって時効の完成が猶予されます。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
催告書などが届いていたことを忘れて時効援用をすると、時効が成立する条件が整っておらず、時効援用が失敗してしまう可能性もあります。
そのため、時効援用をする前には債権者からの郵便物などを全て確認しておく必要があるでしょう。
4.消費者金融から裁判を起こされた場合
消費者金融から裁判を起こされた場合は、時効までのカウントが大幅に中断または猶予されます。
裁判が起こされた段階で時効の進行が止まり、裁判の判決が出るまでは借金の問題が解消されない状態になるのです。
さらに、裁判所で消費者金融側が勝訴した場合、判決によって新たに10年間の時効成立までの期間が設定されてしまいます。
この場合、時効を目指すのは絶望的といえるでしょう。
借金の滞納によって消費者金融側から裁判を起こされた場合、契約通りに返済をしなかった債務者側に非があるので、基本的には消費者金融にとって有利な判決が下されます。
そのため、裁判所からの通知があった場合は、速やかに弁護士に相談して適切に対処しましょう。
消費者金融に対して時効の援用をする際の注意点
消費者金融に対して時効援用を検討している方は、以下の3点に注意してください。
- 時効が成立してもブラックリストに残る可能性がある
- 時効が成立した消費者金融は利用できなくなる可能性がある
- 失敗した場合のリスクが大きい
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
時効が成立してもブラックリストに残る可能性がある
時効の援用を成功させたとしても、信用情報機関に登録される「ブラックリスト」からすぐに名前が消えるわけではありません。
時効を目指して借金を長期間滞納している場合、ほとんどのケースでブラックリストに載っているはずです。
「時効援用によって借金の返済義務がなくなれば、同時にブラックリストも解消されるはず」と考える方も多いかもしれませんが、実情はそう甘くはありません。
時効援用をした場合、信用情報機関に「長期延滞」や「契約終了」として最長5年間事故情報が残るケースがあります。
つまり、時効援用をして返済義務から逃れられたとしても、5年間は新たなローンの申請やクレジットカードの発行が難しくなる可能性があるのです。
時効援用を検討している場合は、時効が成立したあとの生活にどのような影響があるかを事前に理解するのが重要だといえるでしょう。
また、信用情報がどのように扱われているかを確認するために、信用情報機関に開示請求して確認するのも有効です。
時効が成立した消費者金融は利用できなくなる可能性がある
時効援用をおこなうと、借金自体は法的に消滅しますが、その消費者金融のサービスを今後利用できなくなる可能性が高いです。
信用情報機関に記録されたブラックリストの情報は一定期間が立てば消滅しますが、時効援用をしたという事実は消費者金融の顧客情報には半永久的に残ります。
消費者金融側から見ると、時効援用をおこなった人は「信用できない顧客」とみなされるのが通常です。
そのため、時効が成立したあとに再び借り入れを希望しても審査に通らないケースがほとんどでしょう。
また、大手の消費者金融の場合、関連会社などでも顧客情報が共有されるため、グループ会社のカードやローンなども契約できなくなるリスクもあります。
失敗した場合のリスクが大きい
時効援用が失敗した場合、借金の返済義務がそのまま残るだけでなく、消費者金融が裁判を起こす可能性があります。
裁判で債務が認められると、時効期間がリセットされるだけでなく、法的な手段で返済を迫られることになります。
たとえば、給与や財産の差し押さえといった厳しい措置が取られるでしょう。
時効援用に一度失敗すると取り返しがつかない可能性が高いので、時効が本当に成立しているかどうかや、時効援用通知書の内容については入念な確認が必要です。
時効援用のリスクを避けるためには、弁護士へ依頼するのがおすすめ
時効援用を確実に成功させるには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。
弁護士は、時効成立の条件を的確に判断したうえで、法的効力を持つ時効援用通知書を作成してくれます。
そのため、手続きのミスや失敗のリスクを大幅に減らせるでしょう。
また、弁護士は借金問題解決のプロであるため、万が一時効が成立しない場合であっても、債務整理などの他の対処法を提案してくれます。
時効が成立している可能性がある場合には、自分で無理に時効援用をしようとせず、必ず弁護士に相談してください。
消費者金融の時効を成立させるのにかかる費用
消費者金融の時効を成立させるためには、時効援用の手続きが必要不可欠です。
時効援用手続きをおこなうには、自分自身で債権者に通知書を郵送する方法と、弁護士にまとめて依頼する方法の2つがあります。
それぞれの方法では、以下のような費用がかかります。
| 自分でおこなう場合 | 1,500円程度 |
| 弁護士へ依頼する場合 | 5万円~8万円程度 |
それぞれの費用の内訳について、詳しく見ていきましょう。
自分で手続きをおこなう場合
弁護士などの専門家に依頼せず、自分で時効援用の手続きをおこなう場合は、発生する費用は郵送料の1,500円程度だけで済みます。
自分で手続きをすれば、時効援用にかかる費用を大幅に抑えられますが、その分以下のようなリスクがあることを忘れてはいけません。
- 時効の起算日が正確に把握できておらず、時効援用が失敗する
- 時効の更新事由があったことに気付けず、時効援用が失敗する
時効援用が失敗した場合は、借金の返済義務がなくならないうえ、債権者から裁判を起こされるおそれもあります。
裁判になると、給与や銀行口座が差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。
弁護士へ依頼する場合
弁護士に時効援用を依頼する場合の費用相場は、5万円~8万円程度が一般的です。
弁護士に依頼すると、時効が成立しているかどうかを確実に判断してくれるため、安心感があります。
また、時効が成立していない場合でも、債務整理などの他の手段によって借金問題を解決する手助けをしてくれるでしょう。
弁護士事務所によっては、初回相談は無料で引き受けてくれるケースもあるため、まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
時効を成立させるため、消費者金融の借金を返済せずにいる4つのリスク
消費者金融からの借金は、最終返済日から5年が立てば時効が成立しますが、最初から時効を目指して滞納を続けることは大きなリスクが伴います。
消費者金融の借金を返済せずにいると生じるリスクは、以下のとおりです。
- 消費者金融から取り立てをされ続ける
- 遅延損害金が加算され借金が膨らむ
- 滞納期間が長引けば、ブラックリストに登録される
- 訴訟提起され、財産を差し押さえられる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1.消費者金融から取り立てをされ続ける
時効を目指して滞納を続ける場合、借金の時効が成立するまでの長期間にわたり、消費者金融からの取り立てが継続的におこなわれることとなります。
取り立ては、電話や郵便、場合によっては訪問などでおこなわれるケースもあり、精神的な負担が大きくなるでしょう。
取り立ての頻度が増えると、不安やストレスが積み重なることになり、日常生活に支障がでる可能性もあるでしょう。
加えて、滞納が長引き督促を無視し続けていると、実家や勤務先に連絡がいく可能性もあります。
「法的措置を取る」などの強い文言で取り立てを受けるケースも多いです。
取り立てを止めるには、基本的に借金を返済するしかありません。
時効が成立するまでの5年間にわたって督促を受け続けるのは大きな負担となるため、決しておすすめはできません。
2.遅延損害金が加算され借金が膨らむ
借金を返済せずに放置していると、借金の元金や利息に加えて遅延損害金が発生し、借金の総額が膨れ上がるリスクがあります。
遅延損害金とは、借金を約束通りに返済しなかったことによる延滞金のようなものです。
遅延損害金の利率は契約内容によって異なりますが、多くの場合は年利20%程度の高額な設定がされています。
そのため、長期間放置すると元金を大幅に超える負担になるケースもあるのです。
とくに、元々の借金額が大きい場合、遅延損害金によって返済額が膨大になり、返済がますます厳しくなる可能性があります。
3.滞納期間が長引けば、ブラックリストに登録される
借金を返済しないまま滞納期間が長引くと、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります。
一般的には、消費者金融からの借金を2ヵ月~3ヵ月程度滞納するとブラックリストに登録されてしまいます。
一度ブラックリストに登録されると、クレジットカードの新規発行やローンの審査が通らなくなり、日常生活や仕事に大きな制約を受けることになるでしょう。
また、滞納によってブラックリストに登録された場合は、基本的に滞納した借金を完済しない限りはブラックリストは解消されません。
仮に完済できたとしても「滞納した借金を完済してから5年間」は、ブラックリストに情報が残り続けてしまいます。
滞納によるブラックリスト入りは非常にリスクが大きいため、借金問題は放置せず、適切な対処を講じる必要があるといえるでしょう。
4.訴訟提起され、財産を差し押さえられる
消費者金融が時効成立前に裁判を起こすと、借金の返済を法的に求められることになり、財産を差し押さえられるリスクがあります。
裁判で消費者金融側が勝訴すると、給与や銀行預金、不動産といった財産に対して差し押さえ命令が出され、強制的に借金が回収されるのです。
さらに、裁判所の判決に基づき、10年間という新たな時効期間が開始されるため、時効成立も絶望的となります。
そのため、訴訟を提起される前に時効援用をするか、弁護士に相談して借金問題解決の方法を探ることが重要です。
消費者金融へ返済できないなら債務整理の検討を
消費者金融からの借金は、最終返済日から5年間が経過すれば消滅時効が成立します。
しかし、時効が成立するまでの長いあいだ、消費者金融からの取り立てを受け続けることになるほか、債権者側から裁判を起こされるなどのリスクがあるのも事実です。
返済できないからといってはじめから時効を狙うのはおすすめできません。
消費者金融への返済が難しい状況であれば、時効を狙うのではなく「債務整理」による解決を目指すのがおすすめです。
債務整理とは、法律の力を使って合法的に借金を減額・免除してもらう手続きであり、弁護士などの専門家に相談すればスムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、誰でも利用できる債務整理の手続き内容や効果について見ていきましょう。
債務整理の3つの方法
債務整理には大きく分けて、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。
それぞれの主な特徴は、以下のとおりです。
| 債務整理の方法 | 概要 |
| 任意整理 | 消費者金融と直接交渉し、借金にかかる利息や遅延損害金をカットしてもらい、現実的に返済可能になるように返済期間を調整してもらう |
| 個人再生 | 裁判所に申し立てて、借金の総額に応じて最大で10分の1にまで借金を減額してもらう |
| 自己破産 | 裁判所に申し立てて、ほぼ全ての借金の返済義務を帳消しにしてもらう |
自己破産は、消費者金融からの借金やカード会社のリボ払い残高などを全てゼロにできます。
しかし、不動産や自動車など一定以上の価値がある財産は、借金の返済にあてられるため、没収されてしまいます。
一方で、任意整理は財産を失ったり、保証人に迷惑がかかったりするリスクを最小限に抑えられます。
手続きも簡易的である代わりに、自己破産や個人再生と比較すると借金の減額幅が小さく、場合によっては問題解決に繋がらない可能性もあります。
債務整理をするなら専門家に相談がおすすめ
債務整理を検討している場合は、まずは弁護士などの専門家に相談しましょう。
債務整理には3つの手続きが含まれますが、手続きごとに借金の減額効果に差があり、メリット・デメリットも大きく異なります。
借金問題を根本から解決するためには、自分の借金の内容や生活実態に合った手続きを選択することが大切です。
その点、債務整理の実績が豊富な弁護士などの専門家に相談すれば、自分の状況に最適な解決法を提案してくれるでしょう。
初回の相談は無料で引き受けてくれる事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
さいごに|消費者金融に対して時効の援用をするなら専門家へ相談を
本記事では、消費者金融の借金を時効にする方法や、時効にするうえでの注意点などについて詳しく解説しました。
消費者金融からの借金は最終返済日から5年間で時効となりますが、時効までの期間には注意しなければならないことがたくさんあります。
また、消滅時効の成立条件が整っていない状態で時効援用をすると、借金の返済義務がなくならないどころか、債権者から裁判を起こされるリスクもあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。
時効援用を検討している場合は必ず弁護士などの専門家に相談し、失敗リスクを最小限に抑えてください。
必要に応じて、債務整理などのほかの借金解決方法も検討すべきでしょう。
なお、ベンナビ債務整理では、時効援用をはじめとした借金問題解決の実績が豊富な弁護士事務所を多数掲載しています。
「初回相談無料」「分割払い対応可能」など好みの条件で弁護士を探せるため、ぜひご活用ください。