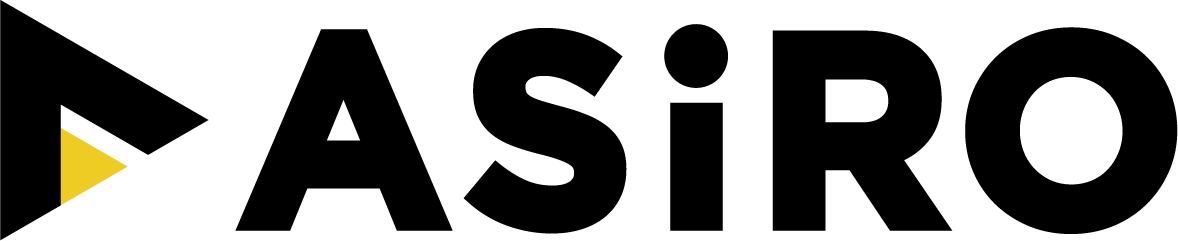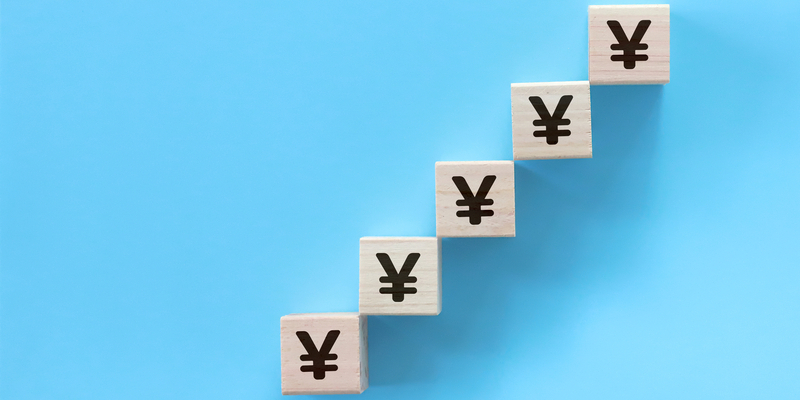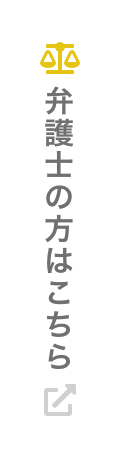- 「自己破産は借金いくらからできる?」
- 「自己破産をするための条件は?」
- 「自己破産をしたほうがよいのはどんな人?」
借金で悩んでいる場合、一度は自己破産について考えたことがある方は多いかもしれません。
しかし、借金額が少ない人の中には「いくらから自己破産できるの?」という疑問を感じる方もいるでしょう。
実は、自己破産をするにはいくつかクリアしなければならない条件が存在します。
そこで本記事では、自己破産はいくらからできるのかを解説するとともに、自己破産の条件や判断基準についても紹介します。
あわせて、自己破産にかかる費用なども説明するので、借金に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
自己破産は借金いくらからできる?
自己破産を検討している場合、いくらからの借金が対象なのか疑問に思う方もいるでしょう。
ここでは、自己破産ができる借金額や、平均負債額について紹介します。
自己破産に借金額は関係ない
結論からお伝えすると、自己破産をする際の借金額に「いくらから」という基準はありません。
そのため、借金が少額でも手続き可能です。
ただし、自己破産の判断基準として支払い不能であることが条件となります。
たとえば、100万円に満たない借金があった場合、生活保護受給者であれば支払い不能と認められるため条件に該当する可能性が高いです。
一方で、500万円の借金を抱えていても、それを支払えるほどの収入がある、もしくは多額の財産や未受領の遺産などがある場合は、自己破産が認められないケースもあるでしょう。
自己破産者の平均負債額は約1,450万円|100万円未満の人も増えている
2020年度の調査では、自己破産者の平均負債額は約1,450万円となっており、年々減少傾向にあります。
近年では、100万円未満の負債額で自己破産をするケースも増えており、負債額が500万円以下の自己破産者の中では、女性が多い傾向にあります。
自己破産をした方はどのような負債を抱えていたかというと、消費者金融などの登録貸金業者が約半数、次いで保証会社やサービサーなどの保証系が多く、とくに銀行系の保証会社が約半数を占めています。
自己破産ができる条件
自己破産をするには、以下3つの条件をクリアする必要があります。
- 支払不能状態にあること
- 債務を抱えている原因が免責不許可事由にあたらないこと
- 抱えている債務が非免責債権でないこと
- ※厳密には、要件ではないですが、検討に必要になります。
現在の状況や借金の原因など、自身の状況が条件に該当するかチェックしてみてください。
1.支払不能状態にあること
ひとつ目の条件は、債務が支払い不能な状態にあることです。
支払い不能とは、借金を返済できる見込みがない状態のことで、全ての債権者に対して一時的ではなく継続的に借金の返済ができない状態を指します。
破産法に基づき、支払い不能かどうかを判断する際は以下の点が考慮されます。
- 債務の総額
- 債務の内容
- 債務者の収入と資産総額・資産内容
- 家族構成
- 生活状況
- 債務を負担するに至った理由
一般的には、現在の借入総額を3年以内に返済できるかどうかが目安となります。
そのため、債務総額が年収の3分の1以上の場合は支払い不能と認められやすいといえるでしょう。
2.債務を抱えている原因が免責不許可事由にあたらないこと
ふたつ目の条件は、債務の原因が免責不許可事由に該当しないことです。
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実のことを指し、借金の理由が免責不許可事由に当てはまる場合は自己破産が認められません。
なお、破産法第252条1項では免責不許可事由として以下が設けられています。
- 債権者を侵害する目的で財産を減少・隠匿した
- 浪費やギャンブルなどで著しく財産を減少させた
- 支払い不能でありながら債権者と信用取引をおこなった
- 裁判所に虚偽の申告や説明を拒否した
- 過去7年以内に免責を受けている
ただし、免責不許可事由があっても、同条2項の裁量免責によって裁判所の判断で許可される場合もあります。
そのため、自己破産が認められない事情があったとしても可能性はゼロではなく、手続きをおこなうことを検討する余地はあります。
3.抱えている債務が非免責債権でないこと
抱えている債務が非免責債権でないことも条件に挙げられます。
破産法第253条1項に定められている非免責債権とは、免責許可決定が出たとしても、その返済義務を免れることができない債務のことをいいます。
主な具体例は以下が非免責債権にあたります。
- 所得税や住民税などの税金
- 社会保険料
- 公共料金
- 養育費
- 損害賠償金や慰謝料
- 罰金
ただし、ほかに多額の借金を抱えている場合にはメリットもあり、借金が免責になれば非免責債権も支払いをしやすくなります。
なお、非免責債権のみを抱えている場合、自己破産をしても債務が残ってしまいます。
自己破産するのにいくらかかる?必要な費用の目安
自己破産では借金が全額免除になる一方で、手続きに伴った費用も必要です。
ここでは、自己破産手続きでかかる裁判所への費用や弁護士費用などを解説します。
裁判所に支払う費用はどのくらい?
自己破産の種類によって金額は異なりますが、裁判所へ支払う費用として約3万円~50万円程度が必要です。
金額は状況によって大きく変動するため、詳しくは司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
以下では、裁判所へ支払う費用の内訳や各手続きの相場について紹介します。
自己破産手続きの種類によって費用は大きく異なる
自己破産には3つの種類があり、それぞれで条件や費用も異なります。
なお、申立てをする裁判所ごとに運用が異なりますので、以下は一例です。
| 手続きの名称 | 概要 |
| 同時廃止 | 総資産が20万円以下、及び免責不許可事由がないという条件を満たした場合、 同時廃止事件として扱われます。 申立人の財産が少ないため、財産を売却したり債権者に分配する手続きはおこなわれません。 そのため、手続きを省略して、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了させます。 |
| 少額管財 | 総資産が20万円以上あるなど、同時廃止の条件に当てはまらない場合で、財産の種類が少ない・弁護士に依頼しているなどに該当する場合は、管財事件の1種である少額管財となります。 弁護士に依頼する必要はあるものの、通常管財よりも短期間で終えることができ、費用も安く済ませることができます。 |
| 通常管財 | 総資産が20万円以上あり、弁護士に依頼していない場合や裁判所が少額管財を扱っていない場合は、通常管財となります。東京地方裁判所などでは特定管財になります。 少額管財よりも複雑な手続きをおこなうため、時間や費用もかさんでしまうことでしょう。 通常管財では、財産の調査をしたり、売却してお金に換える役目の破産管財人へ支払う報酬が高額になるケースもあります。 |
自分の借金額や弁護士へ依頼しているかどうかに応じて、どの手続きが該当するのか確認しておきましょう。
裁判所に支払う費用の内訳
裁判所へ支払う費用の内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 概要 |
| 申立手数料 | 申立手数料は、自己破産を申し立てる際にかかる手数料のことです。 裁判所へ提出する破産申立書や免責申立書などに収入印紙を貼って収めます。 |
| 予納郵券代 | 予納郵券代は、自己破産をした旨を債権者になどに書面で知らせるための郵送料金のことです。 金額は裁判所によって異なり、債権者が多いほど金額も大きくなります。 |
| 官報公告費用 | 国が発行している官報という機関紙に、自己破産者の名前や住所などを掲載するための費用のことを指します。 自己破産をおこなうと、破産手続開始決定時と免責許可決定時に自分の情報が掲載されます。 |
| 引継予納金 | 破産管財人に支払う費用のことを引継予納金といい、少額管財事件・通常管財事件によって金額が異なります。 |
なお、自己破産手続きを弁護士などの専門家に依頼する場合は、依頼費用が別途発生します。
【自己破産の手続き別】裁判所に支払う費用の目安
ここでは、自己破産の手続き別に費用の目安を紹介します。
なお、裁判所によって金額が異なる場合もあるので、詳しくは近くの裁判所へ問い合わせてみましょう。
| 手続きの種類 | 自己破産費用の相場 |
| 同時廃止 | 申立手数料:1,500円 予納郵券代:3,000円~1万5,000円程度 官報公告費用:1万円~1万9,000円程度 引継予納金:0円 |
| 少額管財 | 申立手数料:1,500円 予納郵券代:3,000円~1万5,000円程度 官報公告費用:1万円~1万9,000円程度 引継予納金:20万円~ (地方では30万円からとしているところもあります。) |
| 通常管財 | 申立手数料:1,500円 予納郵券代:3,000円~1万5,000円程度 官報公告費用:1万円~1万9,000円程度 引継予納金:50万円~ |
自己破産にかかる弁護士費用の目安
自己破産は自分で進めることも可能ですが、膨大な書類を漏れなく収集するなど手続きが非常に複雑であり、かなりの労力を要します。
そのため、手続きをスムーズに進めるには、弁護士への依頼が得策です。
ここでは、弁護士に自己破産の手続きを代行してもらった場合、どれくらいの費用がかかるか目安を紹介します。
なお、費用設定は法律事務所によって異なるため、詳細は依頼を検討している法律事務所に問い合わせてみてください。
| 費用項目 | 相場 | 概要 |
| 相談料 | 5,000円~1万円(30分~1時間あたり) | 初回のみ無料相談をおこなっている事務所もあります。 |
| 着手金 | 20万円~30万円 | 依頼時に支払う費用で、最終的に自己破産できなくても返金はありません。 報酬金を高めに設定して着手金を安くしている事務所もあります。 |
| 報酬金 | 20万円~30万円 | 免責許可が決定した際に支払う費用です。 |
| 実費 | 1万円~5万円 | 交通費や切手代など、実際にかかった費用です。 |
| 日当 | 3万円~5万円/半日 | 裁判所へ出向いた場合など、事務所以外で弁護活動をした際にかかる費用です。 |
なお、上記を合計すると約50万円〜80万円程度の金額となります。
弁護士費用は分割払いができるケースも少なくない
弁護士への依頼は多くの費用がかかるため、すでに借金を抱えている方にとってはハードルが高く感じられるでしょう。
中には依頼を諦める方もいるかもしれませんが、必ずしも費用を一括で支払う必要はありません。
弁護士から債権者に受任通知が届くと返済がストップするため、毎月の返済に充てていたお金を申立てに回せるようになります。
その費用を弁護士費用の分割払いに充てれば支払いが楽になるため、費用が心配な場合は分割払いに対応している弁護士へ依頼しましょう。
費用がない場合は法テラスを利用
法テラスでは民事法律扶助制度として、経済的な理由で弁護士に相談できない方のために、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えをおこなっています。
各都道府県の県庁所在地を中心に全国110ヵ所に事務所があり、電話やメールでも相談が可能です。
ただし、法テラスを利用する際は一定の資力要件があり、収入や資産が一定額以下である必要があります。
ある程度の収入がある方は利用できない可能性が高い点に注意しましょう。
なお、生活保護受給者は裁判所に支払う予納金を立て替えてもらえたり、立て替えの支払いを免除してもらえたりすることもあります。
お金がないが自己破産をしたい方は、法テラスを検討してみてください。
ただし、法テラスを利用して自己破産を進める場合、原則として弁護士を自由に選べません。
そのため、依頼を検討している弁護士がいる場合は、法テラスと提携しているかを確認する必要があります。
提携事務所であれば、無料法律相談や弁護士費用の立て替えなどの制度を利用できる可能性があるため、法テラスの各地方事務所のホームページから確認しましょう。
自己破産をする3つのメリット
以下では、自己破産をする3つのメリットを紹介します。
借金が0円になる
自己破産をすると、全ての借金の返済義務がなくなります。
分割や利息をカットしてもらう任意整理や、借金の一部を返済して残りを免除してもらう個人再生とは違い、全ての借金の支払い義務がなくなるのは債務整理のなかで自己破産だけです。
早ければ申し立てから2ヵ月~3ヵ月で免責決定を得ることができ、借金のストレスから解放されます。
そのあとは一切の返済義務がなくなるため、人生を再スタートできる大きなきっかけとなるでしょう。
債権者からの取り立てや強制執行にあう心配がなくなる
自己破産をする方の中には、支払いが滞り債権者からの取り立てに悩んでいる人も多いでしょう。
取り立てだけではなく、裁判所の手続きを経て、強制的に銀行口座や給与が差し押さえとなる強制執行をされてしまう可能性もあります。
裁判所を通じておこなわれる強制執行は、債権者に与えられた権利であるため止めることはできません。
しかし、弁護士に自己破産の申し立て依頼をすると債権者に対して受任通知を送付するため、届いた時点で取り立てがストップします。
また、申立てをして、手続きが開始すると強制執行も止まります。
万が一、そのあとに取り立てなどの督促があった場合でも応じる必要はありません。
取り立てなどの精神的な負担から解放されるのも自己破産のメリットといえるでしょう。
手元に残せる財産もある
自己破産をすると、全ての財産を失ってしまうと認識している方は少なくないでしょう。
しかし、実際はそうでなく、生活に必要な財産は残すことが可能です。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 生活に必要な家具・寝具・衣類
- 生活に必要な食料や燃料
- 時価20万円以下の自動車
- 20万円以下の預貯金
- 99万円以下の現金
自己破産をする6つのデメリット
自己破産をすると、今後の生活にどのように影響するか気になるところです。
ここでは、自己破産によって生じる6つのデメリットを紹介します。
1.クレジットカードやローンを利用できなくなる
自己破産をすると、個人信用情報機関に事故情報として掲載されるため、クレジットカードやローンの契約、新規の借り入れなどが難しくなります。
しかし、事故情報は期間経過によって抹消されるため、免責決定から約5年~7年で事故情報は削除され、自己破産前と変わりなくカードやローンが利用できるようになります。
2.不動産などの高額な財産は処分される
自己破産をすると自宅や不動産などの高額な財産は債務の清算に充てられるため、換価や処分の対象となります。
生活に必要な財産を没収されることはありませんが、20万円を超える預貯金や99万円を超える現金などがある場合も、借金の返済に充てられる点を覚えておきましょう。
3.官報に掲載される
自己破産をすると、破産者の住所・氏名・事件番号が官報に掲載されます。
官報は国が発行する新聞のようなもので、法改正があった際の公示のほか、破産や相続に関する裁判所の公示内容が掲載され、行政機関の休日以外は毎日発行しています。
官報は主に士業や法律の専門家などが閲覧するため、一般の方が目にすることはほとんどありません。
しかし、万が一家族や知人などが見た場合は自己破産の事実を知られる可能性があるでしょう。
4.免責されない債務もある
自己破産をしても、以下のような債務は免責されません。
- 税金
- 罰金
- 損害賠償金
- 婚姻費用
- 養育費
自己破産では基本的に全ての債務が免除されますが、免責対象外の債務がある場合は注意が必要です。
5.一部の職業につけなくなる
自己破産の申し立てをして免責許可が決定されるまでの間、以下の職業に就くことを制限される場合があります。
- 弁護士などの士業
- 公証人など一部公務員
- 貸金業
- 古物商
- 警備員
- 保険の外交員
なお、職業に就くことができないだけで資格が剥奪されることはありません。
制限については免責許可が決定されると解除されるため、あくまで手続き期間中のみが対象となります。
6.保証人に迷惑がかかる
自己破産は自分だけの問題ではなく、保証人や連帯保証人にも多大な迷惑がかかります。
自己破産をすると保証人は弁済義務を負い、一括返済を求められることが一般的です。
なお、保証人が返済できない場合は、保証人が個人再生または自己破産を検討する可能性もあります。
つまり、保証人が身近な人物である場合は今後のことをしっかりと考えなければなりません。
それでも自己破産を選択すると決めた際は、保証人に事情を話したうえで状況を説明する必要があるでしょう。
借金問題を解決するための自己破産以外の方法
自己破産は借金をゼロにできる一方で、避けられないデメリットも存在します。
それらを踏まえて、自己破産以外の借金問題を解決する方法を紹介します。
任意整理|分割や利息分をカットしてもらって返済する
任意整理は、債権者と話し合いのうえで将来分の利息をカットしもらうなどして、借金を3年~5年をかけて分割で支払っていく方法です。
また、複数の借入元から借金がある場合は、どれを任意整理の対象にするか選択できます。
借金の減額幅は自己破産より少ないものの、裁判所を通さないこと、財産や保証人への影響がないことは大きなメリットです。
また、任意整理は官報に掲載されないため、周囲にバレるリスクも軽減されます。
しかし、任意整理も自己破産と同じように事故情報として処理されるため、ブラックリストへの掲載は避けられません。
自身の借金額を考慮しながら、分割で返済できそうな金額であれば任意整理を検討しましょう。
個人再生|借金を大幅に減額してもらい、返済する
個人再生は、裁判所に返済不能を申し立てて再生計画を認めてもらうことで、借金を5分の1~10分の1程度に減額できる方法です。
なお、減額後の借金は原則3年で返済することになります。
自己破産では家などの一定価値以上の財産が没収されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用することでローン返済中の家でも住み続けることができます。
個人再生も自己破産と同様、官報への掲載やブラックリストへの掲載は免れませんが、借金を大幅に減らせる点はメリットです。
自己破産をしたほうがよい人とは?
自己破産に適しているケースとして、以下が挙げられます。
- 返済の目途が立たない
- 支払い不能な状態
- 高額な財産を所持していない
収入に対して多重債務をするなど借り入れが多く、返済の目途がまったく立たない場合は自己破産が適しています。
また、借金がありながら定職に就くことができ、決まった収入がない場合も支払い不能と判断されることが多いため、自己破産に適しているでしょう。
自己破産をすると、借金を免除してもらう代わりに高額な財産を没収・処分されます。
その観点から、手放す財産がない、あるいは財産を没収されても問題ない方も自己破産に適しているといえるでしょう。
さいごに|自己破産はできるか?ベストなのか?弁護士に相談!
自己破産には「いくらから」という借金額の基準条件はありません。
そのため借金額にかかわらず、自己破産の手続きは可能です。
しかし、自己破産には借金額以外の条件があるほか、避けられないデメリットも存在します。
借金額によっては、自己破産ではなく任意整理や個人再生を選択する方法もあります。
現在の生活状況を鑑みて、どうしても返済の目途が立たない、支払い不能な場合は最終手段として自己破産を検討しましょう。
自己破産のメリットやデメリットを把握していても、なにがベストか自分だけでは判断できない場合は弁護士への相談がおすすめです。
また、費用が心配な方は法テラスの利用を視野に、自己破産を検討してみてください。