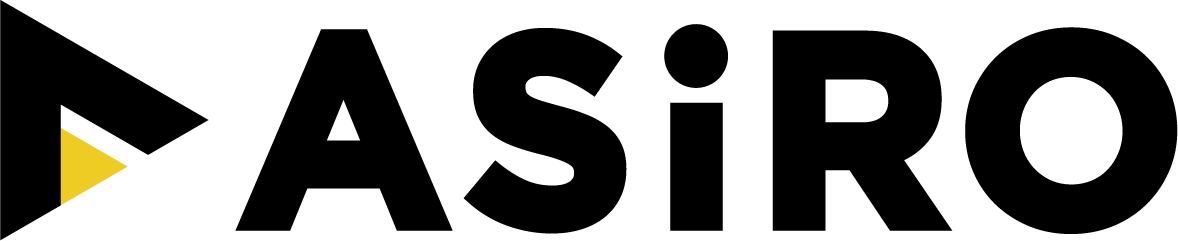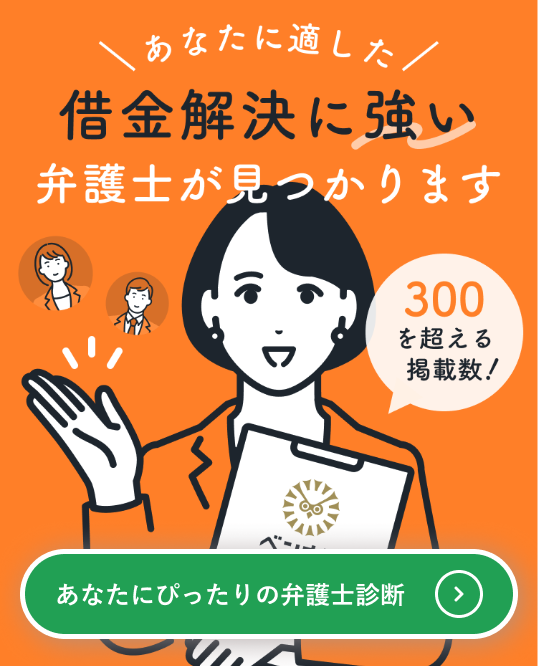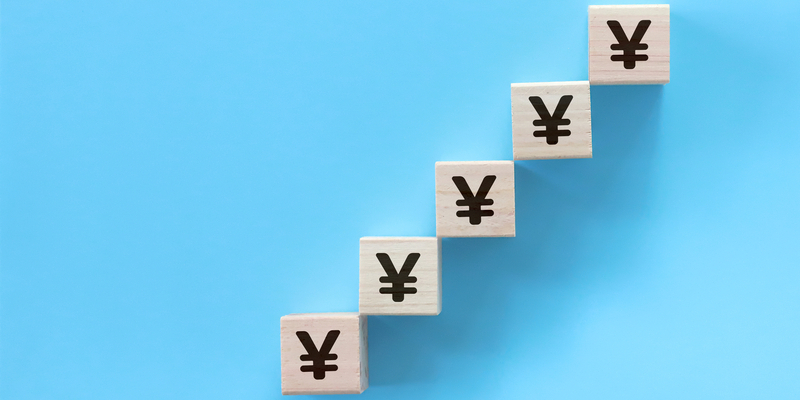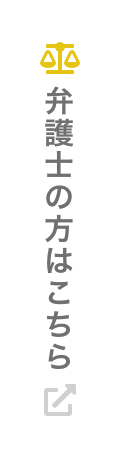多重債務や給料の減少などにより借金苦に困っている場合、自己破産は、その解決策になりえます。
自己破産とは、裁判所から「免責許可決定」を得ることで、債務(借金)の一切を免除できる債務整理の方法です。
自己破産により免責の許可を受けると、返済義務がなくなるため、取立てが止まったり、差押えが解除されたりするメリットが期待できます。
本記事では、借金苦で困っている方に向けて、自己破産のメリットについて解説します。
また、デメリットや自己破産後の影響などについても説明します。
自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わりに最低限の財産以外は手放すことになります。
借金問題を解決する方法には、自己破産以外にも、任意整理や個人再生などの方法があります。
もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。
自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。
- 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
- 面倒な手続きを一任できる
- 依頼した時点で、取立てが停止する など
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しております。
借金問題を解決したい方は、ぜひ下記よりご相談ください。
自己破産とは
自己破産とは、借金が返済できないときにおこなう債務整理の方法のひとつです。
自己破産は、裁判所に申立てをおこない、裁判所から免責が許可されることで成立します。
そして、免責が許可されると、税金や養育費、損害賠償金など一部を除いて、抱えている借金の返済義務がなくなります。
そのため、債務整理のなかでも、もっとも借金を減額できる方法とされています。
自己破産手続きの種類
自己破産の手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
また管財事件は、さらに管財事件(特定管財事件)と少額管財事件に分けられます。
それぞれの自己破産手続きの詳細は、以下のとおりです。
同時廃止事件
同時廃止事件とは、破産手続きの開始と同時に廃止の決定をする自己破産です。
破産管財人の選任や財産の換価処分などがおこなわれない簡易的な手続きであり、管財事件よりも短期間で終了できるメリットがあります。
裁判所に納める予納金(20万円程度)すら支払えないような破産者の場合、同時廃止事件が選択される可能性が高いです。
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第二百十六条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
特定管財事件
特定管財事件とは、破産手続きと同時に破産管財人が選任され、財産の調査や換価処分などがおこなわれる自己破産の手続きです。
同時廃止事件よりも手続きが複雑で多いため、免責決定までの期間は比較的長めとなっています。
換価処分できる財産がある場合や、ある程度の現金がある場合は、特定管財事件になる可能性が高いでしょう。
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第三十一条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 破産債権の届出をすべき期間
二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
少額管財事件
東京地方裁判所などでは、管財事件の例外として少額管財事件という手続きが設けられています。
少額管財は、通常の管財事件よりも簡略化された手続きであり、裁判所に納める予納金も低く設定されているのが特徴です。
なお、弁護士に自己破産の手続きを依頼している場合に限り、少額管財事件になる可能性があります。
自己破産のメリット
自己破産をすることで、次のようなメリットが期待できるでしょう。
- 全ての借金を返済する必要がなくなる
- 債権者からの取立てや強制執行がなくなる
- 生活に必要な最低限の財産は残せる
全ての借金を返済する必要がなくなる
自己破産は、申立人の債務(借金)の一切を免除する手続きです。
そのため、無事に裁判所に自己破産が認められれば、その後は債権者に対して借金や利息を支払う義務がなくなります。
任意整理や個人再生のような債務整理の方法では、手続き後に返済を続ける必要があるため、自己破産で返済義務が免除されることは大きなメリットといえます。
債権者からの取立てや強制執行がなくなる
借金の返済が滞ってしまった場合、債権者から厳しい取立てを受けたり、強制執行によって財産を差し押さえられたりする可能性があります。
そのような場合でも、債務者が裁判所に自己破産を申し立てると、正規の貸金業者は借金の取立てや強制執行ができなくなります。
また、裁判所によって借金の返済義務が免除されたあとは、債権者による取立ての一切がなくなります。
債権者からの厳しい取立てに困っている方にとって、自己破産はおすすめの債務整理です。
生活に必要な最低限の財産は残せる
自己破産をおこなったとしても、全ての財産が処分されるわけではありません。
生活に必要な最低限の財産については、裁判所が自由財産として認めるため、手元に残せるからです。
たとえば、以下の財産は、自己破産の際に換価・処分の対象になりません。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金
- 破産手続き開始後に得た給与などの財産
- 生活に必要な寝具・家具・衣服
- 生活に必要な食料・燃料
- 裁判所が自由財産として認めたその他の財産
借金が帳消しになるだけではなく、上記のような生活に必要な最低限の財産は手元に残しておける点は、大きなメリットであるといえるでしょう。
自己破産のデメリット
自己破産には「全ての借金を返済する必要がなくなる」などのメリットが期待できますが、その一方で以下のようなデメリットもあります。
- 特定の財産以外は手放すことになる
- 5年~7年はローンが組めなくなる
- ブラックリストに載る
- 官報に自己破産をしたことが掲載される
- 一部の職業制限・資格制限がある
- 保証人が一括返済を求められる
- 免責されない債務がある
自己破産は万能な解決策ではないので、デメリットについても正しく理解しておくことが大切です。
特定の財産以外は手放すことになる
自己破産は一切の借金が免除される代わりに、「自由財産」という特定の財産以外は手放さなければなりません。
自由財産には、新得財産(破産手続き後に取得した財産)、差押え禁止財産、99万円以下の現金などが含まれます。
自由財産に含まれない住宅や自動車といった財産は、自己破産の際に手放すことになるでしょう。
5年~7年はローンを組めなくなる
自己破産をすると、5年から7年ほどローンが組めなくなります。
なぜなら、個人信用情報機関に事故情報が登録されるからです。
このため、住宅ローンやカードローンなど、新たなローン契約を利用するための審査に通過できなくなります。
自己破産してから数年間は、ローンが組めなくなることに注意しましょう。
ブラックリストに載る
自己破産といった債務整理をおこなうと、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。
「ブラックリストに載る」という状態です。
ブラックリストに載ると、ローン契約やクレジットカードの新規発行などが難しくなります。
また、それ以外にも携帯端末の分割払いによる購入ができなくなるといった場合もあります。
ブラックリストに載ることで、日常生活に悪影響を及ぼすのです。
官報に自己破産をしたことが掲載される
自己破産をすると、国が発行する官報に名前や住所が掲載されます。
通常、官報に掲載されるタイミングは「破産手続開始後」と「破産手続き廃止及び免責許可決定後」の2回ですが、破産手続き廃止と免責許可の時期が異なる場合は、3回になることもあります。
ただし、官報は士業など法律の専門家などが見るものであるため、一般の方が日常的に目にする機会は少ないといえます。
しかし、仮に近所や職場に官報を読んでいる方がいる場合には、自己破産した事実が知られる可能性はあるでしょう。
一部の職業制限・資格制限がある自己破産の手続きをしている間は、資格制限によって一定期間仕事ができなくなります。
資格制限を受ける代表的な職業といえば、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、宅地建物取引士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの士業と呼ばれる職種です。
また、そのほかにも公証人や警備員、会社役員などが該当する場合もあります。
ただし、資格・職業制限は破産手続き中に限られ、その期間の目安は6ヵ月~1年程度です。
免責決定後に改めて登録手続きをすれば、その資格の仕事を再開できるでしょう。
保証人が一括返済を求められる
自己破産で債務が免除されるのは、破産者本人に限られます。
そのため、保証人や連帯保証人を付けて借金をしていた場合、保証人や連帯保証人に対して借金の取立てがおこなわれます。
借金の返済方法は、債権者によって異なりますが、基本的に保証人や連帯保証人の場合は「一括返済」であることが多いです。
自己破産することで、債務の保証人に対して迷惑をかけることになるでしょう。
免責されない債務がある
自己破産による免責が許可されたとしても、全ての借金が帳消しになるわけではありません。
借金の中には、免責されない債務もあるからです。
この債務のことを「非免責債権」と呼びます。
主には、行政機関に支払う借金がこれにあたります。
たとえば、以下のような債務については、免責を受けることができません。
- 税金
- 社会保険料
- 養育費
- 罰金 など
借金のなかにこのような債務がある場合には、自己破産をしたとしても、借金の返済義務は、残り続けることに注意する必要があります。
自己破産が認められる条件
自己破産は多くの人が選択できる債務整理の方法ですが、破産法によって定められている条件を満たしていない場合、自己破産の手続きをおこなえません。
また、借金の状況や弁護士の有無などにより、自己破産の種類も異なります。
ここでは、自己破産が認められる条件について確認しておきましょう。
支払いが不能であること
個人が自己破産をする場合、債務者が支払不能の状態でなければなりません。
支払不能とは「債務者が支払能力を欠いているため、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態」を指します(破産法第2条11項)。
要するに債務者の借金の返済額が収入や財産を上回り、客観的に見て「返済が続けられない」と判断できる状態をいいます。
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
免責不許可事由に該当していないこと
破産法第252条に規定されている免責不許可事由に該当する場合は、裁判所から自己破産の免責許可が得られない可能性があります。
代表的な免責不許可事由は、財産を隠している場合や浪費・ギャンブルで借金している場合、7年以内に一度、自己破産をしている場合などです。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
ただし、免責不許可事由に当てはまる場合でも、裁判所の裁量によって免責されることもあります。
免責不許可事由に心当たりがある場合でも、まずは弁護士に相談し、免責許可を得られるように目指すのがよいでしょう。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
非免責債権以外の借金があること
各種税金、国民健康保険料、国民年金保険料、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などは、免除されません。
そのため、自己破産をしても実質的に意味がないでしょう。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
自己破産を検討している借金がどのような性質の借金であるのか、今一度確認する必要があるといえます。
自己破産のメリットが享受できないケース
自己破産したくてもできずに、メリットを享受できない場合があります。
以下のいずれかに当てはまる方は、自己破産以外の債務整理の方法を検討する必要があるでしょう。
債務に対して返済能力がある
自己破産をおこなうためには、債務の金額があまりに大きく支払不能の状態であると、裁判所に認められる必要があります。
そのため、借金があるものの、支払いに充てる収入が十分である場合や、借金の金額自体が少額である場合には、返済能力があるとみなされる可能性があります。
債務に対して返済能力があるとみなされると、自己破産による免責が認められない場合があるのです。
制限を受ける仕事に就いている
自己破産手続きをおこなうことで、資格や職業に制限がある仕事に就いている場合は、自己破産の影響を受けることがあります。
たとえば、弁護士や司法書士、警備員、会社役員などの職種では、自己破産を申し立てることで一時的に、仕事を続けられなくなるでしょう。
ただし、手続きが終了すれば、再び働けるようになります。
そのため、自己破産の申立てをおこなう際には、そのリスクについて慎重に検討する必要があるといえます。
予納金が用意できない
予納金とは、自己破産を申し立てる際に裁判所に支払う費用です。
予納金の金額は自己破産の種類によって異なりますが、同時廃止事件の場合で、1万円〜3万円程度、管財事件の場合には、50万円以上になることがあります。
予納金を納付できない場合には、手続きを進めることができないため、自己破産を完了させることができません。
そのため、あらかじめ予納金を積み立てておく、または家族や友人から支援してもらうなどの対策を講じる必要があります。
自己破産後は人生にどのような影響があるのか
自己破産後の人生には、ポジティブな側面とネガティブな側面の両方の影響があります。
ポジティブな側面でいえば、借金の返済義務が免除されることで、返済に追われる生活から解放される点が挙げられます。
これにより、経済的な負担が軽減し、新しい人生をスタートさせるきっかけを得ることができます。
一方、ネガティブな側面でいえば、信用情報機関に事故情報が登録されることでローンやクレジットカードの利用が一定期間制限される点や、不動産や自動車などの財産が処分される点などが挙げられます。
ただし、生活していくための最低限の財産は保証されるため、人生が終わるわけではありません。
自己破産という言葉にはマイナスのイメージが伴いますが、新生活をスタートさせるための重要な手続きとなるでしょう。
自己破産すると家族にはどのような影響があるのか
自己破産すると、家族に特別なデメリットがあるのではないかと気になる方もいるでしょう。
ここでは、本人が自己破産した場合に、家族にどのような影響があるのかみていきます。
家族の生活への影響はほとんどない
自己破産しても、基本的に家族の生活への影響はほとんどないといえます。
なぜなら、自己破産は、債務者本人の借金を解決するための方法だからです。
したがって、債務者ではない家族には、ほとんど影響はありません。
ただし、家族が自己破産をおこなう債務の保証人になっている場合には、返済義務が引き継がれることになります。
また、不動産など家族と共同名義で共有している財産については、処分の対象になるため、家族の生活環境に影響を与える可能性があります。
このような場合には、自己破産以外の債務整理の方法を検討することが有効です。
家族の信用情報に影響を与えない
自己破産をすると、破産者本人は個人信用情報に登録されますが、破産者本人の家族まで登録されることはありません。
そのため、家族の信用情報に傷はつきません。
したがって、引き続き、家族名義でローンを組んだり、クレジットカードを申し込むことは可能です。
ただし、審査の際に家族の事故情報について確認されることはあります。
その結果、ローンやクレジットカードの審査で不利になる可能性はゼロではありません。
自己破産手続きをおこなう際の流れ
では、自己破産の手続きをおこなう際の具体的な流れについてみていきましょう。
自己破産には、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件という3つの種類がありますが、いずれの場合も手続きに大きな差はありません。
裁判所に自己破産を申し立てるまでの手続きは、おおむね次のように進行します。
- 弁護士に相談・依頼する
- 弁護士が債権者に受任通知を送付する
- 債務者の借金の状況を調査する
- 申立てに必要な書類を用意する
- 裁判所に破産手続きを申し立てる
そして、裁判所に自己破産を申し立てたあとの対応は、自己破産の申立てが管財事件になるか、同時廃止事件になるかで大きく変わります。
それぞれの場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
管財事件の流れ
管財事件または少額管財事件の場合は、破産管財人の選任からはじまり、破産手続きの終結決定または破産手続き廃止の決定が出ることで、借金が免除されます。
具体的な流れは、以下のとおりです。
- 破産管財人と面談する
- 財産の売却や処分をおこなう
- 債権者集会が開催される
- 財産が分配される
- 借金が免除される
はじめに、破産管財人と面談し、財産や借金に関する聞き取り調査がおこなわれます。
続いて、生活に最低限必要な財産を除く財産が、破産管財人によって売却・処分されます。
そして、債権者集会が開かれて、破産管財人が財産の状況や処分の結果を報告します。
また、このときに現金化した資金がどのように分配されるのかについても報告されます。
債権者集会が終わると、実際に債権者に資金が分配されます。
その後、残った残債について、借金が免除されるという流れです。
同時廃止事件の流れ
同時廃止事件の場合には、破産管財人の選任はおこなわれません。
その代わりに免責審尋に移行し、免責許可が下りることで、自己破産の手続きが完了します。
具体的な流れは、以下のとおりです。
- 免責審尋がおこなわれる
- 免責許可が決定される
まず、裁判所で破産者本人に対して、審尋がおこなわれます。
審尋では、氏名や住所などの基本事項の確認から、申立て内容に相違がないか、免責不許可事由がないのかなどが確認されます。
そして、審尋の内容に問題がなければ、裁判所が免責許可の決定を出します。
これにより、借金の返済義務が免除されます。
自己破産にかかる費用
自己破産をする場合、裁判所に対して一定の手続き費用を支払う必要があります。
また、弁護士に依頼する場合には別途、弁護士費用を支払わなければなりません。
ここでは、自己破産をするのに必要な費用を確認しましょう。
裁判所に支払う手続き費用
裁判所には、申立手数料、予納郵便代、官報公告費用、予納金を支払う必要があります。
これらの金額は、同時廃止・特定管財・少額管財で異なります。
ここでは「東京地方裁判所立川支部」を参考に、それぞれの目安額をまとめておきます。
| 同時廃止事件 | 特定管財事件 | 少額管財事件 | |
|---|---|---|---|
| 申立手数料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 予納郵便代 | 本人:4,210円(代理人:3,630円) | 3,630円 | 3,630円 |
| 官報公告費用 | 11,859円 | 50万円~ | 18,543円 |
| 予納金 | 不要 | 20万円~ | |
| 合計 | 17,569円 | 50万5,130円~ | 22万3,673円~ |
弁護士に依頼した場合の費用の目安
弁護士に相談・依頼する場合、相談料、着手金、報酬金などを支払う必要があります。
これらの費用は各法律事務所によって異なるため、ここでは「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」などを参考に目安額を紹介します。
なお、正式な契約をする前には、必ず弁護士に「費用がいくら必要になるのか」を確認しておきましょう。
相談料
弁護士と正式な契約をする前には、相談料(法律相談料)を支払って相談することになります。
相談料は、30分あたり5,000〜1万円程度が相場です。
ただし、借金問題や債務整理に関する相談の場合は、無料で受け付けている法律事務所も多くあります。
できる限り出費を減らすためにも、無料相談を利用することをおすすめします。
【関連記事】自己破産を弁護士に無料相談できる窓口4選|相談の流れや弁護士の選び方も解説
着手金
弁護士に債務整理の手続きを正式に依頼する場合、契約するタイミングで着手金を支払うことになります。
この着手金は、自己破産の成否に関係なく、弁護士に支払います。
なお、自己破産の着手金は20万円以上が相場となっています。
ただし、分割払い・後払いに対応してくれることもあるので、事前に弁護士に相談するとよいでしょう。
報奨金
無事に裁判所から自己破産が許可された場合、弁護士に対して報酬金を支払うことになります。
この報酬金は、免除できた金額に応じて支払うのが一般的です。
法律事務所によって報酬金の計算方法は異なりますので、正式な契約をする前に報酬金の有無や計算方法などについて確認しておきましょう。
自己破産の解決を弁護士に相談・依頼するメリット
日本弁護士連合会の「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査(破産事件記録調査)」によると、調査対象の自己破産者のうち90%以上に弁護士が関与しています。
この数字からも多くの方が弁護士に依頼していることがわかります。
自己破産の手続きは破産者本人もできますが、弁護士に依頼することで、次のようなメリットを享受できます。
- 自身の状況に適した解決策を知れる
- 依頼した時点で債権者からの取立てが停止する
- 書類作成・破産手続きを代行してもらえる
- 免責許可が下りる可能性が高まる
- 少額管財事件が利用できる場合がある
弁護士に相談・依頼することで、自己破産が債務整理の方法として適しているのかという判断から、免責許可を得るための手続き完了まで、全面的なサポートを受けることができます。
自己破産を検討している方は、早めに弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
自己破産に関するよくある質問
最後に、自己破産に関するよくある質問についてみていきましょう。
自己破産はどのような方に向いていますか?
自己破産による債務整理は、次のような方に向いているといえます。
- 返済の見込みが立たないほど大きな借金を抱えている
- 借金の原因が免責不許可事由に該当しない
- 債権者からの借金の取立てに悩まされている
- 任意整理や個人再生では解決できそうにない
- 財産がほとんどない
また、自身が自己破産に適しているのかわからない方は、まずは無料相談を活用し、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
債務整理に強い弁護士であれば、自身の状況に適したアドバイスを受けることができるからです。
クレジットカードやローンは一生使えなくなる?
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されるため、新しくローンを組んだりクレジットカードに申し込んだりする際に不利になります。
しかし、自己破産に関する事故情報は5年〜10年ほど経過すると削除されます。
そのため、事故情報が削除されたあとは、通常どおり、ローンやクレジットカードなどの申し込みができるでしょう。
自己破産後は引っ越しや旅行はできなくなる?
自己破産の手続き中は居住地に関する制限を受けるため、引っ越しや旅行を自由にすることができなくなります。
ただし、裁判所に申し立てをおこなって、許可を受けた場合に限り、その居住地を離れることができます(破産法第37条)。
なお、自己破産の申立てをする前と、免責許可決定が出された後は、居住地に制限はなく、自由に移動することができます。
(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
自己破産すると何が失われますか?
自己破産をすると失われるものは、主に財産や信用です。
財産であれば、不動産や自動車やブランド品などの高額な動産、また20万円を超える預貯金などが売却または処分されます。
また、信用については、自己破産したことが信用情報機関に登録されるため、破産者本人の信用に傷がつくことになります。
ただし、生活に必要な最低限の財産は残せるほか、家族の信用情報には影響を与えません。
自己破産した記録は何年で消えますか?
自己破産したという記録は、5年から最長10年間登録されます。
そのため、最長でも10年を経過すれば、自己破産したという記録は信用情報から抹消されます。
したがって、このあとは、ローンの契約やクレジットカードの審査を問題なく、おこなえるようになるでしょう。
まとめ|自己破産で人生の再スタートができる
一般的に自己破産は、ネガティブな印象が強いですが、「債務(借金)を解消し、人生の再スタートをしたい」と考える方にとっては、おすすめの債務整理の方法といえます。
自己破産は手続きが複雑なので、一般的には弁護士に依頼することが多いです。
その際、弁護士費用が問題になりやすいですが、無料相談や分割払いに対応している法律事務所も多くあります。
まずは「ベンナビ債務整理」で、そのような法律事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わりに最低限の財産以外は手放すことになります。
借金問題を解決する方法には、自己破産以外にも、任意整理や個人再生などの方法があります。
もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。
自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。
- 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
- 面倒な手続きを一任できる
- 依頼した時点で、取立てが停止する など
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しております。
借金問題を解決したい方は、ぜひ下記よりご相談ください。