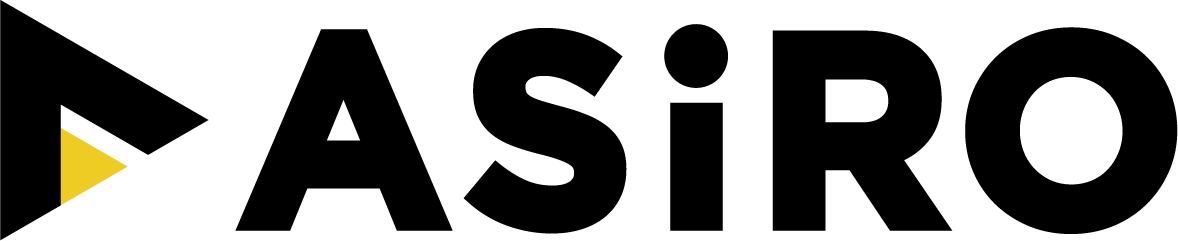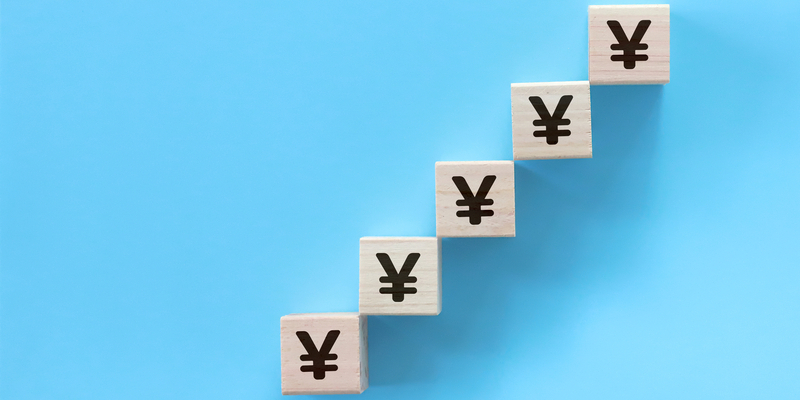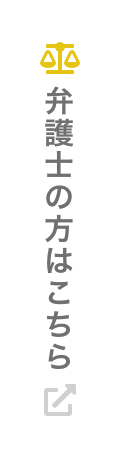「自己破産するにはどうしたらいいのだろう……」
借金が膨れ上がりどうしようもなくなったとき、自己破産を考える方も少なくないでしょう。
しかし、多くの方にとって自己破産は初めての経験なので、そもそも自己破産できるのか、どのような手順を踏めばよいのか、自己破産した場合どのようなデメリットがあるのかなど、疑問も生じてくるはずです。
自己破産とは、保有する財産を債権者に配当するとともに、残った借金の支払い義務を裁判所に免責してもらう手続きです。
申立てには多くの書類を作成、収集しなければならないため、弁護士をはじめとした法律の専門家の助けが必要といえるでしょう。
本記事を読むことで、以下の点が理解できるようになります。
- 自己破産できる条件
- 自己破産の必要書類
- 自己破産の種類と流れ
また、弁護士に依頼するメリットや、依頼した場合の費用についても解説しているので、自己破産を考えている方は参考にしてください。
自己破産をするには、裁判所での手続きが必要です。
手続きにあたっては、金融や法律などの知識が求められます。
また、自己破産にはデメリットもあり、あなたの状況次第では、自己破産以外の債務整理のほうが適している可能性もあります。
日弁連の調査では、自己破産をした調査対象者の内、約9割に弁護士が関与していました。(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会)
自己破産をして後悔しないためにも、弁護士への相談が有効です。
弁護士に相談することで、次のようなメリットが期待できます。
- 自身の状況にあった解決策を提案してもらえる
- 自己破産をするにあたって、必要なことがわかる
- 自己破産に関する不安な点を聞くことができる など
初回無料相談が可能な弁護士事務所も多数掲載しておりますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域をご選択ください。
自己破産をするにはどうすればいい?満たすべき条件や事前準備
まずは、自己破産に必要な条件や、自己破産のために準備すべきことを解説します。
免責を受けるために必要な条件
自己破産が認められると、債権者にとっては貸したお金を回収できず、損をするというデメリットがあります。
したがって、自己破産は簡単に認められるものではありません。
自己破産が認められるには、破産法に定められた一定の要件を満たす必要があります。
1.支払い不能状態に陥っていること
自己破産によって免責を受けるには、支払い不能状態にあることを裁判所に認めてもらう必要があります。
「支払い不能」とは、支払い能力がなく、支払い期日が到来している債務を返済できない状態のことです(破産法第2条11項)。
収入面だけでなく、財産をお金に換えても返済する余力がない場合が該当します。
また、一時的ではなく、継続的に支払いが不可能な状態でなければなりません。
具体的には、債務総額を3年で完済できるかを判断の目安にするとよいでしょう。
ただし、「支払い不能状態」といえるかどうかは債務総額・収入・貯金額など、さまざまな点が考慮されたうえで判断されるため、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
2.非免責債権以外の借金があること
支払い不能に陥っても、債権の性質によっては、自己破産でも免責されない債務もあります。
以下のような債務を「非免責債権」といいます(破産法第253条1項)。
- 税金や社会保険料等の租税請求権
- 故意、もしくは重過失で与えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用、養育費など、家族間、夫婦間または親族間で発生する費用負担義務
- 個人事業主の従業員の給与など
- わざと債権者一覧表に記載せず、裁判所に報告しなかった債権
- 罰金などの請求権
非免責債権があったとしても、破産をおこなうこと自体は可能です。
しかし、非免責債権は破産をしても免責されることはありません。
3.免責不許可事由がないこと
「免責不許可事由」がある場合、原則として裁判所から免責決定を受けることができません。
免責不許可事由とは、以下のような行為をいいます。
- ギャンブルや浪費で借金をする
- 財産を隠す、譲渡する
- 帳簿の隠ぺいや改ざんをおこなう
- 相手を騙して借金をする
- 不当に債務を負担する
- 特定の債権者だけに返済する
- 虚偽の債権者名簿を提出する
- 裁判所の調査に回答しない、嘘をつく
- 破産管財人の調査に協力しない
- 破産管財人の業務を妨害する
- 過去7年以内に自己破産している
ただし、破産法252条2項では、「裁量免責」を認めています。
免責不許可事由に該当しても、破産に至った全ての事情を考慮し、裁判所の裁量で免責が許可されるケースがあるのです。
そのため、免責不許可事由がある場合は、申立ての当初から隠し事をせず、きちんと事情を説明するようにしましょう。
自己破産をする際に必要な準備
次に、自己破産をする際に必要な準備を解説します。
一つひとつが重要な作業なので、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
債権の調査
自己破産を申し立てるにあたって、まず、債権の調査をして債権者一覧表を作成しなければなりません。
債権者一覧表は、申立書と併せて裁判所に提出する書類のひとつです。
裁判所は債権者一覧表をもとに、自己破産の必要性などを検討していきます。
債権者一覧表に記載する主な項目は、以下のとおりです。
- 債権者名
- 債権者の住所
- 借入始期・終期
- 現在の残高
- 借入れの原因・使途
- 保証人の氏名
- 最終返済日
公共料金や勤務先・知人・親族からの借入れ、家賃滞納分、連帯保証債務などは、債権者一覧表への記載が漏れてしまうことが多いので注意しておきましょう。
また、特定の債権者を意図的に一覧表から除外することは絶対にしてはいけません。
記載漏れがあった場合、発覚のタイミング次第では免責決定に悪影響が出る可能性もあります。
自身の財産の調査
次に、自分の所有財産を調査し、「財産目録」を作成します。
自己破産手続において重要視されるのは、債権者の利益です。
裁判所は財産目録をもとに、債権者に対してどの程度の財産を分けられるのかを徹底的に調査します。
財産目録には、主に以下のような財産を記載しなければなりません。
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 保険の解約返戻金
- 自動車
- 過払い金
- 退職金
- 直近2年間に処分した財産
また、自身の財産の内容を説明するために以下のような書類の添付も必要です。
- 預貯金通帳の写し(概ね過去2年分の取引がわかるもの)
- 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、不動産査定書
- 賃貸の場合は賃貸借契約書など
- 保険証券の写し
- 生命保険の解約返戻金試算表
- 車検証、車の売却査定書
- 退職金支給明細書 など
裁判所によって必要な書類が異なる場合があるため、自己破産手続をする前に手続きをする裁判所で詳細を確認してください。
陳述書の作成などに必要な情報の調査
自己破産の申立てをおこなう際には、陳述書の作成などに必要な情報も事前に調査しておきましょう。
たとえば、陳述書には自己破産を申し立てるに至った事情を記載しなければなりません。
そのため、借入時期や借入金額だけでなく、借入れをしたときの経済状況なども正確に調査しておく必要があります。
とはいえ、自己破産の手続きを進めるにあたって調査しておくべき情報は人それぞれ異なるため、まずは専門家のアドバイスを得ることが大切です。
自己破産申立書の作成
自己破産を進めるうえで、申立書の提出は必須です。
主には、申立人の氏名・職業・連絡先や申立ての趣旨、破産手続の開始原因などを記載することになります。
申立書の作成自体は難しくありませんが、申立書の書式は裁判所によって異なる点に注意が必要です。
必ず自身が申立てをおこなう裁判所の書式を使用するようにしてください。
その他申立書類の収集
自己破産の申立てにあたっては、申立書のほかに以下のような書類を添付する必要があります。
- 陳述書
- 住民票
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 源泉徴収票・課税証明書
- 預貯金通帳のコピー
- 収入がわかる書類(給与明細書など)
- 居住地がわかる証明書(賃貸借契約書・不動産登記簿謄本など)
そのほか、添付書類は個々の状況に応じて異なるため、悩んだときは弁護士などに相談してみることをおすすめします。
破産手続の3つの種類
自己破産手続は、資産額や債務額などによって、以下の3つに分類されます。
- 同時廃止事件
- 管財事件
- 少額管財事件
ここでは、それぞれの破産手続が適用される条件などを詳しく見ていきましょう。
なお、最終的にどの手続きで進めるかは、管轄裁判所が判断します。
1.同時廃止事件|債権者に分けるべき財産がない場合
「同時廃止事件」とは、申立人が債権者に分けるべき財産を所有していない場合に適用される破産手続です。
破産管財人が選任されず、破産開始決定と同時に破産手続が終了します
同時廃止となる主な条件は、以下のとおりです。
- 自由財産以外の財産が20万円相当以下で、少額管財の予納金を準備できないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
- 申立人が個人であり、事業による負債ではないこと
なお、管轄裁判所ごとに条件は異なります。
「同時廃止事件」は、もっとも費用負担が軽く手続き期間も短い方法です。
破産申立事件の中でもっとも件数が多く、2020年の司法統計では、個人の自己破産7万2,329件のうち、約70%にあたる4万5,464件が同時廃止事件として終局しています。
【参考記事】2020年破産既済事件数―破産者及び終局区分別|裁判所
2.管財事件|債権者に分けるべき財産がある場合
「管財事件」とは、債務者の財産が一定以上ある場合、お金に換えて債権者に配当する破産手続です。
管財事件では、円滑・公平に配当をおこなうために、破産管財人が選任されます。
破産管財人には、弁護士などの法律専門家が選任されるケースが一般的です。
破産事件は破産管財人主導で進み、換価した財産を債権者に配当することで終結します。
管財事件は3つの手続きの中でも手続き期間が長くなりやすく、通常50万円以上の予納金がかかります。
なお、2020年における自己破産手続のうち、管財事件として破産管財人がついたのは全体の3割程度でした。
3.少額管財事件|管財事件のうち弁護士を代理人としている場合
「少額管財事件」とは、管財事件のうち弁護士を代理人とした場合に適用される破産手続きです。
裁判所に納める予納金が大幅に少なく済み、手続きも簡略化されます。
個人が破産手続をおこなう場合、同時廃止に該当しなければ、少額管財事件となるケースがほとんどです。
裁判所に納める予納金は20万円程度です。ただし、予納金の額は裁判所ごとに異なるため、実際に手続きをおこなう際に確認してください。
また、裁判所によっては、少額管財事件を採用していないこともあります。
自己破産手続期間中の注意点
破産手続期間中、債務者はある程度生活に制限を受けます。
破産期間中は以下のようなことに注意し、管財人や裁判所の指示に従いましょう。
旅行・引っ越しが制限される
管財事件では、破産手続中の旅行や引っ越しが制限されます。
管財事件の場合、保有している財産を換価して、債権者に配当しなければなりません。
そのため、財産の持ち逃げや身勝手な処分を防ぎつつ、破産管財人の換価処分に対していつでも協力できるように、申立人は行動が制限されるのです。
ただし、すべての移動が禁止されるわけではありません。2泊以上の旅行や引っ越しも、破産管財人に報告し、裁判所の許可をとれば可能となる場合があります。
同時廃止事件の場合は破産手続開始決定と同時に破産手続が終了するため、原則として移動制限は受けません。
一定の職業や資格が制限される
破産手続中には、以下のとおり、一定の資格・職業が制限されます。
- 弁護士・司法書士・公認会計士などの士業
- 一部の公務員
- 商工会議所、信用金庫などの役員
- 生命保険募集人や警備員など現金を扱う可能性のある職業 など
基本的に制限されるのは手続き中のみで、免責許可決定が確定すれば復職は可能です。
ただし、職業によっては破産手続をおこなうことで退職や罷免になるケースもあります。
郵便物が破産管財人に転送される
管財事件や少額管財事件の場合、開始決定と同時に本人宛の郵便物は破産管財人宛てに転送されるようになります。
破産管財人が郵便物を確認し、隠している財産や把握できていない債務などがないかチェックするためです。
実際、年末調整のために届いた保険会社からの支払い保険料の通知書により生命保険が発覚したり、証券会社からの取引報告書から株式が発覚したりするケースなどがあります。
破産手続が終了すれば転送解除され、自宅に郵便物が届くようになります。
なお、宅配などの財産に直接関係しないものは、そのまま自宅に届くので安心してください。
自己破産をする手続きの流れと免責までの期間
自己破産の条件や事前準備、注意点などがわかったところで、実際に自己破産をおこなう際の流れと、自己破産にはどれくらい時間がかかるのかについて解説します。
自己破産をする際の手続きの主な流れ
自己破産の手続きは、管財事件・同時廃止事件でそれぞれ以下の流れで進行します。
なお、弁護士に依頼した場合は以下の手続きに入る前に「債権者への受任通知書の発送」がおこなわれます。
| 管財事件(少額管財事件を含む) | 同時廃止事件 |
|
|
自己破産を完了させるまでには、さまざまな手続きが必要になります。
そのため、自力でおこなうことは現実的ではなく、弁護士に依頼するのが賢明な判断といえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、裁判官との面接や債権者集会での説明なども手厚くサポートしてもらえます。
免責までの期間
破産手続の申立てから免責許可決定までの期間は、事件の内容によって大きく変わりますが、以下の期間を目安にしておくとよいでしょう。
- 同時廃止事件:3ヵ月~4ヵ月程度
- 少額管財事件:4ヵ月~6ヵ月程度
- 管財事件:6ヵ月~1年程度
また、自己破産は申立てをおこなうまでの調査や書類収集にも時間がかかります。
弁護士に依頼した場合は、事前準備に3ヵ月から6ヵ月程度を要するケースが一般的です。
自己破産をする際は専門家に依頼するケースがほとんど
自己破産の手続きは複雑かつ専門的なので、法律の専門家である弁護士に依頼すべきです。
また、弁護士に依頼すれば取り立てを停止させることができるため、落ち着いて手続きを進められる点でもメリットがあります。
日本弁護士連合会が1,240人を対象におこなった調査報告書によると、専門家への依頼の有無に関して以下のような結果が出ています。
- 弁護士に依頼:1,123人(90.56%)
- 司法書士に依頼:94人(7.58%)
- 代理人なし:9人(0.73%)
不明・記載漏れ:14人(1.13%)【参考記事】2020年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会
自分で自己破産の申立てをおこなっている人はまれで、弁護士などの専門家に依頼している人がほとんどです。
なお、司法書士ができるのは書類作成のみで、代理人となることはできません。
そのため、裁判所での面接や債権者集会などに対応してもらえないので注意してください。
司法書士が手続きに一貫して関わることができないという意味でも、破産手続は弁護士に委任するのがおすすめです。
自己破産をする際に必要となる費用
実際に自己破産を申し立てる際には、裁判所へ納める手続き費用と、申立代理人の弁護士に支払う弁護士費用が必要です。
手続きの種類によっても金額は変わるので、以下で解説します。
裁判所へ納める手数料
自己破産を申し立てる際に裁判所に提出する費用には、以下のものがあります。
- 申立手数料:収入印紙で納付
- 予納金:破産管財人の報酬など
- 官報公告費:破産開始決定等の事実を官報に掲載する費用
- 予納郵券:裁判所が関係者に通知するための郵送費用
| 同時廃止事件 | 少額管財 | 管財事件 | |
| 申立手数料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 予納金 | 1万円~3万円 (官報公告費として) | 20万円~ (官報公告費含む) | 50万円~ (官報公告費含む) |
| 予納郵券代 | 3,000円~15,000円程度 | 3,000円~1万5,000円程度 | 3,000円~1万5,000円程度 |
予納郵券は、債権者数によっても金額が変わります。
また、予納金は事件の複雑さや管財人の事務処理量の多さなどを考慮し、裁判所が決定します。
弁護士への依頼費用
自己破産を申し立てる際にもうひとつ必要になるのが、弁護士費用です。
弁護士費用は、主に以下のような項目に分けられます。
- 相談料:弁護士に法律相談をする際にかかる費用
- 着手金:自己破産の手続きを依頼した時点で発生する費用
- 成功報酬:自己破産が成功した場合に発生する費用
弁護士費用は各法律事務所が個別に設定しているため、一律に示すことはできませんが、以下の金額を目安にしておくとよいでしょう。
- 同時廃止事件:20万円~30万円程度
- 少額管財事件:30万円~50万円程度
- 管財事件の順:30万円~80万円程度
弁護士費用の支払いが難しい場合は、相談料無料の法律事務所を利用する、分割払いにできないか打診するといった対策が考えられます。
また、法テラスを利用するのもひとつの方法です。
一定の収入・資産基準を満たしている場合は、弁護士に無料で相談できるほか、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。
自己破産は弁護士に依頼するのが望ましい理由
これまで述べてきたとおり、自己破産を申し立てるのであれば弁護士に依頼するのがおすすめです。
ここでは、弁護士に依頼するメリットを紹介します。
1.自分にあった借金問題の解決策を提案してくれる
弁護士に相談するメリットのひとつは、自分にあった借金問題の解決策を提案してくれることです。
債務整理には自己破産のほかに、任意整理や個人再生といった方法があり、それぞれ異なる特徴をもっています。
しかし、自分が置かれている状況にあった方法を選ぶことは簡単ではありません。
特に自己破産は強力な効果がある反面、デメリットも大きく、安易に選択してしまうと取り返しのつかない事態に陥る可能性もあるので注意が必要です。
その点、弁護士に依頼すれば、任意整理や個人再生の可能性も検討したうえで、最適な債務整理の提案を受けることができます。
2.自己破産の申立てにおける面倒な手続きをすべて任せられる
自己破産の申立ては複雑かつ煩雑なので、自力での対応は基本的に困難です。
弁護士に対しては、破産の申立てから免責決定を受けるまで一貫して対応を委任することができます。
ただし、一口に弁護士といっても対応できる分野は多岐にわたります。
自己破産を依頼するなら、債務経理を得意としている法律事務所や経験が豊富な弁護士を選ぶようにしてください。
3.取立てや請求が停止する
弁護士が依頼を受け、債権者に対して受任通知を送付することで、債権者は債務者に直接取り立てができなくなります。
そのため、弁護士に依頼したあとは、余裕をもって生活を立て直しつつ、破産申立ての準備を進めることができるでしょう。
自己破産後の生活への影響
自己破産をおこなうと、日常生活において以下のような支障が生じるおそれがあります。
- 自宅、車、生命保険など、20万円以上の財産は失うことがある
- 保証人・連帯保証人は引き続き支払い義務を負う
- 新しくローンが組むことが難しくなるい
- クレジットカードの新規作成や利用ができなくなる
- 子どもの奨学金など、借金の保証人になれない場合がある
- 家電などの分割払いができなくなる場合がある
自己破産は、借金の返済義務を免れることのできる強力な手続きです。
一方で上記のようなデメリットもあるため、実行に移すかどうかは、弁護士や司法書士とも相談したうえで慎重に判断するようにしましょう。
まとめ
自己破産をするには、客観的に「支払い不能」に陥っていなければなりません。
財産を返済に充てても、自身の給与などの中から3年程度の分割払いで支払いきれない負債を抱えた状態であれば、「支払い不能」といえる場合が多いでしょう。
とはいえ、ケースバイケースな部分もあるので、自身が自己破産できるか、または自己破産すべきかを判断することは簡単ではありません。
そのため、多重債務に苦しんでいる場合は、まずは債務整理を得意とする弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、自身にあった債務整理の方法を提案してもらえるほか、必要な手続きを一任したり、取り立てや返済をストップさせたりすることができます。
免責に不利な事情があったとしても、裁判所への報告の仕方や今後どのように向き合っていくかなど必要な助言を受けつつ、免責決定を得られるように尽力してもらえるでしょう。
自己破産をお考えの場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。