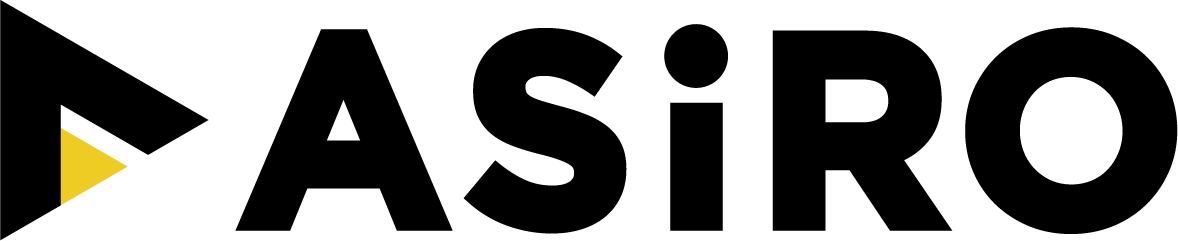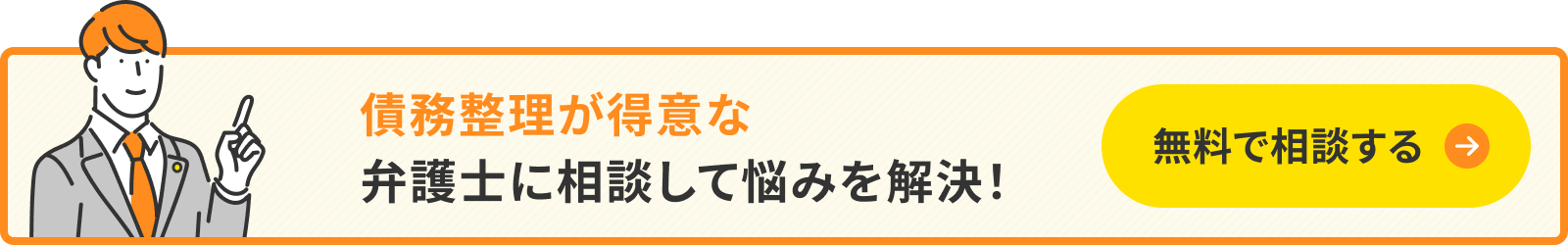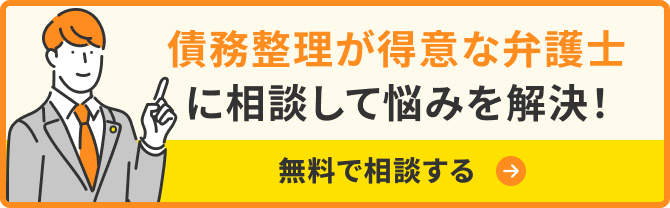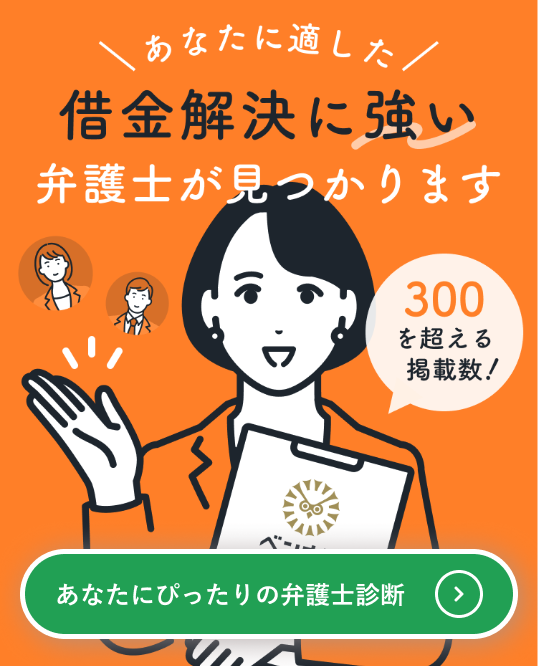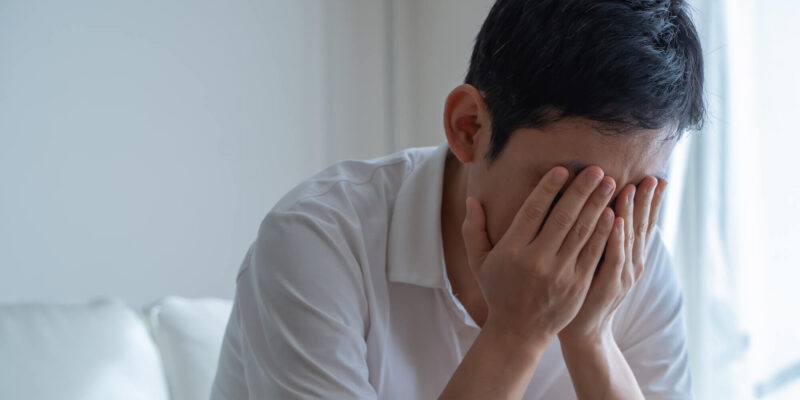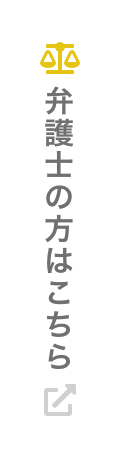借金の返済が滞り督促状が届いてしまったら、次のような焦りや心配を抱いても不思議ではありません。
- このまま支払わなかったらどうなるのだろう
- 何か法的な手段をとられてしまうのかもしれない
もっとも、督促状は「記載されている期限内に支払いをすることを求める書面」ですから、直ちに強制執行等がなされる可能性は低いですが、放置をしておいていいものでもありません。
そのまま放置していると訴訟提起や支払督促といった裁判所を経た手続きにより、最終的には、財産を差し押えられてしまう可能性もあります。
本記事では、督促状を送ろうとしている方や届いた方のために、次のような点を解説します。
- 督促状にはどういった役割・意味があるのか
- 督促状が届いたときの正しい対処法
- 督促状を放置しているとどうなるのか
- 督促状を送付したあとの流れはどうなるのか
- 支払えないときにはどうしたらよいか など
対処法がわからない、どうしたらよいか教えてほしいという方は参考にしてください。
借金の督促状が届いているが、ご自身で返済することができないような方は、借金の救済制度である「債務整理」を活用するのがおすすめです。
そのまま督促状を放置していると、給料差し押さえや裁判所からの督促・強制執行など大変な事態に陥ってしまうことがあります。
債務整理には種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
借金でお悩みの方は、早めに弁護士に相談・依頼しましょう。
- 自分にあった借金の解決策を提案してくれる
- 債務整理に手続きを任せられる
- 依頼した時点で督促・催促が停止する など
まずは下にある都道府県リンクを選択して、あなたにぴったりの弁護士を探してください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!

無料相談できる弁護士一覧
督促状とは|法律的にどのような意味があるのか
まずは、督促状とはどのようなものなのか、法的にどのような意味を持つのか、基本的な概要について確認しておきましょう。
督促状は支払いを促すもの
督促状(とくそくじょう)とは、指定の期限までに借金を支払わなかったときに、債務者の返済を促すために送付する書面のことです。
「督促」の言葉が持つ「約束の履行や実行を促すこと」の意味のとおり、督促状は「期限が過ぎた返済を早くおこなってください」と伝える書面にすぎません。
そのため、督促状は「何らかの理由で期限に返済されていなかったので、記した期限までに入金してください」といったニュアンスで送られる請求書のようなものと理解しておくとよいでしょう。
督促状に法律的な強制力はない
督促状そのものには、支払いを強制する法的な効力はありません。
したがって、仮に督促状どおりに返済しなかったとしても、直ちに財産を差し押さえられるといったことはないのです。
とはいえ、そのまま借金を返済しないでいると、遅延損害金など通常以上の利息の支払を求められたり、法的措置を経たうえ、財産を差し押さえられたりするリスクがあります。
督促状が届いたら内容を確認し、できるだけ速やかに支払うようにしましょう。
督促状は時効の完成を先延ばしにできる
督促状は返金の遅れを知らせることのみが目的で、法律的な意味がまったくないかといえば、そうではありません。
実は、借金の返済には時効があります。
弁済期間(借金や利息の返済期日)から一定期間を経ると、消滅時効が完成し、時効の援用をおこなうことによって、返済の義務がなくなるのです。
そして、民法第150条では、催告、つまり、督促状を送付するなどして債権者が債務者に支払を請求する意思表示をすれば、その時から6ヵ月を経過するまで、時効が完成しないと定められています。
つまり、法律的には、督促状を送付することで時効の完成を猶予することができるという効果があるのです。
もっとも、通常は、督促状は期日を過ぎた借金の返済を促すことを目的としています。
そのため、時効の完成を先延ばしする目的で送付するケースは、時効の完成が迫っているような場合に限られます。
なお、消費者金融からの借入れは、期限の利益を喪失(通常は、2回以上支払を滞納した場合です。)した時点より、5年の経過により、消滅時効が完成します。
督促状と催促状の違い
督促状と似たものに、「催促状」があります。
どちらも返済や対応を促す書面ですが、書面を送る目的や内容に若干の違いがあります。
一般的に督促状は、期限を過ぎた支払いを促す最初の書面として送付されます。
一方で、催促状は督促状を送ったにもかかわらず、問い合わせや支払いがない場合に送られる書面です。
書面の内容には、より強い文言が使われる傾向にあります。
例えば、催促状には「期日までに支払いがないときには、ただちに法的な手段を検討する」など、心理的なプレッシャーを与える文言が記載されることがあり、最終通告としての役割を担う場合があります。
ただし、いずれの書面も法律上の強制力を持つものではありません。
したがって、督促状と催促状は、返済や対応を促す書面という点で共通しているものの、送付されるタイミングや内容に違いがあり、催促状のほうがより警告的な性質を持った書面であるといえます。
督促状と支払督促の違い
督促状と似た書類に「支払督促」というものがあります。
これが届いた場合には、十分な注意が必要です。
というのも、この支払督促は、債権者が「支払督促」を申し立てたときに裁判所から送付されるものであるからです。
到着から2週間以内に「督促異議」を申し立てなければ、債権者は仮執行宣言を得た後に強制執行をかけることができるようになります。
つまり、支払督促を無視していると、預貯金口座の差押えや給与差押えによる強制的な財産の回収がなされる可能性があります。
早急な対応が必要になるので、支払督促が届いたらすぐに弁護士に相談してください。
督促状の書き方
督促状には法的な効力がないため、必ずしも決まった形式や書き方にしたがう必要はありません。
しかし、必要な情報が欠けていると相手に意図が伝わりにくくなる可能性があります。
そのため、以下のような内容を書面に記載することが一般的です。
- 宛先
- 発行日
- 差出人
- 表題
- 支払内容
- 振込先
- 法的措置に関する事項
これらの内容を適切に記載することで、相手に意図が伝わりやすくなります。
それぞれの項目の具体的な書き方は、以下のとおりです。
宛先
企業に送る場合には、宛先に企業名を記載します。
また、必要に応じて支店名や部署名を付け加えます。
担当者とやり取りしている場合には、役職や担当者名も明記します。
一方で、個人に送る場合には、個人名を記載するのではなく、「会員様」や「ご利用者様」などの形式的な表現にすることが一般的です。
これによって、過度に強い印象を与えることを避けることができます。
発行日
発行日には、督促状を作成する日付を記載します。
これは発行日を記載しておくことで、その後、事実関係で争いが生じてしまう可能性を減らすことが期待できます。
差出人
差出人の欄には、会社名と担当部署、担当者名及び、必要に応じて上役の名前と捺印を記載します。
これらを記載することで、債務者としても誰からの連絡であるのか正確に認識でき、その後の対応をスムーズに進めることができます。
表題
表題には、基本的に「督促状」と記載します。
ただし、単に「督促状」であると、相手に強い印象を与えすぎる場合があります。
このような場合には「お支払いのお願い」など、柔らかい表現を選ぶこともあります。
相手にどのような印象を与えたいか考えたうえで、適切な表題を付けるとよいでしょう。
支払内容
支払内容には、以下の事項を具体的に記載します。
- どの債務に対する督促状であるのか
- 支払いが必要な金額
- 支払期限
これらの情報を記載することで、債務者が現在の状況を正確に認識し、適切に対応できるようになります。
振込先
振込先を明記します。
振込先の金融機関や口座番号、支払方法について正確に記載しましょう。
これらの情報を明確に記載することで、相手もスムーズに入金の事務に着手しやすくなります。
法的措置に関する事項
法的措置に関する事項については、支払いがおこなわれなかった場合に法的手段を検討する可能性を示唆する内容を記載します。
また、この項目には遅延損害金や延滞利息が加算される旨についても明記するとよいでしょう。
支払督促などの法的な措置を検討している旨を記載することで、債務者が何らかの対応をする可能性が高まります。
督促状に書く内容・文言
次に、督促状に書かれている内容・文言について確認しておきましょう。
督促状は、送る回数によって、書く内容や文言が変わることが通常です。
ここでは、1回目、2回目、3回目以降と、送られてきた回数別に、督促状の記載例などを、おさえておきましょう。
1回目の文言例
督促状 拝啓 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 ●●様が弊社よりお借入れをされた●万円につきましては、毎月●●日がご返済期限となっておりますが、本日に至ってもまだご入金の確認がとれておりません。 つきましては、本状到着後、直ちに、下記の口座に、今回請求金額をお支払いいただくようお願いいたします。 本状と行き違いにご入金いただいておりました場合はご容赦願います。 その他ご不明点がございましたら、0120-○○○○-○○○○までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 なお、お支払いが遅れた場合には、契約の継続が困難になることもございます。ご注意ください。 敬具 記 【請求金額】 【ご入金先口座】 以上 |
1回目の督促状の簡易的な例は、上記のとおりです。
主に、次のような内容が記載されています。
- 入金の確認がとれていないこと
- 入金の金額
- 入金先口座 など
1回目の督促状は、比較的丁寧な文章で記載されていることが通常です。
弁済期までに支払していないことについては、債務者に非があるものの、高圧的な文章にすると、過剰に身構える可能性があるからです。
2回目の文言例
督促状 拝啓 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 貴殿が弊社に対して負担している債務につきまして、●月分の返済が本日に至ってもまだ確認がとれておりません。 つきましては、本状到着後直ちに、下記の口座に今回請求金額をお支払いいただくようお願いいたします。 その他ご不明点がございましたら、0120-○○○○-○○○○までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 なお、お支払いが遅れた場合には、契約の継続が困難になることもございます。ご注意ください。 敬具 記 【請求金額】 【ご入金先口座】 以上 |
2回目の督促状の例は、上記のとおりです。
1回目と同じく、支払い金額や支払先の口座などが記載されているのが一般的です。
もっとも、2回目も丁寧な表現が使われているものの、より強い口調になっていることも少なくありません。
相手に心理的なプレッシャーを与えて、返金を促すことが目的です。
3回目以降の文言例
催告書 拝啓 当社は、貴殿に対し令和●年●月●日、年利●%、遅延損害金年利●%との約定で金●●万円をお貸しいたしました。 貴殿に対し、再三にわたり請求しておりますが、ご連絡もなく、本日に至るまでご返金いただいておりません。 つきましては、下記金額を令和●年●月●日までに後記振込口座までお支払いください。 なお、上記期日内にお支払いいただけない場合、民事訴訟及び強制執行の法的手続にやむを得ず移行することを申し添えます。 敬具 記 【請求金額】 【振込先口座】 以上 |
3回目以降の簡単な例は、上記のとおりです。
なお、3回目以降は、書面のタイトルが「督促状」から「催告書」に代わっているケースも少なくありません。
口調もより強くなる傾向にあり、法的手続に移行する旨が記載されていることもあります。
3回目以降も対応しないでいると、「支払督促」や「訴状」が裁判所から届くことにつながります。
できれば初回の督促状で適切に対応しておきたいところです。
督促状を送付したあとの流れ
督促状を送付したあとは、以下のような流れになることが、一般的です。
1.電話での連絡・督促状を再度送る
督促状を送付しても入金が確認できない場合は、再度督促状を送ります。
ただし、相手の郵便事情を考慮し、十分に日数を空けてから送付するようにしましょう。
また、督促状を再送付したにもかかわらず反応がない場合には、債務者に直接電話で連絡を取り、支払いを請求します。
それでも入金が確認できない場合には、内容証明郵便で催促状を送付します。
なお、支払の確定期限が到来した場合、元金や利息に加えて遅延損害金を請求することが可能となるので、督促状を送付する時点では、遅延損害金も計上することができます。
2.保証人・連帯保証人に連絡する
督促状や催促状を送ったのにもかかわらず、連絡がない場合は、債務者の保証人や連帯保証人に連絡を入れます。
保証人と連帯保証人には、以下のような違いがあります。
| 項目 | 保証人 | 連帯保証人 |
| 【催告の抗弁権】 契約者に変わり返済を請求されたときに「主債務者に請求してほしい」と主張する権利 | あり | なし |
| 【検索の抗弁権】 主債務者が返済できるのに返済しなかったときに、主債務者に弁済可能な資産がある場合は、「主債務者の財産を強制執行してほしい」と主張する権利 | あり | なし |
| 【分別の利益】 (連帯)保証人が複数いる場合に、支払義務を保証人の頭数で等分できる権利 | あり | なし |
3.信用情報機関に事故情報を登録する
次に、信用情報に事故情報を登録します。
一般的に「ブラックリストに載る」といわれる状態です。
信用情報とは、クレジットやローンの支払状況などの客観的な取引事実を登録した個人情報のことです。
日本では「CIC」「JICC」「全国銀行個人信用情報センター」の3社が管理しており、銀行やクレジット会社、貸金業者などが個人の「信用」を判断するときの参考資料として用いられます。
債権者が上記の信用情報機関のいずれか加入している場合、事故情報が載るため、債務者は新たな借入れやクレジットカードの作成・利用、携帯電話の分割購入などができなくなります。
4.一括請求の通知を送付する
保証人や連帯保証人に連絡を入れても、入金がない場合には一括請求の通知を送付します。
これは、債務者が「期限の利益」を失うことを知らせる書面です。
期限の利益とは、簡単にいうと債務を分割で支払える権利のことです。
ローンは分割払いできることが通常ですが、これは「期限の利益」があるからです。
期限の利益を喪失する場合、債権者は元金と利息、遅延損害金の全てを一括で請求できるようになります。
5.裁判所を通じて特別送達を送る
一括請求が無視された場合、法的手続に移行します。
まずは、裁判所から債務者に対して、特別送達による書類が送付されます。
これによって、債務者が対応しなかったとしても、裁判手続を進めていくことができるようになります(なお、債務者が訴状等を受け取らない場合は、別の送達方法を検討する必要がある点には注意が必要です。)。
たとえ相手から無視されてアクションがなかったとしても、こちら側の主張が100%認められることになるでしょう。
なお、特別送達で裁判所が送る書面には、「訴状」と「支払督促」の2種類があり、裁判所に申し立てる手続によって、送付される書類が異なります。
訴状
「貸金返還訴訟」等を提起した場合に送られる書面です。
貸金返還請求には、さらに、60万円以下の請求について原則1回の裁判で判決がでる少額訴訟や通常訴訟があります。
どちらも、主張する金銭の支払いを裁判所に認めてもらうための訴訟手続で、判決書を基に強制執行を申し立てられるようになります。
支払督促
「支払督促」を申し立てた場合に送られる書類です。
支払督促は訴訟のように裁判所で審理をせず、提出した書面のみの審査で債務者に金銭を請求する手続きです。
支払督促正本(1回目)を受領してから2週間以内に債務者が異議申立てをしない場合、債権者からの依頼で裁判所は支払督促に仮執行宣言を付します。
その後、仮執行宣言付支払督促正本(2回目)を債務者が受領し、再度、2週間以内に異議申立てがなされない場合は、この支払督促が確定することとなります。
これらの手続きを経たうえで、債権者確定した支払督促に基づいて、強制執行を申し立てることができます。
6.差押えを実行する
強制執行により、債務者の財産を差し押さえ、債権の回収を図ります。
差押えの対象となる財産には、以下のようなものがあります。
- 預貯金
- 給与のうちの一定額
- 土地や建物などの不動産
- 自動車などの動産
これらの財産を差し押さえて換価することで、回収できていない債権を取り戻すことができるでしょう。
督促状の内容どおりに返済できないといわれた場合の対処法
督促状を送付しても、相手方がどうしても返済の目途を立てられない場合には、いくつかの対処法があります。
ここでは、債務整理について詳しく見ていきましょう。
債務整理を提案する
督促状を繰り返し送付しても返済の見込みが全く立たない場合、債権者側は債権全額を回収できないリスクが生じます。
そのため、こうしたリスクを回避する手段として、債務整理を提案することがあります。
債務整理とは、利息制限法や民事再生法、破産法などに則って、借金支払の猶予や借金減額、借金免除などをして、借金問題を解決する手段のことです。
債務者が債務整理をおこなうことで、全額が回収不能となる貸倒れのリスクを軽減し、一部でも回収できる可能性が高まるのです。
債務整理の種類
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三つの方法があります。
それぞれどういった違いがあるかについて確認しておきましょう。
任意整理
任意整理とは、貸金業者との和解交渉によって、債務を分割返済する手続きです。
基本的には、遅延損害金と将来利息をカットしたうえで、負債を3~5年程度で分割返済する形で和解を結ぶことになります。
任意整理では、遅延損害金や将来の利息を回収することはできませんが、貸した元本については、返済される可能性が高くなります。
そのため、全額回収ができないような貸倒れのリスクを軽減できるでしょう。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて、現在負っている債務の支払義務を減額する手続きです。
この手続きがおこなわれると、債務者の借金は最大10分の1まで圧縮されます。
そのため、任意整理よりも減額が大きくなることが多いのが特徴です。
個人再生が認められると、債権者が回収できる債権が大幅に減ることになります。
もっとも、任意整理と異なり、裁判所を通じた厳格な手続きであるため、債務者の支払いに対するプレッシャーも大きくなりやすく、減額された負債額の回収についてはある程度見込まれます。
自己破産
自己破産とは、裁判所を通じて、現在負っている債務の支払義務をなくす手続きです。
自己破産に伴う免責が認められると、債権者は原則として債権の回収ができなくなります。
この場合には、債権者にとって債権の回収が不可能となるリスクがあります。
そのため、自己破産に至る前の段階で、任意整理や個人再生などの手続きに応じるほうが、貸倒れのリスクを軽減することにつながります。
弁護士に依頼する
債務者が債務整理をおこなう場合、債権者としても弁護士に依頼することが重要です。
なぜなら、弁護士を活用することで、債権を回収できる可能性を最大化できるからです。
その主な理由は、以下のとおりです。
- 裁判所を通した手続きをスムーズに進められる
- 貸倒れになるリスクを抑えられる
弁護士に依頼すると、裁判所での手続きをスムーズに進められます。
特に債務整理の場合、裁判所を通じた法的な手続きがおこなわれ、債権者側は債権届出や再生計画案の意見提出をおこなうことを求められます。
弁護士のサポートを受けることで、これらの手続きを正確におこなえます。
また、弁護士に依頼すると、債務者の状況から返済できる現実的な返済計画を提案することが期待できます。
これにより、債権者は貸倒れリスクを軽減できるでしょう。
督促状が届いたときの対処法
では、督促状が届いた場合どのように対処したらよいのでしょうか。
ここでは、督促状が届いた側の視点から、その対処法について確認します。
架空請求などの詐欺でないことを確認する
督促状が届いたら、まずは請求の内容をしっかり確認しましょう。
近年では裁判所や債権回収業者を装った架空請求も少なくありません。
身に覚えのある請求かどうか、きっちりと把握することが大切です。
もしも届いた書面が架空請求の書面である場合、期限を過ぎると直ちに強制執行ができるような不正確な内容の記載がされており、受け取った人を慌てさせるように作られています。
本記事の情報とも見比べながら、架空請求かどうかを見極めてください。
時効期間が経過していないか確認する
返済期日から数年後に突然返済を求められることも少なくありません。
この場合、時間の経過によっては消滅時効にかかっている場合があります。
この場合には、時効の援用により、借金を返済する義務がなくなります。
消滅時効とは、一定の期間(5年又は10年)権利が行使されないときに、当該権利を消滅させる制度のことです。
借金でいえば、一定期間、返済がなされなかった場合に、消滅時効が完成します。
ただし、消滅時効が成立しているのに返済の猶予を求めたり、一部弁済をしたりすると、時効が中断してしまう可能性があるので注意が必要です。
なお、消滅時効が完成したからといって、自動的に返済の義務がなくなることはありません。
前述のとおり、消滅時効の完成により債務を消滅させるためには「時効の援用」という手続を経る必要があります。
また、消滅時効に関する法律(民法)は令和2年4月に改正されており、借入れの時期により、消滅時効完成の期間が異なる場合があります。
消滅時効が完成しているかどうか、時効の援用の手続をどう進めるべきかについては個人での判断が難しいことがありますので、「消滅時効にかかっているかも?」と考えられる場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
可能であれば期限までに返済する
督促状が身に覚えのあるもので、かつ、消滅時効にもかかっておらず、返済の原資も賄えるような場合は、記載されている期限までに支払うほうがよいでしょう。
冒頭でもお伝えしましたが、督促状には「請求書」に近い意味合いがあります。
つまり、督促状内で指定されている期限内に指定の料金を支払えば、特に問題もありません。
「お金が足りない」という方以外は、直ちに対応するようにしましょう。
返済できないなら債権者に相談する
期限までに支払えそうにないのであれば、債権者に相談する方法もあります。
通常であれば、督促状に連絡先が記載されていますので、電話で相談してみましょう。
債権者によっては、期日の延長や、返済金額の減額(分割払い)に応じてもらえることもあるかもしれません。
督促状を送るなら「ベンナビ債権回収」がおすすめ
督促状を送る際、「督促状はどのように書けばいいのか」「督促状を送付したが連絡がないがどうしたらいいのか」などの疑問を感じることがあるでしょう。
そのような場合には、「ベンナビ債権回収」を利用するのがおすすめです。
ベンナビ債権回収では、売掛金や業務請負、家賃など、さまざまな債権回収の問題に強い弁護士を多数掲載しています。
弁護士はお近くの地域から探すことができるので、債権者に最適な弁護士を見つけることができるでしょう。
法人・個人を問わず債権回収のプロセスにお悩みの方は、活用してみてください。
督促状が届いたら「ベンナビ債務整理」がおすすめ
督促状が手元に届いた際、どのように対処すべきかわからず、不安に感じる方もいるでしょう。
そのような場合には「ベンナビ債務整理」を利用するのがおすすめです。
ベンナビ債務整理を使えば、お住まいの地域から簡単に債務整理に強い弁護士を見つけることができます。
弁護士に相談することで、督促状への対応や債務整理について専門的なアドバイスを受けることが可能です。
なお、ベンナビ債務整理では、初回無料相談を実施している法律事務所が数多く掲載されています。
まずは、無料で相談できる弁護士を検索してみるとよいでしょう。
まとめ|督促状が届いたら弁護士に相談しよう
督促状は、支払い期限が過ぎた借金について返済を促すための書面です。
督促状が送付されることで、直ちに法的な効果が発生することはありませんが、無視しておくと財産の差押えを受ける可能性があるため、早急な対応が必要となります。
督促状が届いたら、まずは架空請求ではないことを確かめたうえで、支払えるのであれば早めに支払っておくほうがよいでしょう。
なお、返済の目途が立たないのであれば債権者に電話して相談するのもひとつの方法です。
また、どうしても借金が返済できないのであれば、債務整理を検討してください。
一方で、あなたが債権者の場合には、貸倒れになるリスクを防ぐとともに、法的手続によって回収可能かどうかを見極めるためにも、弁護士に相談するのがおすすめです。
まずは、弁護士に相談して最適な解決方法を探りましょう。
借金の督促状が届いているが、ご自身で返済することができないような方は、借金の救済制度である「債務整理」を活用するのがおすすめです。
そのまま督促状を放置していると、給料差し押さえや裁判所からの督促・強制執行など大変な事態に陥ってしまうことがあります。
債務整理には種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
借金でお悩みの方は、早めに弁護士に相談・依頼しましょう。
- 自分にあった借金の解決策を提案してくれる
- 債務整理に手続きを任せられる
- 依頼した時点で督促・催促が停止する など
まずは下にある都道府県リンクを選択して、あなたにぴったりの弁護士を探してください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!

無料相談できる弁護士一覧