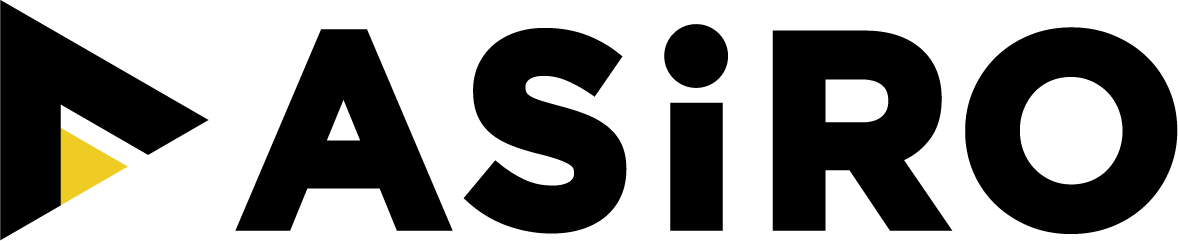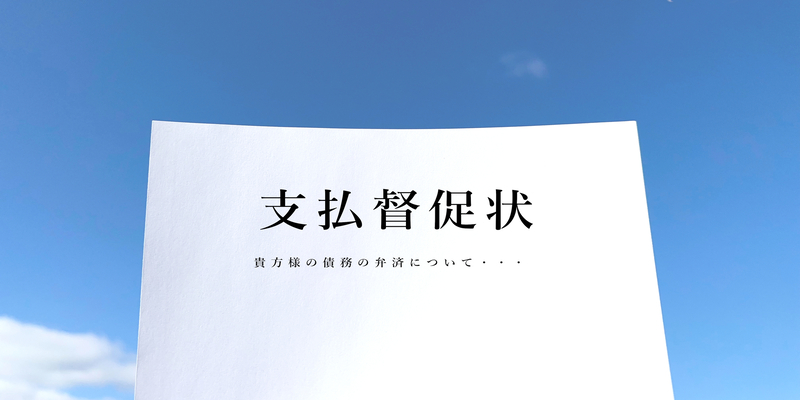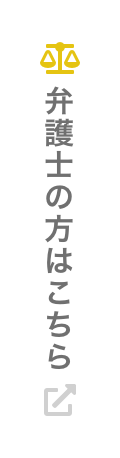代金の後払いサービスはユーザーにとっては便利な支払い方法ですが、企業にとっては滞納リスクを伴います。
そのため、「万が一、滞納された場合に備えておきたい」という担当者も多いでしょう。
後払いの滞納リスクを最小限にするためには、日々の管理と実際に滞納が発生した場合の対処法を知っておくことが大切です。
そこで本記事では、後払いの滞納リスクの管理方法と実際に滞納が起こった際の対処法について紹介します。
滞納リスクを適切に管理・対処するためにも、ぜひ参考にしてください。
代金後払いを導入する際は滞納リスクの管理が必須!
そもそも顧客が選択できる決済手段には、以下のように前払い・即時払い・後払いの3つの方法があります。
- 前払い:商品やサービスの提供前に代金を支払う方法
- 即時払い:商品やサービスの提供と同時に代金を支払う方法
- 後払い:商品やサービスの提供後に代金を支払う方法
このうち後払いは、ほかの方法と比べて新規顧客を獲得しやすく、離脱率の低下による売り上げアップが期待できる方法です。
しかし、商品やサービスを提供したあとに支払いを受ける分、滞納が起こりやすく、普段からリスク管理をしておく必要があります。
なお、後払いの滞納の理由は、大きく以下3つのタイプに分けられます。
- うっかり忘れていた
- 支払えなくなってしまった
- 支払うつもりがない
商品やサービスの購入代を確実に回収するには、滞納理由に応じた対処をすることも大切です。
後払い代金の滞納リスクを管理するための3つの方法
後払い代金の滞納リスクを管理するために、以下3つの方法を検討しましょう。
- 購入者の決済状況がわかるリストを作成する
- 滞納の有無を確認する業務をルーチン化する
- 滞納されたあとの請求フローを明確にしておく
それぞれについて、詳しく解説します。
1.購入者の決済状況がわかるリストを作成する
まず、購入者のリストを作成し、代金の回収状況を一目で確認できるようにしておきましょう。
リストがあることで後払い代金の滞納発生に気付きやすいだけでなく、ほかの社員とも情報を共有しやすくなります。
リストは、エクセルでも簡単に作成できますが、取引量が多い場合は支払管理システムを利用するのが一般的です。
自動で支払いステータスを変更してくれたり、支払いが遅れている購入者についてアラートを表示してくれたりするサービスだと、より管理しやすいでしょう。
2.滞納の有無を確認する業務をルーチン化する
滞納リスクを予防するには、こまめな入金状況を確認するのもおすすめです。
確認作業をスケジュールにルーチンとして組み込んでおけば、滞納に早い段階で気付けます。
ただし、確認作業を特定の社員だけに任せてしまうと、繁忙期などの見落としが発生するリスクもあります。
滞納リスクを漏れなく管理するためには、確認業務は複数の社員で担当するのが望ましいでしょう。
3.滞納されたあとの請求フローを明確にしておく
滞納している代金の未回収を防ぐためにも、滞納が発生したら、速やかに督促をしなければなりません。
万が一に備えて、あらかじめ請求フローを定めておきましょう。
具体例として、以下のような対処が考えられます。
| 時期 | おこなう内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 発生直後 | 督促のメールを送る | ・注文内容、請求額、支払い期日を明記のうえ、至急支払うよう促す ・「本メールと入れ違いでご入金頂いていた場合はご容赦ください」などの一文も入れておく |
| 発生から1週間程度 | 2度目の督促メールを送る | ・支払い期日を設定し直し、請求する |
| 発生から1週間程度 | 電話や手紙でも督促をする | ・2度目の督促メールと同時期に開始 ・電話がつながらなければ、留守番電話にメッセージを残す |
| 設定し直した支払い期日後 | 3度目の督促メールを送る | ・法的措置を取る可能性があることも含めておく |
後払い代金を滞納している人のタイプ別の対処法
後払い代金の滞納理由は、大きく以下の3つのタイプに分類でき、対処法もそれぞれで異なります。
- うっかり支払いを忘れていたタイプ
- お金がなくて支払えないでいるタイプ
- 代金をあえて支払わないでいるタイプ
ケースごとにどのタイプに当てはまるのかを見極め、適切に対処しましょう。
1.うっかり支払いを忘れていたタイプ
後払い代金の滞納理由で最も多いのは、支払う意思も支払えるだけのお金もあるのに、「うっかり忘れていた」「口座にお金がなかった」などというケースです。
この場合、一度督促をすれば、支払いに応じてくれる場合がほとんどでしょう。
特に対策を講じなくても、すぐに解決できるはずです。
2.お金がなくて支払えないでいるタイプ
次に多いのは、支払う意思はあるものの、お金がないために支払えないというケースです。
この場合は、本人と話し合って何とか支払える方法を探します。
支払い期日を伸ばす、分割支払いにする、といった方法も検討しましょう。
なお、支払期日を変更したり、分割払いにしたりした場合は、その後の支払いを管理する必要があります。
会社としてどこまでを許容するのかをあらかじめ決めておき、管理できる体制を整えておきましょう。
3.代金をあえて支払わないでいるタイプ
多くはないものの、中にはあえて後払い代金を支払わずにいる人もいます。
何度督促をしても、支払うつもりが感じられないのであれば、法的手段を講じるしかありません。
以下の手順で対処しましょう。
- 内容証明郵便を送付する
- 裁判所で支払督促、または少額訴訟の手続きをする
- 警察に被害届けを提出する
内容証明郵便を送付する
まずは、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・どんな内容の書類を送付したか、を証明できる郵便方法のことです。
法的な強制力はありませんが、今後の訴訟において証拠として扱えるので、まずは内容証明郵便を送付するのがよいでしょう。
内容としては、督促をする旨、再度設定した支払い期日、それでも支払わない場合は法的手続きに移行する旨を記載します。
裁判所で支払督促、または少額訴訟の手続きをする
内容証明郵便を送付しても支払いがなければ、支払督促、または少額訴訟の手続きをします。
支払督促とは、滞納者に対して裁判所から支払いを命じる制度です。
オンラインでも手続き可能で、24時間受け付けてもらえます。
また、少額訴訟は、債権額が60万円以下のケースで利用可能な訴訟手続きです。
裁判期日は原則、1回で終結します。
どちらも時間も手間もあまりかけずに進められる方法なので、顧問弁護士と相談しながら手続きを進めてください。
警察に被害届けを提出する
後払い代金の滞納があまりに悪質な場合は、「詐欺罪」が成立する可能性もあります。
「滞納を何度も繰り返している」など、悪質性がある場合は警察への被害届の提出も検討しましょう。
警察が捜査を始めるとは限りませんが、毅然とした態度を示すことも大切です。
なお、故意に支払いをしないユーザーに対する法的措置は、弁護士に相談することをおすすめします。
債権回収を弁護士に任せれば、手間もかかりませんし、回収に成功する可能性も高まります。
後払い代金の滞納リスクを弁護士に相談する3つのメリット
代金の後払いを採用しているなら、滞納が発生する前に弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
後払い代金の滞納リスクについて、事前に弁護士へ相談することで、次のようなメリットが期待できます。
1.債権管理に関するアドバイスが受けられる
弁護士に相談することで、債権管理に関するアドバイスを受けることができます。
会社によっては、債権管理が担当者任せになっているケースも多いでしょう。
しかし、それではいざ滞納が起こった際に、スムーズかつ効果的な対応ができない可能性が高いです。
そのため、滞納による損失を防ぐためにも、トラブル発生前に企業としてのルールを定めておくことが大切です。
弁護士に相談すれば、適切な債権管理方法や滞納が起こった際の対処についても、適切にアドバイスをしてもらえます。
2.滞納された場合の法的措置について知れる
後払い代金の滞納について、購入者に何度督促しても支払ってもらえない場合は法的措置を講じるしかありません。
しかし、法的措置には支払督促、少額訴訟、通常訴訟といった複数の方法があります。
適切な方法によって対処しなければ、金銭面、時間面において非効率となるケースもあるでしょう。
その点、弁護士に相談すれば適切な対処法を教えてもらえるだけでなく、依頼すれば手続きを任せることも可能です。
3.滞納が発生した際にスムーズに債権回収を依頼できる
後払い代金の滞納による損失を防ぐには、迅速な対応が肝心です。
事前に弁護士に相談し、備えておくことで、実際にトラブルが起こった場合でもスムーズに対処できます。
滞納が起きた際に改めて弁護士を探す手間もありませんし、全ての対応を任せられるので、担当者にかかる負担も最小限で済みます。
さいごに|代金後払いを導入するなら滞納リスクに備えておこう!
代金の後払いは、新規顧客の獲得、離脱率の低下による売り上げの上昇など、大きなメリットが期待できる方法です。
一方で、滞納という看過できないリスクもあるため、事前に対策をしておくことが大切といえます。
トラブルが起こる前に、弁護士に相談し、万全の備えをしておきましょう。