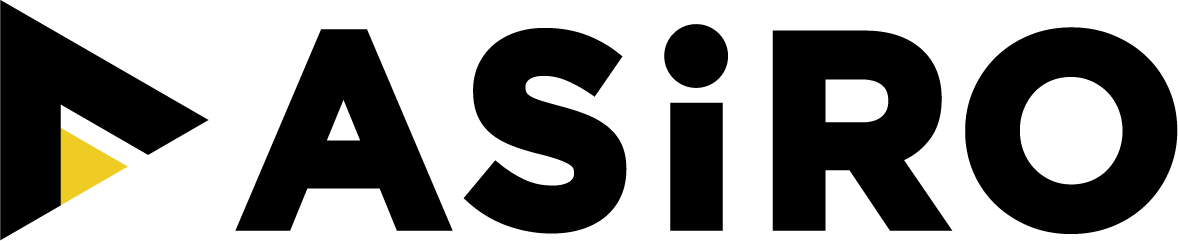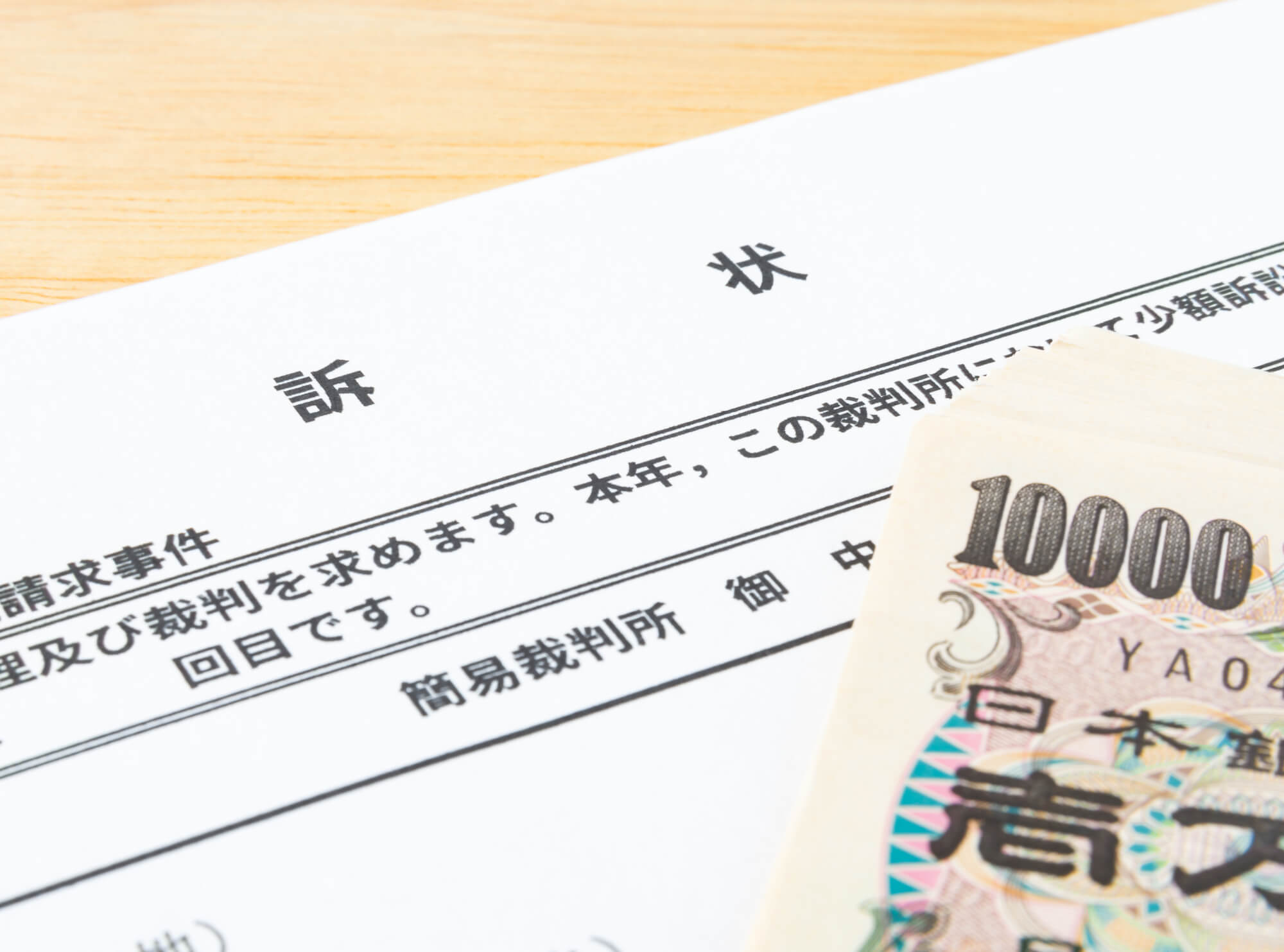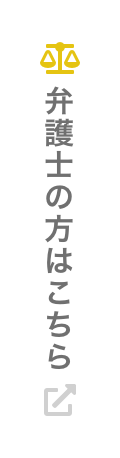「引っ越しの時、敷金が返ってこなかった」「お得意先の売掛金が回収できない」といった金銭トラブルは、少額訴訟という方法がおすすめです。
この記事では、少額訴訟でかかる実費や専門家に依頼した場合の費用、手続きの流れについて解説していきます。
債権額100万円未満について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
少額訴訟にかかる費用の目安
少額訴訟は弁護士や司法書士に相談しなくても、一人で手続きをすることが可能です。
ここでは、少額訴訟に必ずかかる訴訟費用や、弁護士・司法書士など専門家に依頼した場合の費用について解説していきます。
収入印紙
少額訴訟で必要となる収入印紙は、訴訟する目的の金額によって変動します。裁判所が定めている手数料は下記のとおりです。
- 10万円まで:1,000円
- 20万円まで:2,000円
- 30万円まで:3,000円
- 40万円まで:4,000円
- 50万円まで:5,000円
- 60万円まで:6,000円
収入印紙とは、裁判の訴状などといった課税文書を作成する際に必要となる書類です。コンビニや郵便局・法務局などで購入できます。
ただし、コンビニで購入できる収入印紙は200円のみの場合が大半です。収入印紙は1円~10万円まで幅広いものがありますので、必要となる金額分を集めるなら郵便局や役所などで購入することをおすすめします。
【参考記事】裁判所|手数料額早見表
弁護士費用
弁護士の依頼費用は弁護士事務所によって変わります。ただ過去定められていた「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を利用している事務所もあります。
参考までに、日本弁護士連合会弁護士報酬基準に基づいた少額訴訟の弁護士費用を紹介していきます。
法律相談等
初回市民法律相談料:30分ごとに5000円~1万円の範囲内の一定額
一般法律相談料:30分ごとに5000円~2万5000円以下
着手金
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合8%
報酬金
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%
少額訴訟は弁護士に依頼することも可能ですが、弁護士に依頼する方は司法書士に比べ少ないといわれています。少額訴訟手続きが簡単であることと、一般的に司法書士のほうが依頼費用が安いといわれているためです。
しかし、近年の弁護士事務所は相談無料にしたり着手金無料にしたりとかなり自由に価格を設定しているため、費用面だけがネックな場合比較検討の余地はあるといえるでしょう。
また、少額訴訟で納得のいく結果にならなかったとき、本格的な訴訟も視野に入れるとなると、少額訴訟から弁護士に依頼しておくほうが、その後やり取りが少なく済みスムーズです。
ただし、費用倒れにならないように注意が必要です。弁護士に依頼するまえに、必ず費用がどのくらいかかるのか確認しておきましょう。
【参考記事】(旧)日本弁護士連合会報酬等基準|宮崎県弁護士会
司法書士費用
司法書士の中でも、特別な試験に合格した「認定司法書士」の資格を保有している司法書士事務所なら、少額訴訟の対応が可能です。司法書士の費用は、自由化されており個々の事務所によって異なります。一般的にいわれている報酬としては下記のとおりです。
法律相談等
30分~1時間で5000円
着手金
~30,000円
報酬金
回収額の8~15%
上記のほか、当日に同行してもらう期日同行には大体10,000円程度の費用が加算される場合があります。
弁護士費用と比べてみると、成功報酬がやや低く設定されていることがわかります。さらに、少額訴訟の司法書士費を助成してくれる「少額裁判司法書士報酬助成制度」も存在します。
この制度は、請求金額が50万円以下の訴訟に限り、東京司法書士会の会員司法書士に依頼することで利用可能です。
着手金は20,000円と相場より安めに設定されており、成功報酬部分も助成されるので、結果として弁護士に依頼するより安く手続きが可能です。
【参考記事】東京司法書士会|少額裁判司法書士報酬助成制度
その他の実費
少額訴訟の手続きを進めるためには、上記のほかにも負担しなければならない実費が存在します。たとえば下記などが挙げられます。
- 予納郵券代
- 交通費等
- 登記事項証明書の取得費用など
ここでは実費としてかかる予納郵便代と交通費等、登記事項証明書の取得費用について解説していきます。
予納郵券代
予納郵券代はいわゆる郵便切手のことです。訴状や収入印紙と同じく裁判を起こすにあたって必要になります。金額は少額訴訟をおこなう裁判所によって異なります。
相手の住所を管轄する裁判所に申し立てをおこなうことになるので、事前に相手の住所と裁判所を調べておきましょう。
交通費等
少額訴訟は裁判所に足を運ぶ必要がありますので、電車・タクシーといった交通費が必要となる場合があります。
相手の住所を管轄する裁判所となりますので、家が離れている場合は金額が上がる可能性もありますので注意しましょう。
登記事項証明書の取得費用
入手には法務局で交付申請書を記入し申請します。書面請求の場合、1通600円の手数料が必要です。
【参考記事】法務省:登記手数料について
少額訴訟の費用の負担を軽減する方法
ここからは弁護士費用などの少額訴訟でかかる費用負担を軽減する方法について解説していきます。
少額訴訟は対象となる金額が少額なだけに、回収できたとしても費用倒れが起きてしまう可能性もあります。
なるべく出費を抑え利益を最大限にできるようにポイントを押さえておきましょう。
無料相談を活用する
最近の弁護士事務所や司法書士事務所は相談料を無料に設定しているところもあります。無料相談は30分や1時間など制限時間が設けられていることがほとんどです。
事前の準備をしっかりしておきましょう。聞きたいポイントしっかり準備して相談の際に聞き出し、あとの手続きは自分でおこなうことができれば費用を抑えることが可能です。
無料で相談できる範囲としては、「おおまかな期待回収金額」「少額訴訟手続きのおおまかな流れ」等が考えられます。
訴状の具体的な書き方などは難しいかもしれませんが、裁判所の窓口の方が教えてくれることもあるので、弁護士に聞けることを聞いて窓口の方に相談してみるのもよいでしょう。
「相談したら必ず依頼しなければならない」ということはありません。
法テラスを使う
法テラスとは国が運営する法律相談窓口です。所得や資産の条件を満たすことで、弁護士や司法書士のサービスを受けることが可能です。所得や資産の条件は下記等が挙げられます。
- 単身者の場合手取り月収が18万2000円以下
- 資産は、単身者の場合180万円以下
法テラスを利用するメリットは、普通に弁護士や司法書士に依頼するよりも、着手金や相談料が安くなる点です。
また、弁護士・司法書士費用の立て替え払いをしてくれたり、無料相談を3回まで利用できたりといったメリットもあります。
デメリットとしては希望する弁護士や司法書士を選ぶことができないことと、利用のための審査に時間がかかることが挙げられます。
一般的に2週間~1ヶ月ほどかかるといわれていますので、その間手続きは進みません。
自分でできる手続きは自分でおこなう
少額訴訟は申し立てをする本人のみで手続きが可能です。難しいことといえば訴状の書き方くらいですが、裁判所のHPや裁判所の窓口でも書き方の説明が紹介されています。
しっかり調べれば自分一人で手続きを進めることができるので、なるべく出費を抑えたいという方は自分でできるところはすべて自分でおこないましょう。
そもそも少額訴訟とは?
少額訴訟とは、裁判で相手に請求する金額が60万円以下の場合にのみ利用できる簡易裁判制度です。
通常の裁判との違いや少額訴訟のメリット・デメリットを解説していきます。
通常訴訟との違い
少額訴訟と通常の訴訟の違いは、訴訟の金額と手続きの簡単さです。少額訴訟は金額が60万円までで、1日で審理から判決までが完了します。
通常訴訟の場合は問題の額にかかわらず何度も裁判所に通う必要がある一方で、少額訴訟はスピーディーに解決したい方や交通費といった余分なお金をかけたくない方に向いた訴訟方法といえます。
少額訴訟のメリット
少額訴訟のメリットは判決までの時間が早いことや、手続きが一人でできるくらいには簡単であることが挙げられます。
1日で判決が出ますので、とにかく早く解決したいという方に少額訴訟は向いています。
また、必要書類を集めて訴状を書くだけですので、手続きも非常に簡単です。
いわゆる裁判のような、激しい言い合いも繰り広げられることなく、訴状に書いていることの補足説明などをするだけで十分です。
また、スピーディーで一人でも簡単にできることから、訴訟費用も通常の訴訟と比べて安く済ませることができるのもメリットです。
余計な出費を抑えたい・早く解決させたいという方には少額訴訟はおすすめといえます。
少額訴訟のデメリット
少額訴訟のデメリットは控訴ができないこと・時間をかけた審理が望めないことです。
たとえば、判決で分割支払いや損害遅延金のカットが出たとして、納得できなくても合意をしなければなりません。
1日で終わる裁判ですので、こちらの言い分や事情の説明・相手の資産状況の調査をするにも限界があります。
そのため丁寧な審理が望めず、たとえ相手が資産を隠すなどしていても裁判に間に合わない恐れもあるのです。少額訴訟を検討する際は、こうしたことも踏まえて入念な準備が欠かせないというのもデメリットといえます。
「何としても全額回収したい」「損害遅延金もしっかりとりたい」「相手を処罰したい」という感情が強い方は、少額訴訟よりも通常訴訟のほうが向いています。
自分で少額訴訟をおこなう際の必要書類
少額訴訟には収入印紙などのほか、提出書類として必要となる書類がいくつかあります。それぞれ入手先や必要な状況が異なるので、しっかり確認しておきましょう。
【参考記事】訴え(少額訴訟)を起こす方へ… | 裁判所
訴状
訴状は訴訟手続きの際に必ず作成する書類です。各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあるほか、裁判所のHPからもダウンロードできます。
申し立ての前に内容を書いて下書きをしておきたい方は、事前にダウンロードして印刷しておきましょう。
訴状のダウンロードは下記HPから可能です。
訴状の種類
少額訴訟で使う訴状には、その要件によっていくつかの種類があります。主な種類は下記のとおりです。
1:貸金請求
友達同士のお金の貸し借りなどの取引に対して訴訟をするために使用します。
2:売買代金請求
取引先への売掛金の未払いや常連さんのツケといった商売に関わる訴訟をするために使用します。
3:給料支払い請求
従業員が雇い主へ、未払い賃金の請求をするために使用します。
4:敷金返還請求
引っ越しをしたあと、大家さんや不動産の管理会社から敷金の返金がなかったとき、その返還請求のために使用します。
5:損害賠償(交通事故による物損)請求
交通事故などによって身の回りのものが壊れてしまったとき、相手に損害賠償請求をする際に使用します。怪我をしてしまったようなケースでは対象外ですので、注意しましょう。
上記のほか、金銭支払い請求といった種類もあります。少額訴訟の際は、その原因ごとに書式を使い分ける必要があるので、迷ったら弁護士などの専門家に相談しましょう。
訴状の書き方
訴状は原因ごとに書式は変わりますが、おおむね下記の内容は共通して必要です。
- 日付
- 宛先
- 名前
- 当事者の記載
- 事件名
- 訴訟物の価額
- 印紙額
- 請求の趣旨
- 請求の原因
上記の中で注意すべき点としては、請求の趣旨や原因の部分でしょう。ポイントは裁判所に決定してほしい内容を書くことです。
借金の請求であればその請求金額を支払いう旨を記載すれば問題ありません。請求の原因はどのような法的根拠をもって趣旨が正当であるか、理由を記載します。
この部分は少し専門知識が必要となりますので、調べてもわからない場合専門家に相談しましょう。
【参考記事】民事訴訟事件の訴状の書き方について|裁判所
登記事項証明書
登記事項証明書は少額訴訟の申し立てをする方やされる方の属性によっては必要となる書類です。
たとえば、少額訴訟をする方・される方の中に法人が含まれる場合、その法人は登記簿謄本が必要となります。
親権者を証明する戸籍謄本
少額訴訟をする方・される方の中に未成年が含まれる場合、その方の戸籍謄本が必要となります。
未成年者が住んでいる地域を管轄する役所で申請します。1通450円の手数料が必要です。
ただし、未成年者が法人に対して未払い給与等の少額訴訟をするような場合、戸籍謄本は不要です。
アルバイトなどの給与が振り込まれていないケースでは不要なので覚えておきましょう。
訴状副本
訴状副本とは、訴状の写しのことです。裁判所に提出する1つを正本とし、それらをコピーしたモノが「訴状副本」と呼ばれ、これらは訴訟相手の人数分必要です。
訴状副本自体を作成するのに費用はかかりません。しかし、訴訟する方に対して送付することになるので、郵便切手代がその分かかってきます。
債権額100万円未満について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
少額訴訟の流れ
少額訴訟の流れを解説していきます。少額訴訟は1日で審理が終わるスピード感が特徴です。
間違いが起こらないよう、必要書類を集めしっかり内容をまとめておきましょう。
1.訴状の提出
必要書類を集めたら訴状を提出します。提出先は、訴訟相手の住所を管轄する簡易裁判所です。
訴状の内容をチェックして、請求する金額に準じた収入印紙を貼り付けましょう。
証拠、資格証明書または登記簿謄本(当事者に法人が含まれる場合)も提出しましょう。
2.訴状の審査
裁判所で訴状の審理をおこないます。訴状の不備などが見つかれば訂正や再提出が求められる場合もあります。
よくある不備としては、住所などの間違いや金額の間違い、請求の趣旨に原因がかかれているなどがあります。
請求の趣旨は結論のみで、請求の原因に理由や証拠等を記載するように注意しましょう。
言い回しなどは裁判所のHPから見本をダウンロードできますので、そちらを参考にしてください。
3.被告への訴状の送達
審理を通過することができれば、ついに訴訟相手に訴状が送達されます。相手が訴状を受け取ると、口頭弁論期日の決定といった手続きが進みます。
訴訟相手が受け取る書類は訴状の副本と、答弁書・事情説明書といった書類のほか、少額訴訟手続きの内容に関する説明などの書類も同封されています。
4.事前聴取
事前聴取では少額訴訟の事前準備として裁判所の書記官から事実確認や追加で必要な証拠の提出などが求められる場合があります。
もし事前聴取の連絡を受けた場合、速やかに要求された文書や証拠を準備して提出しましょう。
このとき、訴訟相手は答弁書の作成や送付をおこなっており、訴訟される側も事前聴取を求められる場合もあります。
いずれも裁判所が判断することですが、追加の証拠の提出などが求められると少額訴訟のメリットであるスピード感が遅くなってしまう恐れもあります。
なるべく必要がないように、訴状を提出する段階で完璧な状態にしておきましょう。弁護士などの専門家に相談しておくとより安心です。
5.答弁書の受け取り
訴訟相手から答弁書を受け取ったら、内容をチェックしましょう。答弁書には訴訟相手の言い分や反論が書かれています。
事実と異なる点や認識の相違がある点などをしっかり洗い出し、こちらの正当性を主張できるようにしっかり準備しましょう。
認識の相違があるような場合、話が平行線で進まなくなる恐れがあります。
もし相手が事実誤認をしているような雰囲気を感じ取れたら、事実を証明するための証拠品などを集めておきましょう。
6.口頭弁論期日(法廷での審理)
少額訴訟の口頭弁論は、裁判官と当事者がテーブルを囲むように着席します。それぞれが提出した訴状・答弁書・証拠品などを改めて裁判官が確認し、証人尋問などの証拠調べをおこないます。
時間はだいたい30分から2時間前後で終了することが大半です。お互いに認識の統一ができた場合、その場で和解を成立させることもできます。
7.判決
審理が完了したら、裁判官より判決が言い渡されます。判決内容に双方が合意できた場合、和解となります。
もしどちらかが納得しなかった場合、異議申し立てという手続きに移行します。
なお、少額訴訟では反訴はできません。通常の裁判と異なり、判決に納得がいかなかった場合、異議申し立てのみとなりますので注意しましょう。
8.和解
判決に双方が納得した、口頭弁論中に認識が統一され和解に至った場合、裁判所から「和解調書」が当日中に送達されます。
和解調書には、裁判所の判決である支払い命令や支払い期日・その他損害遅延金の取扱いなど、裁判で合意した内容が記されています。
もし万が一、この和解調書の内容に相手が背いた場合、強制執行といった手続きが可能です。しっかりと保管して相手の動きを追っておきましょう。
9.異議申し立て
裁判所から出された判決に納得がいかなかった場合、異議申し立てが可能です。少額訴訟の場合、反訴や控訴といった選択肢はありません。異議申し立てのみ可能なので注意しておきましょう。
簡易裁判所でおこなわれる通常訴訟の場合、異議申し立てや控訴をしたら地方裁判所の管轄となります。
しかし少額訴訟の場合、地方裁判所への控訴はできません。異議申し立てをしたら、通常裁判として同じ簡易裁判所で再度審理されることになります。
なお、異議申し立て後の判決にも納得いかなかった場合、再度異議申し立てはできません。また、控訴や反訴も不可能となります。
10.本訴
本訴とは通常のいわゆる裁判をするための訴訟のことです。ただし、通常の裁判は審理に1ヵ月以上かかることも容易に起こります。
本訴の場合も、訴状を提出するのは訴訟相手の住所を管轄する簡易裁判所です。
少額訴訟と異なる書式の訴状が必要となりますので、裁判所のHPや簡易裁判所で入手して作成しましょう。
11強制執行
和解した・本訴で勝利したにもかかわらず返済がない場合、強制執行が可能です。
なお、強制執行には「直接強制」「代替執行」「間接強制」という3つの種類がありますが、基本的には「直接強制」でおこなわれるのが一般的です。
少額訴訟はおこなうべき?やるべきケースを紹介
ここからは、少額訴訟をおこなうべき方の特徴や、少額訴訟が適しているケースについて解説していきます。
当てはまるモノがあれば少額訴訟がおすすめですので、ご自身の状況を整理して参考にしてみてください。
少額のトラブルである場合
数百万といった大きな金額ではない問題かつ、トラブルを自分で解決するのが難しそうなら少額訴訟はおすすめです。
こうした少額のトラブルは、たとえば個人間のお金の貸し借りや、勤め先の給与未払い、フリーランスの売掛債権の回収や、交通事故等による物損等が当てはまります。
なお、少額訴訟の基準である60万円は、債権の元本や物損等の代替品の金額だけでなく、慰謝料・違約金等全てを合計した金額である点に注意しましょう。
数ヵ月間滞納があり、違約金を請求しようとして60万円をオーバーしてしまうと、少額訴訟はできません。
利息の計算や慰謝料の適正額などは素人判断では難しいものです。もしかしたら少額訴訟ではなく通常の訴訟をしたほうが、慰謝料をとれるようなケースも珍しくありません。
迷ったり悩んだりした場合、弁護士などの専門家の無料相談を活用してみましょう。
早く解決したい場合
少額訴訟のメリットは審理などのスピードが、通常の訴訟に比べ早い点にあります。
「早急に債権を回収したい」「早くこのもやもやから解放されたい」という気持ちが強い方は、少額訴訟がおすすめです。
ただし、少額訴訟でも訴状に不備があればやり直しが求められることもあります。より確実性を求めている方は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
証拠をしっかり抑えてある場合
「お金を貸した際のLINEの文面が残っている」「請求書を送付した記録がしっかり残っている」など、「訴訟相手が債務者である」と明確に証明できる証拠がある場合、少額訴訟でしっかり取り立てできる可能性が高いです。
訴状への記載や事前聴取において、こうした証拠類は事実確認のため裁判所から提出を命じられる可能性が非常に高いです。
動かぬ証拠としてしっかり記録されているものがあれば、スムーズに審理を進め納得のいく判決を受けられるでしょう。
個人間のトラブルの場合
たとえば身内・友達に貸したお金が返ってこないという、個人間のお金の貸し借りは少額訴訟がおすすめです。
このようなケースでは、身近であるがゆえに強く主張できなかったり、曖昧な返事で交わされてしまったりして、貸した側の不満は日に日に大きくなっていきます。
また、感情的になったところで関係に亀裂が入り、回収できない可能性が高まることも考えなくてはなりません。
少額訴訟であれば、裁判所が間に入って強制的に話し合いの場を設けてくれます。第三者がいることでお互い冷静になり、和解案にも合意しやすくなるでしょう。
また、たとえ友達同士・親戚同士であっても、損害遅延金や利息の請求は可能です。処罰感情が大きい場合、そうした対応も念頭に入れておきましょう。
敷金が返ってこない場合
敷金は、賃貸住宅などの契約をしたときにオーナーに預け、解約した際に返金してもらえるお金です。しかし、中には敷金を返金してこない悪徳業者も存在しているため、このような悩みがある方にも少額訴訟はおすすめです。
引っ越しの際は荷物のまとめや役所への届出、免許証の住所変更手続きなどかなり慌ただしくなり、敷金の事がうやむやになりがちです。
悪徳業者はそうしたところに付け入り、何かと理由をつけて返金を先延ばしにしたりします。
しかし、敷金は本来契約した本人に返すのがルールです。少額訴訟をすれば、敷金の請求や、場合によっては損害遅延金の請求なども可能です。
面倒だからとあと回しにせず、断固とした対応をするよう心がけましょう。
未払いの給与請求をしたい場合
コロナ禍による業績低迷などにより、給与が払えないという中小・零細企業も存在しているでしょう。
少額訴訟をうまく使えば、給与の支払いを促せるだけでなく、損害遅延金や未払いの残業代なども請求できる可能性があります。
毎月決められた日に給与を振り込むのは、雇用契約によって定められた法律行為であり、経営状況等を言い訳にした給与未払いは、立派な契約違反行為です。
最悪の場合、給与未払いのまま会社が倒産し、経営者は資産をもって逃げ切るといった自体も想定されます。
給与の未払いは放置せず、即座に対応しましょう。
ツケの支払い請求をしたい場合
ツケの支払い請求をしたい場合、少額訴訟は有効です。訴訟されたという事実があるだけで、相手側はビジネスにおける信用に傷がつく恐れがあります。
少額訴訟をうまく利用することで、資金の回収がより容易になる場合があるのです。
日本の商習慣では、先に商品を納入し現金を徴収、請求書を月末日に数字だけまとめて送付するといった取引をしている業態・会社もまだまだ多いものです。
また、掛け取引としてあとから発注書と請求書を交換するような取引や、先に商品を納品し、翌月支払いの請求書を送るといった取引もあるでしょう。
納品者としては、代金の回収ができないまま消費税や所得税などを納めなければならないタイミングも出てきます。
特にフリーランスなどで活動している方の場合、少額でも資金の遅延は死活問題になりかねないので、ぜひ少額訴訟を検討してみましょう。
まとめ|少額訴訟は費用倒れに注意
少額訴訟の場合、弁護士費用が回収金額を上回る「費用倒れ」のリスクがあります。
しかし、無料相談自体は有効活用が可能です。手続きを自分で進める場合でも、一度相談しておくとより安心でしょう。
債権額100万円未満について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |