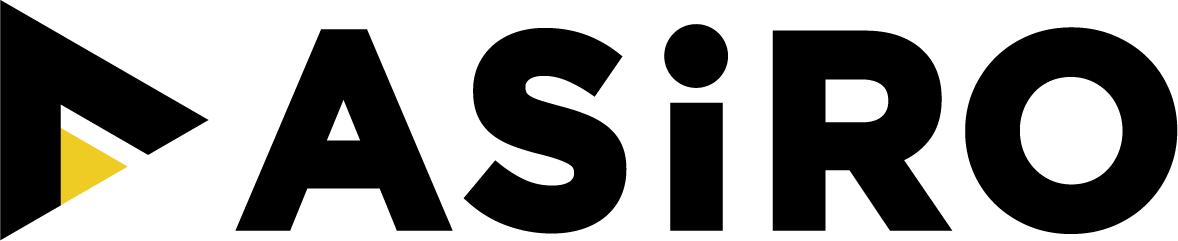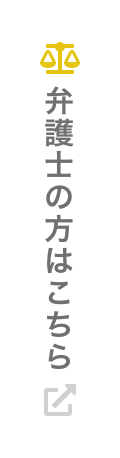- 「配偶者の不倫が原因で離婚するのに、財産分与は必要なのか」
- 「相手が悪いのに、財産を2分の1ずつ分けるのは納得いかない」
不倫した配偶者との財産分与で、このような悩みを抱えていませんか? 離婚の原因が相手にあるにもかかわらず、財産分与で公平な扱いとなることに不満をもつのは当然です。
本記事では、不倫が原因で離婚する場合も、財産分与は2分の1ずつが原則である理由や、そのことに納得できない場合にどのような選択肢があるか、相手と財産分与でもめた場合の対処法について解説します。
財産分与で損をしないためには、本記事で解説した知識を正しく把握しておくことが必要です。
本記事の内容を参考にすれば、配偶者が不倫して離婚をする場合の財産分与について、納得できるかたちで解決しやすくなります。
不倫が原因で離婚する場合も、財産分与は2分の1ずつが原則
不倫が原因で離婚する場合でも、財産分与は2分の1ずつが原則です。
財産分与は婚姻期間中に形成された共有財産を、夫婦が公平に分ける制度であり離婚の有責性を問うものではありません。
不倫の責任を追及するのであれば慰謝料を請求すべきであり、財産分与とは別の問題になります。
訴訟になった場合も、不倫の事実に関わらず財産分与は2分の1ずつとされることが多い
夫婦間の話し合いや調停の場で財産分与の問題が合意できない場合、訴訟で争うことになります。
仮に訴訟となった場合でも、不倫の事実に関わらず財産分与は2分の1ずつとされることが多いです。
話し合いで財産分与の割合を任意で変更するのは自由
夫婦の話し合いで離婚を決める協議離婚では、夫婦で自由に財産分与の内容や方法を決定できます。
お互いが納得しているときは、財産分与の割合を好きに変更しても構いません。
たとえば不倫した夫を3割、不倫された妻を7割にするといった取り決めも可能です。
このように、不倫によって離婚原因をつくった側が離婚の合意を得るために、条件面で相手に譲るケースも珍しくありません。
相手の不倫が原因で離婚するのに、2分の1ずつの財産分与に納得できない場合は?
相手の不倫が原因で離婚する場合、「2分の1ずつの財産分与では到底納得できない」というケースもあるでしょう。
「向こうが悪いのに、同じ取り分なのはおかしい」と思うのも当然です。
ここでは、2分の1ずつの財産分与に納得できないときの対処法や、財産分与の権利を強制的に放棄させられないことについて解説します。
不倫慰謝料を請求する
不倫された側は、財産分与とは別に不倫に対する慰謝料を請求できます。
不倫慰謝料は、配偶者が自分以外の者と肉体関係をもつことをさす「不貞行為」によって受けた精神的苦痛に対する賠償であり、財産分与とは別の性質をもつためです(民法第709条、第710条)。
慰謝料の相場は50万円〜300万円程度ですが、離婚に至ったかどうかで金額に大きな差が生じます。
- 離婚に至った場合:200万円〜300万円程度
- 婚姻関係を継続した場合:50万円〜100万円程度
また以下にあげるような要因によって、慰謝料の金額に差が生じる可能性があります。
| 慰謝料が高くなる要因の例 | ・婚姻期間が長い ・不倫期間が長い ・夫婦間に子どもがいる ・相手に資力がある ・不倫が原因で精神疾患を発症した ・不倫発覚後も不倫をやめなかった |
| 慰謝料が安くなる要因の例 | ・婚姻期間が短い ・不倫期間が短い ・不貞行為の回数が少ない ・W不倫をしていた ・不倫相手に資力がない |
慰謝料的財産分与を求める方法もある
不倫慰謝料ではなく、慰謝料的財産分与を求める方法もあります。
慰謝料的財産分与とは、通常の財産分与に慰謝料的要素を考慮する方法のことです。
財産分与と慰謝料請求を別々におこなう方法と違い、慰謝料的財産分与であればそれらを一括して解決させられます。
そのため慰謝料を請求したいが、早期に離婚を決めたい場合は慰謝料的財産分与を求める方法は適しているでしょう。
慰謝料請求を別個におこなうべきか、慰謝料的財産分与をおこなうべきかはケースによって異なります。
どちらが多くの慰謝料を獲得できるかは、一概には言えません。
そのためどちらの方法にすべきかは弁護士とよく相談して決めるとよいでしょう。
相手が悪いとしても、財産分与の権利を強制的に放棄させることはできない
いくら相手に非があっても、財産分与の権利を強制的に放棄させることはできません。
財産分与請求権は離婚する夫婦双方に認められた権利であり、財産分与と離婚の原因は無関係であるためです。
たとえば「相手が不倫したせいで離婚することになった」というような事情があっても、財産分与は、民法で認められている権利であり(民法第768条第1項)相手から一方的に財産分与請求権を奪えません。
そのため財産分与請求権を放棄してもらいたい場合は、相手方と話し合って納得してもらうしかありません。
ただし、相手に財産分与請求権を手放すことにメリットはないと考えられるため、単に「財産分与を諦めてほしい」と頼むだけでは納得しない可能性が高いでしょう。
たとえば「離婚に同意する代わりに財産分与を放棄してもらう」など、相手にとってのメリットを用意することが重要です。
不倫した配偶者と、財産分与でもめた場合の対処法
不倫した配偶者と財産分与でもめた場合の対処法として、以下の3つの方法があります。
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚訴訟を提起する
- 財産分与調停を申し立てる
不倫問題が絡む財産分与では、感情的に対立し話し合いが難航するケースも珍しくありません。
法的手続をおこない第三者が介入することで、客観的な視点から解決策を模索できるでしょう。
ここでは、それぞれの法的手続について解説します。
離婚調停を申し立てる
夫婦間の話し合いで解決できなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停とは、裁判官と調停委員が当事者の間に入り、双方の主張を聞きながら合意を目指す手続きです。
夫婦だけでの話し合いでは感情が先走りがちですが、調停ではお互い別室で待機するため直接顔を合わせることなく話し合いを進められます。
第三者を介すことで、感情的にならず冷静な判断ができるでしょう。
また、双方が納得する解決策を探るのが調停の目的であるため、時間がかかることはありますが、不倫された側に有利な割合で合意できる可能性があります。
双方が合意すれば調停は成立し、その日が法律上の離婚成立日となりますが、合意できなければ調停不成立で調停手続は終了します。
そのあとの流れは以下のとおりです。
| 調停が成立したとき | 1.調停調書の謄本を請求する 2.離婚成立日から10日以内に離婚届を提出する |
| 調停不成立で終了したとき | 裁判所が「調停に代わる審判」で審判離婚を命じるかどうか判断する 【審判離婚が命じられた場合】 2週間以内に異議申立てをしなければ離婚が成立 ※財産分与についても命じられる場合がある 【審判離婚が命じられなかった場合】 離婚訴訟を提起するか、離婚のみ調停で成立させたあと財産分与調停・審判を申し立てる |
なお、不貞をした配偶者が離婚を求めている場合、こちらが離婚に応じない限り、有責配偶者に該当する相手は離婚を請求することができません。
このような場合にまでこちらから離婚調停を申し立てるかについては、慎重に検討するとよいでしょう。
離婚訴訟を提起する
離婚調停不成立後、審判離婚が命じられなかった場合や審判離婚での審判に納得できないときは、離婚訴訟を提起します。
口頭弁論や尋問などのあとに、互いに合意できれば和解することも可能です。合意できない場合は、裁判所の判決によって解決をはかります。
離婚訴訟において財産分与は付帯処分のひとつとして審理され、激しく争われることが少なくありません。
被告・原告双方が互いに主張と証拠を提出し、裁判官が最終的な判決をくだします。
判決前に裁判官がその時点での心証(考え)を開示し、財産分与の問題を含め和解に至ることも多いです。
財産分与調停を申し立てる
すでに離婚が成立している場合でも、離婚後2年以内であれば財産分与について話し合うために調停を申し立てることが可能です。
申立てから1ヵ月程度で第1回調停期日が設定され、そこから1ヵ月程度の間隔で調停が繰り返されます。
なお、調停で合意できないときは自動的に審判へと移行し、裁判所がこれまでに話し合ったことや事情を考慮し、総合的に判断します。
配偶者が不倫した場合の財産分与を弁護士に相談・依頼すべき理由
配偶者が不倫したケースで財産分与を求める場合、弁護士に相談・依頼をすることが強く推奨されます。
理由は以下のとおりです。
- より有利な条件で財産分与を実現できる可能性が高まる
- 精神的な負担や労力を軽減できる
- 財産分与の対象となる財産を正確に把握できる
- 離婚の問題に対して総合的なサポートを受けられる
ここでは、財産分与の問題弁護士に相談・依頼すべきこれらの理由について解説します。
より有利な条件で財産分与を実現できる可能性が高まる
財産分与では、原則として夫婦で財産を2分の1ずつ分ける「2分の1ルール」が実務上の基準となっています。
弁護士に相談・依頼すれば、不倫問題に関する法的知識や交渉経験を活かし、より有利な条件で財産分与ができるよう対応してくれるでしょう。
また話し合いで解決せず調停や裁判へ移行した場合、当事者だけで法的根拠に基づく適切な主張をおこなうのは簡単ではありません。
その点、弁護士は調停委員や裁判官に対し適切に主張を提出してくれます。その結果、依頼人にとって有利な結果が出やすくなるのです。
精神的な負担や労力を軽減できる
不倫による離婚はとくに感情的になりやすく、当事者だけで交渉すると精神的に大きな負担がかかります。
不倫した配偶者だけならまだしも、不倫相手と交渉するとなればなおさらです。
しかし弁護士に相談・依頼すれば、相手方との交渉を全て弁護士に任せられます。
顔を合わせるストレスを感じずに済むことはもちろん、不倫された配偶者本人が交渉するよりも、こちらの要望を聞き入れてもらえる可能性が高いでしょう。
また、自分で全て対応する場合は書類作成や裁判手続も自分でおこなう必要があり、仕事をしている人は仕事の合間に動かなければなりません。
弁護士に任せれば書類作成や裁判手続も代行してくれるので、時間や労力をかけずに手続きを進められるでしょう。
財産分与の対象となる財産を正確に把握できる
弁護士に相談・依頼することで財産分与の対象となる財産を正確に把握できます。
不倫した配偶者が離婚後もより多くの財産を手元に残すため、財産を開示しなかったり隠したりすることも少なくありません。
配偶者の財産隠しが疑われる場合、弁護士は弁護士照会などの方法により相手の財産を調べることができるのです。
相手が財産を隠している場合、自分だけで調査するのは簡単ではないでしょう。
なるべく早く弁護士に相談・依頼して、損をしないよう対応を進めることが推奨されます。
離婚の問題に対して総合的なサポートを受けられる
弁護士に相談・依頼することで、離婚問題に対して総合的なサポートを受けられます。
弁護士には財産分与だけでなく、以下問題についても相談できます。
- 不倫慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
それぞれの問題は相互に関連しているため、総合的な視点から解決策を提案してもらえるでしょう。
不倫問題を含む離婚全体を見据えた交渉戦略を立てられるのは、弁護士ならではの強みです。
不倫した配偶者と財産分与を進める際の注意点
不倫した配偶者と財産分与を進める際は、以下の2点に注意しましょう。
- 合意内容は離婚協議書に残しておく
- 離婚届の受理から2年が経過すると財産分与請求権が失われる
以下、それぞれ詳細を解説します。
合意内容は離婚協議書に残しておく
財産分与について合意した内容は必ず書面化し、離婚協議書として残しておくようにしましょう。
離婚協議書とは、協議離婚の際に夫婦間で合意した離婚条件を書面化した契約書のことです。
協議は口頭でも成立しますが、あとから「言った・言わない」のトラブルになりやすく、法的効力の面でも問題が生じます。
しかし離婚協議書を作成しておけば、夫婦間の取り決めを客観的に証明できます。
離婚協議書は、公証役場で公正証書化しておくことが推奨されます。
公正証書とは、公務員である公証人が権限に基づいて作成する公文書です。
高い証明力と執行力をもち、原本は公証人が保管するため改ざん・紛失の心配がありません。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、相手が約束どおり支払わなかったときに裁判を経ることなく預貯金や給与を差し押さえられます。
離婚協議書の書き方や公正証書化の手続きには専門的なルールがあり、個人では難しいと感じる場合も多いでしょう。
手続きに不備があると、無効となったり期待した効果が得られなかったりする可能性も否定できません。
そのため弁護士に依頼して、作成や公正証書化の手続きを任せることが推奨されます。
離婚協議書作成について無料相談ができる弁護士の見つけ方については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】離婚協議書作成について無料相談できる弁護士の見つけ方と手続き方法
離婚届の受理から2年が経過すると財産分与請求権が失われる
財産分与請求権は、離婚の成立から2年で消滅します。
この2年という期限は「除斥期間」といい、時効とは違い進行を止められません。
離婚後でも財産分与は請求できますが、財産分与を請求しないまま離婚成立から2年が経過すると、家庭裁判所への申立てができなくなります。
たとえば、とりあえず離婚だけ成立させ、「財産分与については後日話し合おう」と曖昧にしてしまうと、気づけば請求権が消滅していたなどという事態になりかねないため注意しましょう。
ただし、離婚から2年以内に財産分与調停や審判を申し立てれば、調停・審判の間に2年が経過してしまっても、財産分与請求権は消滅しません。
また、2年が経過したあとでも、当事者間の合意があるなら任意での財産分与が可能です。
なお、2024年の民法改正により、財産分与請求権の除斥期間は2026年までに5年へと延長されることが予定されています。
ただし、改正法施行前に離婚から2年が経過したときは、5年の除斥期間は適用されません。
そのほか、除斥期間とは別に、財産分与が確定したあとの支払いや財産の移転に関する請求権には10年の消滅時効があります。
たとえば財産分与を分割払いでおこなっており、途中で支払いが滞った場合、定められた支払期日から10年間請求しなければ時効により請求できなくなります。
さいごに|財産分与をめぐるトラブルは弁護士に相談を!
不倫した配偶者との財産分与に納得できないときの対処法や、財産分与を弁護士に相談・依頼すべき理由などについて解説しました。
原則として、財産分与は夫婦で2分の1ずつ分けることとされており、それは相手が不倫をしたときでも変わりません。
2分の1ずつの財産分与に納得がいかないときは、相手に不倫慰謝料を請求したり、慰謝料も含めた慰謝料的財産分与を求めたりといった方法があります。
不倫した配偶者と財産分与でもめた場合は、離婚調停や訴訟、財産分与調停を申し立てるなどの方法で対処しましょう。
財産分与をスムーズにすすめるために、弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。
弁護士に相談することで、より有利な条件で財産分与を実現できる可能性が高まり、精神的な負担や労力を軽減できます。
また、相手が財産隠しをしようとしても、弁護士に依頼すれば見抜ける可能性が高まるでしょう。