確かな法律知識をお届けするために、法ナビ債務整理では、法律・弁護士業界に精通した編集部が記事を作成、全ての記事を弁護士が法律的に正しいかチェックしています。加えて、ベンナビに掲載中の弁護士から、無料相談対応の弁護士を探すことも可能です。あなたの悩みが一刻も早く解決するよう、ぜひご活用ください。



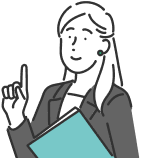
任意整理は、借金の返済負担を軽減する有効な手段ですが、人によっては任意整理が最適な解決方法とは限りません。 任意整理による借金の減額効果や、任意整理後のリスクについて十分に理解しておかないと、あとで後悔するケースもあるで...

突然の出費や生活費の不足などでお金が必要になったとき、カードローンや消費者金融などからの借金に頼る人は多いでしょう。 しかし、すでに多重債務に陥っている場合や、信用情報に傷がある場合には、どこからもお金を借りられないとい...

ジャックスの支払いをうっかり忘れてしまったり、お金が用意できなくて滞納してしまったりした場合、「少しくらい遅れても大丈夫だろう」と考えていませんか? ジャックスの支払いを滞納すると、遅延損害金の発生やカードの利用停止、さ...

dカードの支払いが遅れてしまったとき、「すぐに支払えば問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。 しかし、たとえ数日間の滞納でも、遅延損害金の発生やカードの利用停止などのリスクが生じます。 また、滞納が数ヵ月にわ...

イオンカードの支払いをうっかり忘れてしまったり、経済的な事情で滞納してしまった場合、「放置しているとどうなるの?」「すぐに何か対処すべき?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。 イオンカードを滞納すると、遅延損害金...

バンドルカードの「ポチっとチャージ」は、今すぐお金が必要なときに便利なサービスですが、返済を滞納してしまうとさまざまなデメリットやリスクが生じます。 「少額だから大丈夫」「少し遅れても問題ないだろう」と軽く考えていると、...

レイクへの支払いが遅れてしまい「このまま放置しても大丈夫だろうか」と不安になる人も多いでしょう。 返済を滞納すると、遅延損害金が発生するだけでなく、信用情報に傷が付いたり、最悪の場合は財産の差し押さえといったリスクに発展...

テレビCMやインターネットの広告などで、過払い金請求について知った人も多いのではないでしょうか? 過払い金請求は、かつて消費者金融などで借入れをしていた方にとって、払い過ぎたお金が戻ってくる可能性のある手続きです。 しか...

リボ払いに興味があるものの「リボ払いはやばい」という評判を耳にして利用をためらっている人も多いのではないでしょうか。 リボ払いは、毎月の返済額が一定で家計管理がしやすい一方で、仕組みを正しく理解していないと深刻な返済地獄...

自己破産を検討している方にとって、「借金の免除が認められなかったらどうしよう」と不安になるのは当然のことです。 自己破産では、裁判所が借金の返済義務を免除する「免責許可」を出すかどうかを判断しますが、その際に問題となるの...
