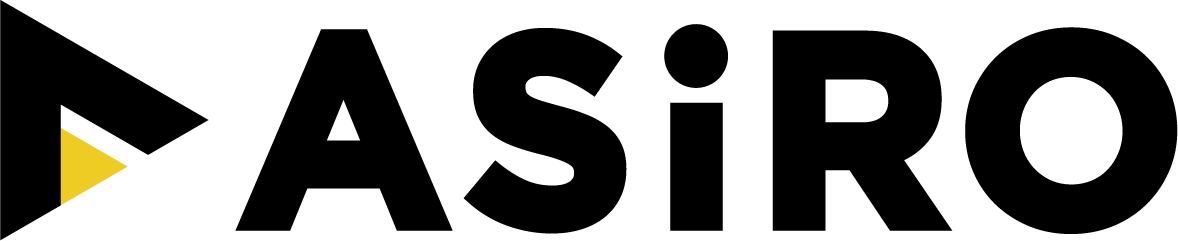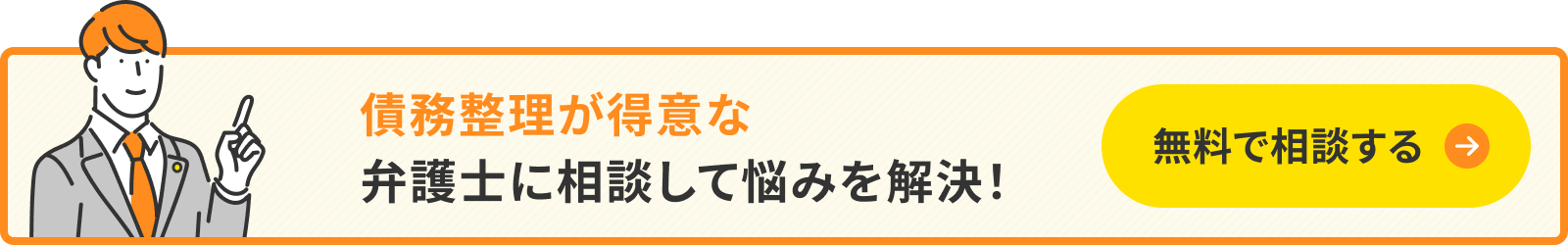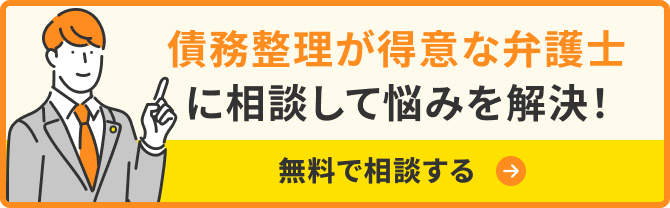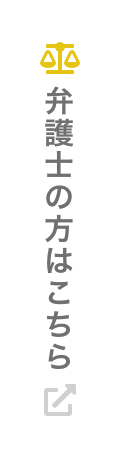支払い過ぎた利息の返金を求めるのが、過払い金請求という手続きです。
過去に消費者金融から借り入れをおこなったことがあり、過払い金請求を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、そもそもどのようなケースで過払い金請求が可能なのか、どのようなメリット・デメリットがあるのかなど、あらかじめ正しい知識を身につけておきたいものです。
本記事では、過払い金請求のデメリットや過払い金請求が失敗するケース、デメリットを回避する方法などを解説します。
請求できる条件や請求方法なども紹介するので、支払い過ぎたお金を取り戻したい方は参考にしてください。
過払い金請求のデメリット・リスク
まずは、過払い金請求をおこなうことでどのようなデメリット・リスクがあるのかを押さえておきましょう。
1.ブラックリストに載る可能性がある
返済中に過払い金請求をおこなうと、クレジットやローンなどの信用情報を管理する「信用情報機関」に事故情報が登録される可能性があります。
このように信用情報機関に事故情報が登録されることを、一般的に「ブラックリストに載る」と言います。
ブラックリストに載ってしまうと審査に影響が出て、クレジットカードを新規作成できなくなったり、ローンの審査に落ちてしまったりするおそれがあります。
2.過払い金請求先のクレジットカード・借入れが利用できなくなる
過払い金請求をおこなうと、請求した業者から借り入れができなくなったり、クレジットカードが利用できなくなったりする可能性があります。
業者によって対応は異なるため一概にはいえませんが、契約が強制解除されたり、新規契約を受け付けてもらえなくなったりすることも少なくありません。
3.書類や手続きの過程で家族にバレる可能性がある
過払い金請求する際は、基本的に債権者と書面でやり取りをおこなうことになります。
その際、自宅に書類が送られてきて家族に知られることもありますし、必要資料などを準備しているところを家族に見られて発覚することもあるでしょう。
4.費用倒れになる可能性がある
過払い金の計算は複雑であるうえ、素人では債権者との交渉が難航する場合もあるため、弁護士などに手続きを依頼するのが一般的です。
ただし、過払い金が少額のケースなどでは、回収額よりも弁護士費用のほうが高くなって「費用倒れ」になってしまう可能性があります。
過払い金請求のデメリット・リスクを回避する方法
ここでは、上記のようなデメリット・リスクを回避する方法を解説します。
不安な点は事前に弁護士に相談する
過払い金請求に関する不安がある場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
過払い金請求が得意な弁護士であれば「具体的に何をすればよいのか」「全額回収するためにどうするべきか」など、状況に応じた的確なアドバイスが望めます。
弁護士事務所の中には初回相談無料のところもあり、相談時に見積もりを出してもらうこともできるため、費用面が不安な方もまずは相談してみましょう。
借金を完済してから過払い金請求をする
過払い金請求をするとブラックリストに載る可能性がありますが、これはあくまでも借金返済中の場合に限られます。
借金を完済してから過払い金請求をおこなうのであればブラックリストには載らないため、経済的に可能な場合はまずは完済を目指しましょう。
あらかじめクレジットカードを作成しておく
過払い金請求をすると、請求先のクレジットカードが利用できなくなったり、クレジットカードの新規作成ができなくなったりする可能性があります。
過払い金請求後もクレジットカードを利用したい場合は、請求前に他社でクレジットカードを作成しておくと安心でしょう。
過払い金請求のメリット
過払い金請求をおこなうと、主に以下のような3つのメリットがあります。
- 支払いすぎた利息が戻ってくる
- ブラックリストに載らずに済む
- 裁判をしないで済む可能性が高く、負担が軽い
1.支払いすぎた利息が戻ってくる
過払い金請求をおこなう最大のメリットは、支払いすぎた利息が戻ってくることでしょう。
そもそも、過払い金は本来支払う必要のなかったお金です。
適切に請求手続きをおこなえば支払いすぎた分をしっかり回収できますし、「50万円ほど借り入れていたが30万円近く戻ってきた」というようなこともあり得ます。
また、過払い金に5%の法定利息分をつけて回収できることもあります。
その際は貸金業者側に悪意があったことを示さなければなりませんが、ほとんどの貸金業者は過払い金の事実を知っていたはずなので、証明はさほど難しいことではないでしょう。
2.ブラックリストに載らずに済む
過払い金請求をおこなっても、借金を完済している状態であれば信用情報機関に事故情報が載ることは基本的にありません。
過払い金請求は正当な行為であり、それだけでマイナスの評価を受けるものではないからです。
ただし、借金を全額返済できていない場合は、過払い金請求をおこなう中で事故情報が登録されるケースもあるため注意してください。
3.裁判をしないで済む可能性が高く、負担が軽い
過払い金請求は、裁判をしなくても直接交渉で、あまり時間や手間がかからずに回収できる可能性が高いという点もメリットといえます。
相手方の対応次第では交渉で解決することも十分可能ですが、利息まで回収したい場合には基本的に裁判を起こす必要が高いでしょう。
任意交渉で済ませるか裁判を起こすかは、弁護士とよく相談して決めましょう。
過払い金・過払い金請求の基礎知識
ここでは、過払い金請求をおこなう際に知っておくべき知識について解説します。
過払い金・過払い金請求とは
以下では、過払い金や過払い金請求の定義について解説します。
過払い金とは「貸金業者に支払い過ぎた利息」のこと
過払い金とは、貸金業者に対して支払い過ぎた利息のことです。
2010年6月17日以前に借り入れをおこなっている場合、法律で定められた上限金利を超えて利息を支払っている可能性があります。
上限金利を超えた利息は無効となるため、本来支払うべきだった金額との差額を返金してもらえるわけです。
過払い金請求とは「支払い過ぎた利息の返還を求める手続き」のこと
過払い金請求とは、支払い過ぎた利息の返金を求める手続きのことです。
過払い金は、自動的に返金されるわけではありません。
こちらから適切な方法で請求しなければ取り戻せないため注意してください。
また、貸金業者の利用者全員が過払い金請求できるわけではない、ということも理解しておきましょう。
後述するように、各種条件を満たしているのであれば、支払い過ぎたお金を回収できる可能性があります。
過払い金請求ができる条件
次に、過払い金請求ができるかどうかの判断基準を解説します。
主に2つの判断基準があり、どちらも満たしている場合は過払い金請求を前向きに検討しましょう。
1.2010年6月17日以前に借り入れを開始している
2010年6月17日以前に借り入れを開始している場合は、過払い金請求できる可能性があります。
多くの貸金業者において法律の上限を超える金利が設定されていたのは、2010年6月17日以前です。
当時の上限金利には、以下のような2つの基準がありました。
- 出資法(年29.2%)
- 利息制限法(年15.0%〜20.0%)
利息制限法の上限を超えていても、出資法の29.2%を超えていなければ刑事罰は科せられませんでした。
この上限金利の差は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの賃金業者が利用していました。
現在では利息制限法の上限金利を超える部分は無効となり、無効部分の金銭の返還を求めることが認められるようになったというわけです。
たとえば、100万円の借り入れであれば利息制限法の上限金利は年15.0%です。
しかし、2010年6月17日以前にグレーゾーン金利の25.0%が適用されていた場合、2 5.0%-15.0%=10.0%分を返金してもらえる可能性があります。
2010年6月18日に出資法の上限金利は20.0%に改正され、グレーゾーン金利は解消されました。
2.借金を完済してから10年以内である
借金を完済してから10年以内であることも、過払い金請求をおこなうための条件です。
なぜなら、過払い金請求権は「最後の返済日から10年」で消滅時効となり、権利を失うからです。
たとえば、2015年1月1日に完済している場合、2025年1月1日までに請求手続きをおこなわなければ過払い金を回収できなくなります。
ただし、2020年4月1日以降に完済している場合には、民法が改正された関係で「最後の返済日から10年」または「過払い金請求できることを知った日から5年」のどちらか早いほうの時効が採用されます。
過払い金請求が失敗する5つのケース
次のいずれかのケースに該当する場合は、過払い金請求ができない可能性が高いと考えられます。
1.過払い金の返還請求が難しい業者と取引している場合
そもそも、過払い金の返還請求が難しい業者も存在します。
全ての貸金業者がグレーゾーン金利を設定していたわけではないからです。
当然、適正な金利が適用されていれば、そもそも過払い金自体が発生していないということになります。
過払い金請求が難しい業者と請求できる可能性がある業者は、以下のとおりです。
| 過払い金請求が難しい業者 | モビット・オリックス・キャッシュワン・アットローン・ダイレクトワン・銀行・公庫 など |
| 過払い金請求できる可能性がある業者 | アコム・プロミス・アイフル・レイク・セゾン・オリコ・ニコス・エポス・イオン・シンキ・セディナ・CFJ・ポケットカード・高島屋カード など |
2.貸金業者がすでに倒産している場合
貸金業者がすでに倒産してしまっている場合、当然過払い金は返ってきません。
過払い金請求をして回収ができるのは、相手が正常な会社経営を続けている場合に限ります。
たとえば、以下のような貸金業者からは回収できません。
- クロスシード
- 武富士
- クラヴィス
- ネットカード
- SFコーポレーション など
なお、会社が倒産する際には、通常債権者に対して一定の清算がおこなわれます。
過払い金請求権も債権のひとつであるため、本来の過払い金よりは少額になるケースがほとんどですが、数%程度を回収できる可能性はあるでしょう。
とはいえ、貸金業者が倒産しないうちに満額回収することが大切なので、できるだけ早く行動に移しましょう。
3.利用方法がキャッシングではなくショッピングの場合
キャッシングではなくショッピング利用やショッピングリボ払いを利用していたケースでは、過払い金請求は認められません。
なぜなら、ショッピング利用はカード会社に利用代金を立て替えてもらっているに過ぎないからです。
このため、利息制限法の対象とはなりません。
また、ショッピングリボ払いで支払うお金は利息ではなく手数料です。
単なる手数料は出資法や利息制限法の対象外であるため、過払い金とは一切関係がありません。
4.過払い金請求の時効が成立している場合
「過払い金請求ができる条件」で解説したように、すでに時効が成立している場合は請求権が消滅するため過払い金は戻ってきません。
ただし、素人では時効の判断が難しいこともあるため、正確な状況を知りたい方は弁護士に相談することをおすすめします。
5.銀行カードローンや自動車ローンを利用している場合
銀行カードローンや自動車ローンなどについては、そもそも利息制限法内で金利を設定しているため過払い金は発生しません。
たとえ長年利用していた場合でも、過払い金請求の対象外となります。
過払い金請求の手続きの流れ
ここでは、自分で過払い金を請求する場合の手順について解説します。
- 取引履歴の開示請求をおこなう|1週間~1ヵ月程度
- 過払い金の引き直し計算をおこなう
- 貸金業者へ過払い金返還請求書を送付する
- 貸金業者との和解交渉をおこなう|1ヵ月~3ヵ月程度
- 過払い金が返還される|和解交渉後から1ヵ月~3ヵ月程度
なお、過払い金請求は自分でおこなうことも出来なくはないですが、出来るだけ多くの金額を回収するのであれば弁護士に依頼したほうが無難です。
自力での手続きが不安な場合や出来るだけ多くの金額を回収したい方は、弁護士に依頼することを検討しましょう。
1.取引履歴の開示請求をおこなう|1週間~1ヵ月程度
まずは、取引履歴の開示請求をおこないます。
過払い金の額を確定させるためには、そもそもいくら支払ったのかを明らかにしなければなりません。
そのため、貸金業者が保管している取引履歴を送付してもらう必要があります。
開示請求への対応スピードは、業者によってさまざまです。
早ければ1週間、遅い場合だと1ヵ月程度かかることも珍しくありません。
なお、開示請求を受けた貸金業者は、情報を開示する義務を負います。
取引履歴が1ヵ月以上送られてこない場合や、開示を拒否された場合は法律違反にあたるかもしれません。
2.過払い金の引き直し計算をおこなう
取引履歴が明らかになったら、過払い金の計算をおこないましょう。
現在の上限金利で利息を計算し、実際に支払った利息から差し引くことで算出できます。
しかし、利息の計算は複雑になるケースも少なくありません。
たとえば、うるう年がある場合や遅延損害金を支払っている場合などは、特殊な計算方法を用いる必要があります。
計算を誤ると過払い金が少なくなったり、請求に応じてもらえなくなったりするため注意してください。
3.貸金業者へ過払い金返還請求書を送付する
過払い金が計算できれば、貸金業者に過払い金返還請求書を送付します。
決まった様式はありませんが、債権者の氏名・住所・連絡先・過払い金の額・振込先口座などを記載するケースが一般的です。
引き直し計算書もあわせて送付しておくとよいでしょう。
4.貸金業者との和解交渉をおこなう|1ヵ月~3ヵ月程度
過払い金返還請求書を送付したあとは、業者側と和解交渉を進めます。
過払い金の額・支払い方法・支払い時期などを具体的に決めていきましょう。
しかし、個人で交渉する場合、業者によってはまともに応じようとしないこともあります。
時間をかけずに満額回収を目指したいのであれば、弁護士などのサポートが欠かせません。
問題なく合意形成がなされた場合、あとは過払い金の返還を待つだけです。
交渉不成立の場合は過払い金返還請求訴訟を起こす
和解交渉が成立しなければ、過払い金返還請求訴訟を起こす必要があります。
正しい順序で適切な額を請求している場合は、訴訟によって過払い金を回収できる可能性は高いといえるでしょう。
しかし、訴訟を起こすとなると訴状の作成や証拠収集などを進める必要があるため、法律の知識のない個人が自力で対応するのは困難です。
訴訟に至ったときは、弁護士に依頼するのが賢明な判断といえるでしょう。
5.過払い金が返還される|和解交渉後から1ヵ月~3ヵ月程度
和解交渉や裁判の結果、こちら側の主張が認められれば、1ヵ月~3ヵ月程度で過払い金が返還されます。
基本的には、過払い金返還請求書に記載した口座に振り込まれるため、金額に誤りがないかを必ず確認しておきましょう。
過払い金請求に関するよくある質問
次に、過払い金請求に関するよくある質問について解説します。
同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Q1.借金返済中でも過払い金請求はできる?
借金を返済している途中でも、過払い金請求はできます。
ただし、過払い金請求をおこなって借金が残ってしまった場合は、債務整理と同様の扱いになるため注意が必要です。
信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードやローンの利用が制限されてしまいます。
まずは借金を完済したうえで、過払い金請求をおこなうようにしましょう。
Q2.過払い金請求は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべき?
過払い金請求は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士なら相手方との交渉はもちろん、裁判を起こすことも可能です。
司法書士の場合、交渉や訴訟が認められているのは一部の認定司法書士に限られます。
さらに、簡易裁判所での訴訟にしか対応できないため、控訴・上告する場合は弁護士に頼らざるを得ません。
また、司法書士は1件あたり140万円以下の案件しか扱えないという点にも注意してください。
借入額が140万円を超える場合、選択肢は弁護士だけに絞られます。
弁護士は司法書士よりも費用が高い傾向にはあるものの、過払い金請求については安い費用で受けている弁護士も多いため、そのような弁護士を探して依頼するのがおすすめです。
【関連記事】過払い金請求の無料相談窓口5選|弁護士に相談するメリットとポイント
Q3.弁護士費用が過払い金よりも上回ってしまう可能性はある?
なかには、回収できた金額よりも弁護士費用のほうが上回ってしまうこともあります。
弁護士に依頼する際には、相談料や着手金などの弁護士費用を支払う必要があります。
過払い金の回収に失敗した場合などは、当然のことながら相談料や着手金を支払った分だけ損することになります。
ただし、法律事務所によっては相談料や着手金が無料に設定されているケースもあります。
そのような事務所であれば初期費用無しで依頼でき、過払い金を取り戻せた場合はそこから成功報酬を支払って、手持ちのお金を一切持ち出さずに済むこともあります。
Q4.過払い金請求をするとローンは組めない?クレジットカードは使えない?
借金返済中に過払い金請求をしてブラックリストに載ってしまった場合は、クレジットカードを新規作成できなくなったり、ローンの審査に落ちてしまったりするおそれがあります。
一方、借金完済後に過払い金請求をおこなえば、基本的に審査などにも影響せずに問題なく利用できます。
さいごに|過払い金請求を考えているなら早めに弁護士に相談を!
過払い金請求を考えている場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
過払い金請求権には「最後の返済日から10年」「過払い金請求できることを知った日から5年」などの時効があります。
権利を失ってしまう前に過払い金請求をおこなうことで、本来支払うべきではなかったお金を回収できます。
ただし、素人では適切に請求手続きを進められず、返還される金額が少なくなってしまうおそれもあります。
その点、弁護士に依頼すれば満額回収できる可能性が高まるうえ、もともとの返済額に利息を上乗せできるかもしれません。
相談料や着手金を無料にしている法律事務所も多いので、まずは過払い金の請求について気軽に相談してみましょう。