
確かな法律知識をお届けするために、法ナビ刑事事件では、法律・弁護士業界に精通した編集部が記事を作成、全ての記事を弁護士が法律的に正しいかチェックしています。加えて、ベンナビに掲載中の弁護士から、無料相談対応の弁護士を探すことも可能です。あなたの悩みが一刻も早く解決するよう、ぜひご活用ください。


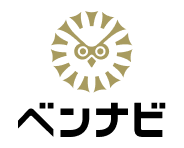
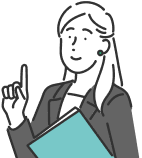
痴漢をしてしまったら、その場では逃げたり解放されたりしても、あとから逮捕されるケースは決して珍しくありません。 被害者や目撃者の証言が集まったり、防犯カメラで犯人が特定されたりすることがあるからです。 痴漢の加害者になっ...

捜査機関による逮捕は捜査機関が無制限に行うことができるわけではなく、一定の逮捕要件が必要とされています。 また、逮捕された被疑者の身柄拘束には一定の期限があるため刑事手続は非常にスピーディーに進みます。 そのため、逮捕さ...

自動車を運転中に不注意で人にけがを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪が成立して刑事処分や行政処分などを受ける可能性があります。 事故を起こしてしまった方のなかには「自分にはどのような刑罰が科されるか心配」「減刑のために...

刑事事件を起こしてしまった加害者の方の中には、経済的な理由から法テラスへの相談・依頼を考えている方もいるのではないでしょうか。 しかし、結論からお伝えすると、刑事事件について法テラスで相談・依頼することはできません。 刑...

窃盗罪で捕まってしまった場合、初犯であれば前科がつかない可能性もあります。 前科がつかないようにするためには、信頼できる弁護士をなるべく早く探し、被害者との示談交渉を進めることが推奨されます。 盗んだ物の金額や悪質さによ...
未成年者と「みだらな行為」をしてしまい、逮捕されるのではないかと不安に感じていませんか? 「自分のケースは「淫行」にあたるのか?」「逮捕や起訴を免れるにはどうしたらよい?」などの疑問を抱えている方も多いでしょう。 本記事...

「大麻所持で検挙されたら、初犯でも実刑を受けるのだろうか。」 「大麻所持の初犯で検挙されたらどうなるだろう。」 大麻を所持していたら、大麻取締法違反で検挙・逮捕されます。 ただ初犯であれば、「不起訴や執行猶予ですむのでは...

殺人は極めて重大な犯罪であり、その刑事手続・裁判を受けるにあたり弁護士による法的支援が欠かせません。 弁護士との相談は原則有料ですが、刑事事件であれば当番弁護士制度を利用することで無料相談ができます。 また、無料法律相談...

「些細なけんかのつもりが被害届を出された」 「家族が暴行罪で逮捕されてしまった」 このようなときには、できる限り早く弁護士に相談をしましょう。 弁護士に相談・依頼することで、長期間の勾留を回避できたり、不起訴処分などを獲...

「他人を脅してお金を奪った」 「家族が恐喝罪で警察に逮捕された」 このような恐喝事件に関するトラブルは、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。 本記事では、恐喝罪について弁護士と無料で相談できる窓口について...
