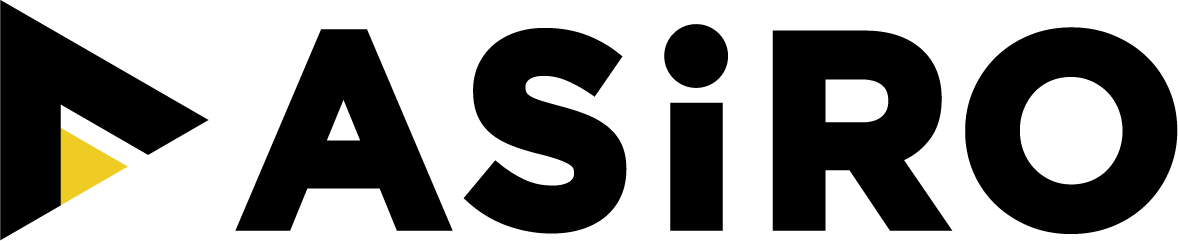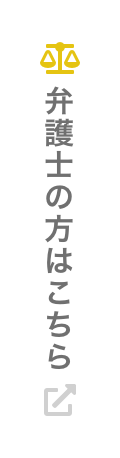売掛金が回収できずに困ったとき、弁護士に依頼することで回収できる可能性をぐんと高めることができます。
売掛金は、そのまま放置しておくと取引先が経営破綻してしまうリスクもあるため、できるだけ早く、確実に回収するために、弁護士の力を借りるのがおすすめです。
本記事では、弁護士に相談をするメリットや売掛金回収のおおまかな流れ、依頼する際の費用相場について解説します。
売掛金回収は弁護士に依頼することをおすすめする5つの理由
なかなか支払われない売掛金の回収に自社で取り組むのは、困難な場合が少なくありません。
本項では、売掛金回収を弁護士に依頼することをおすすめする5つの理由を解説します。
弁護士が関わるだけで、相手方が態度を改める可能性がある
これまで支払いが滞っていた相手であっても、弁護士から連絡をするだけで態度が大きく変わることが少なくありません。
弁護士は法律や訴訟のプロフェッショナルです。
そのため、「このままでは訴えられてしまうかもしれない」と考え、支払いに応じてくれやすくなるのです。
法的な回収手続きをスムーズに実行できるようになる
債権回収の手続きは、法律の専門知識を必要とする種類が多いです。
内容証明郵便の作成・発送、支払督促、通常訴訟、強制執行といった手続きに慣れている方は少ないでしょう。
仮に無理をして自分たちだけですすめても、不備があれば無効になってしまいます。
その点、法律知識が豊富な弁護士に依頼すればこれら手続きをスムーズに実行してくれるのです。
これにより債権回収の効率が大幅に向上します。
スピーディーかつより確実に回収できる可能性が高まる
売掛金は、なるべく早く回収するべきものです。
回収が遅れるほど相手方の経済状態が悪化してより回収が困難になったり、ほかの債権者に先を越されたりします。
また回収が遅れれば、相手方が自己破産などの手続きをとり、回収が事実上不可能になる可能性も否定できません。
弁護士は状況に応じた最適な回収方法を選択し、自社でおこなうよりずっとスピーディーにそれらを実行してくれます。
その結果、売掛金をより迅速かつ確実に回収できる可能性が高まるのです。
相手との交渉を全て任せて経営に専念できるようになる
弁護士に売掛金回収を任せる重要なメリットとして、経営に専念できるということがあります。
支払うべきお金を期日までに支払わない債務者を相手として、交渉をおこなうのは容易なことではないでしょう。
催促をしても支払いがなされない場合、内容証明の送付などを検討することになります。
弁護士でなくとも内容証明を送ることは可能ですが、知識なく効果的な文章を作成するのは簡単ではありません。
さらに、裁判所を通じた法的措置を講じる場合は、複雑な書類作成・証拠集め・裁判所とのやりとりなどが発生します。
弁護士に任せれば、全て代わりにおこなってくれるため、自社でこれらの作業をしなくて済み、ほとんど結果を待つだけでよくなります。
経営に専念することができるため、売上減少や機会損失を防ぐことにつながります。
精神的な負担を軽減できる
売掛金回収を弁護士に任せることで、債権者にかかる精神的な負担を軽減できます。
支払いを催促される側の債務者だけでなく、債権者にとっても売掛金回収は精神的に大きな負担がかかる手続きです。
経済状況が悪い相手方に対して、支払いを催促するのはストレスになります。
相手方と言い合いになることも少なくありません。
また面倒で難しい法的な手続きについて自分で調べたり、裁判所とやり取りしたりしながら進めるのもストレスが大きいでしょう。
弁護士に依頼すれば、これら交渉や手続きをほぼ全て任せることができます。
その結果、精神的な負担を軽減できるわけです。
売掛金回収のおおまかな流れ
売掛金回収はどのようにおこなうのでしょうか。
本項では、おおまかな流れをみていきましょう。
1.まずは相手に連絡して未入金の理由を明確化する
まずは、相手に電話などで連絡をして、未入金の理由をヒアリングします。
相手方の単純なミスで支払いが遅れている場合は、すぐに支払ってもらえるでしょう。
一方で「今は金銭的に厳しいので待ってほしい」や「業者から入金がなく支払えない」といった理由なら、対応を検討しなくてはなりません。
2.支払いを催告する
約定日まで入金がなく、それが相手方の単純なミスでない場合はすぐに対応をはじめるべきです。
まずは、改めて支払いを催促することになります。
内容証明郵便を送付する
相手方に支払いを催促する際は、内容証明郵便を使うことが推奨されます。
内容証明郵便は、相手に送った書類の謄本が郵便局にも保管される特殊な郵便で、「いつ、誰が、誰に、どのような内容を送ったか」を、郵便局が証明してくれます。
そのため、相手は「聞いていない」「書類が届いていない」などと言い訳をすることができません。
仮に裁判になった場合も、内容証明郵便を使えば、相手へ催促をしたことを示す有力な証拠となります。
また弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便が送付されると、相手方は「支払わないままだと裁判を起こされるかもしれない」とプレッシャーを感じるでしょう。
その結果、相手が支払いに応じてくれる可能性が高くなります。
3.取引を停止する
催告をしても支払いがない場合、なるべく早く取引を停止します。
相手が支払えない状況であれば、こちらが納品を続けても、さらに払ってもらえない売掛金が増えてしまうばかりなので、損失が大きくなってしまいます。
一般的には、契約書において売掛金の未払いが発生したら取引を停止するという条項が掲げられているため、取引を停止しても問題ありません。
また、契約書に記載がない場合でも、民法第533条では、相手に支払いがないという未履行があるときに納品という対応する自社の履行をする必要はないという旨が定められています。
これを同時履行の抗弁権といいます。同時履行の抗弁権を行使するにはいくつかの条件がありますが、弁護士に依頼すれば、条件にあてはまるかどうかを判断してもらうことができます。
4.状況に適した法的手続きを取る
催促をしても支払いがおこなわれない場合、何らかの法的手段を検討しなくてはなりません。
具体的な手段としては、以下があげられます。
民事調停|調停委員の仲介のもと弁済について話し合う
民事調停とは裁判所が任命した調停委員に仲介してもらいながら、話し合いにより問題を解決する手続きです。
法的手段による売掛金回収のなかでも、民事調停は費用が低額なうえに手続きも簡単です。
そのため民事調停は自社でおこなうこともできます。
ただし弁護士に依頼した方が、調停委員を納得させられるような法的な主張立証をしやすいでしょう。
また裁判所とのやり取りも任せられるので、負担も軽減できます。
支払督促|裁判所を介して支払いの催促をおこなう
支払督促とは、裁判所を介して支払いを促す手続きです。
債権者が裁判所へ申し立て、裁判所から支払督促という書類を相手へ送付します。
相手から異議がなければ、段階を経て強制執行へと移行することができます。
支払督促の申し立て自体は、裁判所が提供している書式を使って簡単におこなうことができます。
しかし、相手からの異議申し立てがあれば通常訴訟に移行するか否かを決定しなければならないため、弁護士に相談してから手続きをするのがおすすめです。
保全処分|債務者の財産が散逸するのを未然に防ぐ
保全処分とは債務者が財産を処分することを防ぐ手続きです。
債務者が財産を処分してしまうと、将来的に勝訴判決を得ても売掛金回収ができなくなってしまいます。
保全処分によって、財産が散逸してしまうのを防ぎ、確実に売掛金を回収できるようにするのです。
保全処分は、仮差押えと仮処分の2種類に分類されます。
まず仮差押えとは裁判所が債務者の金銭債権を暫定的に差し押さえて、その財産が処分されてしまうのを防ぐことです。
たとえば銀行預金が仮差押えされると債務者は預金を引き出せなくなり、不動産が仮差押えされると債務者は不動産を売却できなくなります。
一方で仮処分とは、金銭債権以外の債権を保全するための手続きです。
金銭債権以外は仮差押えができないため仮処分が用意されています。
言葉の説明だけでは分かりづらいかもしれないので、一例を出しましょう。
たとえばA社がB社に商品を売却しB社がお金を支払ったにも関わらず、その商品が引き渡されなかったとします。
その間に、A社が第三者に商品を引き渡してしまえば、B社は商品を手にすることができません。
この場合は、B社は仮処分により商品が散逸してしまうのを防ぐのです。
仮処分によって保全されるのは、「所有権に基づく(物の)引渡請求権」になります。
訴訟手続|裁判を起こして支払いを求める
相手が督促や調停に応じないであろうときは、訴訟手続きで支払いを求めることができます。
裁判の判決というかたちで支払いを命じることによって、相手が売掛金を支払ってくれる可能性は格段に高くなります。
相手方は敗訴すれば、素直に支払いに応じてくれ強制執行までせずとも済むことが少なくありません。
相手が支払わなければ、強制執行により相手の財産を差し押さえることも可能です。
しかし、勝訴すれば必ず売掛金が回収できるというわけではありません。
いくら裁判所が支払いを命じても、財産がなければ相手はお金を払うことができないからです。
そうなると、せっかくの勝訴判決も無駄になってしまいます。
そのため、先に紹介した保全処分を事前におこない仮差押えをしておくなど、相手の状況を見極めたうえで適切な手続きを選ぶことが肝心です。
強制執行手続|強制的に財産を差し押さえる
裁判をして相手が支払うべき確定判決が出た場合や、調停をおこなって調書として支払うことが決定した場合、それでも相手が売掛金を支払わなければ、裁判所に強制執行を求めることができます。
たとえば、債権執行として銀行預金を差し押えることができます。
回収すべき金額の範囲内であれば、差し押さえた預金残高は回収可能です。
また、相手がお金を直接受け取る予定がある、別の取引先が判明している場合は、相手に支払われる前に差し押えることができます。
弁護士に売掛金回収を依頼した場合の費用相場
売掛金回収を弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
依頼内容ごとのおおまかな相場を紹介します。
| 催告書・支払督促 | 書面作成のみなら3~5万円程度。催告書送付のあとの交渉も依頼するなら着手金10万円程度で、成功報酬は回収額の10~16%程度。 支払い督促を依頼した場合の着手金は請求額の1~2%程度で、成功報酬は回収額の5~8%程度。 |
| 任意交渉 | 着手金は請求額の5~8%程度(最低額10万円)、報酬は回収額の7~10%程度。 |
| 民事調停 | 着手金は請求額の5~8%程度(最低額10万円)、報酬は回収額の7~10%程度 |
| 訴訟 | 着手金は5~8%程度(最低額10万円)、報酬は回収額の10~16%程度 |
| 仮差押え・仮処分 | 着手金額は請求額の2.5%~4%程度(最低額10万円)、報酬については、仮差押え・仮処分の命令が得られたことを報酬発生の条件とする場合には被保全債権(請求額)の3~5%程度。 しかし、本案(訴訟)の報酬を含め、回収できたときを報酬発生の条件とすることも多く、その場合には訴訟の報酬を含め、回収額の10~16%程度が報酬となる。 |
| 強制執行 | 強制執行のみを依頼した場合は請求額の2.5%~4%程度(最低額10万円)、報酬は回収できた金額の2.5~4%程度。 一般的には強制執行の前の訴訟から依頼しているケースが多いと考えられ、その場合は、強制執行は着手金のみかかり、報酬については訴訟を含めて回収額の10~16%程度とすることが多い。 |
売掛金が回収不能になった場合の対応策
さまざまな手立てを検討・実施したものの、売掛金の回収が不能になってしまったら、どうすればよいのでしょうか。
対応策をみてみましょう。
売掛金の放棄・損金処理をする
会計上、売掛金は、回収できなくても売上として計上しなければなりません。
つまり、その分の税金が課されるということです。
そのため、回収見込みがない売掛金は権利放棄して損金として処理するのが賢明です。
それによって、未回収の売掛金にかかる税を軽減することができます。
売掛金を放棄するには、その旨の意思表示が必要です。
通常、債権放棄通知書という書類を作成し、相手に通知します。
「取引企業倒産対応資金」の融資を検討する
取引企業が倒産してしまったら、日本政策金融公庫が実施している融資制度「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」を利用できる可能性があります。
取引企業などが倒産したことで経営が困難になっている場合、3,000万円を限度に融資を受けることができます。
返済期間は8年以内で、利率は使いみち・返済期間・担保の有無などによって異なります。
取引企業倒産対応資金を利用するためには、倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権を有しているなど、6つの条件のうちいずれかに当てはまる必要があります。
日本政策金融公庫のWebサイトで確認しましょう。
債権譲渡を利用する
サービサーと呼ばれる債権回収会社へ、債権譲渡をする方法もあります。
サービサーは、支払われないお金を、代わりに回収することを専門としている民間企業です。
未回収分の売掛金債権を買い取ってくれるため、現金を得ることができます。
サービサーが取り立てをおこなうので、自社で取り立てる必要がなくなります。
ただし、買取価格は本来の売掛金の額よりも安くなります。
また、手数料が発生します。
自社で回収する場合のコストと比較してから利用しましょう。
買掛金と相殺する
相手が自社の製品やサービスを購入した際に発生するのが売掛金ですが、逆に自社が相手の製品やサービスを購入した際に発生するのが買掛金です。
相互に代金を支払う状況なのであれば、同額を相殺つまり支払ったことにすることができます。
お金だけではなく、ものやサービスであっても等価であれば相殺ができます。
相殺するには、どちらも支払い期日が到来していることなど、いくつかの条件があり、民法第505条以下に規定されています。
相殺をする場合には必ず確認しましょう。
原則的には一方的な意思表示によって相殺することが可能ですが、いくら相手が売掛金を支払ってくれていないとはいえ、今後の信用を損ねたくない場合には同意を得るのが賢明です。
また、個別の契約書で禁止されている場合には、相殺することはできません。
契約書の内容も再確認しましょう。
売掛金を回収不能にしないために心がけるポイント
今後、売掛金をしっかり回収するために、心がけ、実施するべきポイントを紹介します。
取引先の与信調査(信用調査)を徹底する
これまで与信調査をおこなっていなかった場合、これから契約する際は必ず取引先の与信調査をおこなうようにしましょう。
相手が過去に取引したことがある企業なら、当時の取引履歴や資料をチェックします。
新規契約の場合は、決算報告やIR情報が公開されているのであれば、必ず確認しましょう。
また、信用調査会社を活用するケースも増えています。
企業調査を専門としている調査会社に依頼することで、より確実な情報が入手できるはずです。
取引先とこまめなコミュニケーションを欠かさない
支払いが滞ってしまわないためには、取引先とのこまめなコミュニケーションが重要です。
全てをメールやオンラインで済ますのではなく、電話や対面でのやりとりを少しでも増やしておきましょう。
何気ない会話のなかから相手の経営状況がみえる場合もあります。
また、こまめなコミュニケーションによって信頼関係が築けていれば、相手は心理的に信頼を裏切りたくないという思いから、きちんと支払いをしてくれる場合もあります。
入金が遅延しないための仕組みを整える
入金が遅延しないよう、仕組みを整えるのも重要です。
契約締結時に保証人をつけたり、相手方の設備に譲渡担保権を設定したりするなど、いくつかの方法があります。
ただし、これらは相手の承諾がないとできないため、こちら側ができることとして決済代行サービスを活用するのがおすすめです。
決済代行サービスを活用する
クレジットカード・電子マネー・QRコードなどを利用した決済を促すことで、売掛金が未回収になってしまうリスクを大幅に軽減することができます。
近年では、あらゆる法人間の手続においてデジタルへの移行が進んでいます。
そのため、法人用のクレジットカードを活用している会社も増えています。
相手企業が法人カードを利用しているなら、法人カードで支払ってもらうのがよいでしょう。
また、売掛金回収の代行を専門におこなっている会社に依頼するのもおすすめです。
掛け払い代行サービスともよばれます。
与信管理や請求業務の効率化を図ることができ、未回収のリスクを大幅に減らすことができます。
ただし、決済代行サービス会社に手数料を支払う必要があります。
売掛金の消滅時効までに適切な対応をおこなう
従来の民法では、債権の種類によって1~3年で時効消滅する短期消滅時効の制度がありました。
しかし2020年4月施行の改正民法では、売掛金を含めた債権の時効期間は、行使できることを知ったときから5年、あるいは権利行使できるときから10年として統一されています(民法166条)。
そのため2020年4月以降に発生した売掛金に関しては、基本的に5年で時効が完成すると考え、5年以内に対処するようにしましょう。
さいごに | 売掛金回収は弁護士に任せて早期回収を
支払う意思や能力がない相手から売掛金を回収するのは、たいへんなことです。
会社のリソース的にも、担当者の精神的にも、大きな負担になります。
また、回収できない状態が続くことで税金を多く課されることにもなります。
さらに、時効が完成してしまえば、支払ってもらうことができなくなります。
売掛金回収は早めに弁護士に相談し、任せることで、より確実に早期の回収を実現しましょう。
弁護士なら、相手が催促に応じない場合の法的手続きにもスムーズに移行できます。
また、仮に回収できなかった際の手立てに対してアドバイスもしてくれます。
無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、まずは相談してみましょう。