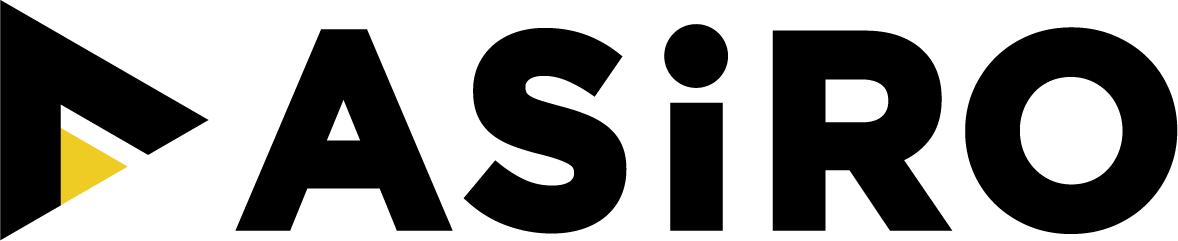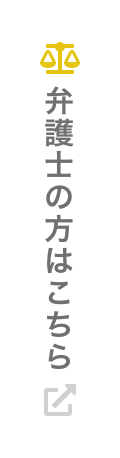「離婚を考えているけれど、どう進めればいいのだろう」
「協議離婚の手続きは複雑で不安だ」
協議離婚で失敗しないためには、財産分与や年金分割、慰謝料などのポイントを押さえたうえで、感情的にならず法律に則って話を進めることが重要です。
本記事では、協議離婚のメリット・デメリットやほかの離婚方法との違い、流れや注意点などを詳しく解説していきます。
協議離婚をしたいものの、話し合いが進まずに困っていませんか?
結論からいうと、協議離婚での話し合いがうまく進まない場合は弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 協議離婚について法的観点からアドバイスがもらえる
- 慰謝料を請求できるか判断してもらえる
- 依頼した場合、スムーズに話し合いを進めるためのサポートをしてくれる
- 依頼した場合、離婚に必要な手続きや交渉を代行してくれる
当サイトでは、離婚・不倫問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
協議離婚とは?夫婦間の話し合いで離婚に合意する手続きのこと
協議離婚とは、夫婦二人の話し合いによって離婚を成立させるもっとも一般的な方法です。
民法第763条によれば、次のとおり定められています。
(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
国立社会保障・人口研究所が発表した「人口統計資料集(2022)」によると、2020年に離婚した夫婦の88.3%が協議離婚を選択しています。
このように、多くの夫婦が裁判所の手続きをとおさずに離婚を成立させています。
協議離婚による離婚の成立件数
協議離婚という言葉をあまり耳にしない人も多いと思いますが、2022年には156,802件の協議離婚が成立しています。
それぞれの離婚手続方法における離婚件数については、以下のとおりです。
【2022年1年間の離婚件数の内訳】
| 区分 | 件数 |
| 総数 | 179,099 |
| 協議離婚 | 156,802 |
| 調停離婚 | 14,117 |
| 審判離婚 | 3,716 |
| 和解離婚 | 2,557 |
| 認諾離婚 | 9 |
| 判決離婚 | 1,898 |
【参考】人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚 年次 2022年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
協議離婚とそのほかの離婚手続の違い
離婚手続には、主に以下の3種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
離婚の話し合いは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の順番で進めるのが一般的です。
そして、夫婦の状況や合意の程度に応じて選ばれます。
また、近年では離婚ADRという専門機関のサポートを利用する方法も選択肢として増えています。
それでは、各方法の特徴と協議離婚との違いについて詳しくみていきましょう。
調停離婚|離婚調停を申し立てて裁判所で離婚の話合いをする手続き
調停離婚は、協議離婚で合意が得られなかった場合に裁判所に申立てをおこないます。
とくに、調停委員のもとで離婚に関する話合いを進める方法です。
協議離婚に比べて法的な手続きとしての色合いが濃くなり、ただ、あくまで裁判所は中立的な立場で離婚に関する話合いの仲介をおこなうという手続きです。
また、調停離婚では裁判所が判断を下すのではなく、双方が納得する解決を目指す点も特徴です。
たとえば、子どもの親権問題で合意できない場合、調停離婚では調停委員が双方の意向を受けて法律的な基準に基づいて解決策を提案してくれることもあります。
争いになった点について、感情論でまとまりがつかないというだけで打ち切られてしまうのではなく、場合によっては、普段は調停委員の裏に控えている裁判官が、法律的な判断の仕方を案内し、議論が正しく進んでいくことをサポートしてくれることもあります。
裁判離婚|離婚を求める訴訟を提起し、法廷で離婚の是非を争う手続き
裁判離婚は、協議や調停で合意が得られない場合に、裁判所に離婚を求める訴訟を提起する手続きを通じ、裁判所から離婚を認める判決をもらって、相手方の反対などの意見にかかわらず離婚を成立させる方法です。
法廷では双方の主張が聞かれ、裁判官が離婚の是非を判断します。
裁判離婚では、財産分与が難航するケースで、裁判官が法律に基づき財産の分与額を定めるといった、離婚に伴う問題もまとめて裁判を下してもらって解決できるという特徴をもっています。
ただし、時間と費用、そして尋問などでの少なくない労力がかかることが協議離婚との大きな違いとして挙げられます。
離婚ADR|専門機関のサポートを受けながら離婚の成立を目指す手続き
離婚ADRは、弁護士会など専門機関のサポートを受けて離婚の成立を目指す手続き方法です。
手続きを担当・仲介する弁護士がメディエーター(調停者)として、中立的な立場で双方のコミュニケーションをサポートします。
財産分与や親権について双方が納得する解決策を見つけるサポートをおこなうケースが一般的です。
協議離婚との違いは、メディエーターが夫婦間のコミュニケーションを促進しつつ、専門的なサポートを提供する点にあります。
このように、協議離婚のそのほかの離婚手続は、それぞれ特徴や利点をもっています。
協議離婚を選択するメリット・デメリット
協議離婚を選択すると、メリット・デメリットがそれぞれあります。
協議離婚のメリット
協議離婚のメリットは、主に以下の3つです。
【協議離婚の主なメリット】
- 離婚成立を早期化できるケースがある
- 法律で定められた離婚理由が不要
- 手続きが簡単で費用も不要(又は安価)
協議離婚のデメリット
協議離婚のデメリットは、主に次の3つです。
【協議離婚の主なデメリット】
- 直接話し合いが必要で口論になりやすくストレスが発生する
- 法律の専門家による仲介がなく離婚条件の合意に難航し泥沼化するケースも
- 「離婚条件を詳細に議論しない」「話し合いの過程を記録として残さない」などあとでトラブルが生じる可能性
- 口が達者な人が得をして、そうでない方がいつの間にか損をしていることがある
協議離婚は離婚届を役所に提出するだけでも成立させることができますから、離婚手続きの中でもっとも簡単な方法であるのは確かです。
ただし、離婚は生涯において大きな決断のひとつであり、どの離婚手続を選ぶかによってもその後の生活に大きな影響が出る可能性があります。
協議離婚のメリットとデメリットを熟慮し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも大切です。
協議離婚の大まかな流れ|離婚の意思表示から離婚届の提出まで
協議離婚の進める際、大まかな流れと知っておきたいポイントは、次の4つです。
- 相手に離婚の意思を伝える
- 夫婦で離婚条件を話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を提出する
特に、3番目の「離婚協議書を作成する」は法的な知識が必要となるため、弁護士に依頼するケースも多いところです。
では、ひとつずつみていきましょう。
1.相手に離婚の意思を伝える
離婚を考える際、最初のステップは相手に離婚の意思を伝えることです。
ただ、実際にその場面になると容易ではないでしょう。
以下の点を意識しながら進めることをおすすめします。
対話するための準備をおこなう
まず、離婚の意思を伝える前に自分の感情を整理し、冷静な状態で対話を進める準備をします。
離婚の理由や今後の生活についての計画を明確にし、相手に対しても考えを押し付けずに理解を求めるように努めましょう。
また、離婚に至る理由を明確に説明すると、相手にも納得してもらえる可能性が高まります。この際、相手を責めるのではなく、たとえば、いわゆるI(アイ)メッセージを用い、「私は、こう感じた。」「私は、こう考えた。」という枠組みで話せると冷静に話しやすいです。
また、話の内容・流れとして、相手自身が、「確かにこのまま結婚生活は続けられない」そして「離婚した方が良い」と自発的に思えるよう、話をしていくシナリオを考えられるとベストです。
財産分与の準備をする
財産分与は離婚協議の重要なポイントです。
可能であれば、離婚を切り出す前に配偶者の財産を調査し、自分にとって不利にならないように準備をします。
離婚を切り出すタイミングを間違うと、配偶者が財産を隠す可能性もあるため、事前調査は重要です。
何か証拠を取れそうでしたら、写真だけでも証拠にすることができますから、少しでも役立ちそうなものがあればどんどん写真に撮っておきましょう。
証拠の確保をする
離婚の原因が相手の不倫である場合、慰謝料を請求するためには証拠の確保が必要です。
離婚の話し合いや別居をする前に、有効な証拠を確保しておきましょう。
証拠の確保をきちんとしているかによって、その後の協議に大きく影響します。
安全な環境の確保
離婚の話を切り出す際は、相手が感情的になる可能性を考慮して安全な環境を整えることが重要です。
暴力をふるわれる可能性も想定しなければなりません。
- 必要に応じて子どもを友人や家族に預ける
- DVを受ける可能性を考えて避難のために数日分の必需品を準備しておく
- もし可能であれば別居宅まで用意できると、家からの追出しや暴力などがあった場合でも対処できます
こうした計画の検討をおすすめします。
伝えるタイミングを選ぶ
離婚の話を切り出すタイミングも重要です。
相手が冷静に話を聞ける状況を選び、最適なタイミングで話し合いを提案してください。
休日の午前中や相手が飲酒していないときなど、冷静に話し合える環境を作り出す配慮が必要です。
対話方法の検討する
離婚を切り出す方法も検討するポイントです。
直接面と向かっての話合いも良いですが、電話、メール、LINE、場合によっては文書にまとめて意思表示をする方法も考えましょう。
そして、合意することができた場合には、速やかに、手書きでも良いので文書にまとめて双方が署名(押印は必須ではありません)をしましょう。
メールやLINEで合意したというだけでは、後から覆される可能性があるため注意が必要です。
2.夫婦で離婚条件を話し合う
離婚条件の話合いは、夫婦関係を法律的に終了させ、お互いが新しい生活をスムーズにスタートさせるために重要なステップです。
この段階で夫婦が話し合うべき内容として、代表的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権・養育費
- 面会交流
離婚手続きにおいて、離婚条件の合意形成は法的な手続きにおいても大きな意味をもちます。
そして、離婚後のトラブルを防ぐ安全策にもなるポイントです。
子どもがいる場合を含めて、この段階で丁寧かつ詳細に協議をしておくと、将来にわたって離婚後もお互いの関係を良好に保つ土台ともなり得ます。
財産分与の確認
財産分与は離婚において重要な要素のひとつです。
離婚後の生活を安定させるためにも、夫婦間の財産をどのように分けるかを決める必要があります。
一例として、持ち家や自家用車、貯金などの財産を公平に分配する方法を話し合い、合意を目指します。
慰謝料の話し合い
慰謝料は、配偶者がおこなった違法といえるほどの行為による精神的なダメージを補償するための金銭です。
夫婦間でしっかりと話し合ったうえで、慰謝料の金額や支払い方法について明確な合意を目指しましょう。
たとえば、一方の不倫が離婚の原因である場合、不倫をしたほうに慰謝料を支払う義務があることを明らかにし、具体的な金額を十分に話し合います。
親権と養育費の話し合い
夫婦に子どもがいる場合、親権と養育費(特に教育費)の取決めに関する話合いで難航するケースが多く、重要な論点となります。
具体的には、親権者を決定し、養育費の額や支払い方法を話し合います。
たとえば、まずは、親権者が基本的に育児を担当し、もう一方の親は離れて暮らしながら養育費を支払う、という合意をし、それから教育費などの話合いへと段階的に進めて合意を目指すこともあります。
面会交流の取り決め
子どもとの面会交流は、非親権者が子どもとの関係を保ちながら交流できる貴重な時間です。
面会の頻度や時間、場所などを具体的に話し合い、お互いに納得できる取り決めをします。
専門家への相談
離婚条件の話し合いは複雑で感情的なものとなる可能性があります。
そのため、夫婦や家族で話し合いが難航する場合は弁護士など離婚の専門家に相談することもおすすめです。
弁護士に相談することで、法律的な観点からのアドバイスが受けられるため、公平な合意を目指すのに役立ちます。
3.離婚協議書を作成する
離婚協議書は、離婚に関する合意事項を正式に文書化する重要なステップです。
文書には、離婚条件の話し合いでテーマとなった財産分与、親権、養育費、慰謝料などの重要な項目についての合意を明記します。
将来的に争いが生じた場合、離婚協議書は重要な証拠となるものです。
そのため、細部にわたって明確に記述する意識が求められます。
特に財産分与や養育費、慰謝料など経済的な部分は具体的な項目が多く、内容が複雑になります。
たとえば、財産分与については、共有財産の分割方法や個人の財産についての割り出し、そして、それぞれの財産の資産価値の算出が重要です。
また、子どもがいる場合には、親権者の決定や養育費の額、支払い方法、面会交流の頻度など、具体的に記載しなければなりません。
そして、将来的に条件が変わった場合の対応についても話し合い、記載しておくこともありますので、事前に検討しておきましょう。
例を挙げると、養育費の額を変更する条件や手続き、新たなパートナーが登場した場合の子どもとの関係をどう扱うかなどです。
もし夫婦でまとめられないと感じたら、専門家や弁護士に相談し代理作成を依頼するのもひとつの手です。
弁護士に依頼すると法律的に適切かつ公正な協議書を作成できるため、将来的なトラブルを避けるメリットが得られます。
4.離婚届を提出する
協議離婚の最終段階に当たるステップは、離婚届の提出です。
正式に離婚について法的効力をもたせる重要な手続きといえます。
※離婚届を提出する前に、夫婦間で親権、財産分与、慰謝料などについての合意を固め、離婚協議書を作成しておくことが重要です。
すでに作成している場合も、改めてお互いに内容を確認し合いましょう。
離婚届は、夫または妻の住所地もしくは本籍地の市区町村役場に提出します。
この時点で協議離婚の手続きは完了です。
なお、離婚届には親権者の記載欄があるため、提出時までに親権を決めておかなければなりません。
そのため、親権について双方の合意がとれない場合は、家庭裁判所に申し立てて親権を決定する手続きをとる必要があります。
親権の決定は、子どもの将来に大きな影響を与える問題です。
したがって、夫婦間で冷静に話し合い、子どもの利益を最優先に考える視点が求められます。
また、協議離婚には証人2名が必要です。
証人をお願いする人に証人欄に署名と捺印をもらいます。
ちなみに、証人は特に何か責任を負うという訳ではなく、成人2名の形式的な協力だけで事足ります。後から連絡がいくということもありません。
それまで冷静に話し合っていた場合でも、離婚届の提出になると感情が高まるケースも少なくありません。
そのため、あくまで落ち着いて冷静に対処する必要があります。
離婚は夫婦だけでなく子どもやお互いの家族・親戚を含め、多くの人たちの家族構成を変えるものです。
人生において大きな決断となるため、法的な発想・要求に適う協議離婚の手続きを適切におこなって、トラブルを避ける意識をもってください。
協議離婚で必ず話し合うべき内容|お金のことと子どものこと
協議離婚のおおまかな流れで紹介した内容を、より詳しく説明します。
特に、協議離婚で話し合うべき代表的な内容は次の6つです。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
財産分与|夫婦の共有財産は原則として2分の1ずつ分ける
離婚時の財産分与は、夫婦間で共有していた財産を公平に分ける重要なポイントです。
たとえば、夫婦が共有していた持ち家や自家用車、預貯金などが財産分与の対象となります。
法律により、共有財産は原則として2分の1ずつの評価で分けなければなりません。
ただ、具体的な分配は夫婦間の話し合いや離婚協議書にて定められます。
財産分与で不公平が生じないように、適切な資産評価や法律的なアドバイスを受けることも重要です。
年金分割|年収の少ない人が他方から厚生年金の一部を受け取れる
年金分割は、離婚にともなって年収の少ない配偶者が他方の配偶者から厚生年金の支払実績の一部を受け取る制度です。
主に家庭を支えていた配偶者が働いていた配偶者から一定の年金そのものを受け取るのではなく、年金の算定の元になっている支払実績の部分を一部受け取ることができます。
たとえば、夫が高収入で妻が専業主婦であった場合、離婚後に妻が夫の厚生年金の支払実績の一部を受け取る仕組みです。
なお、年金分割の具体的な割合は、夫婦間の協議や法律により決定されますが、年金事務所で単純におこなわれるお役所的な手続きです。分け方も折半以外には基本的にあり得ないという運用となっています。
慰謝料|有責配偶者に対して不法行為に基づく慰謝料請求ができる
慰謝料は、離婚の原因となった配偶者の不法行為に対する補償を求めるものです。
具体的には、離婚に至った原因がある場合に、被害を受けた配偶者が有責配偶者へ請求できます。
たとえば、夫または妻の不倫が離婚の原因であった場合、被害者となった方が不倫相手に対して慰謝料を請求できるルールです。
親権|子どもがいる場合は夫婦のどちらか一方のみが親権者になれる
親権は、子どもがいる場合に離婚後の子どもの監護権をどちらの親がもつかを定めるものです。
日本の法律では、原則として夫婦のどちらか一方のみが親権者になることができます。
そのため、子どもがいる場合、離婚後にどちらの親が子どもの親権をもつのかを決める必要があります。
養育費|原則として裁判所の養育費算定表に従って養育費を決定する
養育費は、子どもを養育するために必要な費用を、非親権者である親が親権者である親に支払う制度です。
法的に親権をもたない親は、子どもの生活費や教育費などを支えるために養育費を支払うべき生活保持義務を負います。
養育費の額は、裁判所の養育費算定表に従って決定されることが一般的です。
面会交流|子どもと離れて暮らす親は定期的に子どもに会うことができる
子どもと離れて暮らす非親権者である親も、定期的に子どもに会う権利があります。
面会交流の具体的な取り決めは、夫婦間で話し合って決めることが多くみられます。
また、合意した取り決めを離婚協議書に記載するケースが一般的です。
協議離婚を夫婦たちだけでおこなう際の4つのポイント
協議離婚を夫婦だけでおこなう際には、下記4つのポイントがあります。
- 話し合う内容を事前に決めておく
- 感情的にならずに冷静に話し合う
- 離婚後の生活のことを考えておく
- 離婚協議書は公正証書で作成する
特に4番目の「離婚協議書は公正証書で作成する」は、合意した離婚条件を法的に確定させるために役立つところです。
では、具体的に紹介します。
1.話し合う内容を事前に決めておく
離婚の際にはさまざまな問題が浮上します。
そのため、財産分与や親権、養育費、慰謝料など、話し合うべきポイントをリストアップしておきましょう。
そして、それぞれの項目について、あらかじめ自身がどのような解決を望んでいるのかなども整理しておくことが重要です。
たとえば、財産分与の際には、共有の不動産や預貯金の分配について明確に計算しておきましょう。
事前に準備しておくことで、冷静かつ効率的な話し合いが可能となります。
2.感情的にならずに冷静に話し合う
離婚は感情が高ぶりがちなテーマです。
しかし、感情的になると冷静な判断ができなくなります。
話し合いの際は冷静に、そしてお互いに尊重の念をもって進めるよう心がけましょう。
たとえば、パートナーが不倫など過去の過ちについて話す際は冷静に対処し、話の焦点を解決ベースに保つことが重要です。
3.離婚後の生活のことを考えておく
離婚は新たな生活の始まりです。それぞれがどのような生活を送るのか、どのように子どもとの関係を築くのかを具体的に計画し、話し合う必要があります。
特に、子どもの親権をどちらがもつのか、面会交流はどのような頻度でおこなっていくのか、子どもの行事はどうするのか、養育費は具体的にいくらにするのかなどをはっきりとさせ、離婚後の生活スタイルの変化が子どもに与える影響についても考慮します。
4.離婚協議書は公正証書で作成する
離婚協議書を公正証書で作成すると、合意内容が法的に確定されます。
公正証書は、地域の公証役場の公証人が作成し、文書の内容は法的により強く保障されるものです。
もし離婚後に争いが生じた場合でも離婚協議書の内容が法的にそのまま認められる可能性が高まるという効果があります。
たとえば、公正証書で親権や財産分与の取り決めを明記しておくと、相手方が子どもや財産に不服があった際にも法的に守られるため、将来にわたるトラブルを避けられます。
とりわけ公正証書のメリットは、具体的な金額まで合意されたお金の支払いが怠られた時に、直ちに強制執行をかけられる可能性が非常に高まるという点です。
逆に言えば、そのような強制執行の必要がないような場合には、わざわざ費用をかけて公正証書にしなくても、良いともいえます。
その場合には、離婚協議書をきちんと作り込んでおければ基本的には問題がないということにもなります。
協議離婚で話がまとまらないときの3つの対処法
協議離婚で話がまとまらないときは、以下3つの対処法があります。
- 別居する
- 離婚調停を申し立てる
- 弁護士に相談・依頼する
特に3番目の「弁護士に相談・依頼する」は、法的な知識も必要になるケースにおいて、心強い味方となってくれるでしょう。
では、ひとつずつみていきましょう。
別居をする
感情が高ぶりがちな離婚協議中には、一時的な別居も対処法のひとつです。
別居により、お互いに冷静さを取り戻し、新たな視点で問題に向き合える場合があります。
たとえば、夫婦が互いに頻繁に口論となる場合なら、別居をとおして冷静になり、次回の話し合いの際にはより冷静に話し合えるかもしれません。
ただ、それまで同一生計だった場合、別居中の生活費の問題についても考えておく必要があります。
何よりも別居をすることのメリットとしては、近年では離婚に向けた別居であれば約3年間継続していることで判決での離婚が認められやすくなっていることです。
つまり、他に十分な離婚事由が無い場合や、相手が感情的になってまったく離婚に応じようとしない状況に陥っても、最終的には離婚を達成することができる目処が立つということです。
さらに、最終的にはどうせ離婚になるという前提を作っておければ、離婚ありきで協議や調停を進めやすくなり、離婚をしてもらうために相手から無闇に譲歩を求められる事態を防ぐこともできるのです。
離婚調停を申し立てる
話合いを重ねても協議離婚が難しいと感じた際には、裁判所を通じて離婚調停を申し立てる選択肢も有り得ます。
中立的な立場の調停委員が双方の話を聞き、公平な解決策を模索しやすい点がメリットです。
離婚調停は法律に基づいた適切な解決が期待でき、離婚のプロセスをスムーズに進める可能性をもっています。
弁護士に相談・依頼をする
離婚協議が進まないときには、弁護士に相談する選択もよいでしょう。
弁護士は法律の専門家として、離婚協議を円滑に進める方法や、法的観点から適切にアドバイスしてくれます。
具体的には、財産分与や親権に関する問題が難航している際、弁護士に依頼すると法的に有利な立場で協議を有利に進められます。
協議離婚を無効・取消しにさせないための注意点
せっかく話し合いを重ねてまとまった協議離婚を無効・取り消しさせないためには、以下2つの注意点があります。
- 一方的に勝手に離婚届の提出をしない
- 話合いで詐欺や強迫などをおこなわない
どちらも法的に問題がある行為なので、しっかり把握しておきましょう。
一方の都合で勝手に離婚届を提出しない
協議離婚の際は、双方の合意が必要です。
片方だけが勝手に離婚届を作成し提出すると、離婚は無効とされる可能性があります。
たとえば、配偶者が知らない間に離婚届を提出してしまったケースでは、離婚は無効と判断されることがあります。
話合いで詐欺や強迫などをおこなわない
詐欺や強迫によって離婚を進めると、あとで離婚を取り消される可能性があります。
具体例として、暴力や脅迫を使って離婚届に署名させたりする行為は、法律により離婚の取り消しを認められうる事情とされています(民法第764条、第747条1項)。
上記2つの事例で大切な点は、協議離婚を進める際には公正かつ透明な話合いが重要だということです。
誤解や不信感を避けるためにも事実を明らかにし、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
また、離婚の意向がしっかりと双方に伝わっていることを確認しましょう。
とりわけ、離婚届を提出する際には双方の同意が得られていることをもう一度確認することも重要です。
協議離婚や離婚手続に関するよくある質問
ここでは、協議離婚や離婚手続に関して、よくある質問と回答を3つ紹介します。
協議離婚が成立するまでにはどれくらいの期間がかかるのか?
協議離婚を進めるには多くの場合、おおよそ6ヵ月から1年の期間がかかります。
ただ、夫婦がしっかりと話し合いを進めれば、もっと短期間で協議離婚が成立することもあります。
離婚自体は離婚届を提出するだけなので、話がスムーズに進んでいるのであれば、即日の離婚成立も可能です。
協議離婚における証人は、手続き上でどのようなことをするのか?
協議離婚の際には、離婚届に2人の証人の署名が必要です。
証人になることができるのは成人ですが、証人といっても特に法的責任を負うわけではありません。
家族・親戚や友人にお願いするケースが一般的です。
ただし、片方が勝手に離婚届を提出することを知っていながらあえて協力するような場合には、証人も法的な責任を問われるおそれがあります。
協議離婚であれば裁判上の離婚事由がなくても離婚できるのか?
協議離婚では、明確な離婚事由がなくても夫婦が離婚について合意できれば離婚できます。
たとえば、暴力や不倫といった不法行為などの具体的理由がなくても話合いで離婚できます。
繰返しになりますが、日本ではほとんどの離婚が協議離婚です。
明確な離婚理由とその立証を必要としないため、離婚が比較的スムーズに進行するケースが多いようです。
さいごに|離婚協議とは夫婦の話し合いで離婚の成立を目指す手続き
協議離婚は、夫婦間の話合いを通じて合意形成して進める一般的な離婚手続きです。
【本記事のポイント】
- まず夫婦で離婚について話し合い、意向を確認する
- 話し合う内容を事前に決め、感情的にならず冷静に進める姿勢が大切
- 離婚後の生活や子どもの親権ついても十分に話し合う
- 合意に基づき協議離婚書を作成する
- 証人2人の署名とともに離婚届を提出すると離婚手続は完了
ここまでみてきたように、協議離婚は話合いをとおしてお互いの協力と理解が求められる離婚方法です。
そのため、十分な準備と対話があればスムーズに離婚の話合いが進められるかもしれません。
しかし、離婚は感情的なものが絡むものです。
人生においても重大な決断であり、夫婦だけでの話合いではうまくいかない場合もあるでしょう。
そんなときは法律の専門家である弁護士に相談し、公正な手続きをつうじて新しい人生のスタートを切る準備を整えることも大切です。