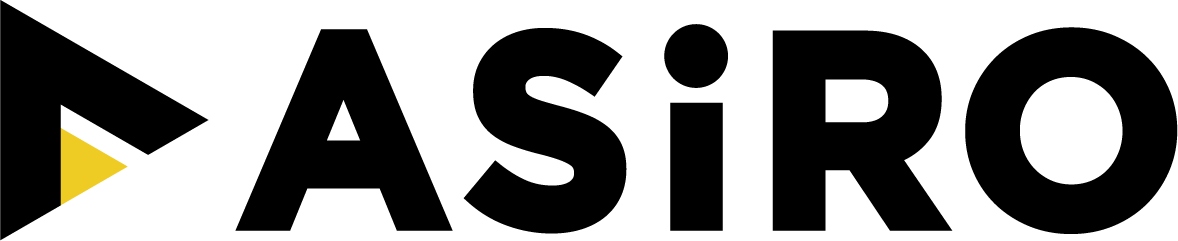刑事事件の手続きは、時間制限に関する厳密なルールの下で進行します。
スピーディに手続きが進行するため、被疑者・被告人としても迅速に対応しなければなりません。早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けながら早期の身柄解放を目指しましょう。
今回は刑事事件の手続きの流れについて、全体像・各手続きの詳細・やるべきことなどを解説します。
刑事事件の流れの全体像
刑事事件の手続きは、以下の流れで進行します。
- 捜査の開始・犯罪事実と被疑者の特定
- 逮捕or在宅捜査
- 起訴前勾留
- 起訴・不起訴の判断
- 起訴後勾留
- 公判手続き
- 判決・上訴
- 判決の確定・刑の執行
刑事事件の流れ①|捜査の開始・犯罪事実と被疑者の特定
刑事事件の手続きは、まず捜査機関が捜査をおこない、犯罪事実と被疑者を特定することから始まります。
捜査をおこなうのは、検察および警察です。たとえば以下のようなきっかけにより捜査を開始し、犯罪事実の目星を付けた上で被疑者を絞り込んでいきます。
- パトロール中の職務質問
- 被害者による告訴や被害届の提出
- 目撃者からの告発
- 防犯カメラ映像
- 検問 など
刑事事件の流れ②|逮捕or在宅捜査
被疑者が特定できたら、捜査機関は被疑者を逮捕するかどうかを検討します。もし逮捕された場合、被疑者の身柄は拘束されます。
一方、状況次第では被疑者を逮捕せず、在宅のまま捜査が進められることもあります。この場合、捜査機関から被疑者に対する任意の取調べなどがおこなわれます。
3種類の逮捕手続き
逮捕には、「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
通常逮捕
被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があると判断すれば、検察官・検察事務官・司法警察職員は、裁判官が発行する逮捕状に基づき被疑者を逮捕できます(刑事訴訟法199条1項)。これを「通常逮捕」といいます。
現行犯逮捕
現行犯人については、何人も逮捕状なくして逮捕することが可能です(刑事訴訟法213条)。これを「現行犯逮捕」といいます。
なお、検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者が現行犯人を逮捕した場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法214条)。
緊急逮捕
死刑・無期・長期3年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足る十分な理由があり、かつ急速を要し逮捕状を求めることができない場合は「緊急逮捕」が認められています(刑事訴訟法210条1項)。
緊急逮捕をした場合、検察官・検察事務官・司法警察職員は、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければなりません。
逮捕か在宅捜査かの判断基準
捜査機関が被疑者を逮捕するか、それとも在宅のまま捜査を進めるかについては、以下に挙げる要素などを総合的に考慮して判断されます。
犯罪事実の重大性
犯したと疑われる罪が重大な場合は、逮捕をするという判断になりやすいです。一方、比較的軽い犯罪が問題になっている場合は、在宅捜査が選択されやすい傾向にあります。
罪証隠滅のおそれ
被疑者による罪証隠滅のおそれがある場合は、逮捕が選択されやすい傾向にあります。
逃亡のおそれ
被疑者が逃亡するおそれがある場合は、逮捕が選択されやすい傾向にあります。
再犯の可能性
被疑者が連続的に犯行に及ぶ可能性がある場合、ほぼ確実に逮捕が選択されます。
現行犯か否か
現行犯の場合は、犯行を制止する観点からも逮捕を選択するケースが多いです。
逮捕期間は最長72時間
逮捕による身柄拘束の期間は、最長で72時間です(刑事訴訟法205条2項)。これは逮捕に限った期間であり、引き続き起訴前勾留による身柄拘束がおこなわれることもあります(後述)。
逮捕期間中は、警察官や検察官による取調べがおこなわれます。被疑者には黙秘権があり、取調べに対して一切回答しないこともできます。
逮捕期間中にやるべきこと
最長72時間の逮捕期間において、被疑者は以下のことをおこないましょう。
弁護人の選任
被疑者は逮捕された時点から、直ちに弁護人(弁護士)を選任できます(刑事訴訟法203条1項、204条1項)。
弁護人を選任すれば、取調べに関するアドバイスを受けられるほか、家族に対する連絡も取り次いでもらえます。刑事事件で逮捕された場合は、一刻も早く弁護人を選任しましょう。
早期の身柄解放を目指した活動
逮捕後起訴されるまでの期間においては、1日も早い身柄解放の実現が大きな目的です。
逮捕に続いて検察官の勾留請求がおこなわれなければ、その時点で被疑者の身柄は解放されます。弁護人を通じて検察官に良い情状を訴えるなど、勾留請求を阻止する活動をおこなうことが考えられるでしょう。
刑事事件の流れ③|起訴前勾留
逮捕に引き続き、検察官がさらに長期の身柄拘束をおこなうべきと判断した場合には、裁判官に対して勾留請求をおこないます。
勾留請求は原則として、検察官が司法警察員から送致された被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕後72時間以内におこなわなければなりません(刑事訴訟法205条1項、2項)。
ただし、検察官自ら被疑者を逮捕した場合には、逮捕後48時間以内に勾留請求をおこなう必要があります(刑事訴訟法204条1項)。
勾留の理由がないと認めるとき、およびやむを得ない正当な事由に基づかずに勾留請求が遅延した場合を除いて、裁判官は勾留状を発します(刑事訴訟法207条5項)。
勾留状が発せられると、逮捕から起訴前勾留へと移行し、被疑者の身柄は引き続き拘束されます。
起訴前勾留の要件
起訴前勾留の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」「勾留の理由」「勾留の必要性」の3つです。裁判官が勾留状を発する際には、すべての要件を満たしていることを確認する必要があります。
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
特定の犯罪の嫌疑につき、客観的・合理的な根拠が存在する必要があります(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。
勾留の理由
以下のいずれかに該当することが必要です(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。
- 被疑者が定まった住居を有しないとき
- 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
勾留の必要性
被疑者の不利益の程度などを考慮し、勾留をすることが不相当な場合には、勾留を認めるべきではないと解されています。
勾留の必要性が否定されるのは、たとえば被害者のいない軽度の犯罪について、勾留すると被疑者が職を失うなどの大きな不利益を被る可能性が高い場合などです。
起訴前勾留期間は最長20日間
起訴前勾留の期間は、当初は原則として10日間以内です(刑事訴訟法208条1項)。裁判官の判断により、検察官が請求した勾留期間が短縮されることもあります。
ただし検察官の請求により、やむを得ない事由がある場合には、裁判官によって最長10日間の勾留延長が認められることがあります(同法2項)。
したがって、起訴前勾留の通算期間は最長20日間で、逮捕と通算すると最長23日間です。
起訴前勾留期間中にやるべきこと
起訴前勾留の期間において、被疑者は以下のことをおこないましょう。
被害者との示談交渉
被害者がいる場合は、犯罪について真摯に謝罪して被害弁償を提案し、示談の成立を目指しましょう。
被害の回復を図ることは、罪を犯した者としてあるべき振る舞いと言えますし、示談が成立すれば刑事処分が軽くなる可能性もあります。
勾留されている被疑者本人が示談交渉をおこなうことはできないので、弁護人に対応を依頼しましょう。
不起訴に向けた弁護活動
犯罪の内容が比較的軽微な場合は、検察官に対して良い情状を訴えることで、不起訴処分となる可能性が高くなります。
被害者との示談交渉のほか、反省の態度と更生に向けた取り組みの意思を示すことや、更生をサポートする親族の協力を得ることなどが効果的です。
家族との連絡
逮捕期間中は家族と面会できませんが、起訴前勾留に移行すると、接見禁止処分がおこなわれた場合を除いて家族と面会できるようになります。
弁護人を通じて心配する家族と連絡をとり、可能であれば面会に来てもらうとよいでしょう。
刑事事件の流れ④|起訴・不起訴の判断
起訴前勾留の期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか否かを判断します(処分保留で釈放される場合もありますが、基本的には勾留期間中に起訴・不起訴が判断されるケースが大半です)。
起訴処分・不起訴処分の種類
起訴処分には、「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
正式起訴
被疑者(被告人)を通常の公判手続き(刑事裁判)にかける処分です。
略式起訴
公判手続きを経ることなく、簡易裁判所の略式命令によって刑を科すことを求める処分です(刑事訴訟法461条1項)。
100万円以下の罰金または科料を求刑する場合に限り、略式起訴がおこなわれる場合があります。略式命令に従って罰金または科料を納付すれば、被疑者の身柄は解放されます。
なお、被疑者は略式手続を拒否して、通常の公判手続きを求めることも可能です。
不起訴処分には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
嫌疑なし
犯人でないこと、または犯罪の要件を満たさないことが明白であることを理由とする不起訴処分です。
嫌疑不十分
犯罪の嫌疑はあるものの、公判手続きにおいて犯罪事実を立証し得る程度には足りないことを理由とする不起訴処分です。
起訴猶予
犯罪の嫌疑は確実であるものの、社会における更生を促すなどの目的でおこなわれる不起訴処分です。
起訴か不起訴かの判断基準
犯罪の嫌疑が確実であっても、正式起訴または略式起訴がおこなわれる場合と、起訴猶予(不起訴)処分となる場合の両方があり得ます。
検察官が起訴か不起訴かを判断する際の考慮要素としては、以下の例が挙げられます。
犯罪の重大性
犯した罪が重大であれば起訴処分、比較的軽微であれば不起訴処分がおこなわれやすいです。
被害弁償(示談)の状況
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分がおこなわれやすくなります。
再犯の可能性
常習性があり、再犯の可能性が高い場合には、刑罰を科すために起訴処分がおこなわれる傾向にあります。
反省の程度
被疑者が真摯に反省していれば、不起訴処分の可能性が高まります。
更生をサポートする人の存在
被疑者の更生をサポートしてくれる人が身近にいれば、不起訴処分の可能性が高まります。
刑事事件の流れ⑤|起訴後勾留
検察官が被疑者を正式起訴した場合、被疑者の身柄拘束は自動的に、起訴前勾留から起訴後勾留へと移行します。
起訴後勾留は2か月|1か月毎に延長可
起訴後勾留の期間は、起訴された日から2か月間です。ただし、特に継続の必要がある場合は、1か月ごとに更新が認められています(刑事訴訟法60条2項)。
起訴後勾留は起訴前勾留と異なり、原則として通算期間に制限がないのが特徴です。
起訴後勾留中は保釈が認められる場合あり
起訴後勾留されている被告人は、起訴前勾留の段階とは異なり、裁判所に対して保釈を請求できます。
保釈請求は、弁護人や被告人の親族などもおこなうことができます(刑事訴訟法88条1項)。
裁判所は、一定の除外事由に該当しない限り、被告人等の保釈請求を認めなければなりません(権利保釈、刑事訴訟法89条1項)。
除外事由に該当する場合でも、裁判所の職権により保釈を許すことができます(裁量保釈、刑事訴訟法90条1項)。
なお、保釈決定に基づいて身柄を解放されるためには、裁判所の定める保釈保証金を納付する必要があります(刑事訴訟法94条1項)。
起訴後勾留期間中にやるべきこと
起訴後勾留の期間中に被告人がおこなうべきことは、公判手続きの準備です。
具体的には、無罪を主張するか情状酌量を求めるかの方針を決定し、裁判所に提出する証拠資料などを準備します。弁護人に相談しながら、状況に合わせて適切に準備を進めましょう。
刑事事件の流れ⑥|公判手続き
起訴から1~2か月後を目安に、裁判所の公開法廷にて公判手続きが始まります。
公判手続きでは、検察官が犯罪要件のすべてを立証します。一つでも犯罪要件の立証に失敗すれば、被告人は無罪となります。
被告人としては、あくまでも無罪を主張するか、それとも罪を認めて情状酌量を求めるかが方針の分岐点です。弁護人と相談しながら、どのような方針で公判手続きに臨むかを決めましょう。
情状酌量を求める場合には、被害者と締結した示談書や、反省・更生の意思を表明する文書などを証拠提出する例がよく見られます。
公判手続きに提出する証拠の検討や準備についても、弁護人に相談すれば全面的にサポートしてもらえます。
刑事事件の流れ⑦|判決・上訴
公判手続きにおける審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。刑事裁判における判決には、以下の種類があります。
無罪判決
犯罪要件のうち、立証できていないものが1つでもあれば、被告人は無罪となります(刑事訴訟法336条)。無罪判決が言い渡された場合、被告人は直ちに釈放されます。
有罪判決
犯罪要件がすべて立証された場合には、有罪判決が言い渡されます。有罪判決には「実刑判決」「全部執行猶予付判決」「一部執行猶予付判決」の3種類があります。
実刑判決
被告人を実際に刑に服させる旨の判決です。懲役・禁錮であれば刑務所に収監され、罰金・科料であれば金銭の納付が命じられます。
全部執行猶予付判決
被告人に対して刑を言い渡しつつ、その全部の執行を一定期間猶予する判決です(刑事訴訟法25条)。3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金を言い渡す場合に限り、全部執行猶予が付されることがあります。
一部執行猶予付判決
被告人に対して刑を言い渡しつつ、その一部につき執行を一定期間猶予する判決です(刑事訴訟法27条の2)。3年以下の懲役もしくは禁錮を言い渡す場合に限り、一部執行猶予が付されることがあります。
判決に不服がある場合は、高等裁判所に対して控訴することができます(刑事訴訟法372条)。控訴期間は、判決の言渡し日の翌日から起算して14日間です(刑事訴訟法373条)。
高等裁判所の判決に不服がある場合は、さらに最高裁判所への上告が認められることがあります(刑事訴訟法405条、406条、411条)。
上告期間は控訴と同様、判決の言渡し日の翌日から起算して14日間です(刑事訴訟法414条、373条)。
刑事事件の流れ⑧|判決の確定・刑の執行
期間内に適法な控訴・上告がおこなわれなかった場合、または上告審判決の言渡しから原則10日間が経過した場合には、判決が確定します(刑事訴訟法418条)。
実刑判決または一部執行猶予付判決が確定した場合は、確定判決に基づき刑が執行されます。
全部執行猶予付判決が確定した場合は、被告人は釈放され、執行猶予期間が開始します。
犯罪捜査の対象になったら弁護士にご相談を
警察や検察による捜査の対象になってしまった場合、逮捕・起訴を経て、最終的には刑事手続きにより刑罰を科される可能性があります。
早期の身柄解放を目指し、さらに重い刑事処分を回避するには、弁護士のアドバイスとサポートを受けることが非常に重要です。
自身や家族が犯罪捜査の対象となった場合や、警察に逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士まで相談してください。