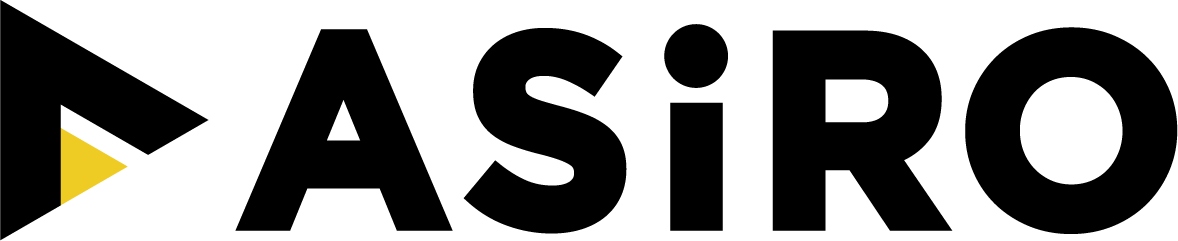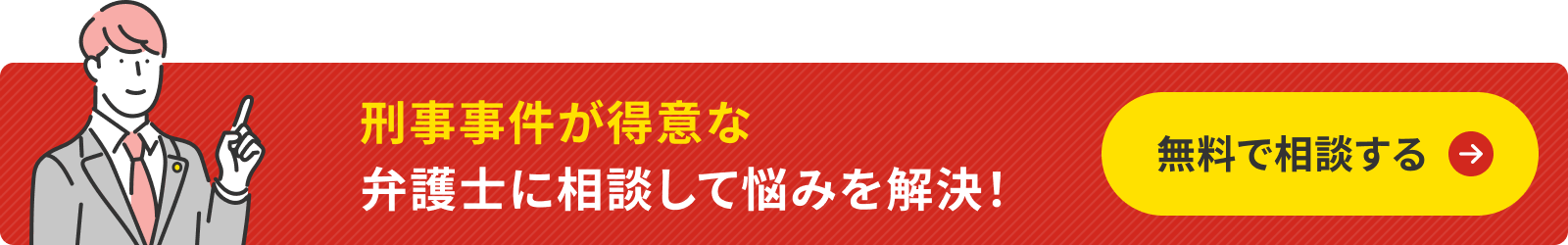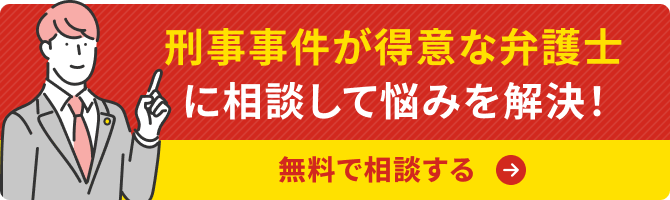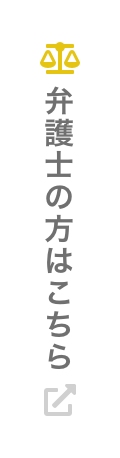- 「警察から呼び出されたけど、逮捕はされていない…」
- 「在宅事件って言われたけど、どういう意味なのかよくわからない……」
このような不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
在宅事件になると、逮捕や勾留を受けることなく、普段通りの生活を続けながら捜査に応じられます。
ただし、在宅のままでも起訴や裁判に進む可能性は十分にあり、決して油断はできません。
在宅事件の仕組みや、身柄拘束を避けるためのポイントをあらかじめ理解しておけば、精神的な負担が軽くなり、より適切な対応ができるようになるでしょう。
本記事では、在宅事件の基本的な意味や身柄事件との違い、在宅事件になった場合に知っておくべきポイントなどを解説します。
手続きに関する不安を少しでも軽減するためにも、ぜひ参考にしてください。
在宅事件とは?身柄を拘束されない刑事事件のこと
在宅事件とは、被疑者が逮捕や勾留などの身柄拘束を受けずに、捜査が進められる刑事事件をいいます。
たとえ犯罪の疑いがあっても、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるなど、法律で定められた条件を満たさなければ、逮捕されることはありません。
条件を満たさない場合には、任意の手続きによる捜査が適切とされるため、強制力を伴わない任意捜査である在宅事件として処理されるのです。
そして、在宅事件では被疑者が留置所に入る必要がないため、通常の生活を続けながら捜査に対応することになります。
しかし、身柄を拘束されない分、捜査が長期化する傾向があり、定期的に数ヵ月、あるいはそれ以上にわたって取り調べを受けるケースも少なくありません。
また、ある日突然逮捕されたり裁判にかけられることもあるので、注意が必要です。
【関連記事】逮捕とは|3種類の逮捕の特徴・その後の流れと対処法を解説
捜査機関に逮捕・勾留される場合は「身柄事件」と呼ばれる
身柄事件とは、被疑者が逮捕や勾留を受けて捜査が進められる刑事事件をいいます。
身柄事件と在宅事件の主な違いは、以下の3つです。
| 項目 | 身柄事件 | 在宅事件 |
| 取り調べ方法 | 留置所に収容された被疑者へおこなう | 被疑者を任意で出頭させておこなう |
| 弁護人の選任 | 国選弁護人を選任できる | 国選弁護人を選任できない(私選弁護人を選ぶ必要がある) |
| 捜査期間 | 最長23日間 | 期間制限がない(長期間にわたることも多い) |
在宅事件になった場合の刑事手続きに関する基本理解
在宅事件では逮捕や勾留といった身柄拘束はされませんが、捜査は進行していることに変わりはないので、手続きについてある程度理解しておいたほうがよいでしょう。
ここでは、在宅事件になった場合の刑事手続きに関する基本的な知識を解説します。
1.普段どおり会社や学校に通える
在宅事件の大きなメリットは、普段通り会社や学校に通える点です。
身柄事件の場合、起訴・不起訴の判断が出るまで最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
この間は出勤や登校ができず、欠勤や欠席の理由を十分に説明できないと、職場で解雇や減給、学校で退学などの不利益を受けるリスクが生じます。
一方、在宅事件では身柄拘束がないため、通常の生活を続けることが可能です。
そのため、仕事や学業に与える影響が比較的少なく、社会的信用を失うリスクも抑えられます。
2.通常は数回程度呼び出しがある
在宅事件では、警察や検察から呼び出しを受けることがありますが、その回数は事件の内容や対応状況によって異なります。
軽微な事件で容疑を認めている場合は、警察の取り調べが1回〜2回、検察官による聴取が1回程度、合計3回前後の呼び出しで済むことが一般的です。
ただし、容疑を否認している場合や被害が大きい場合、共犯者が関わる事件では呼び出し回数が増えることがあります。
また、書類送検後に補充捜査が必要と判断されれば、再度呼び出されるケースもあります。
なお、警察や検察からの連絡や呼び出しには誠実に対応しましょう。
無視して出頭を拒むと、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕される可能性が高まってしまいます。
3.途中で逮捕される場合がある
在宅事件として捜査が進んでいても、あとから重要な証拠が見つかった場合などには、突然逮捕される可能性があります。
「在宅事件になったから安心」と安易に判断せず、状況によっては警察や検察の捜査方針が変わる可能性があることを理解しておきましょう。
4.起訴される可能性はある
捜査によって十分な証拠が集まり、犯罪の嫌疑が強いと判断された場合には、在宅事件であっても起訴される可能性があります。
起訴後は、身柄を拘束されないまま刑事裁判を受けます。
裁判所から指定された期日に自宅から裁判所へ出向く必要がありますが、通常は期日の調整が可能であり、仕事や学業への影響も比較的少なく済むのが一般的です。
在宅事件になった場合に不起訴を獲得するためのポイント
刑事手続きが進む中で不起訴処分を得られれば、前科がつかずに事件を終結できます。
そして、不起訴となる可能性を高めるためには、以下のようなポイントを押さえることが大切です。
- 被害者がいる場合は謝罪と示談をする
- 犯罪を認める場合は素直に取り調べに応じる
- 刑事事件が得意な弁護士にサポートを依頼する
ここでは、不起訴を目指すうえで特に意識したい3つのポイントを解説します。
1.被害者がいる場合は謝罪と示談をする
被害者への謝罪と示談の成立は、不起訴の可能性を高めるために効果的です。
検察官が起訴の可否を判断する際、被害者との関係が修復されているかどうかを重要な要素とします。
そのため、示談が成立し、被害者が「これ以上の処罰を望まない」という意思を示せば、不起訴処分となる可能性が高まるのです。
なお、示談を成立させるためには、被害者に誠意をもって謝罪をおこないましょう。
示談書には「今後は処罰を求めない」という内容を記載するのが一般的で、これを検察官に提出すれば反省と被害回復の意思を伝えられます。
ただし、トラブルの原因となりやすいので、被害者との連絡は慎重におこなう必要があります。
可能であれば、弁護士を通じてやり取りしましょう。
2.犯罪を認める場合は素直に取り調べに応じる
自分に非があると感じている場合は、警察や検察の取り調べに素直に応じましょう。
捜査機関に嘘をついたり、事実を隠そうとしたりすると、「反省していない」または「証拠隠滅のおそれがある」と判断され、刑罰が重くなるおそれがあります。
一方で、率直に事実を認め、深く反省している姿勢が伝われば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
また、供述調書に記載される内容は起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
取り調べで「今後は同じことを繰り返さない」といった反省の言葉や生活改善の努力を伝えれば、検察官は再犯可能性が低く更生の可能性が高いと判断する材料となるでしょう。
ただし、犯行内容にまったく身覚えがない場合は、無理に事実を認める必要はありません。
この場合は、弁護士と相談しながら否認の意思をはっきり示しましょう。
3.刑事事件が得意な弁護士にサポートを依頼する
不起訴処分を獲得するためには、刑事事件を得意とする弁護士に依頼することも非常におすすめです。
弁護士は、取り調べに関する助言、被害者との示談交渉、検察官に提出する意見書の作成など、あらゆる面で被疑者をサポートすることができます。
在宅事件であっても、後日逮捕される可能性がゼロとはいえません。
そのため、万が一に備えて早めに弁護士に相談し、安心して捜査に対応できるよう準備しておくことが大切です。
在宅事件になった場合に気を付けるべき3つの注意点
在宅事件になった場合に注意すべきポイントがいくつかあります。
ここでは、主なポイントを3つ紹介します。
1.自分で不起訴かどうか調べる必要がある
在宅事件では、不起訴になったかどうかを自分で確認する必要がある点に注意が必要です。
なぜなら、不起訴処分が決まったとしても、「不起訴になりました」といったお知らせが自動的に自宅に郵送されてくるわけではないからです。
不起訴となったかどうか確認するには、自分で「不起訴処分告知書」を取得する必要があります。
告知書の取得は義務ではありませんが、会社から提出を求められたり、ビザや永住権の申請に必要になったりする場合があります。
将来のトラブルを避けるためにも、できるだけ取得しておくことをおすすめします。
弁護士に依頼している場合は、代わりに請求してもらえることもあります。
ただし、国選弁護人を利用した場合、釈放後に対応が終了してしまい、告知書の請求まではおこなってもらえないケースが一般的です。
弁護士がいない場合は、本人が郵送または検察庁に直接出向いて請求します。
郵送する際は、必要事項を記入した申請書と切手を貼った返信用封筒を同封して送付しましょう。
窓口で請求する場合は、事前に検察事務官と日程を調整し、身分証明書とシャチハタ以外の認印を持参しましょう。
2.捜査期間が長引く可能性が高い
在宅事件では、身柄事件と比較すると捜査機関が長期化する傾向がある点に注意が必要です。
身柄事件では、最長23日以内に起訴・不起訴を判断する必要があります。
しかし、在宅事件では期間期限がないので、数ヵ月から1年以上不安な日々を過ごさなければならない場合もあります。
「もう終わったのでは?」と思っていたタイミングで、突然起訴状が届くというケースも少なくありません。
いつ終わるかわからない不透明な状況が続くと、精神的な負担も大きくなるでしょう。
3.国選弁護人制度を利用できない
逮捕された場合は、勾留期間中から「国選弁護人制度」を利用できるのが通常です。
しかし、在宅事件の場合、起訴前に国選弁護人制度を使うことはできません。
「逮捕されていないし、裁判にもならないだろう」と考えて、弁護士への依頼を先送りにする方もいます。
しかし、在宅事件であっても、示談交渉や証拠の整理、検察への対応など、早めに進めておくべき重要な対応が数多くあります。
これらをひとりで対応するのは非常に難しいので、弁護士のサポートがなければ、不起訴の可能性を逃してしまうかもしれません。
さいごに|在宅事件の場合でも起訴の可能性はあるため弁護士に相談しよう
本記事では、在宅事件についてわかりやすく解説しました。
在宅事件は、逮捕や勾留を受けずに捜査が進むため、「それほど重大な問題ではない」と軽く考えてしまう方も少なくありません。
しかし、在宅事件であっても、犯罪の嫌疑が固まれば起訴される可能性はあります。
また、身柄を拘束されない分、捜査が長引く傾向があり、処分結果が出るまでに時間がかかるケースも多くあります。
先の見えない不安を抱えながら過ごすことは、精神的にも大きな負担となるでしょう。
こうした不安を少しでも和らげるためには、できるだけ早い段階で私選弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、現在の状況や今後の見通し、不起訴に向けた適切な対応などについて、専門的なアドバイスを受けられます。
「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、相談内容やお住まいの地域に応じて、刑事事件を得意とする弁護士をスピーディーに検索できます。
起訴のリスクを少しでも抑えるためにも、ベンナビ刑事事件を活用し、自分にあった弁護士を見つけましょう。