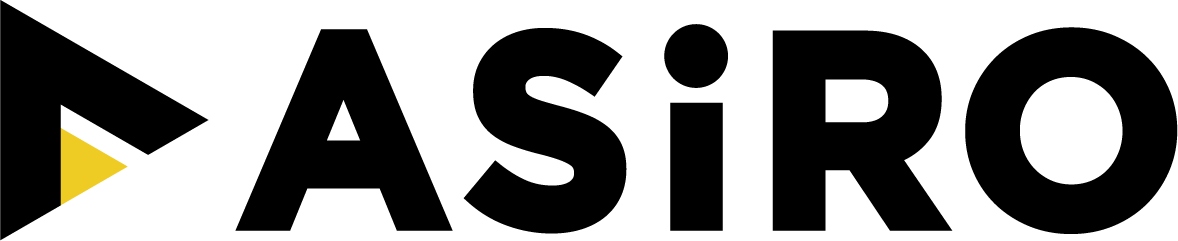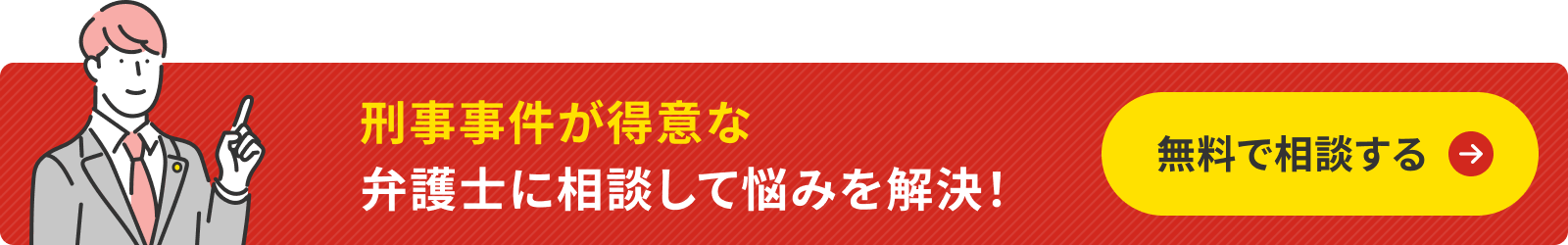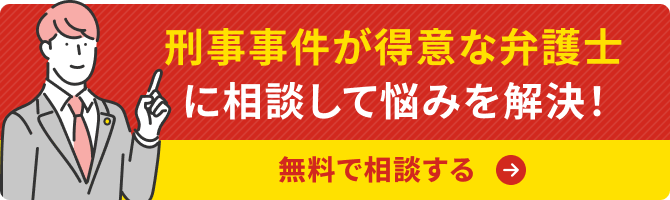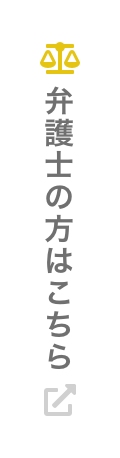運転中についつい前の車の動きにイライラしてしまい、車間距離を詰めすぎたり、クラクションを鳴らしたりしてしまった経験はありませんか?
そんな行為があおり運転と受け取られ、相手に通報されてしまったらどうなるのでしょうか。
「まさか逮捕されることはないだろう」と思っていても、あおり運転と認められれば、逮捕され重い処罰を受ける可能性があります。
本記事では、あおり運転で逮捕された場合の刑罰内容や考えられるリスク、通報された場合の適切な対処法について詳しく解説します。
あおり運転で逮捕されたらどうなる?
あおり運転で逮捕された場合、2020年6月に新設された「妨害運転罪」により、これまで以上に厳しい刑罰が科されるようになりました。
従来は暴行罪などで対応していましたが、あおり運転の悪質性を考慮し、より重い罰則が設けられています。
ここでは、あおり運転で逮捕された際の具体的な刑罰内容について詳しく解説します。
あおり運転は「妨害運転罪」が適用され、厳しい罰則を受けることになる
あおり運転で逮捕された場合、2020年6月に新設された「妨害運転罪」が適用されます。
従来、あおり運転は道路交通法にくわえ刑法の暴行罪が適用されてきました。
暴行罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料」です。
妨害運転罪は以下のとおり2段階で刑罰が設定されており、暴行罪より厳しい刑罰が科されることになります。
| 種類 | 概要 | 刑罰 |
| 【1】妨害運転 (交通の危険のおそれ) | 他車両などの通行を妨害し交通の危険を生じさせる一定の行為(次項で紹介する10つの行為)をおこなった場合 ※道路交通法 第117条の2の2 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 【2】妨害運転 (著しい交通の危険) | 【1】の行為により高速道路でほかの自動車を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合 ※道路交通法第117条の2 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
このほか、あおり運転では以下の行政処分も受けることになります。
- 妨害運転(交通の危険のおそれ)
違反点数25点/免許取消し(欠格期間2年) - 妨害運転(著しい交通の危険)
違反点数35点/免許取消し(欠格期間3年)
妨害運転罪の対象となる10つの行為
妨害運転罪の対象となる行為は、以下のとおりです。
| 違反行為 | 違反する条文 | 具体的な行為内容 |
| 通行区分違反 | 道路交通法第17条 | 対向車線にはみ出したり、逆走する行為 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 道路交通法第24条 | 不要な急ブレーキをかける行為 |
| 車間距離不保持 | 道路交通法第26条 | 車間距離を詰めて接近する行為 |
| 進路変更禁止違反 | 道路交通法第26条の2第2項 | 急な進路変更や割り込みをする行為 |
| 追い越し違反 | 道路交通法第28条 | 左車線からの追い越しや危険な追い越し行為 |
| 減光等義務違反 | 道路交通法第52条第2項 | 執拗なパッシングや不必要なハイビームの継続 |
| 警音器使用制限違反 | 道路交通法第54条 | 執拗にクラクションを鳴らす行為 |
| 安全運転義務違反 | 道路交通法第70条 | 幅寄せや蛇行運転などの行為 |
| 最低速度違反 | 道路交通法第75条の4 | 高速道路での故意の低速走行 |
| 高速道路駐停車違反 | 道路交通法第75条の8 | 高速道路での駐停車行為 |
これらの行為を「ほかの車両の通行を妨害する目的」でおこない、交通の危険を生じさせた場合に妨害運転罪が成立します。
それぞれの行為は単独でも道路交通法違反として取り締まりの対象となりますが、妨害目的でおこなわれた場合はより重い妨害運転罪が適用されることになります。
あおり運転で人を死傷させた場合は、さらに厳しい罰則を受ける
あおり運転によって人を負傷させたり死亡させたりした場合は、妨害運転罪に加えて「危険運転致死傷罪」が適用されます。
この罪は自動車運転処罰法第2条に規定されており、妨害運転罪よりもはるかに重い刑罰が設けられています。
危険運転致死傷罪の刑罰は以下のとおりです。
- 人を負傷させた場合:15年以下の拘禁刑
- 人を死亡させた場合:1年以上の有期拘禁刑
妨害運転罪の最高刑が5年以下の懲役であることを考えると、人身事故を起こした場合の刑罰は格段に重いといえるでしょう。
また、死亡事故の場合は実刑判決となるため、長期間の服役が確実となる点にも注意が必要です。
あおり運転では免許停止・取り消しなどの罰則も受ける
妨害運転罪が成立した場合、刑事罰とは別に行政処分も科されます。
行政処分とは、違反点数の累積に応じて免許を停止・取り消しにする処分のことです。
あおり運転では、通常の交通違反とは異なり、一発で免許取り消しとなります。
また、悪質度に応じて違反点数と欠格期間が設定されており、最長で10年間は運転免許の再取得ができません。
そのため、あおり運転で免許取り消しになると、通勤や日常生活、仕事に深刻な影響を及ぼすこともあるでしょう。
トラックドライバーやタクシー運転手など、運転を職業とする人にとっては職を失うリスクも伴います。
あおり運転で逮捕された場合に適用される可能性があるその他の罪
あおり運転では、妨害運転罪以外にも具体的な行為によって複数の罪が適用される可能性があります。
以下の表は、あおり運転で成立する可能性のある罪名と法定刑をまとめたものです。
| 罪名 | 適用される場面 | 法定刑 |
| 暴行罪 | 相手を停車させ、胸倉を掴む・殴る・蹴るなどの暴力行為を働いた場合 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・拘留・科料 |
| 傷害罪 | 暴力行為によって相手にけがをさせた場合 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 脅迫罪 | 「殺すぞ」「降りてこい」等の暴言で相手に恐怖感を与えた場合 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 器物損壊罪 | 相手の車両を叩くなどして故意に傷つけた場合 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 |
| 殺人罪 | 「死んでもかまわない」という意思で車を衝突させ、相手を死亡させた場合 | 死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑 |
これらの罪は妨害運転罪と併せて適用されることが多く、複数の罪で起訴されると刑罰も重くなります。
とくに人身事故や暴力行為が伴う場合は、非常に重い刑罰を受ける可能性があるでしょう。
あおり運転で逮捕された場合に考えられるその他のリスク
あおり運転で逮捕された場合、刑事罰や行政処分だけでなく、社会生活に以下のような影響を与えかねません。
- 前科がついて就職や生活に影響が生じる可能性がある
- 会社や学校にバレて、退学や解雇などの処分を受ける可能性がある
- 実名報道などにより、社会的な制裁を受ける可能性がある
- 被害者から損害賠償を請求される可能性がある
各リスクについて、詳しく説明します。
前科がついて就職や生活に影響が生じる可能性がある
あおり運転で有罪判決を受けると、実刑・執行猶予・罰金刑のいずれであっても前科がつきます。
前科がつくことで生じる影響は、以下のとおりです。
- 就職・転職活動への影響:履歴書の賞罰欄への記載が必要となり、前科を隠して採用された場合は経歴詐称として懲戒処分の対象になります
- 職業制限:士業や金融業など、前科があると就けない職業があります
- 国際的な影響:海外渡航時に入国を拒絶される場合があります
- 家族関係への影響:結婚や家族関係に悪影響を及ぼす可能性があります
前科は一生消えることがありません。
一時的な感情でおこなったあおり運転によって、生涯にわたって大きな影響を与える可能性があることを覚えておきましょう。
会社や学校にバレて、退学や解雇などの処分を受ける可能性がある
あおり運転で逮捕された場合、身柄拘束により長期間職場や学校を欠席することになるため、逮捕事実を隠し続けるのは困難です。
そして、会社や学校に逮捕されたことがバレると、以下のような処分を受ける可能性があるでしょう。
【会社での処分】
- 就業規則に基づく懲戒処分(戒告・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇等)
- 社会的信用の失墜による昇進・昇格機会の喪失
- 職場での人間関係の悪化
【学校での処分】
- 学則や校則に基づく処分(譴責・停学・退学等)
- 学校の名誉毀損を理由とした厳しい処分
実名報道などにより、社会的な制裁を受ける可能性がある
あおり運転は社会的な関心が高いため、事件化すると実名報道やSNSでの拡散により、法的制裁を超えた社会的制裁を受ける可能性があります。
一度でもネットに顔写真や名前が掲載されると、完全に情報を消去するのは困難です。
そのため、自分の名前で検索されると、あおり運転で逮捕された事実を簡単に知られてしまうおそれもあるでしょう。
その結果、就職や転職で不利になったり、これまでの人間関係に亀裂が入ったりする可能性があります。
被害者から損害賠償を請求される可能性がある
あおり運転によって被害が発生した場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
あおり運転による事故では、原則として加害者の過失割合が100%とされるため、全ての損害を賠償する責任を負います。
具体的な損害賠償の内容は、以下のとおりです。
- 車両の修理費用や代車費用
- 治療費や慰謝料(人身事故の場合)
- 精神的苦痛に対する慰謝料(事故がない場合でも請求される可能性)
なお、あおり運転は極めて悪質な行為と判断されるため、通常の交通事故よりも慰謝料が増額される可能性があります。
あおり運転で逮捕された判例
あおり運転による実際の事件では、行為の悪質性に応じて重い刑罰が言い渡されています。
ここでは、あおり運転の厳罰化のきっかけとなった事件や、被害者への暴行がおこなわれた事件の判例を紹介します。
あおり運転厳罰化のきっかけにもなった「東名あおり運転」の判例
2017年6月に神奈川県の東名高速道路で発生した事件は、あおり運転厳罰化の大きなきっかけとなりました。
【事件の詳細】
- パーキングエリアで注意されたことに腹を立てた被告が、注意した男性の車を時速100kmで追走
- 追い越し車線上で被害者の車を停車させる
- 後続のトラックが追突し、夫婦が死亡、同乗していた娘二人が負傷
【判決の経緯】
- 一審:危険運転致死傷罪で懲役18年の判決
- 弁護側の主張により差し戻し審が実施
- 2024年2月:東京高裁の差し戻し控訴審で再び懲役18年を支持
- 被告側は最高裁に上告(2025年5月時点で判決未確定)
この事件は、あおり運転による死亡事故の深刻さを社会に知らしめ、妨害運転罪の新設につながる重要な契機となりました。
あおり運転で被害者の車を停止させ暴行を働いた事件の判例
2019年に常磐自動車道で発生した事件では、被告が幅寄せや割込みを繰り返して被害者の車を停止させ、さらに車外に出て暴行を加えました。
【事件の詳細】
- 高速道路上で執拗なあおり運転を繰り返し実施
- 被害者の車を強制的に停車させる
- 車外に出て被害者の顔面を拳で殴打し、約1週間の治療を要する顔面打撲傷等を負わせる
- 被害者の車に設置されたドライブレコーダーで一部始終が記録
【判決の経緯】
- 強要罪、傷害罪で起訴
- 懲役2年6月、保護観察付執行猶予4年の判決
- 被害弁償として合計293万円を支払い
この事件では、高速道路上での極めて危険な行為として重い刑罰が科され、執行猶予が付いたものの保護観察による厳格な監視下に置かれることになりました。
あおり運転で逮捕され裁判で判決が出るまでの流れ
あおり運転で通報された場合、現行犯で逮捕される可能性があります。
また、最近ではドライブレコーダーの普及により、証拠映像から運転者を特定できるケースも増えているため、犯行当時は逮捕されなくても、後日突然警察がやってきて逮捕されるおそれもあるでしょう。
ここでは、あおり運転で逮捕された場合の刑事手続きの流れを詳しく解説します。
警察から連絡が来て逮捕される
あおり運転で通報されると、警察は独自に捜査活動を開始し、以下2つのパターンで加害者に接触します。
任意での出頭要請
警察が運転者を特定すると、電話連絡や自宅訪問により任意での出頭要請をおこなうのが一般的です。
「あおり運転の事件について事情を聴きたい」という内容で、法的な出頭義務はありません。
しかし、任意での事情聴取を拒絶すると、逮捕状が請求されて通常逮捕手続きに移行する危険性が高くなります。
そのため、出頭要請には素直に応じることが重要ですが、事前に弁護士に相談しておくのが無難でしょう。
通常逮捕
以下のような場合には、任意での事情聴取を飛ばして、いきなり逮捕される可能性があります。
- あおり運転の態様が決して軽微とはいえない場合
- 妨害運転罪の前科・前歴がある場合
- あおり運転によって交通事故が発生した場合
- 飲酒運転や薬物事犯などの前科・前歴がある場合
通常逮捕の場合、ある日突然警察が自宅にやってきて逮捕状を提示され、その時点から警察に身柄が拘束されます。
【逮捕後48時間以内】警察から取り調べを受け検察へ送致される
逮捕後は留置場に入り、48時間以内に取り調べを受けます。
この期間中は、会社や家族などの外部と一切連絡を取れません。
警察は48時間以内に、取り調べの結果をふまえて次の段階を決定します。
検察官への送致が必要と判断した場合は身柄と事件書類を引き継ぎ、身柄拘束の必要がないと判断した場合は釈放します。
なお、被疑者には取り調べに対して黙秘する権利(黙秘権)や、弁護士を呼ぶ権利(弁護人選任権)が保障されています。
不利な供述調書が作成されないよう、これらの権利を適切に行使することが重要です。
【逮捕後72時間以内】検察官が引き続き身柄を拘束するか決める
警察から事件と身柄の送致を受けた検察官は、送致から24時間以内(逮捕後72時間以内)に、引き続き身柄を拘束して捜査を進める必要があるかどうかを判断します。
この段階で、検察官が身柄拘束の必要がない、あるいは証拠が不十分だと判断した場合は釈放されます。
一方、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ「証拠隠滅の恐れ」または「逃亡の恐れ」があると判断した場合は、さらなる身柄拘束(勾留)を裁判官に請求します。
この場合でも、裁判官が勾留を認めなければ釈放されます。
つまり、この24時間が早期釈放につながるかどうかの重要な分岐点となるのです。
【最大20日間】身柄拘束(勾留)が継続し、検察が起訴・不起訴の判断をする
検察官から勾留請求を受けた裁判官が、勾留の理由と必要性があると判断した場合に「勾留状」を発付します。
勾留期間は原則として10日間です。
しかし、やむを得ない理由があると認められた場合には、さらに最大10日間延長され、合計20日間まで勾留されます。
勾留期間中に、検察官は起訴するかどうかの最終判断を下します。
あおり運転をしたことが明白であっても、運転の態様、反省の態度、被害者との示談交渉の状況などを総合的に考慮した結果、不起訴処分を獲得できる可能性があるでしょう。
刑事裁判となり判決が下される
起訴処分が下されると、公開の刑事裁判における審理を経て判決が下されます。
第1回口頭弁論期日は起訴から1ヵ月〜2ヵ月後に指定されるのが一般的です。
あおり運転などについての反論がなければ初回で結審し、後日判決が言い渡されます。
あおり運転の成否自体を争う場合には、弁論手続・証拠調べ手続きを経て最終的な判決に至ります。
初犯なら罰金刑もしくは執行猶予付き判決が下されるのが一般的ですが、過去に同種前科がある場合には実刑判決の可能性もあります。
なお、検察官が罰金刑を求刑する場合には、略式裁判手続で早期に刑事手続きを終結させることも可能です。
あおり運転で相手に通報されたらどうすればいい?
あおり運転で通報された場合、適切な対応を取ることで事態の悪化を防ぐことができます。
具体的には、以下の対応をとるようにしましょう。
- 通報した相手の連絡先がわかっている場合はすぐに連絡して謝罪する
- 通報内容に覚えがないか誤りがあれば、反証するための証拠を集める
- 警察の取り調べには誠実に対応する
- 弁護士に今後の対応について相談する
それぞれの対処法について、詳しく解説します。
通報した相手の連絡先がわかっている場合はすぐに連絡して謝罪する
相手の連絡先が判明している場合は、できるだけ早く連絡を取り、丁寧に謝罪することが重要です。
その場で謝罪すれば、通報を取り下げてもらえる可能性があります。
また、あおり運転のつもりがなかった場合は、誤解を解く機会にもなるでしょう。
なお、相手がわからない場合でも、車両ナンバーが判明していれば、陸運支局で登録事項等証明書を取得することで所有者を特定できます。
ただし、手続きが煩雑なため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
通報内容に覚えがないか誤りがあれば、反証するための証拠を集める
あおり運転をした覚えがなく、通報が誤報である場合は、自身の無実を証明する証拠を集める必要があります。
具体的には、自分の車に設置されたドライブレコーダーの映像、周辺の防犯カメラの映像、目撃者の証言などが有効な証拠となります。
これらの証拠は時間が経つと入手が困難になる場合があるため、可能な限り早急に収集することが重要です。
警察の取り調べには誠実に対応する
警察から呼び出しを受けた場合は、取り調べに対して誠実な態度で応じることが重要です。
反省の態度を示し、事実を素直に認めることで、心証を良くし、身柄拘束の期間を短縮できる可能性があります。
一方で、反省せず反抗的な態度を取ると心証を悪くし、通常逮捕手続きに移行するリスクが高まります。
また、「被害者に謝罪したい」と申し出れば、被害者の承諾を得られる限り、連絡先を教えてもらえる場合もあります。
弁護士に今後の対応について相談する
あおり運転で通報された可能性がある場合は、できるだけ早く刑事事件の実績豊富な弁護士に相談することが重要です。
弁護士に依頼することで、被害者の特定や示談交渉、警察対応のアドバイス、証拠収集など、幅広いサポートを提供できます。
逮捕前であれば逮捕回避に向けた対応を、逮捕後であれば被害者との示談交渉や勾留回避に向けた活動をおこなうことが可能です。
また、社会復帰や更生に向けた総合的なサポートも期待できるでしょう。
さいごに | あおり運転で逮捕されるか不安な場合は弁護士に相談を!
あおり運転で逮捕された場合、妨害運転罪をはじめとする重い刑罰が科せられ、前科がつくことで就職や社会生活に長期間にわたって影響を与える可能性があります。
また、実名報道や損害賠償請求など、刑事罰以外のリスクも深刻です。
とはいえ、適切な対応を取ることで、これらのリスクを最小限に抑えることは可能です。
通報された段階での謝罪、証拠収集、警察への誠実な対応など、初期対応が非常に重要になります。
とくに弁護士への早期相談は、逮捕回避や不起訴処分の獲得、被害者との示談交渉など、さまざまな面でメリットがあります。
ひとりで抱え込まず、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することで、最適な解決策を見つけることができるでしょう。