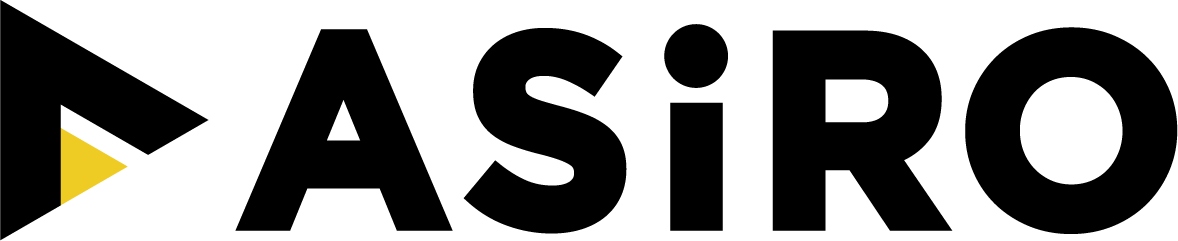「刑事事件の加害者になってしまい、逮捕されそう」
「身近な人が刑事事件を起こしてしまった」
などといった事情で、刑事事件の流れを知り、心づもりをしておきたいという方もいるかもしれません。
刑事事件を起こして、逮捕や勾留をされれば、通常の生活を送ることができなくなります。
捜査の結果、起訴されれば、ほとんどのケースで有罪になり、前科がつきます。
刑事事件では、全体の流れを知って、早めに手を打つことが大切です。
本記事では、刑事事件の流れを順に解説し、各段階でおこなわれる手続きの内容と注意点を紹介します。
刑事事件の流れの全体像
刑事事件の手続きは、以下の流れで進行します。
- 捜査開始
- 逮捕
- 起訴か不起訴か決定される
- 公判手続
- 判決・上訴
- 判決の確定・刑の執行
刑事事件の流れ①|刑事事件の発生・捜査開始
刑事事件は、警察が事件の発生を知ったときから始まります。
目撃者によって110番通報をされたり、パトロール中の警察官に目撃されたりすることで発覚する場合もあります。
そのほか、被害者が被害届を提出して捜査が開始されるケースもあるでしょう。
刑事事件の流れ②|逮捕・捜査
現行犯などで被疑者がわかっている場合は、その場で逮捕されます。
被疑者がわからない場合や証拠が不十分な場合は、警察による捜査のあとに逮捕されることになるでしょう。
なお、刑事事件を起こしても、必ずしも逮捕され、身柄を拘束されるとは限りません。
「身柄事件」とされるか「在宅事件」とされるかによって、対応がそれぞれ異なります。
身柄事件とは|逮捕で身柄が拘束される事件のこと
逮捕後、身柄を拘束される事件のことです。
留置場や拘置所で寝起きし、取り調べの際に警察署や検察庁、裁判所に移動させられます。
通常どおりの日常生活は送れません。
在宅事件とは|身柄が拘束されずに捜査される事件のこと
事件発覚後、逮捕されずに捜査が進められる事件です。
警察からの呼び出しがあれば、出頭して取り調べを受けます。
在宅事件は、身柄事件と異なり、検察が起訴するかどうかを判断するまでのタイムリミットがありません。
そのため、長期化するケースが多くあります。
身柄事件か在宅事件かの判断基準
身柄事件とされるか、在宅事件とされるかの判断は、以下のポイントを基になされます。
| 要件 | 内容 |
| 犯罪事実の重大性 | 殺人・強盗・放火・強姦などの凶悪犯罪のほか、略取・誘拐・強制わいせつなどの重大な犯罪かどうか |
| 罪証隠滅のおそれ | 事件に直接関わる証拠を隠したり、目撃者や共犯者などの証人と口裏を合わせたりするなど、犯罪の証拠を隠滅させる可能性があるか |
| 逃亡のおそれ | 所在不明となるおそれがあるかどうか、年齢・住所・職業・定職の有無・暴力団員やその関係者かなどの事情から判断されることが多い |
| 現行犯か否か | 目の前で犯罪がおこなわれていたり、犯行直後であったりする場合は、逮捕状がなくても逮捕され、身柄事件となる |
刑事事件の流れ③|勾留請求・勾留決定
身柄事件の場合は通常、逮捕されると48時間以内に検察官へ身柄を送致されたあと、24時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります。
検察官の勾留請求に対して裁判所が相当と判断し、勾留決定を発布すれば身柄拘束期間が延長され、取り調べが続きます。
裁判所が勾留を認めるかどうかは、以下の勾留の要件を満たすかどうかによります。
| 要件 | 内容 |
| 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある | 捜査機関による主観ではなく、客観的な証拠があり、合理的な嫌疑であるといえる |
| 勾留の理由 | ・被疑者が定まった住所を要しない ・被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある ・被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき |
| 勾留の必要性 | ・勾留理由はあるものの、勾留によって被る被疑者の不利益が不相当に大きいとみなされる場合は、勾留の必要性がないとされる ・比較的軽い犯罪の場合には、必要性の欠如を理由に勾留されない場合が多い。 |
起訴前の勾留期間は最長20日間
起訴前勾留の期間は、当初は原則として10日間以内です(刑事訴訟法208条1項)。
裁判官の判断により、検察官が請求した勾留期間が短縮されることもあります。
ただし、検察官の請求によりやむを得ない事由がある場合には、裁判官によって最長10日間の勾留延長が認められることがあります(同法2項)。
したがって、起訴前勾留の通算期間は最長20日間で、逮捕と通算すると最長23日間です。
刑事事件の流れ④|起訴・不起訴の判断
原則として、勾留期間が満了するまでに、検察官によって起訴か不起訴かの判断がなされます。
起訴決定の前に、処分保留として釈放される場合もありますが、そのようなケースはまれでしょう。
起訴処分・不起訴処分の種類
検察による判断には、以下のような種類があります。
| 起訴処分・不起訴処分の種類 | 内容 |
| 正式起訴 | 通常の公判手続を請求される処分 |
| 略式起訴 | ・簡易裁判所の略式命令によって刑を科すことを求める処分 ・100万円以下の罰金または科料を求刑する場合に限り認められる ・非公開でおこなわれ、かつ「命令」であるため被告人は反論できない |
| 嫌疑不十分 | 犯人でないこと、または犯罪の要件を満たさないことが明白なことを理由とする不起訴処分 |
| 嫌疑なし | 犯罪の嫌疑はあるものの、公判手続きにおいて犯罪事実を立証し得る程度には足りないことを理由とする不起訴処分 |
| 起訴猶予 | 犯罪の嫌疑は確実であるものの、社会における更生を促すなどの目的でおこなわれる不起訴処分 |
起訴か不起訴かの判断基準
検察官が起訴か不起訴かを判断する際の考慮要素としては、以下の項目が挙げられます。
| 判断基準 | 内容 |
| 証拠の有無 | 被疑者が罪を犯したと客観的な証拠をもって立証できるか |
| 被疑者の状況 | 被疑者に分別があったか、犯罪時14歳に満たない、心神喪失状態にあったなどの場合は不起訴となる |
| 犯罪の重大性 | 犯した罪が重大であれば起訴処分、比較的軽微であれば不起訴処分となりやすい |
| 被害弁償(示談)の状況 | ・被害者との間で示談が成立しているか ・示談が成立していれば、被害者感情はある程度回復したとみなされやすく、不起訴処分になりやすい |
| 再犯の可能性 | ・常習性があるか ・再犯の可能性が高いと判断される場合には起訴となりやすい |
| 反省の程度 | 被疑者が真摯に反省しているか |
| 更生をサポートする人の存在 | 被疑者の更生をサポートしてくれる人が身近にいるか |
起訴後の勾留は起訴されてから2ヵ月|保釈が認められることもある
起訴されたあとも勾留は続きます。
期間は、原則として起訴された日から2ヵ月間ですが、必要に応じて1ヵ月ごとに更新することが認められているのです(刑事訴訟法60条2項)。
ただし、保釈制度を利用すれば釈放される可能性もあります。
保釈制度は、弁護人や被告人の親族などが請求し、保釈金を納付すれば、一定の除外事由に該当しない限り釈放が認められる制度です。
また、除外事由に該当する場合でも裁判所が保釈が適当だと判断すれば、職権により許可されることもあります。
刑事事件の流れ⑤|公判手続
起訴されると、約1~2ヵ月以内に第一回公判期日が指定され、裁判がおこなわれます。
刑事事件の裁判の流れは、以下のとおりです。
被告人が起訴内容を認める自白事件では、1回の公判でこれらの手続きが全て終了し、結審に至るケースが多いでしょう。
被告人が起訴内容を認めない否認事件や証人尋問をする事件、裁判員裁判となる事件では、公判期日は複数回にわたる場合がほとんどです。
冒頭手続|基本的な質問や確認の手続
裁判は、以下のような基本事項の確認から始まります。
- 人定質問:氏名、生年月日、本籍、現住所などを尋ね、被告人が本人であることを確認する
- 起訴状朗読:検察官が起訴状を読み上げることで、裁判の目的を明らかにする
- 罪状認否:起訴内容について被告人が認めるかどうかの意見をする
証拠調手続|弁護側と検察側の証拠提出や主張
起訴内容を否認する場合、冒頭手続では裁判での争点を明らかにします。
証拠調べは、冒頭手続で明白となった争点についておこなうものであり、刑事裁判において最も重要な手続きです。
証拠となるのは、供述調書や捜査報告書などの書類、被害者や目撃者などの証人、実際の犯行に使用された物です。
書類は前文朗読が原則ですが、時間を要するため、実務では裁判官への要約説明に留めるのがほとんどでしょう。
証人は尋問を、物は裁判官に示す方法でおこないます。
弁論手続|検察側の論告・求刑と弁護側の主張
証拠調べが終わると、検察による論告・求刑と、弁護人から意見を主張する弁論手続がおこなわれます。
論告・求刑とは、検察から被告人の科せられる刑について意見を述べるものです。
それに対して弁護人は、被告人にとって有利にはたらく汲むべき事情を主張し、適当と考える刑を意見します。
弁論手続が終了すれば、審理を終えたとされ、結審します。
刑事事件の流れ⑥|判決・上訴
公判手続き最終日には、一連の裁判手続きで明らかになった事実を基に裁判所が判決を下し、被告人の処分を言い渡します。
有罪判決には3種類ある
起訴内容が証明され、被告人が罪を犯したことが立証されれば、有罪判決が下るでしょう。
有罪判決には、以下の3種類があります。
実刑判決|刑に服させる旨の判決
猶予期間なく、直ちに刑が執行される判決です。
懲役・禁錮であれば刑務所に収監され、罰金・科料であれば金銭の納付が命じられます。
全部執行猶予付判決|刑について一定期間執行を猶予する判決
刑の執行までに1~5年程度の猶予期間を与えてもらえる判決です。
猶予期間を問題なく過ごせば、刑の執行を受けずに済みます。
一部執行猶予付判決|一部の刑について一定期間執行を猶予する判決
3年以下の懲役もしくは禁錮となった場合に、その期間の一部を1~5年程度猶予してもらえます。
猶予期間を除いた期間については、刑の執行を受けねばなりません。
先に刑が執行され、刑期が満了したあとに猶予期間がスタートします。
2016年6月から導入されたもので、厳密には実刑判決の一種ですが、罪を犯してしまった人を社会の中で更生させるという狙いがあります。
第一審の判決に不満があれば上訴手続きをおこなう
判決内容に不服がある場合は、上訴手続きをおこない、再審を請求できます。
上級裁判所に対しておこない、第二審を請求することを「控訴」、第三審を請求することを「上告」といいます。
上訴には期限があり、判決を受けてから14日以内におこなわねばなりません。
刑事事件の流れ⑦|判決の確定・刑の執行
期間内に控訴・上告がおこなわれなかった場合、または上告審判決の言い渡しから原則10日間が経過した場合には、判決が確定し、刑が執行されます。
最後に
刑事事件を起こして、逮捕、勾留されれば、いつもどおりの生活はできません。
学校や会社に行けなくなり、退学や退職を余儀なくされる可能性もあるでしょう。
さらに、刑事事件で起訴されればほとんどの場合、有罪となります。
有罪となれば前科がつき、今後の社会生活で何らかの影響を受けることもあるでしょう。
過ちを犯してしまったのだから、十分に反省し、科された処罰や処分は甘んじて受けなければなりません。
しかし、反省後はもう一度人生をしっかりやり直すためにも、できるだけ不当に重い処遇を受けるのは避けたいところです。
そのためにも、早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、適切な弁護活動によって、加害者の力になってもらえます。
勾留や起訴を免れたり、起訴されても減刑となったりする可能性が高まるでしょう。
ぜひ刑事事件の解決を得意とする弁護士に特化したベンナビ刑事事件を活用し、早急に近くの頼れる弁護士を見つけてください。