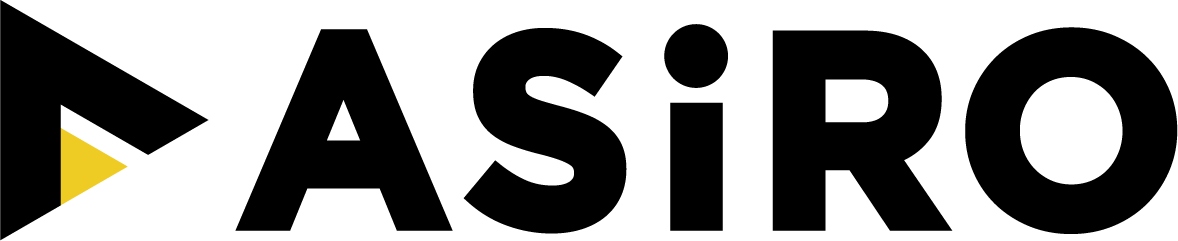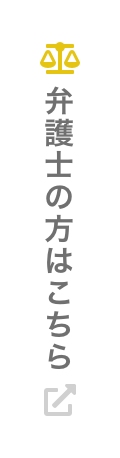- 「会社から支給された備品を無断で持ち帰って自宅用のものにしてしまった」
- 「お客さんから預かったお金を自分の口座に入れてしまった」
上記のような行為は、業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪は、最大で10年の懲役刑が科されることとなる、非常に罪が重い犯罪です。
ただし、窃盗やそのほかの犯罪と区別がつきにくく、自分の行為が業務上横領にあたるのかどうか判断が難しいのも事実です。
なかには罪の意識があまりないまま横領してしまうケースなどもあり、業務上横領罪の成立要件や罪を犯してしまった場合の量刑などを理解しておくことはとても重要です。
本記事では、業務上横領の具体例や業務上横領罪の刑罰、逮捕後の流れや減刑獲得のポイントなどを解説します。
業務上横領とは?
まずは、業務上横領罪が成立する要件や具体例などを解説します。
業務上横領罪の構成要件
業務上横領罪は、仕事や業務など社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務で委託を受けて自分が管理している他人の物を自分のものにした場合に成立する犯罪で、刑法第253条で定められています。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
業務上横領罪の構成要件は6つあり、以下の全てを満たしている場合に成立します。
- 業務性があること
- 委託信任関係に基づいて占有していること
- 他人の所有物であること
- 横領したこと
- 故意があること
- 不法領得の意思があること
ここでいう業務とは「社会生活上の地位に基づいて反復継続しておこなわれる事務」を指し、いわゆる仕事だけでなく町内会やサークルの会計係などのようなものも含まれます。
また、他人の所有物については、金銭だけでなく会社から支給されているパソコンや筆記用具、コピー用紙といった事務用品なども含まれます。
なお、横領行為については、他人の物を売却したり消費したり、質に入れたり隠ぺいしたりなど、非常に広義なケースで認められています。
業務上横領の具体例
たとえば「銀行員が客から預かった現金を自分のものにした」というようなケースでは、業務上横領罪が成立して処罰を受ける可能性があります。
ほかにも、「出納係が金庫から現金を持ち出して、自分の飲食代や買い物などに使ってしまった」というのも業務上横領でよくある事例のひとつです。
また、自分に支給されているペンやパソコンなどを無許可で持ち帰る行為も、業務上横領罪に該当する可能性があります。
業務上横領で逮捕されやすいケース・逮捕されにくいケース
一口に業務上横領といっても、逮捕されるケースもあれば身柄拘束されないケースもあります。
基本的には、横領した金額や犯行の悪質性なども考慮して、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうかという観点などから判断されます。
逮捕されやすいケース・逮捕されにくいケースをまとめると以下のとおりです。
| 逮捕されやすいケース | 逮捕されにくいケース |
|---|---|
| ・横領した金額が多額である ・独身で子どもなどもおらず、逃亡のおそれがある ・証拠隠滅をされる可能性がある など | ・横領した金額が少額である ・家庭や社会的な地位などから、逃亡が困難である ・すでに示談が済んでいる など |
業務上横領は「示談」が重要
業務上横領のような横領事件では「示談が成立するかどうか」がひとつのポイントとなります。
多くの場合、業務上横領に関しては会社側が警察に被害申告することで捜査が開始されます。
犯行後速やかに「被害申告しない」と定めて示談すれば刑事事件化せずに済む可能性がありますし、すでに被害申告されていても示談をして被害届を取り下げてもらうことで逮捕を回避できる可能性があります。
示談は加害者にとって有利な事情として働くため、すでに逮捕・勾留されている場合でも不起訴処分となって捜査が終了したり執行猶予が付いたりすることもあります。
業務上横領罪の刑罰
ここでは、業務上横領罪の刑罰や、「前科・前歴がないケース」や「被害金額が少額のケース」での扱いなどについて解説します。
10年以下の懲役刑のみで罰金刑はない
業務上横領罪の刑罰は「10年以下の懲役刑」です(刑法第253条)。
量刑は、横領した金額や犯行の悪質性などを総合的に考慮して判断されます。
最大で懲役10年の刑が科されることになるため、非常に重たい罪といえます。
初犯でも実刑判決が下される可能性がある
量刑を判断する際は前科前歴の有無なども考慮されますが、初犯だからといって必ずしも執行猶予が付くわけではありません。
たとえば、多額のお金を横領していた場合や、長年にわたって組織的に横領していた場合などは、被害状況や悪質性などが考慮されて実刑となる可能性があります。
被害金額が少額でも業務上横領罪は成立する
たとえ横領した金額が少額であっても、業務上横領罪は成立します。
業務上横領罪の構成要件には「被害額が○○円以上の場合は罰する」などの基準はないため、被害額が数万円程度でも処罰される可能性はあります。
業務上横領罪の時効
業務上横領に関しては「刑事上の公訴時効」と「民事上の損害賠償請求権の時効」の2種類の時効があります。
ここでは、各時効期間について解説します。
刑事上の公訴時効は7年
刑事上の公訴時効は「横領行為が終わったときから7年」です(刑事訴訟法第250条2項4号)。
公訴時効とは「犯罪がおこなわれてから一定期間を過ぎると起訴されなくなる制度」のことです。
業務上横領罪の場合、7年を過ぎて時効が完成すると検察官が起訴できなくなるため、刑事裁判にかけられることもなく刑事手続きは終了します。
民事上の損害賠償請求権の時効は3年または20年
業務上横領をした場合、会社側から損害賠償請求を受けることもあります。
損害賠償請求権についても時効があり、以下のどちらかが経過して時効が完成すると損害賠償請求できなくなります(民法第724条)。
- ・被害者が横領の被害と加害者を知ったときから3年
- ・横領行為がおこなわれてから20年
業務上横領罪の判例
ここでは、業務上横領罪に関する判例を3つ紹介します。
約120万円を横領して懲役3年・執行猶予5年の判決が下されたケース
加害者は市の職員として働いており、知人のデザイン業者に架空の請求をさせて合計約120万円を横領したというケースです。
このケースでは、加害者は横領したお金を借金返済やギャンブルなどに使っており、犯行後はデザイン業者とのメールのやり取りを削除するなどして隠ぺい工作もおこなっていました。
裁判所は、犯行について同情の余地はないものの、被害額を全て弁償済みであるのと同程度と評価できること・すでに懲戒免職されていること・前科前歴がないことなどが考慮され、最終的には懲役3年・執行猶予5年の判決が下されました。
【参考元】横浜地方裁判所横須賀支部 令和元年12月11日判決
約1,800万円を横領して懲役3年6ヵ月の実刑判決が下されたケース
加害者は病院の事務長として医薬品を管理しており、医薬品を水増し発注して不正に転売するなどして、約2年半で合計約1,841万円を横領したというケースです。
裁判所は、加害者に前科前歴がないことや家族が監督することを約束していることなどを踏まえても、被害額を一切弁償しておらず責任逃れの供述をしていたことから、最終的には懲役3年6ヵ月の実刑判決が下されました。
【参考元】大分地方裁判所 平成29年2月3日判決
約10億5,569万円を横領して懲役10年の実刑判決が下されたケース
加害者は会社で経理を担当して会社口座を管理しており、約6年間で合計約10億5,569 万円を横領したというケースです。
裁判所は、加害者に前科前歴がないことや被害額を一部弁償していることなどを踏まえても、被害額が大きいうえに常習性が極めて高く悪質であることから、最終的には懲役10年の実刑判決が下されました。
【参考元】名古屋地方裁判所 令和3年4月15日判決
業務上横領がバレたら、会社はどう対応する?
業務上横領が発覚した場合、会社側の対応としては以下があります。
懲戒解雇される
会社で業務上横領をおこなってしまうと、懲戒解雇されてしまうおそれがあります。
たとえ会社に残れたとしても、降格処分や左遷といった処置がなされる可能性もあります。
また、周囲の視線や態度などが変わってしまい、懲戒解雇されなくても自ら退職しなければならない状況に陥ってしまうこともあります。
損害賠償請求や返還請求を受ける
業務上横領については、懲役刑などの刑事罰だけでなく、民事上の責任が問われて横領してしまった金品などの損害賠償請求を受けることもあります。
なお、なかには「自己破産をすれば返済義務はなくなる」と考えている方もいるでしょう。
しかし、横領などの悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権については原則として免除されないため、自分で支払わなければなりません。
刑事告訴される
会社に業務上横領の事実が知られると、処罰を求めて捜査機関に申告される可能性があります。
刑事告訴されて逮捕・起訴されると、最大10年の懲役刑(※2罪以上あるときは最大15年)が科される可能性があります。
また、前科が付くことで再就職が難しくなったり、インターネット上に自身の名前などが拡散されたりするなどのリスクもあります。
業務上横領がバレたら、すぐに弁護士に相談を
業務上横領が発覚した場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
会社との示談が成立すれば事件化せずに済んだりする可能性がありますが、一個人が会社相手にスムーズに交渉を進めるのは難しく、会社によっては交渉にすら応じてもらえないこともあります。
弁護士なら、どのように対応すればよいか状況に適したアドバイスが望めるだけでなく、代理人として交渉を依頼することもできます。
弁護士が間に入ることで適切な額の示談金で示談成立できる可能性が高まりますし、逮捕の回避や不起訴処分の獲得なども望めます。
法律事務所のなかには夜間や土日でもスピーディに対応してくれるところもあるので、まずは一度詳しく話してみることをおすすめします。
業務上横領罪と似ている罪
業務上横領罪と似た罪としては、単純横領罪・背任罪・窃盗罪などがあります。
ここでは、それぞれどのような違いがあるのか解説します。
業務上横領罪と単純横領罪の違い
単純横領罪とは、自分が管理している他人のものを自分のものにした場合に成立する犯罪です(刑法第252条)。
たとえば、レンタカーを借りたまま返さなかったり、友人から借りたゲーム機を売ったりした場合に成立します。
業務上横領罪との違いは、横領行為が業務に関連しているかどうかです。
横領行為が業務に関連している場合は業務上横領罪、業務に関連していない場合は単純横領罪となります。
業務上横領罪と背任罪の違い
背任罪とは、委託された業務や責任に反して損害を与える行為をおこなった場合に成立する犯罪です(刑法第247条)。
たとえば、パチンコ店に勤務する従業員が客にパチンコ台の設定情報を漏らして店に損害を与えたり、銀行の理事などが資金繰りに困って本来であれば融資が不適当な会社に対して、十分な担保をとることなく貸付をおこなったりした場合に成立します。
背任罪の場合、業務上横領罪とは処罰対象となる行為や目的などが異なります。
業務上横領罪は自己の利益のためにおこなわれた場合に成立しますが、背任罪では第三者の利益のためにおこなわれた場合でも成立します。
ほかにも、業務上横領罪は金銭や物などが横領された場合に成立しますが、背任罪では会社に財産上の損害が生じた場合でも成立するなど、背任罪のほうが成立範囲が比較的広いといえます。
業務上横領罪と窃盗罪の違い
窃盗罪とは、他人が占有するお金や物などを自分のものにした場合に成立する犯罪です(刑法第235条)。
たとえば、コンビニの商品を万引きしたり、電車で隣の人の財布を盗んだりした場合に成立します。
業務上横領罪との違いは、奪った物が自分の占有下にあったかどうかです。
自分が委託を受けて占有している物の場合は業務上横領罪、他人が占有している物の場合は窃盗罪となります。
業務上横領で逮捕された場合の流れ
業務上横領で逮捕された場合、捜査機関による取り調べを受けたのち、起訴された場合は刑事裁判にかけられて有罪・無罪の判決が下されます。
具体的な流れは以下のとおりです。
1.警察による取り調べ
警察に逮捕されたあとは、留置場で取り調べがおこなわれます。
事件の経緯や動機など、事件に関するさまざまな事柄を聴取されます。
この際に作成される供述調書は裁判で重要な証拠となり、不用意な発言をしたりするとのちのち不利に働くおそれがあります。
取り調べの最後には供述調書の内容を確認するタイミングがあるため、話した内容と誤りがある場合にはすぐに訂正を依頼しましょう。
一度署名・捺印をしてしまうと訂正ができなくなります。
2.検察への送致・勾留
逮捕されてから48時間以内に検察へ身柄が引き渡され、検察では警察同様に取り調べを受けることになります。
送致後24時間以内に検察によって勾留請求がおこなわれ、裁判所が請求を認めた場合はさらに10日間身柄を拘束されることになります。
また、検察が引き続き身柄の拘束が必要と判断した場合には、さらに10日間勾留が延長されることもあり、逮捕後から起訴まで最大23日間身柄を拘束される可能性があります。
なお、逮捕後72時間は家族や友人と面会することはできません。
勾留決定がされて接見禁止が付された場合には、弁護人を通じて接見禁止の解除申立をするなどの手続きを取らなければ、その後の勾留中も家族や友人と面会することはできません。
3.起訴・不起訴の決定
勾留期間中に、検察は起訴をするかどうかの判断を下します。
不起訴の場合は、速やかに身柄が解放されて前科も付きません。
一方、起訴された場合は身柄拘束が続き、刑事裁判にかけられることになります。
なお、逃亡や証拠隠滅をおこなう可能性が低いと判断された場合は、起訴後に保釈されることもあります。
4.刑事裁判
刑事裁判では、検察官が被告人の有罪を立証します。
日本の刑事裁判においては99%以上が有罪となっているため、起訴された場合は高い確率で有罪となります。
無実を主張するか、それとも罪を認めて情状酌量を求めるか、どのように裁判を進めるべきか弁護士とよく相談して決めましょう。
5.判決の言い渡し
十分に主張立証が尽くされたところで、裁判官によって判決が下されます。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」であり、有罪判決となった場合は刑務所に入ることになります。
ただし、判決が3年以下の懲役刑であれば執行猶予が付くこともあり、執行猶予が付いた場合は刑務所に入らずに日常生活に戻ることができます。
業務上横領で不起訴処分や執行猶予を獲得するための方法
業務上横領をしてしまった場合に不起訴処分や執行猶予を獲得するための方法としては、主に以下のようなものがあります。
会社に弁償して示談交渉をおこなう
業務上横領をしてしまった場合は、素直に罪を認めて速やかに示談交渉を始めて弁済をおこなう姿勢を見せることが重要です。
状況によっては、会社側としても「なるべく大事にしたくない」「警察沙汰は避けたい」などと考えていることもあります。
速やかに生じた損害分を弁償することができれば、被害申告せずに穏便な形で済ませてくれたり、被害申告を取り下げてくれて逮捕や起訴されずに済んだりする可能性があります。
弁護士に相談する
業務上横領をしてしまった場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
自分で会社と直接交渉したりして解決できるケースもありますが、やはり素人では限界があります。
弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉力などを活かして交渉を進めてくれるため、自力で交渉するよりも穏便かつスムーズな解決が望めます。
また、弁護士なら逮捕直後でも制限なく接見することができ、取り調べで不利な供述などをしないように受け答えのアドバイスなどもしてくれます。
一人で悩んでいると、どんどん時間が過ぎて平和的な解決が難しくなってしまいますので、そうなる前に弁護士にサポートしてもらいましょう。
さいごに
業務上横領罪は被害金額が少額でも成立し、初犯でも実刑判決となる可能性があります。
業務上横領のような横領事件では「被害者との示談が成立するかどうか」がひとつのポイントで、弁護士に依頼することでスムーズな示談成立が望めます。
弁護士のサポートを受けることで事件化せずに済むこともあり、すでに逮捕されていても不起訴処分となって身柄が解放され、捜査終了となることもあります。
当社が運営する「ベンナビ刑事事件」では、横領事件の加害者弁護に強い全国の法律事務所を掲載しています。
お住まいの地域から対応可能な法律事務所を一括検索でき、夜間や土日でも迅速に対応してくれるところも多くあるので、まずは利用してみましょう。