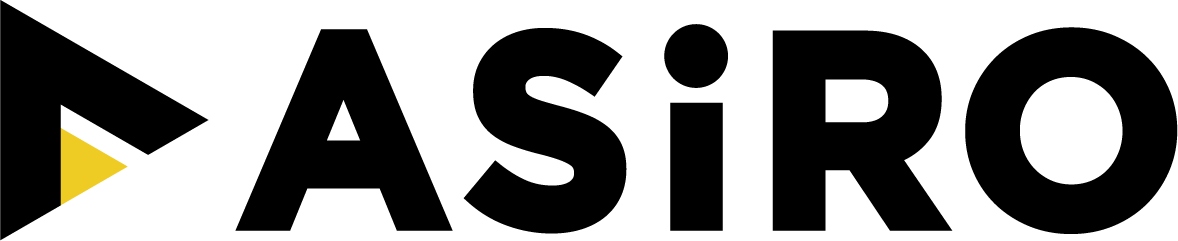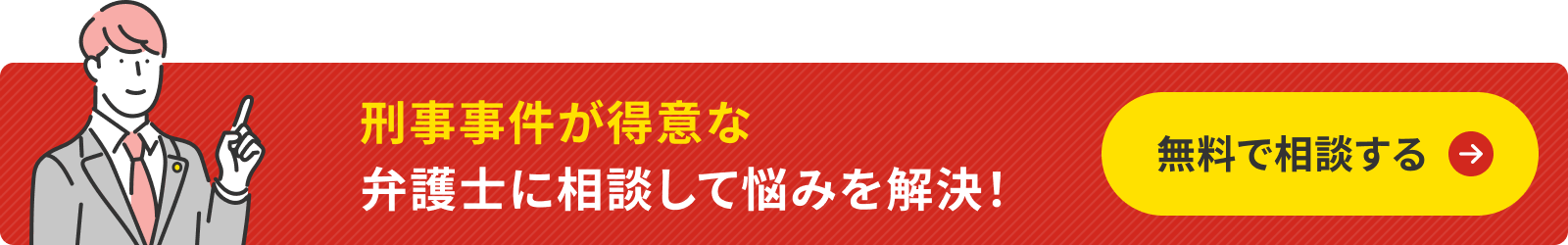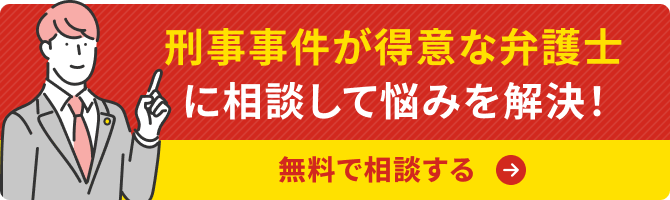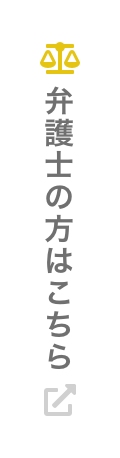- 「引っ越し先のマンションで、前の住人宛の郵便物をうっかり開封してしまった」
- 「間違えて他人の手紙を読んでしまった」
このような行為が何らかの法律に違反しないか、不安に感じている方も多いでしょう。
他人宛の郵便物などを許可なく開封すると、信書開封罪に問われる可能性があります。
しかし、全てのケースで罪が問われるわけではありません。
具体的な状況や開封した理由によっては、罪に問われないケースもあります。
本記事では、信書開封罪の性質や成立要件、刑罰や時効、実際に手紙などを誤って開封してしまった場合の対応方法について解説します。
正しい知識を持つことで、自分の行為が何らかの罪に該当するか判断できるようになりましょう。
信書開封罪とは?信書の秘密を侵す罪
信書開封罪とは、正当な理由がないにもかかわらず、封がされたままの信書を無断で開封した場合に成立する犯罪です。
他人のプライバシーや通信の秘密を保護するための規定です。
信書開封罪の根拠条文は、刑法第133条です。
第十三章 秘密を侵す罪
(信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|e-Gov 法令検索
ここからは、信書開封剤の成立要件や刑罰について、詳しく見ていきましょう。
成立要件|正当な理由なく封をしてある信書を開けること
信書開封罪の成立要件は、「正当な理由なく封をしてある信書を開けること」です。
成立要件の主なポイントは、以下の3つです。
- 「正当な理由」があるかどうか
- 信書に「封がしてある」かどうか
- 開封したものが「信書」に該当するかどうか
それぞれについて、以下で詳しく説明します。
「正当な理由なく」の意味
「正当な理由」があるとされるのは、法律や特別な事情により信書の開封が認められている場合を指します。
以下にて、「正当な理由がない」とされる主なケースと、「正当な理由がある」とされる主なケースをまとめましたので、ご確認ください。
| 「正当な理由」がないといえるケース | 「正当な理由」があるといえるケース |
| ・引っ越し先に届いた、前の住人宛の郵便物を興味本意で開封すること ・勤務先や組織内で、個人宛に送付された郵便物を勝手に開封すること ・宛名人の同意なしに郵便物を開封すること | ・夫宛てに届いた請求書を妻が開封すること ・破産管財人が、破産手続き中の破産者に届いた信書を開封すること ・捜査機関が、捜索差押許可状に基づいて被疑者宛の郵便物を開封すること ・親権者が、監護権の行使の一環として未成年の子ども宛ての信書を開封すること ・宛名人が、開封に同意していると推定できるとき |
「封をしてある」の意味
「封をしてある」とは、信書の内容が第三者に見られないように密閉されている状態を指します。
以下にて、「封をしてある」とはいえない例といえる例をそれぞれまとめました。
| 「封をしてある」といえないもの | 「封をしてある」といえるもの |
| ・封筒の口をクリップで留めている ・紐で軽く結んでいる | ・セロハンテープでしっかり閉じられている ・ステープラーでしっかり閉じられている |
「信書」の意味
郵便法第4条第2項によると、信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。
つまり、個人間での意思伝達や連絡を目的とした文書が信書に該当します。
以下に、信書に該当するものと該当しないものの具体例をそれぞれまとめました。
| 信書に該当するもの | 信書に該当しないもの |
| ・書状 ・請求書など ・会議招集通知など ・許可証など ・各種証明書 ・ダイレクトメール | ・小切手 ・プリペイドカード ・乗車券 ・クレジットカード ・チラシやパンフレット ・遺言書 |
刑罰|1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
信書開封罪が成立すると、「1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」が科される可能性があります。
拘禁刑とは、従来の刑罰である懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰をいいます。
時効|信書を開けたときから3年
信書開封罪の公訴時効は「3年」と定められています。
公訴時効とは、一定の期間が経過すると検察官が被疑者を起訴できなくなる制度です。
公訴時効は、犯罪行為が終了した時点からカウントされます。
ここでいう「犯罪行為が終了した時点」とは、犯罪によって結果が発生した時点を含むと解釈されています。
信書開封罪では、実際に信書を開封した時点が犯罪行為の終了時点とみなされます。
そのため、信書を開封してから3年が経過すれば、刑事責任は問われなくなります。
信書開封罪は親告罪!告訴されなければ罪に問われない
刑法第135条では、信書開封罪が「親告罪」にあたることが定められています。
つまり、被害者が警察や検察に対して「処罰してほしい」と正式に告訴しなければ、検察官は事件を起訴できません。
起訴されなければ裁判が開かれることもなく、有罪判決を受けたり、前科がついたりすることもありません。
なお、告訴できる人物は信書の差出人だけではない点に注意が必要です。
信書が受取人に届いたあとであれば、受取人も告訴できると解されています。
信書開封罪に関してよくある質問
ここでは、信書開封罪に関してよくある質問をまとめました。
似たような疑問を抱えている方は、ぜひここで疑問を解消してください。
家族を信書開封罪で訴えることはできる?
信書開封罪は、家族間であっても成立する可能性があります。
ただし、実際に犯罪が成立するかどうかは具体的な状況によって異なるため注意しましょう。
たとえば、夫宛てに知らない女性から封がされた手紙が届いたとします。
妻が夫の浮気を疑い、その手紙を本人の了承なく開封した場合、正当な理由がないと判断されれば、信書開封罪に該当する可能性があります。
一方で、夫が突然連絡を絶ち、行方不明になったような緊急事態において、居場所の手がかりを得る目的で手紙を開封した場合には、正当な理由として認められるケースも考えられます。
このように、家族間であっても信書を開封する際には正当性について慎重な判断が必要です。
メールやSNSを無断で見る行為は信書開封罪にあたる?
メールやSNSを無断で見る行為は、信書開封罪には該当しません。
なぜなら、信書開封罪の対象は、「信書」に限られるからです。
ただし、他人のメールやSNSを無断で閲覧する行為は、「不正アクセス禁止法」などのほかの法律に違反する可能性があります。
法的なトラブルを防ぐためにも、他人のメールやSNSを勝手に見るのは控えましょう。
勘違いで封書を開けた場合も信書開封罪になる?
信書開封罪は、「故意に信書を開封した場合」にのみ成立する犯罪です。
そのため、勘違いで開封してしまったようなケースでは、原則として信書開封罪には該当しません。
たとえば、従業員個人宛ての信書が誤って会社宛てに届き、総務担当者などが業務上の郵便物と誤解して開封してしまう場合がよくあります。
このような場合、開封に悪意がなく単なる勘違いであったと判断されれば、「過失による開封」として信書開封罪は成立しません。
さいごに|信書開封罪の罪に問われたときは弁護士に相談を!
本記事では、信書開封罪についてわかりやすく解説しました。
信書開封罪は、正当な理由なく封がされた信書を開封した場合に成立する犯罪です。
信書開封罪は親告罪であるため、被害者による告訴がなければ起訴されませんが、告訴があれば実刑判決を受ける可能性があります。
実刑判決を受けるリスクを軽減するためには、できるだけ早めに刑事事件を得意とする弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士に相談すれば、具体的な事情に応じて今後の対応方針について的確なアドバイスが得られます。
また、示談交渉や刑事手続きの代理なども依頼できるため、最善な方法での解決を目指せるでしょう。
「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、信書開封罪を含む刑事事件の対応を得意とする弁護士を、地域や相談内容に応じて簡単に検索できます。
今後の対応について不安や疑問がある方は、ぜひ一度ご利用ください。