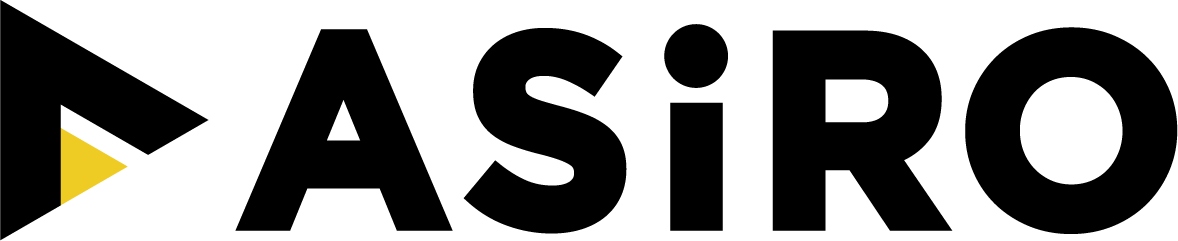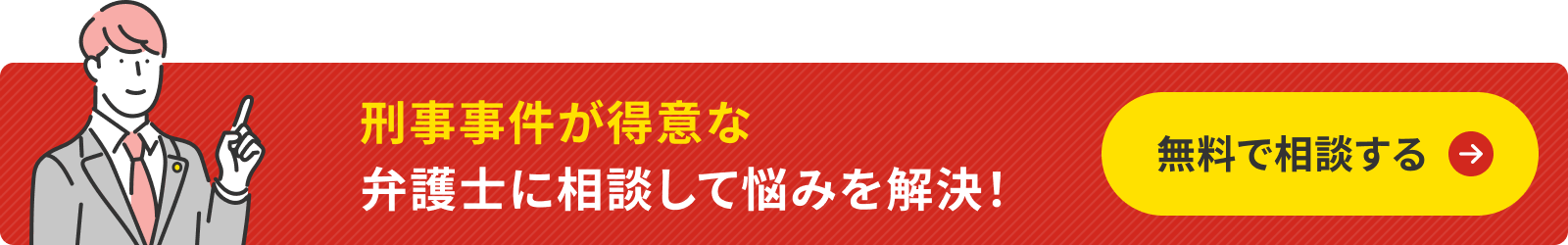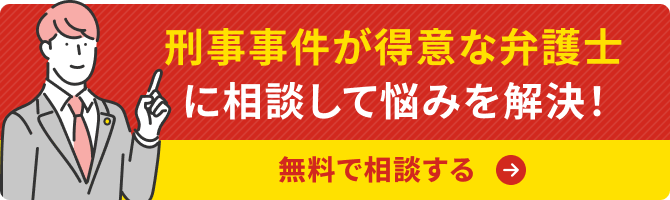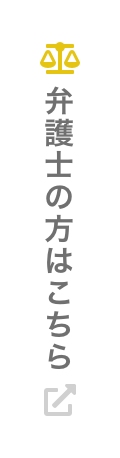家族が突然逮捕され、留置所に拘束されたという知らせを受けたときの戸惑いや不安は計り知れません。
これまで一度も刑事手続きに関わったことがない場合、「面会はできるの?」「何を持っていけばいいの?」「いつ話せるの?」など、疑問や心配ごとが次々に浮かぶことでしょう。
そこで本記事では、はじめて面会を経験されるご家族に向けて、留置所での面会に関する基本ルールや注意点をわかりやすく解説します。
差し入れの可否や持ち物、面会で話してよい内容のほか、面会自体が禁止される「接見禁止」の制度や、その解除方法についても触れるほか、弁護士に接見を依頼することで得られるメリットについても解説するので、家族ができる最善のサポートとは何かを考える一助としてください。
留置所の面会に関する基本ルール
警察署の留置所では、勾留中の被疑者に対して面会の機会が設けられています。
ただし、自由に誰でもいつでも面会できるわけではなく、さまざまな制限や条件が存在します。
まずは、面会が可能となるタイミングや曜日、回数、面会できる人やその人数など、面会の基本ルールを確認しましょう。
留置所で面会できるのは、原則として逮捕されて約3日経過してから
逮捕された直後の72時間は、警察・検察による取り調べや身柄の送致、勾留請求の判断などに充てられるため、家族や友人であっても面会は認められません。
勾留が決定したあと、原則としてその翌日以降から一般の面会が可能となります。
ただし、捜査の都合や接見禁止の有無によって、さらに面会が制限される場合もあります。
留置所にて面会できる回数は1日1回、1回あたりの制限時間は15分~20分
面会は、原則として1日に1組までしか認められません。
たとえば、家族が午前中に面会した場合、同日に別の友人が面会に訪れても受付されません。
そのため、あらかじめ家族内で誰が面会に行くのかを調整しておく必要があります。
なお、1回の面会時間は15分~20分程度です。
限られた時間で伝えたいことを正確に伝えるためには、あらかじめメモを準備しておくことをおすすめします。
留置所の面会時間は、平日の日中 | 土日祝日や夜間は不可
面会の受付は、各警察署の留置係でおこなわれます。
受付時間は署ごとに異なりますが、一般的には平日の午前9時~12時、午後1時~4時など、昼間の時間帯に限られています。
土日祝日や夜間は、面会できません。
事前に対象となる警察署に電話で面会可能時間を確認しておくと安心です。
例外的に面会場所が、留置所以外になることもある
被疑者が取り調べのために検察庁へ移送されていたり、健康上の理由で病院へ搬送されている場合など、留置所以外の施設に一時的に身柄を移されることがあります。
このような場合、たとえ通常の面会時間内であっても面会はできません。
また、警察署に戻ってくる時間が不明確なケースや、長時間の取り調べ・診察が予定されているときには、面会が終日不可能と判断されることもあります。
こうした事情は当日の朝にならないとわからないことが多いため、面会に向かう前に、必ず警察署へ電話を入れて「本日は面会可能かどうか」を確認しておくのが安心です。
留置所で面会できる人に制限はない | 友人・彼女・会社の同僚もOK
留置所で面会ができるのは、家族だけではありません。
友人や恋人、勤務先の同僚などでも、本人と面識があれば面会が可能です。
ただし、事件との関係や被疑者の供述内容によっては、面会が制限される場合もあります。
とくに共犯者がいる事件や、組織的犯罪が疑われている場合などは注意が必要です。
留置所で面会できる人数は、1回につき原則3人まで
一度に面会できる人数は、多くの警察署で3人までとされています。
面会室の広さや警察官の監視体制にも限りがあるため、大人数での面会は認められていません。
家族や親族で訪れる場合は、代表者を決めて交代で面会するようにしましょう。
留置所での面会では、必ず警察官の立会いがある
一般の方が留置所で被疑者と面会する際には、必ず警察官が立ち会います。
面会は接見室と呼ばれる専用の部屋でおこなわれ、被疑者と面会人の間にはアクリル板や金網などが設置されています。
警察官は、接見中の様子を終始監視しており、会話の内容にも注意を払っています。
これは、面会を通じて証拠隠滅や口裏合わせなどがおこなわれるのを防ぐための措置です。
そのため、面会中の会話には一定の制限があり、事件や捜査に関する話題は避けなければなりません。
留置所の面会で話すこと、話せることには制限がある
留置所での面会では、話してよい内容に制限があります。
とくに、事件の詳細、証拠の場所、共犯者との関係、供述や取り調べの状況などについては、捜査妨害や罪証隠滅のおそれがあるとみなされるため、話してはいけません。
また、面会中は録音や録画がされることは原則としてありませんが、必要に応じてメモを取られることがあります。
そのため、面会では、本人の体調や生活上の困りごと、家族の近況など、事件に関係しない話題にとどめましょう。
なお、本人から「自宅を掃除してほしい」といった依頼があっても、証拠隠滅につながるおそれがある内容には応じないよう注意が必要です。
どうしても事件に関する確認をしたい場合は、弁護人を通じておこなうようにしましょう。
留置所での面会における差し入れの基本ルール
留置所での面会に際しては、被疑者本人の生活を支えるために、衣類や現金、書籍などを差し入れることが可能です。
ただし、なんでも自由に持ち込めるわけではなく、警察署ごとに細かな制限やルールが設けられています。
ここでは、差し入れの方法や注意点について、基本的なルールを整理してお伝えします。
直接渡すことはできず、窓口で申し込み警察官に手渡すか郵送なども可
留置所への差し入れは、面会時に本人へ直接手渡すことはできません。
警察署の留置係窓口で「差し入れ希望」と申し出て、持参した品を警察官に預けることになります。
預けた差し入れを警察官が確認し、許可されたもののみが被疑者の手元に届きます。
また、面会せずに差し入れだけをおこなうことも可能です。
遠方に住んでいて来署が難しい場合は、郵送による差し入れが認められている警察署もあります。
事前に電話で対応可否を確認し、宛先や記載方法などを確認しておきましょう。
差し入れができるもの、できないものがある
留置所への差し入れには明確なルールがあり、持ち込める物と禁止されている物があります。
家族であっても、全ての品が許可されるわけではないため、事前に確認したうえで適切な品を選んで差し入れることが大切です。
以下に、差し入れできるものと差し入れできないものの例をまとめました。
| 区分 | 差し入れできるもの | 差し入れできないもの |
| 衣類・身の回り | 下着、Tシャツ、靴下など 紐・金具のないもの | フード付きパーカー、紐つき衣類、ベルトなど |
| 書籍・文具 | 漫画・小説、便箋、封筒、切手 | ホチキス留め冊子・書き込み可能な教材など |
| 現金・貴重品 | 現金 | 財布、時計、スマートフォンなどの貴重品 |
| 飲食物 | 一切不可 | 弁当、お菓子、飲み物など全般 |
| 医薬品 | 一切不可 | 風邪薬、ビタミン剤、湿布、処方薬・市販薬など |
| その他 | 事前に許可が取れている写真や手紙 | タオル、マフラー、電化製品、液体物など警察が不適切と判断した物 |
上記はあくまで一般的な目安であり、警察署ごとに運用が異なることもあります。
とくに衣類や書籍の形式、差し入れ可能な金額などは事前確認が重要です。
迷ったときは、警察署の留置係に問い合わせて確認しましょう。
差し入れされて喜ばれるのは?
留置所での生活は非常に限られており、外部からの差し入れは本人にとって貴重な支えとなります。
なかでも喜ばれるのが現金の差し入れです。
留置施設内では、自費で飲み物や日用品を購入できるため、現金があれば必要な物を自分で用意することができます。
差し入れできる金額には上限がありますが、1万円から2万円程度が目安です。
また、下着やTシャツなどの清潔な衣類や、小説や漫画などの気分転換になる書籍も喜ばれるでしょう。
本人の状況を思いやりながら、必要とされている物を届けてあげることが大切です。
接見禁止により、留置所で面会できない理由
勾留中の被疑者には家族や知人との面会が認められていますが、例外として「接見禁止」が付くと、弁護士以外の面会が一切できなくなります。
ここでは、接見禁止が付されるケースや、接見禁止中の対応、解除の可能性について解説します。
組織的な犯罪で逮捕された場合は接見禁止になりやすい
接見禁止とは、被疑者が外部と接触することで証拠隠滅や口裏合わせを図るおそれがあると判断された場合に、裁判所がおこなう措置です。
なかでも、組織的な犯罪が疑われる事件では、この措置が取られやすい傾向にあります。
たとえば、詐欺罪や覚せい剤、大麻などの薬物犯罪は、複数人が関与する組織型犯罪であるケースが多く、関係者同士が連絡を取り合うことで証拠が隠されたり、供述が変化するリスクがあると判断されがちです。
このような事件では、被疑者が組織の中でどのような役割を担っていたのか、共犯者が誰なのかといった広範な捜査がおこなわれるため、外部との接触を遮断する必要性が高まります。
その結果として、家族であっても面会が認められず、接見禁止が付される可能性があるのです。
接見禁止中も差し入れは可能
接見禁止が付されると、家族や友人を含めた弁護士以外の面会や手紙のやりとりが一切禁止されますが、完全に外部との接触が遮断されるわけではなく、一定の範囲で差し入れは認められています。
たとえば、現金や衣類、書籍など、通常の面会時と同様の物品については、警察署の窓口を通じて差し入れが可能です。
しかし、差し入れ内容の確認は通常以上に厳格におこなわれることが多くなります。
なお、差し入れ時に伝言やメモを同封することは認められていないため、あくまで物品のみの差し入れとなる点には注意が必要です。
何を持参できるか不安な場合は、事前に警察署の留置係に問い合わせ、接見禁止中でも受付可能な品目や手続きについて確認しておくことをおすすめします。
接見禁止は起訴まで続くことが多い
接見禁止の処分は、原則として勾留期間中に限られますが、最大で20日間続くこともあるため、家族との面会が長期間できないケースも少なくありません。
さらに、事件の内容によっては、起訴されたあとも接見禁止が継続されることがあります。
共犯者がいる場合や、組織的な関与が疑われる事件では、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために、裁判中であっても接見が制限されることがあるのです。
こうしたことから、接見禁止は一時的な措置にとどまらず、実際には数週間から1ヵ月近く続く可能性があると理解しておく必要があります。
接見禁止の解除を試みることは可能
接見禁止が付された場合でも、それを解除してもらうための手続きをすることが可能です。
代表的な方法として「接見禁止の一部解除の申立て」があります。
これは、弁護士を通じて裁判所に対し、「家族など特定の人物に限って面会を認めてほしい」と申し出る手続きです。
たとえば、両親や配偶者、子どもとの面会を求めるケースがよく見られます。
申し立てが認められるかどうかは、事件の性質や共犯の有無、家族との関係性、被疑者の供述状況など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
捜査への影響が大きいと判断された場合は、たとえ家族であっても許可が下りないこともあるでしょう。
なお、申し立ては弁護士が代理しておこなうのが通常であり、家族が個別に請求することはほとんどありません。
面会ができず不安な場合には、まず弁護士に状況を伝えたうえで、必要があれば一部解除の申し立てを検討してもらいましょう。
留置所での面会申し込みに関する基本ルール
はじめて警察署で面会を申し込む場合、流れや必要な持ち物がわからず不安に感じる方も多いかもしれません。
ここでは、留置所での面会をスムーズに進めるための申し込み方法や注意点を解説します。
予約はできず、警察署へ直接行って申し込む
留置所での面会は、原則として事前予約制ではありません。
電話での受付はおこなっていないため、平日の日中に警察署へ直接足を運び、窓口で申し込みをおこなう必要があります。
なお、面会に訪れる際は、ほかの家族や知人と予定が重ならないよう、あらかじめ調整をしておくとスムーズです。
1日に1組しか面会できないというルールがあるため、複数人での申し込みには注意が必要です。
事前に電話で面会可能か確かめるとよい
警察署での面会は当日の事情によって実施できないことがあります。
たとえば、被疑者が検察庁での取り調べや現場検証などで庁舎外に出ている場合や、すでにその日に面会が済んでしまっている場合などが該当します。
こうした事態を避けるには、警察署へ向かう前に、あらかじめ電話で面会が可能かどうかを問い合わせておくのが確実です。
なお、電話をする際は「留置管理課につないでください」と伝えれば、担当部署に取り次いでもらえます。
本人の名前を告げたうえで「今日は面会ができそうか」を尋ねれば、現時点での対応可否や注意点を教えてもらえるはずです。
面会時に必要なもの | 身分証のほか印鑑が必要となる場合も
留置所で面会をするには、本人確認のために身分証の提示が求められます。
運転免許証や健康保険証など、公的な証明書を忘れずに持参しましょう。
面会申込書への記入も必要で、氏名や住所、生年月日、連絡先、被疑者との関係などを記載します。
また、複数人で面会に訪れる場合は、全員分の身分証と記入が必要です。
警察署によっては、印鑑の提出や携帯電話の電源オフ、預かりなどを指示されることもあります。
持ち物や手続きは署によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
不備があると面会ができない場合もあるため、万全の準備を心がけましょう。
弁護士に留置所での接見(面会)を依頼するメリット
留置所での一般面会には、時間や回数、会話の内容などにさまざまな制限がある一方で、弁護士による接見は、一般の面会とは大きく異なる特徴があります。
ここでは、弁護士に接見を依頼することで得られる具体的なメリットを紹介します。
弁護士は逮捕直後から接見(面会)して、取り調べの受け方などのアドバイスができる
逮捕された直後は、被疑者がひとりで取り調べに対応しなければならず、精神的にも非常に不安定になりがちです。
その点、弁護士であれば逮捕直後から接見に入り、状況の確認や本人の希望の聞き取りをおこなうことができます。
さらに、取り調べにどう対応すべきか、不利な供述を避けるためにどのような点に注意すべきかなど、法律的なアドバイスをその場で伝えることができる点は、被疑者にとって非常に心強いサポートとなります。
弁護士なら時間制限や立会人なしで接見(面会)ができる
一般の面会は、1日1回・15分〜20分程度という制限が設けられ、警察官が必ず立ち会います。
しかし、弁護士との接見には時間の制限がなく、立会人もつきません。
これは、弁護士と被疑者のあいだの「接見交通権」が認められているためであり、外部に知られることなく自由にやり取りができることが法律上保障されています。
この環境があるからこそ、本人は本音を話すことができ、弁護士も正確な状況把握が可能になるのです。
密室でおこなわれる取り調べに対して適切に対処するためにも、立会なしの接見は極めて重要です。
接見禁止となっても、弁護士であればいつでも面会や差し入れが可能
接見禁止処分が付されると、家族や知人は一切の面会ができなくなりますが、弁護士はこの制限の対象外です。
つまり、被疑者がどのような状況であっても、弁護士は自由に接見が可能です。
また、弁護士は面会だけでなく、差し入れを代行することもできます。
家族が面会できない状況であっても、弁護士を通じて本人の様子を確認したり、必要な支援を届けることができるのは大きな安心材料になります。
さいごに|弁護士に接見を依頼すれば、早期釈放などを実現しやすくなる!
家族が逮捕され、留置所にいるという状況は、多くの人にとって初めての経験であり、大きな不安を伴います。
何をすればよいのかわからず、面会や差し入れを通じて少しでも支えたいと考えるのは自然なことです。
しかし、面会には時間や回数、話せる内容などの制限があり、場合によっては接見禁止で会うことすらできないこともあります。
そうした中で、弁護士は本人に自由に接見できる立場として、大きな役割を果たします。
弁護士は取り調べへの対応を助言し、面会や差し入れも代行可能です。
さらに、勾留への異議申し立てや示談交渉などを通じて、早期釈放や不起訴を目指す動きも可能です。
できるだけ早く弁護士に相談することで、ご家族にとっても安心につながります。
不安な状況だからこそ、専門家の力を頼ることを前向きに検討してみてください。