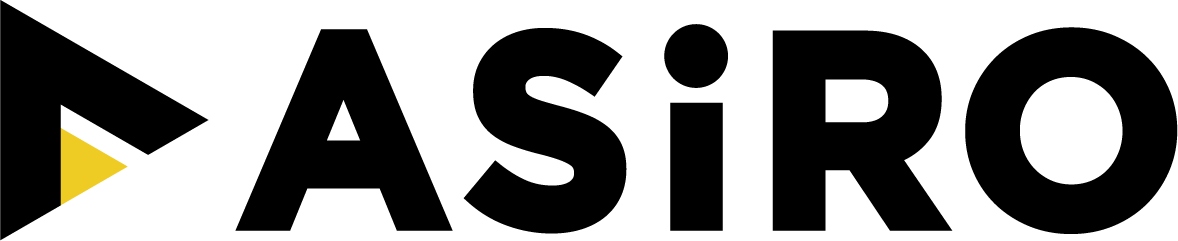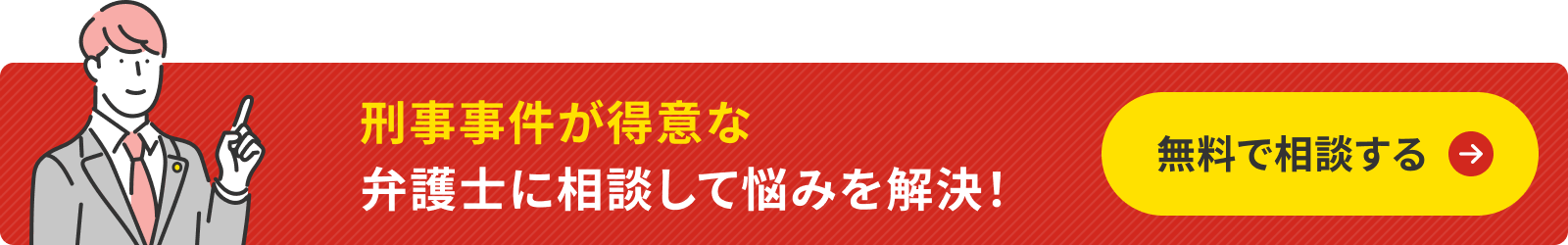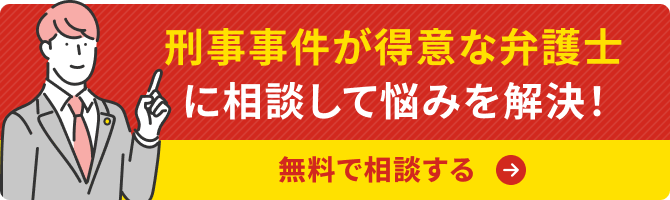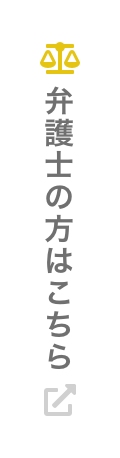「保釈金って何だろう」「払えなかったらどうなるのか」「返ってくるものなのか」など、保釈金に関する疑問や不安を抱えてこのページを訪れた方も多いのではないでしょうか。
突然家族が逮捕され、「保釈すれば出られるらしい」と聞いても、何をどうすればいいのかわからず、戸惑ってしまうのは当然のことです。
特に、保釈金の金額が大きいと聞けば「そもそも用意できるのか」「支払って損をしないのか」といった不安も膨らみます。
この記事では、保釈金の意味や仕組みをはじめ、返金の有無や金額の目安、支払えない場合の対処法、保釈申請から返金までの流れを詳しく解説します。
保釈制度の全体像をつかみ、安心して必要な準備に取りかかるためにも、ぜひ参考にしてください。
保釈金とは?なぜ支払わなくてはならないの?
保釈金とはどのようなもので、なぜ支払う必要があるのでしょうか。
制度の根拠や趣旨がわからなければ、大金を納めることに抵抗や不安を感じるのも当然です。
まずは「保釈」と「保釈金」の基本的な仕組みについて理解しておきましょう。
そもそも保釈とは?起訴後に身柄拘束を解くよう請求する制度
そもそも保釈とは、刑事事件で起訴された被告人の身柄拘束を解く制度です。
被告人は通常、勾留中に起訴されると裁判が終わるまで引き続き勾留されます。
しかし、保釈が許可されれば、自宅などで通常の生活を送りながら裁判に出廷することができます。
保釈金とは、保釈してもらう代わりに被告人が納めなくてはならない保証金
保釈金とは、保釈を許可してもらうために裁判所に預けるお金のことです。
法的には「保釈保証金」と呼ばれ、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりしないようにするための「担保金」の役割を果たします。
保釈金は、被告人が保釈後もきちんと裁判に出廷し、保釈条件を守っていれば、判決後に返金されるのが原則です。
つまり、「罰金」や「使用料」ではなく、「条件を守ること」を前提に一時的に預けるお金であるということです。
保釈金は返ってくる?返ってこない?
保釈金は、一時的に裁判所へ預けるものとはいえ、一般的には高額になるため、「最終的に返ってくるのかどうか」が気になる方も多いでしょう。
実際には、保釈金は一定の条件を守っていれば返還されますが、状況によっては返ってこないケースもあります。
ここでは、保釈金が返ってくる場合と返ってこない場合について、それぞれ見ていきましょう。
被告人が裁判に出廷し、無事に判決が出れば保釈金は全額返ってくる
保釈金は、被告人が裁判にきちんと出廷し、保釈中のルールを守ることを条件として預けられる担保金です。
裁判所から定められた期日に欠かさず出廷し、被害者への接触など禁止されている行動を取らなければ、原則として裁判が終わったあとに全額返還されます。
返金のタイミングは、判決確定後おおむね1週間以内で、裁判所が手続きを進めたうえで、納付者に対して振込で返金がなされます。
なお、被告人が有罪となって実刑判決を受けた場合でも、保釈中の条件を守っていれば返金の対象であることに変わりはありません。
つまり、保釈金は裁判所からの「信用に対する預け金」であり、問題なく裁判を終えれば損をすることはないのです。
被告人が逃亡したり、証拠を隠蔽したりすれば保釈金は返ってこない
被告人が保釈中に定められた条件を破った場合、保釈金は返還されません。
特に、次のような行為があった場合には、全額または一部の没取処分を受ける可能性があります。
- 裁判への出廷を怠った
- 居住制限や連絡義務に違反した
- 被害者や証人など、事件関係者に接触した
- 逃亡や証拠隠滅と疑われる行為をおこなった
また、このような違反が認定されると、保釈は取り消され、被告人は再び勾留されることになります。
保釈金が没取されるだけでなく、裁判所からの心証が悪化し、後の判決にも影響を及ぼす可能性があるので注意しましょう。
保釈金の返金を確実に受け取るためには、裁判が終わるまで慎重に行動し、裁判所が定めた条件を確実に守ることが必要です。
「没取」とは、行政庁・裁判所などが物の所有権を剥奪し、国庫に帰属させる処分のことです。
「没収」が刑法上の刑罰であるのに対し、「没取」は刑罰ではありません。
意味合いとしては「没収」と同じと捉えて概ね問題ありません。
保釈金の相場は?金額を決める基準とは
保釈金は原則として返還されるとはいえ、一時的にまとまったお金を用意しなければならない点で、被告人やその家族にとっては大きな負担となります。
そのため、実際にどのくらいの金額が必要なのか、またその金額はどのように決められているのかを把握しておくことは非常に大切です。
ここでは、一般的な相場と、保釈金の金額が決まる際に考慮される要素について解説します。
保釈金の一般的な相場は150万~300万円程度
実務における保釈金の相場は、概ね150万円から300万円程度といわれています。
これは、被告人の経済状況や事件の性質に応じて「逃亡や証拠隠滅を思いとどまらせる金額」として裁判所が設定するためです。
ただし、これはあくまで一般的な範囲であり、軽微な事件であれば100万円以下となる場合もあれば、重大事件や被告人に相当な資産がある場合などには、1,000万円を超える高額な保釈金が課されることもあります。
保釈金額を決める基準は被告人の資力や罪状など
保釈金の金額は、刑事訴訟法第93条第2項に基づき、裁判所が被告人の状況を総合的に考慮して決定します。
具体的な判断要素は、以下のとおりです。
| 判断要素 | 内容 |
| 被告人の資力 | 資力が大きい場合、仮に逃亡しても痛手とならない金額では抑止力に欠けるため、保釈金は高く設定される傾向 |
| 犯罪の性質・重大性 | 殺人や放火など重大事件であるほど、逃亡や証拠隠滅の動機が強いと判断されやすく、保釈金は高くなりやすい |
| 証拠の内容・証明力 | 裁判で有罪が見込まれるだけの証拠がそろっている場合、逃亡のリスクが高まると判断され、保釈金が加算されることがある |
| 被告人の性格や前科の有無 | 再犯のおそれがあるとされる場合には、逃亡や規則違反のリスクが高いと見なされ、保釈金に影響 |
| 住居や職業などの生活基盤 | 定職がある、住居が固定されているなど社会的な安定がある場合は、逃亡のおそれが低いと判断され、比較的低めに設定されることがある |
このように、保釈金の金額は事件の内容だけでなく、被告人の社会的・経済的背景まで踏まえて個別に判断されます。
なかでも重要なのが、被告人の資力と罪状です。
被告人に多額の収入や資産がある場合、仮に逃亡しても保釈金を失うことに対する心理的な抑止力が弱くなると判断され、保釈金は相場より高く設定されることがあります。
逆に資力がほとんどない場合でも、逃亡を防ぐために最低限の金額は求められやすく、極端に低額にはならない傾向があります。
また、罪の重さも金額に大きく影響します。
たとえば殺人や放火、組織的詐欺など重大な犯罪で起訴された場合、判決で実刑が下される可能性が高く、それに伴って被告人が逃亡する動機も強くなると考えられます。
そのため、裁判所は保釈金を高額に設定して、逃亡や証拠隠滅を防止しようとするのです。
被告人に資力がある場合、保証人が相場をはるかに超えた額になることも少なくない
被告人に多額の資産や高収入があると、保釈金は「逃亡や違反行為を思いとどまらせるのに十分な金額」として、相場を大きく超える額に設定されることがあります。
以下は、被告人の経済力が反映された高額保釈金の例です。
- カルロス・ゴーン元会長(元日産自動車):特別背任などの罪で起訴され、総額15億円の保釈金を納付。これほど高額になったのは、海外逃亡の可能性や極めて高い資力を考慮されたためとされています。
- 堀江貴文氏(ライブドア元社長):証券取引法違反などの容疑で逮捕・起訴された際に、保釈金は3億円に設定されました。大規模な経済事件であり、被告人の資力が大きかったことが影響しています。
- 小室哲哉氏(音楽プロデューサー):詐欺罪で起訴された際、保釈金は3,000万円と設定されました。
事件の内容とともに、被告人の社会的立場や資産状況が考慮された結果とみられます。
これらの事例はいずれも、保釈金がその人の経済的な背景を踏まえて個別に設定されていることを示しています。
保釈金を払えないとどうなる?
保釈が許可されたとしても、指定された金額を納めなければ実際に保釈されることはありません。
ここでは、保釈金を払えない場合に生じる影響や、取るべき対応について解説します。
保釈金を払えないと保釈が認められない
裁判所が保釈を許可しても、その効力が生じるのは「保釈金を納めたあと」です。
保釈金は一括での納付が必要とされており、分割払いや支払いの猶予には対応していません。
そのため、たとえば保釈金が200万円と決まっても、被告人や家族がその金額を一時的に用意できなければ、保釈の許可が出ていたとしても釈放されることはなく、被告人の身柄拘束は続きます。
こうした経済的理由で保釈が実現できない場合、被告人の社会生活や家族の生活にはさまざまな悪影響が及びます。
たとえば、職場への復帰が遅れることで収入が途絶えたり、学生であれば学業の継続が難しくなり、進級や卒業に支障をきたすかもしれません。
また、勾留中は家族や周囲との連絡が制限されるため、信頼関係や精神的な支えが失われることもあります。
このように、保釈金を工面できないことは単なる金銭的問題にとどまらず、被告人とその周囲の生活全体に深刻な影響を与える要因となり得ます。
準抗告により保釈金が減額される可能性はある
保釈の許可が出ても、裁判所が決定した保釈金の金額が高すぎて支払えないという場合には、「準抗告」という手続きを通じて金額の見直しを求めることができます。
準抗告とは、裁判官の決定に対して不服を申し立てる制度のことです。
たとえば、保釈は許可されたが金額が高額すぎて現実的に納付できないとき、その事情を明らかにしたうえで、保釈金の減額を申し立てることが可能です。
準抗告の審理にあたっては、被告人やその家族の経済状況、支払い能力、生活の実態などが具体的に考慮されます。
場合によっては、数十万円から100万円以上の減額が認められることもありますが、保釈金が「逃亡や証拠隠滅を抑止するための担保」である以上、単に生活が苦しいという理由だけでは減額が認められないこともあります。
準抗告が認められるかどうかは個別の事情により異なるため、申立てを検討する際には、弁護士とよく相談することが大切です。
保釈金が払えない場合の対処法
保釈金を一括で納めることが難しい場合でも、保釈をあきらめる必要はありません。
経済的な理由で保釈が実現しない場合に備えて、いくつかの支援制度や代替手段が用意されています。
ここでは、保釈金を支払えないときに検討できる代表的な対処法について紹介します。
まずは弁護士に相談してアドバイスを求めることが推奨される
保釈金の工面が難しいと感じたら、まずは弁護士に事情を説明し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
弁護士は、保釈金の減額申し立ての可能性や、支援制度の活用についての情報を持っており、被告人や家族にとって現実的な選択肢を示してくれます。
また、裁判所とのやり取りや書類作成も弁護士が担うため、スムーズかつ確実に手続きを進めるうえでも、専門家のサポートは欠かせません。
特に支援団体の制度を利用する場合には、弁護士を通じて申請をおこなう必要があるため、早めの相談が重要です。
家族や友人に借りる
保釈金は、被告人本人が用意しなければならないという決まりはありません。
そのため、家族や親族、友人など、周囲の信頼できる人から一時的にお金を借りて納めることも可能です。
実際、保釈金の多くは被告人の家族や支援者によって用意されています。
保釈金は、裁判が終了して被告人が条件を守っていれば返還されるお金であり、返済の見通しが立てやすいことから、事情を説明することで援助を得られる可能性は十分にあります。
ただし、金銭の貸し借りによって人間関係が悪化するのを防ぐためにも、借用書を作成する、返済時期を明確にするなど、誠実な対応を心がけることが大切です。
有価証券などの財産
現金で保釈金を用意することが難しい場合、株式や国債などの有価証券を担保として差し入れる方法もあります。
これは「代用有価証券」と呼ばれる制度で、現金の代わりに一定の価値がある財産を保釈金として納めることが裁判所に認められています。
ただし、全ての有価証券が対象になるわけではなく、裁判所が価値の安定性や換金性を確認したうえで、担保として適切であると判断しなければなりません。
資産の内容や証券の種類によって可否が分かれるため、詳細については個別に確認することが重要です。
「日本保釈支援協会の制度」を利用する
保釈金をどうしても用意できない場合には、一般社団法人日本保釈支援協会が提供する「保釈保証金立替制度」を利用するという選択肢があります。
この制度は、経済的な事情により保釈金の支払いが困難な被告人の家族や支援者に代わって、協会が一時的に保釈金を立て替えるというものです。
利用できる金額には上限がありますが、原則として500万円までの範囲内で立て替えが可能です。
ただし、立て替えにあたっては一定の審査があり、利用者の人柄や事件の内容、再犯の可能性なども考慮されます。
また、立て替えを受ける際には、所定の手数料を支払わなければなりません。
なお、この制度の特徴は、銀行などと異なり担保や保証人が不要である点です。
保釈金は裁判が終われば原則として返還されるため、協会も返金を前提に立て替えをおこなっています。
ただし、被告人が逃亡した場合や条件に違反した場合は、返還されないリスクがあるため、審査は慎重におこなわれます。
利用を検討している場合は、まず弁護士に相談し、手続きの流れや必要書類について案内を受けるのが確実です。
「保釈保証保険制度」を利用する
経済的な事情で保釈金を用意できない場合、全国弁護士協同組合連合会(全弁協)が実施する「保釈保証書発行事業」を活用する方法もあります。
この制度では、裁判所が認めた場合に限り、現金の代わりに「保釈保証書」を提出することで保釈を受けられる可能性があります。
保釈保証書とは、全弁協が「被告人が逃亡等をした場合には、保釈金相当額を弁済する」ことを保証する書面です。
実質的には、全弁協が保証人のような役割を果たし、被告人や家族が現金を直接納めなくても保釈が認められるケースがあります。
ただし、この制度の利用にはいくつかの条件があります。
まず、裁判所が「保証書による保釈」を認める必要があり、全ての事件に適用されるわけではありません。
さらに、全弁協による審査に通過しなければ保証書は発行されません。
保証書の発行には、申請者の資力や信用力に関する確認が必要となり、保釈金額の上限も原則300万円(薬物事件は200万円)に設定されています。
また、保証料として保釈金額の2~3%程度が必要となります。
申請手続きは弁護士を通じておこなうのが原則であるため、制度の利用を希望する場合は、まず担当弁護士に相談し、条件や手続きの流れについて確認することが重要です。
保釈申請から保釈金還付までの流れ
保釈を実現するためには、単にお金を用意するだけではなく、裁判所への申請から保釈金の納付、そして最終的な返還に至るまで、いくつかの手続きを踏む必要があります。
ここでは、起訴後から保釈金の返還に至るまでの流れを6つのステップに分けて紹介します。
1.起訴後、保釈を申請する
保釈の申請は、起訴されて初めておこなうことが可能です。
申請できるのは被告人本人のほか、弁護人、配偶者、直系の親族などに限られています。
通常は弁護士が被告人に代わって保釈請求書を作成・提出します。
申請には、身元引受人の情報や保釈後の生活状況、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す資料が添付されることが一般的です。
2.裁判官面接と検察官意見がおこなわれる
保釈請求が提出されると、裁判所が保釈を許可するかどうかの審査をおこないます。
この過程では、裁判官による被告人や弁護人への面接がおこなわれる場合があるほか、検察官からの意見も聴取されます。
検察官は、保釈を認めるべきではないと考える場合、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」「被告人の行動に不安がある」などの理由を付して反対意見を提出することがあります。
意見聴取の場では、弁護人が身元引受人の信頼性や保釈後の生活の安定性などを丁寧に説明することが、保釈許可に向けた重要なポイントです。
3.保釈許可と保釈金額が決定する
裁判所は、保釈請求とそれに対する検察官の意見、被告人の生活状況や事件の内容などを総合的に考慮したうえで、保釈を許可するかどうかを決定します。
また、保釈が許可される場合はあわせて保釈金の金額も裁判所から通知されます。
保釈の許可が下りたとしても、保釈金を納付しなければ実際に釈放されることはありません。
4.保釈金を納付する
裁判所から保釈が許可されると、指定された保釈金を納める手続きに進みます。
保釈金は原則として現金での一括納付が求められ、通常は裁判所の会計課窓口で支払います。
振込による納付が可能な場合もありますが、裁判所によって対応が異なるため、詳細は弁護士を通じて確認するのが確実です。
保釈金の納付は、原則として平日の日中に限られており、金融機関の営業時間にも関係するため、スケジュールの調整が必要です。
納付が完了すると、裁判所が被告人の釈放手続きを進めます。
保釈金の納付が完了するまで、たとえ保釈が許可されていても身柄の解放は実現しないため、迅速な準備が重要です。
5.保釈金の納付から1~3時間程度で保釈される
保釈金の納付が完了すると、裁判所から拘置所に対して保釈許可の連絡が送られ、拘置所側で手続きが整い次第、被告人は釈放されることになります。
納付から釈放までは通常1〜3時間程度が目安とされていますが、混雑状況や時間帯によって前後する場合もあります。
釈放の際には、被告人に対して保釈中の遵守事項があらためて伝えられます。
たとえば「被害者への接触禁止」「住居の制限」「出頭義務」などが定められている場合、それに違反すると保釈が取り消され、保釈金が没取されるおそれがあるので注意しましょう。
なお、保釈の際は身柄の引受人が釈放予定時刻にあわせて拘置所へ迎えに行くことが一般的です。
無事に保釈されても、裁判は続いていくため、以降の出廷義務などをしっかりと守ることが重要です。
6.判決後、保釈金が還付される
被告人が全ての公判に出廷し、保釈中の条件を守ったまま裁判が終了すれば、保釈金は原則として全額が返還される仕組みです。
判決の内容にかかわらず、保釈中に違反がなければ返還の対象です。
返還の手続きは、裁判の判決が確定したあとに裁判所から通知され、進められます。
返金方法は、裁判所窓口での受け取りのほか、指定口座への振込に対応している場合もあります。
返還までの期間は、判決確定後おおむね1週間から10日程度が一般的です。
なお、保釈中に逃亡や証拠隠滅などの行為があった場合には、保釈金の全部または一部が没取され、返金されないことになります。
返還を受けるには必要書類の保管や手続きの確認が重要となるため、釈放時に交付された書類は大切に保管しておくようにしましょう。
さいごに|保釈金が支払えない場合は弁護士に相談を!
保釈金は、逃亡や証拠隠滅を防ぐための担保として裁判所に預けるものであり、保釈中に定められた条件を守っていれば原則として返還される仕組みです。
しかし、一時的にまとまった金額を用意しなければならないことから、経済的な負担は小さくありません。
とはいえ、保釈金を支払えない場合でも、保釈をあきらめる必要はありません。
準抗告による減額申請のほか、家族や友人からの借入、有価証券の代用、日本保釈支援協会の立替制度、保釈保証書の利用など、さまざまな支援策があります。
こうした制度を適切に活用するためにも、まずは刑事事件にくわしい弁護士に相談することが重要です。
弁護士は被告人や家族の状況を踏まえて最適な方法を提案し、保釈の実現に向けた手続きを全面的にサポートしてくれます。
保釈制度を正しく理解し、適切な支援を受けながら、一日でも早く日常生活を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。