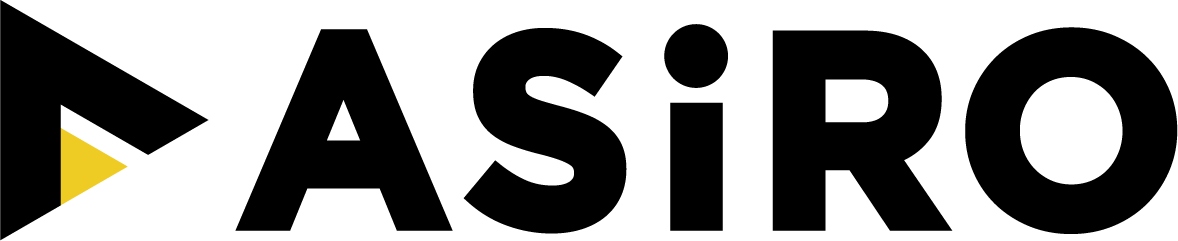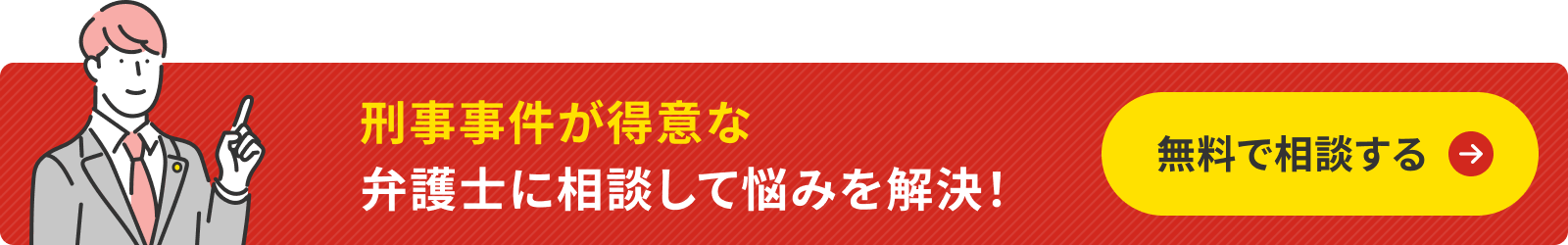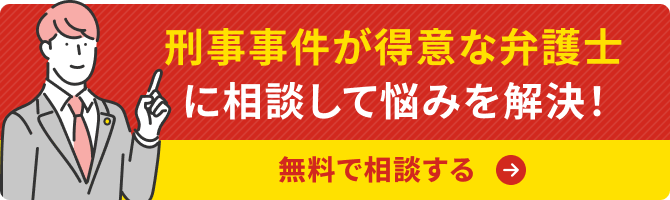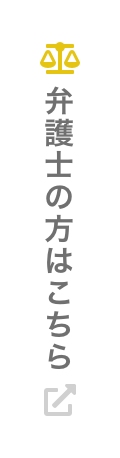窃盗罪の容疑で有罪になると、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の範囲で判決が言い渡されます。
「たかが窃盗程度で刑務所に入ることはないだろう」「スーパーで数百円程度の万引きを常習的に繰り返していただけで何十万円も罰金が科されるはずはない」などと油断をして適切な防御活動を展開しないままだと、初犯でも厳しい刑事責任を問われかねません。
窃盗罪の容疑で刑事訴追されたときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件の対応を得意とする弁護士に相談・依頼するのが大切です。
この記事では、窃盗罪で罰金刑が下されるときの金額相場や統計データ、窃盗罪の罰金の金額が高くなるときの特徴、窃盗罪で逮捕されたときの刑事手続きの流れなどについてわかりやすく解説します。
弁護士に相談するタイミングが早いほど有利な状況を作り出しやすいので、お心当たりの方や刑事訴追されてお困りの方は、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。
窃盗罪は罰金刑ならいくらが相場?懲役刑になることはある?
刑法第235条では、他人の財物を窃取した場合に窃盗罪が成立すると定めています。
ただ、ひとくちに窃盗罪といっても、以下のように幅広い行為態様が含まれる点に注意が必要です。
- 万引き
- 空き巣
- ひったくり
- 置き引き
- 車上荒らし
- 自動車盗
- 自転車盗
- 盗電(電気窃盗)
- 下着泥棒 など
このように、さまざまな行為が同じ窃盗罪として処断されることを理解したうえで、窃盗罪で逮捕・起訴された場合の量刑相場や刑事罰の実情について見ていきましょう。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
また、窃盗罪は未遂犯も処罰対象とされますが、窃盗未遂罪で有罪になる場合も、既遂犯と同じ法定刑の範囲で刑事罰が科されます。
なお、刑法第43条により、未遂犯については刑の裁量的減軽があり得ます。
統計データにみる、窃盗罪の刑罰相場はどのくらい?
ここからは、以下の令和5年の司法統計年報のデータをもとに、窃盗罪で有罪になったときの刑罰相場について解説します。
| 有罪(懲役・禁錮)人員 | 10,551人 |
| 全部執行猶予総数 | 5,227人 |
| 一部執行猶予総数 | 17人 |
| 刑期/執行猶予有無 | 人数 | |
| 15年 | 1人 | |
| 10年以下 | 6人 | |
| 7年 | 43人 | |
| 5年 | 674人 | |
| 3年 | 実刑 | 337人 |
| 一部執行猶予 | 2人 | |
| 全部執行猶予 | 389人 | |
| 2年以上 | 実刑 | 1,413人 |
| 一部執行猶予 | 4人 | |
| 全部執行猶予 | 1,365人 | |
| 1年以上 | 実刑 | 1,988人 |
| 一部執行猶予 | 8人 | |
| 全部執行猶予 | 2,976人 | |
| 6ヵ月以上 | 実刑 | 859人 |
| 一部執行猶予 | 3人 | |
| 全部執行猶予 | 491人 | |
| 6ヵ月未満 | 実刑 | 7人 |
| 一部執行猶予 | 0人 | |
| 全部執行猶予 | 2人 | |
| 金額 | 人数 |
| 総数 | 345人 |
| 50万円以上 | 15人 |
| 30万円以上 | 151人 |
| 20万円以上 | 163人 |
| 10万円以上 | 16人 |
| 金額 | 人数 |
| 総数 | 4,919人 |
| 50万円以上 | 416人 |
| 30万円以上 | 1,863人 |
| 20万円以上 | 2,406人 |
| 10万円以上 | 230人 |
| 5万円以上 | 2人 |
罰金刑より懲役刑を受けている数の方が多い
まず、窃盗罪で有罪になった事案のうち、罰金刑と拘禁刑(懲役刑)のどちらが多いのかを比較しましょう。
令和5年に窃盗罪で有罪になり拘禁刑(実刑判決)が確定した人数は10,551人です。
執行猶予がついた人数を合わせると15,795人になります。
これに対して、罰金刑が確定した人の合計は5,264人です。
つまり、窃盗罪で有罪になる場合には、罰金刑よりも拘禁刑になる確率が高いということです。
拘禁刑が確定すると、刑期を満了するまで服役しなければならず、出所後の社会復帰のハードルも高くなります。
そのため、「たかが窃盗罪」と安易に考えるのではなく、窃盗罪の容疑で刑事訴追された場合には、拘禁刑回避を目指して丁寧に防御活動を展開するべきだと考えられます。
懲役刑は6ヵ月以上3年以内がほとんど、全部執行猶予は約1/3
次に、窃盗罪で有罪になり、拘禁刑が下されるときの刑期や執行猶予の有無に関するデータを整理してみましょう。
まず、拘禁刑(実刑判決)が確定した人数が10,551人、執行猶予付き判決が確定したのが5,244人という点から、窃盗罪の容疑で刑事裁判にかけられて罰金刑を獲得できなかった場合、約67%の確率で実刑判決が下されていることがわかります。
また、執行猶予が付く事件数が全体の1/3に過ぎない点を踏まえると、窃盗罪の容疑で刑事裁判にかけられたときには、「窃盗程度なら当然執行猶予が付くだろう」などと油断せずに、適切な防御活動を展開する必要があるといえるでしょう。
次に、窃盗罪で拘禁刑が下されたときの刑期相場についてです。
窃盗罪を理由に拘禁刑の判断が下される場合、大半の刑期が6ヵ月以上3年以内の範囲に収まっています。
ただし、過去に同種前科がある場合や、窃盗の被害額が高額な事案、累犯加重が適用されるケースなどでは、5年以上の拘禁刑が下される可能性も否定できません。
数ヵ月程度の実刑判決であったとしても、社会生活に与える影響は非常に深刻です。
そのため、窃盗罪の容疑で起訴されて刑事裁判にかけられたときには、刑期の短縮化を目指した防御活動を展開するべきでしょう。
罰金刑は20万円~50万円未満が最多
窃盗罪の容疑で罰金刑が下されるときの金額相場について紹介します。
窃盗罪で罰金刑が下された総数5,264件のうち、約87%に相当する4,583件が、20万円以上50万円未満の罰金を科されています。
ただし、大前提として、窃盗罪で罰金刑が下される事案の90%以上が略式手続きの対象になっている点に注意しなければいけません。
つまり、窃盗罪の容疑で刑事裁判にかけられると、罰金刑ではなく、実刑判決もしくは執行猶予が下される可能性が高いということです。
罰金刑も有罪として扱われる以上、「有罪になりたくない」「前科をつけたくない」などの理由から略式手続きに同意しにくいのは理解できますが、刑事裁判で拘禁刑の判決が下されるリスクを総合的に考慮したうえで、略式手続きへの同意・不同意を冷静に判断するべきだといえるでしょう。
窃盗罪で懲役刑でなく罰金刑になりやすいのは?
ここからは、窃盗罪の容疑で有罪になる事案において、拘禁刑ではなく罰金刑になりやすいケースの特徴について解説します。
初犯や悪質性が低いと、懲役刑ではなく罰金刑が選択されやすい
刑事罰の内容を決めるときには、各刑事事件に関する全ての個別事情が総合的に考慮されます。
窃盗事件の量刑判断の際に、拘禁刑ではなく罰金刑が選択されやすくなる要素は、以下のとおりです。
- 同種前科・前歴がない初犯の場合
- 窃盗の被害額が少額の場合
- 被害者との間で示談が成立している場合
- 被害弁済が済んでいる場合、贖罪寄付をしている場合
- 犯行を認めて反省の態度を示している場合
- 社会生活を送りながらの自主的な更生が期待できる場合 など
ただし、全ての要素を有している場合に罰金刑が選択されるというわけではなく、ここに掲げた事情があるほど罰金刑が選ばれやすくなるという意味合いです。
また、事件の個別事情次第ですが、ここに掲げた事情の多くを有する状況であったとしても、拘禁刑の判断が下される可能性もゼロではありません。
悪質性が高いなど、ケースによっては初犯でも懲役刑になる可能性はある
窃盗罪の容疑で逮捕・起訴されて拘禁刑の判断が下される可能性が高いのは、以下の事情があるときです。
- 過去に同種前科や前歴がある場合
- 執行猶予や保護観察中に再犯に及んだ場合
- 窃盗の被害額が高額の場合
- 組織的犯行、計画性が高いなど、悪質性が高いと判断される場合
- 常習性が認められる場合
- 被害者との間で示談が成立していない場合
- 被害弁済が済んでいない場合
- 刑事手続き中だけではなく、刑事裁判でも犯行を否認している場合
- 身元引受人や家族などの協力を得られず、単独での更生が難しいと判断される場合 など
ただし、刑事裁判でどのような量刑判断が下されるかは、窃盗事件の個別事情によって異なります。
たとえば、被害者との間で示談が成立しており、かつ、過去に前科・前歴がなく完全な初犯であったとしても、犯行態様が悪質で窃盗の被害額が極めて高額な事案の場合には、いきなり拘禁刑の判断が下されることもあるでしょう。
窃盗罪の罰金刑で、罰金額が高くなりやすいのは?
窃盗罪で罰金刑の判断が下される事案では、事件の個別事情によって罰金刑の金額が左右されます。
罰金額が高くなりやすい要素として、以下のものが挙げられます。
- 窃盗の前科・前歴がある場合
- 被害者との間で示談が成立していない場合
- 犯行に悪質性が認められる場合
- 被害額が高額な場合 など
なお、これらの要素がある事案では、罰金刑ではなく拘禁刑の判断が下される可能性も否定できません。
拘禁刑と罰金刑とでは今後の社会復帰の難易度に雲泥の差があるので、「拘禁刑を避けつつ、可能な限り罰金額を引き下げること」を防御目標に掲げて防御活動を展開するべきでしょう。
窃盗罪で罰金刑が科せられた場合の支払い方法
窃盗罪の罰金刑が確定すると、検察庁の徴収担当に罰金を納付する必要があります。
罰金の支払い方法は以下2つです。
- 検察庁から郵送される納付書を使って金融機関で支払う
- 検察庁を訪問して直接支払う
罰金の納付期限は原則として判決確定日から30日以内が指定されます。
また、罰金の支払い方法は現金払いだけで、クレジットカード払いなどのほかの支払い方法には対応していません。
ただし、病気や怪我が原因で今すぐにまとまった現金を用意できない場合や、現金一括では納付は難しいものの分割払いなら確実に完全納付が期待できる場合など、特別な事情がある状況なら、例外的に現金での分割払いが認められる可能性があります。
窃盗罪で罰金刑が科せられたが支払えない場合はどうなる?
検察庁から指定された納付期限までに罰金を支払うことができないと、検察庁から罰金納付に関する督促状が送付されます。
そして、罰金刑未納付のまま督促状に記載された支払い期限が過ぎると、以下の事態が発生する危険性に晒されます。
- 罰金刑を支払えないと財産が差し押さえられる
- 差し押さえるべき財産がなければ労役場留置を強いられる
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
罰金刑を支払えないと財産が差し押さえられる
まず、罰金刑を期限までに支払えないと、財産が強制的に差し押さえられて換価処分される可能性があります。
差し押さえの対象になる財産は、不動産・預貯金・給与などです。
どの財産が差し押さえの対象になるかは検察側の判断次第です。
差し押さえるべき財産がなければ労役場留置を強いられる
罰金刑を支払えずに納付期限が過ぎ、差し押さえるべき財産も存在しない場合には、刑法第18条第1項により、労役場留置が命じられます。
労役場留置とは、罰金を完納できない者を刑務所内に留置して労役に服させる処分のことです。
「罰金刑を支払うことができないなら、代わりに労務を提供しなさい」という趣旨で下されます。
労役場留置による労役は1日あたり原則5,000円に相当します。
たとえば、判決で罰金30万円が確定し、罰金を現金納付できない場合には、60日間の労役場留置が命じられます。
また、労役場留置に付されている期間は、拘禁刑と同じように刑事施設に収容されるので、社会生活から完全に隔離された状態が発生します。
家族などとの面会は可能ですが、会社に出社したり学校に通ったりすることはできません。
そのため、社会生活への悪影響を回避したいなら、指定された期日までに必ず罰金を納付するべきでしょう。
なお、労役場留置に付されたとしても、途中で罰金残額を完納すれば、労役場留置を途中で終わらせることも可能です。
労役場留置の期間が長期に及ぶ場合や、労役場留置を最後まで完遂するのが難しいと感じる場合には、家族や知人などにお金を立て替えてもらうなどの方法を検討してください。
窃盗罪の示談金相場
窃盗罪の容疑で刑事訴追されたときには、できるだけ早いタイミングで被疑者との間で示談交渉を開始する必要があります。
というのも、被害者との間で示談が成立して被害弁償を済ませておけば、拘禁刑を回避して罰金刑の判断を引き出したり、罰金刑の金額を引き下げたりしやすくなるからです。
また、刑事手続きの進捗状況次第では、示談成立によって不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
それでは、窃盗事件を起こしたときの示談金相場はどの程度なのでしょうか。
ここでは、窃盗事件の示談金額について解説します。
初犯でも窃盗罪における示談金相場はかわらない
示談は、刑事事件の被害者と加害者との間で締結する和解契約(示談契約)のことです。
示談契約では、当事者双方の合意が形成される限りにおいて、どのような示談条件を定めるかは自由です。
たとえば、窃盗によって生じた損害分をそのまま示談金にするケースや、被害弁償に加えて慰謝料などを上乗せした金額を示談金にする場合もあります。
そのため、窃盗事件で生じた被害がないような当事者の合意内容によって示談金の金額は変わってくるため、いわゆる「標準的な示談金相場」というものは存在しないのが実情です。
窃盗罪で逮捕され、刑が執行されるまでの流れ
窃盗罪で逮捕されたときの刑事手続きの流れは以下のとおりです。
- 強制的に身柄拘束されて警察段階の取り調べ(主に被疑事実についての認否及び検察官が勾留請求をするかどうかの判断の材料となる取り調べ)が実施される
- 検察官に事件・身柄が送致される
- 検察官が、裁判官に対して勾留請求して裁判官が勾留決定をした場合、勾留される
- 警察及び検察段階の本格的な取り調べが実施され、取り調べの結果を踏まえて、検察官が起訴・不起訴の判断を行う
- 検察官が、略式起訴をした場合は罰金刑、正式起訴をした場合には刑事裁判が開かれる
なお、窃盗事件を起こしたことが警察にバレたとしても、常に逮捕されるわけではありません。
上記の1から5の流れは、逮捕・勾留されたいわゆる身柄事件の場合です。
事件の個別事情、捜査活動の進捗状況次第ですが、逃亡または証拠隠滅のおそれがないと判断された場合には、いわゆる在宅事件として”身柄拘束なしで”任意の事情聴取がおこなわれる可能性もあります。
逮捕・勾留といった強制処分が下されて身柄拘束される期間が生じると、それだけで被疑者の社会生活には大きなデメリットが生じます。
ですから、刑事手続きに巻き込まれたときには、軽い刑事処分を獲得することだけではなく、身柄拘束処分を回避することや身柄拘束期間を短縮化することを目標に防御活動を展開しましょう。
【最大48時間】身柄を拘束され取り調べを受ける
窃盗事件を起こしたことが警察にバレると、逮捕される可能性があります。
逮捕されるシチュエーションはさまざまですが、たとえば、以下のような状況が考えられます。
- スーパーで万引きしているところを店員に見つかり、通報を受けてかけつけた警察官に現行犯逮捕された
- 電車内でスリ行為を働いたところ、犯行を目撃していたほかの乗客にその場で私人逮捕された
- 自動車盗を働いて逃走をしていたが、周囲の防犯カメラ映像を解析するなどによって捜査活動が進められて、通常逮捕(後日逮捕)された など
現行犯逮捕・通常逮捕のどちらであったとしても、被疑者の身柄はその時点で警察に押さえられて警察署に連行されます。
そして、警察署において48時間以内の取り調べが実施されます。
逮捕されたあとに警察で実施される取り調べを拒絶することはできません。
また、逮捕されると留置場に身柄をとどめられるので、会社に出勤したり家族などに電話連絡をしたりすることも許されません。
一定の窃盗事件は微罪処分の対象になる
警察段階の取り調べが終了すると、被疑者の身柄と証拠が検察官に送致されます。
しかし、窃盗罪で逮捕された場合には、微罪処分によって刑事手続きが終了することがある点に注意が必要です。
微罪処分とは、一定の基準を満たす刑事事件について、検察官に送致することなく、警察限りの判断で刑事手続きを終了させる処分のことです。
微罪処分の獲得に成功すれば、警察段階で刑事手続きが終了するので、身柄拘束による悪影響を回避・軽減できるだけではなく、有罪や前科のリスクに怯える必要もなくなります。
微罪処分の対象になる事件の特徴は以下のとおりです。
- 微罪処分の対象事件として事前に検察官から指定を受けた事件類型に該当すること
- 窃盗の被害額が少額であること(2万円以下程度が目安)
- 犯情が軽微であること(衝動的で計画性がない、犯行に及ぶやむを得ない事情があったなど)
- 身元引受人がいること(親、雇用主、弁護士など)
- 被害者の処罰感情が和らいでいること
- 被害弁償が済んでいること
- 前科・前歴がないこと
なお、これらの条件を満たす場合でも、微罪処分を獲得できずに検察官に送致されるケースは少なくありません。
そのため、微罪処分獲得を目指すなら、警察に逮捕されてすぐに刑事事件を得意とする弁護士に連絡をして、早期の示談成立を目指すなどの防御活動をおこないましょう。
【最大24時間】検察へ送致され勾留が請求される
検察に送致されると、今度は検察官から取り調べを受けることになります。
検察官は、送致から24時間以内に勾留請求するかどうかの判断をおこないます。
勾留請求をされると、裁判所で面談がおこなわれ、勾留されるかどうかが決まります。
検察官は、留置の必要があると思料するときに、勾留請求をしなければならない
窃盗事件で、検察官が勾留請求を行う可能性が高いケースは、以下のとおりです。
- 取り調べで被疑者が黙秘・否認をしていたせいで、犯行に関する供述を一切得ることができなかった場合
- 防犯カメラの映像解析や目撃者の参考人聴取に時間を要する場合
- 常習性が疑われる事案で、被害実態の全貌を把握するのに時間を要する場合
- 盗んだ商品などを転売しており、売却ルートなどの捜査活動に時間を要する場合 など
このように検察官が、取り調べ等の「留置の必要があると思料するときは」、刑事訴訟法205条1項に基づき、勾留請求をしなければなりません。
検察官の勾留請求を受けて裁判所が勾留決定をすると、被疑者の身柄拘束期間は、検察官の勾留請求の日にちを含めて原則10日間勾留されることになります。
また、さらに、裁判官は、「やむを得ない事情があると認めるとき」は、検察官の請求により、10日間以内(合計20日間以内)の範囲で勾留を延長することができます。
つまり、逮捕されてから検察官による公訴提起判断がおこなわれるまで、最長23日間(逮捕段階72時間以内 + 勾留段階20日間以内)の身柄拘束期間が発生する可能性があるということです。
【最大20日間】勾留されたまま、起訴されるか決定される
逮捕・勾留期限が到来するまでに、検察官が窃盗事件を起訴するかどうかを判断します。
起訴処分とは、事件を刑事裁判にかける旨の判断のことです。
これに対して不起訴処分は、刑事裁判にかけることなく刑事手続きを終了させる旨の判断を意味します。
「窃盗事件を起こした事実に間違いはないのに、不起訴処分を獲得できる余地はあるの?」と疑問を抱く人も少なくはないでしょう。
窃盗事件を起こした証拠があったとしても、不起訴処分は獲得できます。
というのも、不起訴処分は以下3種類に分類されており、実際に犯行に及んだ事実に間違いがなくても起訴猶予処分獲得を目指す余地は残されているからです。
- 嫌疑なし:犯行に及んだ客観的証拠が存在しない場合。冤罪事犯など。
- 嫌疑不十分:公判を維持するだけの客観的証拠が不足している場合。
- 起訴猶予:犯行を示す客観的証拠は存在するものの、諸般の事情を踏まえると、刑事裁判にかける必要がないと判断される場合。
不起訴処分に付するかどうかを判断するときには、刑事訴訟法第248条により、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」といった事情が総合的に考慮されます。
たとえば、窃盗罪の容疑で逮捕されたとしても、すぐに被害者との間で示談を成立させて被害弁償を済ませ、誠実な態度で取り調べに向き合うことによって、不起訴処分の判断を引き出すことが可能です。
起訴された場合は、刑事裁判で量刑が決定される
検察官が起訴処分の判断を下した場合には、公開の刑事裁判で窃盗事件についての審理がおこなわれます。
公訴事実に争いがなければ初回の公判期日で結審しますが、公訴事実を争う場合には複数回の公判期日が開かれて、裁判所が量刑判断を下します。
なお、窃盗罪で起訴される場合には、略式手続きが適用されるケースが多いです。
略式手続き(略式起訴・略式裁判・略式命令)とは、公開の刑事裁判手続きを省略して、検察官が提出する書面のみで審理がおこなわれる刑事手続きのことです。
簡易裁判所の管轄事件について、100万円以下の罰金刑を言い渡す際に活用されます。
窃盗罪の容疑で起訴する方針が固まったと同時に、公判にて罰金刑を求刑するのが相当と判断された事案については、検察官から略式手続きに同意するかどうかの意見を求められます。
そして、被疑者側の同意が得られたときに限り、略式起訴の形で起訴処分が下されて、罰金刑が即日確定するという流れがとられるのが一般的です。
略式起訴に同意をすると、公開の刑事裁判で主張を展開したり、無罪を狙いにいったりする機会を放棄しなければいけません。
その一方で、即時に罰金刑を確定させることができるので、拘禁刑が科されるリスクを回避できます。
窃盗に及んだ事実を基礎付ける客観的証拠がそろっており、無罪を獲得する余地が残されていない状況なら、略式起訴に同意をしたほうが賢明なケースも少なくありません。
担当弁護士の意見を参考にしながら、略式起訴に同意するべきか刑事裁判で争うべきかを冷静に判断しましょう。
窃盗罪の刑罰をできるだけ軽くするには
さいごに、窃盗罪で刑事訴追されたときに、できるだけ軽い刑事処分・判決内容を引き出すためのポイントを紹介します。
逮捕前の場合は自首も検討する
過去に窃盗事件を起こしたものの、現段階では警察に発覚していないというケースも少なくありません。
このようなケースでは、自首をすることも検討してください。
というのも、捜査機関に犯行が発覚する前に自首をすれば、自首減軽によって有利な刑事処分・判決を獲得できる可能性が高まるからです。
ただし、窃盗の被害額が高額だったり、窃盗の常習性が認められる悪質な事件を起こしていたりすると、自首をしたのに逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されたり、重い刑事処分を下されたりしかねません。
そのため、自首をするかどうかについては慎重な判断が必要です。
たとえば、示談交渉を進めてから自首をすれば、ただ単に自首をするときよりも軽い刑事処分を引き出しやすくなりますし、場合によっては、刑事事件化自体を防ぐこともできます。
しかし、刑事実務に詳しくない素人では適切な判断をしにくいので、窃盗事件について自首を検討しているのなら、警察に訪問する前に弁護士に相談し、自首の是非やタイミングについて検討してもらいましょう。
被害者と示談を成立させ、示談金を支払う
窃盗罪の容疑で刑事訴追されたときには、できるだけ早いタイミングで被害弁償を済ませ、また、示談を成立させましょう。
というのも、被害者との間で示談が成立していれば、微罪処分・不起訴処分・軽い量刑判断を引き出しやすくなるからです。
なお、被害者の処罰感情が強い事案では、加害者側がどれだけ誠実に謝罪をしても、被害者側が示談に応じてくれない可能性もあります。
このような事案では、示談金を支払う代わりに贖罪寄付をするのが効果的です。
なるべく早く窃盗事件の対応を得意とする弁護士に相談・依頼する
窃盗罪の容疑で刑事訴追されたときや、窃盗事件を起こした経験があるときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件の対応が得意な弁護士に相談・依頼をしてください。
というのも、窃盗事件の実績豊富な弁護士の力を借りることによって、以下のメリットを得られるからです。
- 取り調べでの供述方針を明確化してくれるので、客観的証拠と矛盾しない一貫した供述をしやすくなる
- 根拠のない逮捕・勾留といった身柄拘束処分に対して、準抗告や取り消し請求などの方法で対抗してくれる
- 被疑者・被告人にとって有利な情状証拠を用意してくれるので、微罪処分・起訴猶予処分・執行猶予付き判決・罰金刑などの有利な判断を獲得しやすくなる
- 弁護士が示談交渉を代理してくれるので、感情的になっている被害者との間でも早期の示談成立を実現しやすくなる
- 警察に発覚していない窃盗事件について、現段階で自首するべきか否かを判断してくれる
- 捜査活動の進捗状況を総合的に考慮して、略式手続きに同意するべきか否かを判断してくれる
窃盗事件だけではなく、刑事事件を起こして逮捕されると、厳格な時間制限のある刑事手続きが着々と進行します。
刑事手続きのステージが進むほど被疑者・被告人は不利な状況に追いやられるので、少しでも刑罰を軽くしたいのなら、できるだけ早いタイミングで刑事実務に詳しい弁護士にアクセスをしてください。
さいごに | 窃盗罪にあたる行為をしてしまった場合は弁護士に相談を!
窃盗罪の容疑で逮捕・起訴されると、重い罰金刑や拘禁刑などの刑事責任を問われる可能性があります。
有罪になると刑事責任を果たさなければいけないだけではなく、前科者として今後の人生を歩まなければいけません。
これでは、どれだけ反省をしていても、社会復帰が難しくなってしまいます。
そのため、窃盗事件を起こした場合には、できるだけ早いタイミングで適切な防御活動を展開して、微罪処分や起訴猶予処分などの軽い刑事処分獲得を目指すべきだと考えられます。
ベンナビ刑事事件では、窃盗事犯などの刑事弁護を得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で弁護士を検索できるので、窃盗事件について少しでも不安がある方は、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。