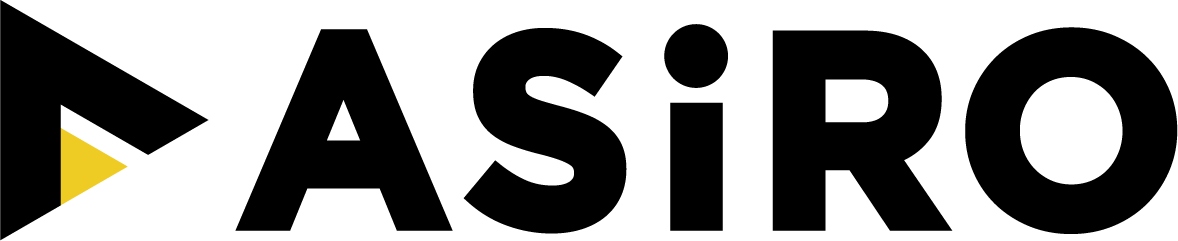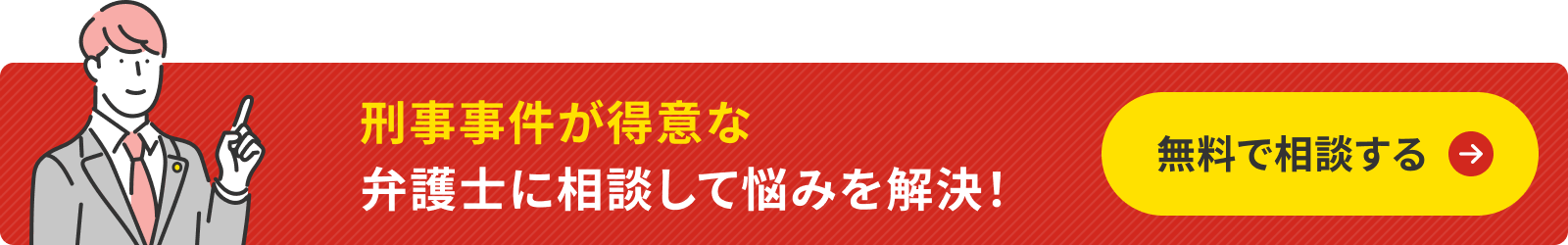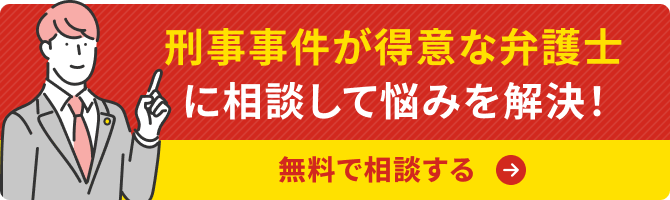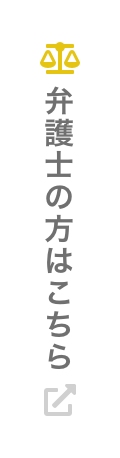- 「うっかり免許の失効に気づかず運転してしまった…」
- 「無免許で運転してしまったら、どんな罰則があるのか不安…」
無免許運転は、重大な交通違反として厳しく処罰される行為です。
意図的でなくても、免許の有効期限切れや停止中の運転などが該当することもあり、知らないうちに法律違反となってしまうケースも少なくありません。
この記事では、無免許運転に該当する行為の種類や、科される罰則、逮捕された場合の流れについてわかりやすく解説します。
無免許運転のリスクを正しく理解し、今後の対応を冷静に考えるための参考にしてください。
 は、刑事事件分野が得意な弁護士を多数掲載中!
は、刑事事件分野が得意な弁護士を多数掲載中!無料相談できる弁護士一覧
無免許運転とは?基本の4種類について
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を得ないで、自動車または一般原動機付自転車を運転することです。
自動車は便利な乗り物ですが、ちょっとした操作ミスや交通ルール違反で人の生命・身体や財産に深刻な損害が生じかねません。
そのため、公道上を運転するには公安委員会が交付する運転免許が必要とされており、運転免許を得ずに自動車などを運転する行為は、違法な「無免許運転」としてさまざまなペナルティが科されているのです。
実際に道路交通法では、以下のように、無免許運転を禁止する規定が置かれています。
(無免許運転等の禁止)
第六十四条第一項 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。引用元:道路交通法|e-Gov法令検索
なお、無免許運転は、その状況に応じて、以下4種類に分類されます。
| 無免許運転の種類 | 内容 |
| 純無免 | 過去に一度も運転免許を取得したことがない人が、自動車や一般原動機付自転車を運転すること。 |
| 取り消し無免 | 交通事故や交通違反が原因で運転免許が取り消されたあと、ふたたび運転免許証の交付を受ける前に、自動車や一般原動機付自転車を運転すること。 |
| 停止中無免 | 運転免許の停止期間中(免停中)に、自動車や一般原動機付自転車を運転すること。 |
| 免許外運転 | 運転免許の対象外の車種を運転すること(例、普通自動車運転免許しか取得していないのに大型自動車を運転すること、など)。 |
ここで注意すべきなのは、「純無免」以外にも無免許運転と判断されるケースがあるということです。
たとえば、免許の取り消しや停止処分を受けたあと、運転免許の効力が復活していないうちに自動車などを運転すると、無免許運転として扱われます。
また、うっかり免許更新を忘れていたケースや、免許の停止期間を勘違いしていたケースでも、自動車などを運転すると無免許運転に該当するので注意しましょう。
一方で、有効な運転免許を交付されているにもかかわらず、自動車などを運転する際にこれを所持していないケースは、いわゆる「免許不携帯」であり、無免許運転とは扱われません。
無免許運転はなぜバレる?
「普通に自動車を運転しているだけなら無免許運転はバレないのでは?」という疑問を抱く人も少なくはないでしょう。
確かに、道路を走行している車両の様子から、運転者が無免許かどうかを判別するのは簡単ではありません。
しかし、実際には、無免許運転は以下のようなシチュエーションで発覚する可能性があります。
- 交通事故発生時に警察から運転免許証の提示を求められる
- 交通違反を起こしたときに警察から運転免許証の提示を求められる
- 自動車検問や職務質問のタイミングで警察から運転免許証の提示を求められる など
自分が交通事故の加害者にならなくても、被害者という立場で交通事故に巻き込まれるケースも想定されます。
そのため、どれだけ自分の運転技術に自信があったとしても、「無免許運転はどこかのタイミングで警察にバレるものだ」と理解しておくことが大切です。
もしも有効な免許を持っていないなら、決して自動車などを運転しないようにしましょう。
無免許運転の罰則と法的責任
ここからは、無免許運転が発覚したときに科される罰則について解説します。
刑罰|3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
無免許運転は道路交通法違反の犯罪です。
無免許運転の罪で有罪になると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の範囲内で量刑が判断されます。
なお、2013年12月の道路交通法改正前までは、無免許運転の罪の法定刑は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑と定められていました。
しかし現在では、拘禁刑・罰金刑の両方が強化されているので、無免許運転の罪で逮捕・起訴された場合には、厳しい刑事処罰が待っていると理解する必要があります。
無免許運転初犯では、罰金刑が科される可能性が高い
検察官・裁判官が無免許運転に対してどのような刑事罰を下すかを判断するときには、刑事事件に関する諸般の事情が総合的に考慮されます。
そのため、無免許運転の罪で検挙されたとしても、以下のようなケースであれば、拘禁刑ではなく罰金刑が選択される可能性が高いです。
- ほかに交通事故を起こしたわけではなく、無免許運転だけで検挙された場合
- 検挙されたのが初犯の場合
- すぐに自動車を手放す、家族などが管理するなどの更生環境が整っている場合 など
なお、これらの事案では拘禁刑の判断が下されるとしても、執行猶予が付くケースが大半です。
ほかの交通違反とあわせて発覚すると罪が重くなる
無免許運転で検挙されたタイミングでほかの交通違反を犯していると、刑事責任が重くなる可能性があります。
たとえば、速度超過でパトロール中の警察に捕まり、そのタイミングで無免許運転が発覚したケースについて考えてみましょう。
このケースでは、被疑者は無免許運転の罪と速度超過の罪の2つの容疑をかけられます。
この2つの犯罪は、いわゆる「併合罪」の関係に立ちます。
併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪のことです。
併合罪の関係にある罪状で有罪判決が下されるときには、量刑判断の際に、以下の修正が加えられて、法定刑が引き上げられます。
- 併合罪のうちの2個以上の罪について有期拘禁刑を下すときには、そのもっとも重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期として景気が判断される。
- 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金刑を下すときには、それぞれの罪状で定められている罰金の多額の合計以下で処断する。
無免許運転の罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、速度超過の罪の法定刑は「6ヵ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
そのため、この両罪の併合罪で有罪になるときには、「4年半以下の拘禁刑または60万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が科されます。
自動車運転処罰法の無免許運転による加重について
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)では、無免許運転で同法に規定されている犯罪行為に及んだ場合に、以下のように法定刑を引き上げています。
| 罪状 | 原則的な法定刑 | 無免許運転の加重 |
| 危険運転致傷罪 | 15年以下の拘禁刑 | 6ヵ月以上の有期拘禁刑 |
| アルコール・薬物・一定の病気の影響によって走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果、アルコール等の影響によって正常な運転が困難な状態におちいり、人を負傷させる罪 | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| アルコール・薬物・一定の病気の影響によって走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果、アルコール等の影響によって正常な運転が困難な状態におちいり、人を死亡させる罪 | 15年以下の拘禁刑 | 6ヵ月以上の有期拘禁刑 |
| 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| 過失運転致死傷罪 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 10年以下の拘禁刑 |
無免許運転の状態で人に死傷結果が生じるような交通事故を起こした場合には厳罰が下される可能性が高いので、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することを強くおすすめします。
行政処分|違反点数25点/一発で免許取り消し
無免許運転が発覚すると、刑事責任を問われるだけではなく、行政処分も下されます。
無免許運転の違反点数は25点です。
そのため、前歴の有無にかかわらず、一発で免許が取り消されるため、欠格期間中は自動車を運転できなくなります。
無免許運転では、同乗者や車を貸した人物にも免許取り消しなどの罰則がある
無免許運転に以下のような関与をした場合、無免許運転をした本人でなくても、刑事罰や行政処分が下されます。
| 違反行為 | 刑事罰 | 行政処分 |
| 事情を知りながら、無免許運転の運転者に対して、運送を要求・依頼して、同乗すること | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑 | 欠格期間2年以上の免許取り消し処分 |
| 事情を知りながら、無免許運転の運転者に対して、車両を提供すること | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑 | 欠格期間2年以上の免許取り消し処分 |
無免許運転をした張本人が刑事罰や行政処分を下されるのは当然です。
しかし、事情を知りながら同情したり車両を提供したりすると、それに関与した人も厳しく法的責任が追求される点に注意しましょう。
人の車に同情したり、誰かに自動車を貸すときには、有効な運転免許証を所持しているかを必ず確認してください。
無免許運転で捕まると最低2年間の欠格期間中は、免許を再取得することもできない
無免許運転で捕まると、一発で運転免許が取り消されるだけではなく、免許を再取得できない「欠格期間」が生じます。
以下のように、違反点数と欠格期間の関係は、過去3年以内の前歴数によって異なります。
| 過去3年以内の前歴の回数 | 欠格期間 | ||||
| 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | |
| 前歴なし | 45点以上 | 40点以上44点以下 | 35点以上39点以下 | 25点以上34点以下 | 15点以上24点以下 |
| 前歴1回 | 40点以上 | 35点以上39点以下 | 30点以上34点以下 | 20点以上29点以下 | 10点以上19点以下 |
| 前歴2回 | 35点以上 | 30点以上34点以下 | 25点以上29点以下 | 15点以上24点以下 | 5点以上14点以下 |
| 前歴3回以上 | 30点以上 | 25点以上29点以下 | 20点以上24点以下 | 10点以上19点以下 | 4点以上9点以下 |
無免許運転の違反点数は25点なので、少なくとも2年の欠格期間が生じることがわかります。
免許取り消し期間中に改めて無免許運転をすると、欠格期間が延長される
免許取り消し・停止期間中は運転免許は有効ではありません。
そのため、免許取り消し期間中に自動車などを運転すると、無免許運転と扱われます。
そして、免許停止中の無免許運転については、停止処分を受けている違反点数に無免許運転分の25点を加算して欠格期間を算定するルールになっています。
たとえば、前歴なしの人が累積違反点数が10点に達して60日間の免許停止処分を下されているケースにおいて、無免許運転をしてしまったケースについて考えてみましょう。
この場合には、「前歴1回、無免許運転25点」が根拠にされるのではなく、「前歴なし、違反点数10点 + 無免許運転25点 = 前歴なし、違反点数35点」と扱われます。
そのため、欠格期間は3年に延長されます。
自動車が使えないことでさまざまな不便を強いられるかもしれませんが、無免許運転をするとさらにペナルティが加算されるので、運転免許が有効でないときには絶対に運転はしないようにしてください。
無免許運転による欠格期間の確認方法
免許取り消し処分が下された場合、運転免許取消処分書が交付されます。
運転免許取消処分書には、違反点数・欠格期間が記載されているので、この文面を確認すれば、いつまで自動車などを運転できないかがわかるでしょう。
なお、運転免許取消処分書を紛失した場合には、お住まい地域を管轄する運転免許センターの行政処分課に問い合わせをすれば、欠格期間などに関する回答をもらえます。
無免許運転で捕まるとどうなる?刑事手続きの流れ
無免許運転は刑事罰が法定されている犯罪です。
また、無免許運転で人身事故を起こしたり、危険運転に及んだりすると、法定刑が加重されるという性質もあります。
そのため、無免許運転が警察に発覚すると、ほかの犯罪に及んだときと同じように、逮捕されて刑事手続きへの対応を強いられる可能性が高いです。
ここでは、無免許運転が原因で逮捕されたときの刑事手続きの流れについて解説します。
警察に逮捕される
交通事故や交通違反、検問などのタイミングで無免許運転が発覚すると、警察に「現行犯逮捕」される可能性があります。
また、交通事故を起こしたあと、無免許運転が発覚するのをおそれて現場から逃走したものの、捜査活動によって身元が特定されたようなケースでは、警察による「通常逮捕(後日逮捕)」が実施されることも想定されるでしょう。
現行犯逮捕も通常逮捕も、被疑者の身体・行動の自由を制約する強制処分です。
そのため、逮捕処分が適法に実施されると、被疑者はその場で身柄拘束されて、警察署に連行されます。
連行されるタイミングを調整したり、連行される前に家族や会社などに電話連絡をしたりすることは一切許されません。
警察で取り調べを受ける
逮捕後、警察署に連行されると、取り調べが実施されます。
警察段階の取り調べには48時間以内の制限時間が設けられています。
取り調べでどのような供述をするかは自由ですが、取り調べ自体を拒否することはできません。
また、取り調べがおこなわれている時間帯以外は、留置場に身柄をとどめられます。
そのため、自宅に戻ったり、外部と電話で連絡をとったりすることができません。
検察官による取り調べを受ける
警察段階の取り調べが終了すると、無免許運転事件が検察官に送致されて、検察で取り調べが実施されます。
検察官による取り調べの制限時間は原則として24時間以内です。
ただし、警察段階の48時間以内と検察段階の24時間以内の取り調べだけでは必要な捜査活動を尽くすことができない場合には、検察官が勾留請求をおこなう可能性があります。
たとえば、防犯カメラやドライブレコーダーの映像を解析するのに時間を要する場合や、被疑者が黙秘している場合などでは、勾留請求が認められることが多いです。
そして、裁判所が勾留状を発付すると、被疑者の身柄拘束期間は最長20日間延長されます。
検察官が起訴・不起訴を決定する
検察官は、逮捕期限または勾留期限が到来するまでに被疑者を無免許運転の罪で公訴提起するかどうかを判断します。
- 起訴処分:公開の刑事裁判にかける判断のこと
- 不起訴処分:公開の刑事裁判にかけずに検察段階で刑事手続きを終了させる判断のこと
不起訴処分の獲得に成功すれば、その時点で刑事手続きが終了するので、有罪や前科のリスクはゼロになります。
一方、起訴処分が下されると、公開の刑事裁判で無免許運転事件について審理されます。
刑事裁判にかけられると高確率で有罪になるので、「有罪になりたくない」「前科者として社会復帰を狙うのは嫌だ」などと考えているなら、不起訴処分獲得を目指した防御活動が不可欠です。
無免許運転の罪に対して罰金刑が下される場合には略式手続きの対象になる
無免許運転の罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑と定められていますが、実際の刑事実務では、無免許運転の罪で検挙された場合、罰金刑の判断が下されることが多いです。
そして、罰金刑に処するのが相当だと検察官が判断する場合には、略式裁判(略式起訴、略式命令)に付される可能性があります。
略式裁判とは、検察官の請求によって、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金または科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで、検察官が提出した書面によって審査する裁判手続きのことです。
略式手続きに同意をすると公開の刑事裁判で反論などを展開する機会を喪失し、無罪を獲得する余地がなくなります。
その一方で、正式裁判手続きを省略して早期に罰金刑を確定できるため、「できるだけ拘束期間を短くしたい」という場合には大きなメリットがあるのです。
刑事裁判にかけられる
無免許運転の罪の容疑で起訴されると、略式手続きの対象にならない限り、公開の刑事裁判が開かれます。
裁判では、証拠調べや証人尋問などの手続きを経て、最終的に裁判官が判決を言い渡します。
仮に判決によって拘禁刑が確定すると、刑期を満了するまで刑務所に服役しなければいけません。
服役が必要な場合、当然一定期間は社会生活から完全に隔離されることになるため、出所後の社会復帰が困難になってしまいます。
たとえば、現在の勤務先を解雇されたり、学校を退学になったりする可能性が高いでしょう。
そのため、無免許運転の罪で起訴された場合には、執行猶予付き判決や罰金刑獲得を目指した弁護活動が不可欠だと考えられます。
さいごに|無免許運転で捕まったら弁護士に相談・依頼を!
本記事では、無免許運転についての種類や刑罰、逮捕後の流れを詳しく解説しました。
無免許運転は立派な犯罪行為です。
場合によっては罰金刑ではなく、実刑が言い渡されるケースもあるので、もしも逮捕の可能性がある場合は早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、交通事犯や刑事事件を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。
- 逮捕・勾留といった強制処分が実施されるのを回避し、在宅事件として処理される可能性が高まる
- 逮捕されたとしても、身柄拘束期間を短縮化するための防御活動を期待できる
- 取り調べへの対応方法や供述内容に関するアドバイスを得られるので、起訴猶予処分獲得の可能性が高まる
- 無免許運転の罪で起訴処分が下されたとしても、罰金刑や執行猶予付き判決など、拘禁刑を回避できる量刑判断を引き出しやすくなる
- 交通事故発生時の被害者との示談交渉など、民事的なトラブル解決のサポートも期待できる など
なお、ベンナビ刑事事件では、さまざまな刑事弁護を得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から、24時間無料で条件に合う弁護士を検索できるので、この機会にぜひご活用ください。