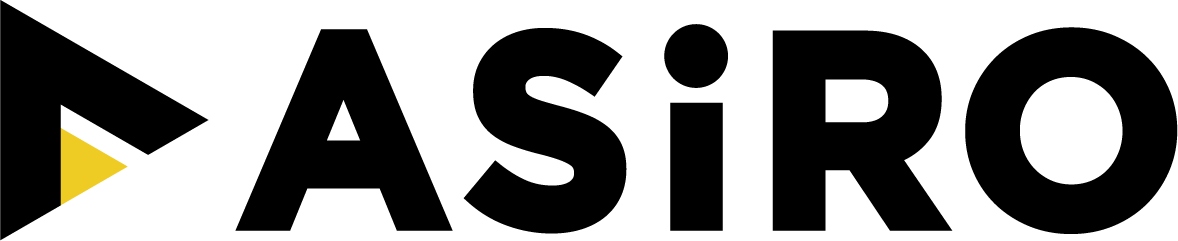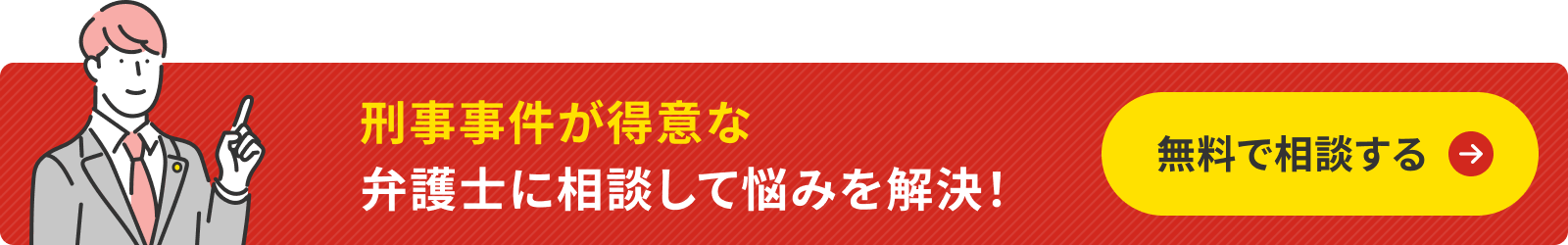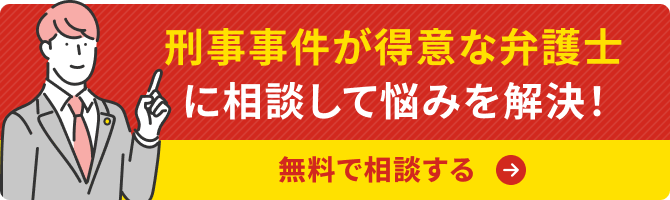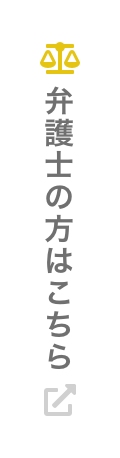人にけがをさせてしまい、傷害罪で逮捕される可能性があるとき、「有罪になってしまうのか」「初犯だから軽い処罰で済むのか」「実際にどのような刑罰を受けることになるのか」と不安になるのは当然のことです。
これまで刑事事件に巻き込まれたことがない方にとって、刑事手続きの流れや処罰の重さは想像がつかず、心配は尽きないでしょう。
そこで本記事では、傷害罪の初犯における起訴の可能性や刑罰の相場、逮捕後の流れについて詳しく解説します。
「つい、かっとなって傷害事件を起こしてしまった」という方は、今後の見通しを立てるためにも、ぜひ最後まで目を通してみてください。
傷害罪は初犯でも起訴され有罪となる?不起訴の確率が高い?
「検察統計2023年」によると、傷害罪で検挙され検察に送検された事件において、初犯者と前科者では起訴率に差があることがわかります。
初犯者の場合、検察が起訴した件数は3,504人(33.1%)で、起訴猶予で不起訴処分となった件数は7,082人(66.9%)でした。
一方、前科者では起訴が2,266人(44.6%)、起訴猶予が2,812人(55.4%)となっています。
この数字から、初犯者は前科者と比べて不起訴(起訴猶予)を目指しやすい傾向があるといえるでしょう。
しかし、初犯であっても約3分の1の人が起訴されているのも事実です。
日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率が99.9%以上と非常に高いため、起訴されれば有罪となる可能性は非常に高いといえます。
そのため、傷害罪の初犯で捕まった場合は、早期に弁護活動を展開し、不起訴処分となるための対策を講じることが大切です。
傷害罪の初犯で科される刑罰の相場は?罰金刑で済む?
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められており、刑罰の幅が非常に広いのが特徴です。
では、初犯の場合はどの程度の刑事罰が科されることが多いのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
傷害罪の初犯で懲役刑になる場合は何年が相場?
「令和5年 司法統計年報 刑事編」によると、傷害罪によって懲役刑が科された場合の刑期は、以下のようになっています。
| 刑期 | 人数 |
| 15年以下 | 8人 |
| 10年以下 | 31人 |
| 7年以下 | 19人 |
| 5年 | 67人 |
| 3年 | 実刑:22 一部執行猶予:0 全部執行猶予:79 |
| 2年以上 | 実刑:95人 一部執行猶予:1人 全部執行猶予:312人 |
| 1年以上 | 実刑:261人 一部執行猶予:1人 全部執行猶予:590人 |
| 6ヵ月以上 | 実刑:149人 一部執行猶予:0人 全部執行猶予:173人 |
| 6ヵ月未満 | 実刑:18 一部執行猶予:0 全部執行猶予:6 |
【参考元】「令和5年 司法統計年報 刑事編」
データを見ると、傷害罪によって懲役刑が科された場合でも大半の場合は、6ヵ月以上3年以下の刑期で済むと考えられるでしょう。
ただし、本データは初犯の人に限らず、前科者も含めたものです。
初犯の場合、そもそも起訴される可能性が低いことを考えると、刑期も少なく済む可能性は十分考えられます。
また、3年以下の懲役刑が科された場合、執行猶予が付きやすい点も見逃せません。
データにおいては、刑期3年の場合、即座に刑務所に入った人が22人、懲役3年のうち一部の期間だけ執行猶予が付いた人は0人、執行猶予期間中に再犯しなければ刑務所に入らなくてよいとされた人は79人いたことがわかいます。
これらを踏まえると、傷害罪の初犯での懲役刑の場合、6ヵ月以上3年以下、かつ執行猶予ありとなるのが相場と考えてよいでしょう。
傷害罪の初犯でも、実刑や重い刑罰をうけやすいケースとは?
初犯であっても、以下のようなケースは重い刑罰が科される可能性が高く、最悪の場合実刑判決を受けるリスクがあります。
- 被害の程度が重大なケース
- 犯行態様が悪質なケース
- 被害者が複数いるケース
- 犯行動機が身勝手であるケース
- 反省の色が見られないケース
- 被害者との示談交渉に取り組んでいないケース
被害の程度が重大な場合、たとえ初犯であっても重い処罰が科される可能性があります。
たとえば、骨折などの重い後遺症が残るようなけがを負わせたケースでは、刑罰の重さも増す傾向にあります。
さらに、犯行の態様が悪質と判断されるケースも同様です。
ナイフや金属バットなどの凶器を使用していたり、計画的に犯行をおこなっていたり、共犯者とともに実行していた場合なども、刑事責任は重くなります。
そのほか、犯行動機が身勝手であったり、取り調べや裁判で反省の態度が見られない場合、被害者との示談に誠実に取り組まない場合も、厳しい判決が下される可能性があるでしょう。
このように、悪質性が高いとみなされるケースでは、初犯であっても軽い処分は期待できません。
傷害罪の初犯で逮捕された場合の流れ
傷害罪の初犯で逮捕された場合、以下のように刑事手続が進みます。
具体的な流れについて、以下で詳しく見ていきましょう。
【逮捕後48時間以内】警察で取り調べを受け、検察に送致されるかが決まる
逮捕されると、最初に警察署の留置場で身柄が拘束されます。
この期間中におこなわれるのが、警察官による取り調べです。
取り調べでは、事件の詳細について事情聴取がおこなわれます。
警察による身柄拘束は法律により48時間以内と定められており、検察への送致か釈放かの判断がおこなわれます。
軽微な犯罪の場合は、厳重注意と指紋採取・顔写真撮影のみで釈放される「微罪処分」となる場合もありますが、傷害罪の場合、微罪処分で済むケースはそこまで多くありません。
一方、検察への送致が決まると、引き続き身柄を拘束されることになります。
なお、逮捕後48時間は、家族であっても原則として面会することができません。
唯一、弁護人または弁護人になろうとする者のみが、制限なく面会することが可能です。
そのため、逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士へ相談し、取り調べなどへの対応方法についてアドバイスをもらうことをおすすめします。
【逮捕後72時間以内】検察で身柄を拘束され、勾留するか否かが決定される
警察による身柄拘束で釈放されない場合、身柄は検察に移されます。
検察での身柄拘束期間は、送致を受けてから24時間以内(逮捕から計72時間以内)と定められています。
検察官は、罪を犯したことを疑うに足りる理由があり、かつ「証拠隠滅の恐れ」または「逃亡の恐れ」があると判断した場合、裁判官に勾留を請求します。
勾留とは、被疑者や被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的でおこなわれる身柄拘束のことです。
一方で、勾留の要件が満たされないと判断された場合は、この段階で釈放されることになります。
ただし、逮捕から72時間以内に証拠が収集でき、被疑者が自白している場合を除き、釈放される可能性は低いのが現実です。
裁判官が勾留状を発付すると、最初の勾留期間として10日間が与えられ、さらに捜査が必要な場合は最大10日間延長され、合計20日間の勾留となります。
【逮捕後最大23日間】検察が起訴・不起訴の判断をする
勾留期間中、検察官は起訴するかどうかの最終判断をおこないます。
傷害罪の場合、検察官の処分は以下の3通りにわかれます。
- 正式起訴
公開法廷での刑事裁判を求める処分。「公判請求」とも呼ばれる。 - 略式起訴
簡易裁判所での略式手続による処罰を求める処分。罰金刑を求刑する場合に被疑者の同意があれば適用される。 - 不起訴
処罰を求めない処分。嫌疑なし・嫌疑不十分の場合のほか、嫌疑が確実でも社会復帰が適当と判断される場合(起訴猶予)もある。
不起訴処分の場合は直ちに釈放され、略式起訴の場合は罰金納付後に釈放されます。
起訴された場合は、起訴後も勾留が続き、刑事裁判を待つことになります。
【起訴から約1ヵ月後】起訴後勾留/刑事裁判の開始
正式起訴された場合、被疑者は「被告人」と呼び方が変わり、起訴後勾留により身柄拘束が継続されます。
ただし、この段階では裁判所に保釈を請求することも可能です。
保釈が認められれば、保釈保証金を預けることで一時的に身柄が解放されます。
そして、起訴から約1ヵ月後に地方裁判所で公判手続きが開始されます。
公判では検察官が犯罪事実の立証をおこない、被告人側は罪を認めて情状酌量を求めるか、罪を否認して争うかの方針を決めます。
その後、最終的な判決が言い渡されます。
傷害罪の初犯で重い刑罰を回避するためには?
傷害罪の初犯であっても、適切な対応を取らなければ重い刑罰を受ける可能性があります。
刑罰を軽減し、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指すためには、以下の3つのポイントが重要です。
- なるべく早く弁護士に相談する
- 被害者と示談を成立させる
- しっかり反省して再発防止に取り組む
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
なるべく早く弁護士に相談する
傷害事件を起こした場合、できるだけ早期に弁護士へ相談することが非常に重要です。
弁護士に依頼することで、今後の対応方針を適切に決定し、早期釈放や不起訴処分を目指すことができるからです。
まず、弁護士は勾留請求を阻止するため、身元引受人や出頭誓約書を用意し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張します。
また、自首を検討する場合も、弁護士が同行することで捜査機関に対して真摯な反省の姿勢を示すことができ、処分の軽減につながる可能性が高まります。
なお、刑事事件においては、国選弁護人を利用する選択肢もありますが、国選弁護人は勾留後でないと選任されないため、逮捕後72時間の重要な初期段階でのサポートを受けることができません(ただし、当番弁護士を利用することは可能)。
一方、私選弁護人であればいつでも選任でき、制限なく面会が可能です。
被害者と示談を成立させる
被害者との示談成立は、不起訴処分となるために極めて重要な要素です。
しかし、加害者が直接被害者と交渉しようとしても、被害者の恐怖や怒りの感情により話し合いを拒否されることも珍しくありません。
その点、弁護士が代理人として示談交渉をおこなえば、被害者が話し合いに応じる可能性が高くなります。
弁護士は被害者の傷害の程度や心情を慎重に確認し、適切な示談条件と金額を提案します。
示談書に「被害者は加害者を許す」という条項が記載されていれば、検察官が不起訴処分とする可能性も高まるでしょう。
しっかり反省して再発防止に取り組む
起訴処分を免れるには、真摯に反省の態度を示すことも大切です。
取り調べでは捜査に全面的に協力し、自分の行為について深く反省していることを示しましょう。
また、傷害事件を二度と起こさないための具体的な対策を実行することも、実刑を回避するためには重要です。
再発防止策は事件の原因や個人の状況によって異なりますが、以下のような対策が考えられます。
- 飲酒が原因の場合:禁酒の誓約、アルコール依存症治療の受診
- 怒りやすい性格の場合:アンガーマネジメント講習の受講、心理カウンセリングの継続
- ストレスや精神的問題:精神科での治療、ストレス管理の専門指導
これらの具体的な取り組みを実際に開始し、その証拠を提出することで、検察官や裁判官に対して真剣な改善意思をアピールできます。
なお、再発防止に取り組む際は、それを支える家族の存在も大きな要素となります。
同居の家族が本人を監督すると誓約することは、有効な再発防止策のひとつになります。
家族による監督体制があることで、社会復帰への意欲と環境が整っていることを示すことができ、処分の軽減につながる可能性が高まるでしょう。
さいごに | 傷害罪の初犯で刑罰を受けるのが不安であれば弁護士に相談を!
傷害罪の初犯であっても、約3分の1の人が起訴されているという統計データが示すように、「初犯だから大丈夫」と楽観視するのは危険です。
日本の場合、起訴されれば有罪率は99.9%以上と非常に高く、実刑判決のリスクも否定できません。
しかし、適切な対応を取れば不起訴処分や執行猶予付き判決を目指すことも十分可能です。
具体的には、早期の弁護士相談、被害者との示談交渉、真摯な反省と再発防止への取り組みが重要なポイントとなります。
特に、逮捕後72時間の初期段階は今後の処分を左右する重要な時期です。
この段階では、国選弁護人は選任されないため、私選弁護人に依頼することを検討しましょう。
なお、ベンナビ刑事事件では、傷害事件を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談に対応している弁護士も多いので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。