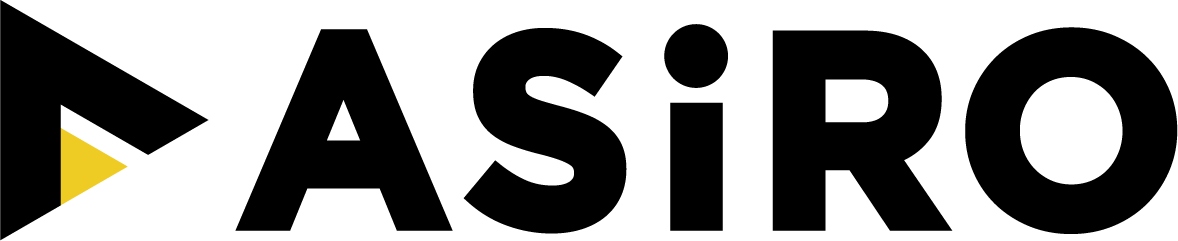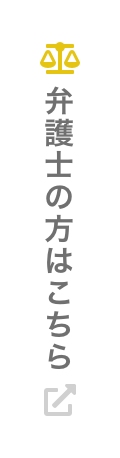- 「盗撮で捕まってしまったけれど、示談って本当に必要なの?」
- 「示談しなかったら、何が起きるのだろう」
盗撮がバレてしまい、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
盗撮事件では、被害者との示談が成立するかどうかが今後の処分や社会生活への影響を大きく左右します。
逮捕・起訴・前科といった深刻な事態を避けるためにも、正しい知識をもって迅速に対応することが重要です。
この記事では、盗撮で示談しないとどうなるのか、示談を進める流れ、示談金の相場、そして弁護士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。
盗撮で示談をしないとどうなる?
盗撮事件で示談をしない場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
以下では、逮捕・勾留・起訴といった刑事手続きの流れに沿って、示談をしないことで起こり得る影響について解説します。
逮捕され取り調べを受ける可能性が高まる
盗撮についての示談が成立していない場合、被害者が被害届を提出すれば警察による捜査が本格化し、逮捕される可能性が高くなります。
近年では、防犯カメラの映像や現場の目撃証言、スマートフォンの位置情報、遺留品など、さまざまな証拠が集められます。そのため、たとえ現行犯を免れたとしても、後日になって身元が特定され、逮捕に至るケースも少なくありません。
さらに、示談が成立していないという状況は、「被害者の処罰感情が強い」と警察に受け取られやすく、逮捕を決断する要因にもなり得ます。
逮捕勾留され、最大23日間も身柄を拘束される可能性が高まる
盗撮の示談をおこなっていないことで逮捕された場合、最長で23日間も身柄を拘束される可能性があります。
この期間が長引くと、日常生活や社会的信用に深刻な影響を及ぼしかねないので注意が必要です。
刑事手続きにおいては、逮捕後72時間以内に勾留が必要かどうかが判断され、勾留が認められれば10日間の拘束が決定されます。
さらに検察官によって勾留の延長請求がおこなわれると、最大で最大20日間にわたって勾留されることになります。つまり、逮捕時から数えると、最大で23日間も警察署の留置施設などに拘束されることになるのです。
そして、この間は外部と連絡はとれないので、仕事を無断で欠勤することになります。その結果、会社から不信感を抱かれ、最悪の場合は解雇につながることもあり得るのです。
また、学校に在籍している場合は、退学処分や内定取り消しにつながるおそれもあるでしょう。
このように、たとえ不起訴となったとしても、拘束された事実だけで社会的信用を失うケースは少なくないのです。
起訴され有罪となる可能性が高まる
盗撮事件で起訴されてしまうと、高い確率で有罪判決を受けることになります。
というのも、日本の刑事裁判では、検察官が有罪を立証できると判断した事件のみを起訴する運用がなされており、起訴された時点での有罪率は99.9%を超えています。
また、たとえ初犯であっても、被害者との示談が成立していなければ、略式起訴によって罰金刑が科されることも少なくありません。この場合も刑事処分を受けたことになり、前科がつくことになります。
そして、前科があると就職・転職・海外渡航・資格更新など、人生のあらゆる場面で支障をきたすおそれがあります。
とくに公務員や医師、教員といった資格職では、有罪判決によって免職・資格停止となる可能性もあるため、注意が必要です。
盗撮の罪は撮影罪の新設で厳罰化されている
2023年7月に施行された改正刑法により、盗撮行為を処罰する「撮影罪」が新たに創設されました。
従来、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例に基づいて処罰されるのが一般的で、法定刑も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と比較的軽いものでした。
しかし、2023年の改正法では「正当な理由なく、ひそかに人の性的な姿態を撮影した者」は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられると規定され、刑罰が大幅に引き上げられています。
さらに、撮影した画像や動画を第三者に提供・送信した場合には、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とされており、被害拡大行為に対する厳罰化も明確に示されました。
つまり、現在の盗撮行為は明確な刑法犯として処理されることになり、以前と比べて起訴・有罪となった場合の社会的影響や刑事責任の重さが大きく変わっているのです。
詳細については、【弁護士監修】撮影罪(盗撮罪)とは?刑罰や構成要件をわかりやすく解説も参考にしてください。
実名報道や解雇などの可能性も高まる
盗撮事件で逮捕・起訴されると、実名が報道されるおそれがあります。
とくに、社会的地位のある職業に就いている場合や、事件の悪質性が高いと判断された場合には、報道機関が実名・顔写真付きで報じるケースも見られます。
こうした報道がなされると、加害者本人だけでなく、その家族や勤務先にも波紋が広がるでしょう。
職場によっては、起訴前の段階では静観する方針を取ることもありますが、起訴が決まった時点で懲戒解雇や契約解除などの処分が下される可能性も否定できません。
また、教員や医師、公務員などの国家資格を要する職業では、有罪判決を受けると資格の剥奪や登録抹消といった重大な影響が生じることがあります。
仮に執行猶予が付いたとしても、社会的信用は大きく揺らぎ、元の立場に戻ることは困難です。
一度名前や顔がネット上に出回れば、事実上「消せない情報」として半永久的に残り続けることにもなります。
報道をきっかけに転居や離職を余儀なくされるなど、生活全般へのダメージは計り知れません。
盗撮で有罪になるのを避けるには、示談成立で不起訴処分を目指すのが現実的
盗撮事件で前科を回避する現実的な手段は、示談を成立させ、不起訴処分を目指すことです。
日本の刑事事件では、一度起訴されてしまうとほぼ確実に有罪となり、前科がついてしまいます。
そのため、起訴前にどう動けるかが極めて重要です。
実際、被害者との示談が成立し、被害届の取り下げや処罰感情の緩和が確認されると、検察官はそれを考慮して起訴を見送る判断を下すケースが多く見られます。
不起訴となれば刑事裁判には進まず、前科もつきません。
また、報道リスクが軽減されるほか、職場や家族への発覚を最小限に抑えることも可能です。
もしも今、盗撮についての示談交渉が進んでいないのであれば、今すぐ弁護士に相談して示談交渉を開始すべきでしょう。
盗撮事件で示談をする流れ
盗撮事件での示談交渉は、加害者本人が直接おこなうのは現実的ではありません。
多くの場合は、刑事事件に詳しい弁護士を通じて交渉が進められます。
以下では、弁護士に依頼してから示談が成立するまでの一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。
1.弁護士に相談・依頼する
まずは、刑事事件を扱う弁護士に相談し、正式に依頼することから始まります。
被害者は精神的に傷ついている状態にあるため、加害者本人が直接連絡を取ろうとすると、逆効果になるおそれもあります。
また、場合によっては「脅迫された」「謝罪を強要された」といった誤解を招き、かえって事態を悪化させかねません。
弁護士を通じて冷静かつ適正に進めることで、被害者側の不安を抑え、交渉の受け入れ態勢を整えることができます。
盗撮事件は当事者だけで示談交渉をすすめるのは難しいケースがほとんど
盗撮の被害者は、顔を見られたくない・加害者と関わりたくないと考えるのが通常です。
そのため、加害者が直接謝罪したいと申し出たとしても、かえって拒否反応を引き起こすケースが少なくありません。
また、当事者間でのやり取りは感情的になりやすく、交渉の糸口がつかめないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
その点、弁護士を通じた交渉であれば、第三者的な立場から話を聞いてもらいやすくなり、示談成立に向けた冷静な話し合いが可能です。
2.弁護士が被害者の連絡先を確認する
弁護士に依頼すると、まずは警察や検察を通じて、被害者側と連絡を取るための調整がおこなわれます。
加害者やその家族が直接、被害者の連絡先を教えてもらうことはできませんが、弁護士であれば「示談交渉を希望している」との申出に基づき、正規の手続きのもとで連絡を取ることが可能です。
とはいえ、警察が被害者の個人情報をそのまま弁護士に渡すことはなく、まずは「加害者側が示談を望んでいるが、交渉に応じる意思があるか」を被害者に確認します。
そのうえで、被害者が「話を聞いてもいい」と応じた場合に限り、連絡先が共有され、交渉が進むことになります。
被害者が強い処罰感情を抱いている場合には、この段階で交渉自体が拒否されることもあるため、弁護士の初動対応と伝え方が非常に重要です。
3.被害者と示談交渉をおこなう
被害者と連絡がついたら、弁護士を通じて示談交渉が始まります。
盗撮はデリケートな問題のため、加害者本人が直接謝罪することは避けるのが通常です。交渉は全て弁護士が窓口となって慎重に進められます。
弁護士はまず、加害者の反省と謝罪の意志を丁寧に伝えたうえで、再発防止の誓約や示談の意向を示しながら、被害者の要望や処罰感情を確認していきます。
そして、慰謝料にあたる示談金や支払い方法、データの削除、今後の接触禁止といった条件について、合意点を探ることになります。
示談成立に必要なのは、条件の提示ではなく、誠実な態度です。
強引な交渉はかえって信頼を損なうおそれがあるため、弁護士による粘り強く丁寧な対応が鍵となります。
4.示談条件を合意して示談書を作成する
示談交渉の結果、被害者が条件に同意すれば、示談成立となります。
このとき重要なのが、合意内容を書面に残すことです。
弁護士は、示談金の金額や支払い方法、今後の接触禁止、データの削除確認、再発防止の誓約など、合意事項を盛り込んだ「示談書」を作成します。
示談書には、被害者がこれ以上刑事処罰を求めないことへの同意、いわゆる「宥恕(ゆうじょ)」が明記されるのが一般的です。
なお、示談金の支払いについては、原則として一括払いが求められますが、経済的事情によっては分割払いが認められるケースもあります。その場合も、支払いスケジュールや遅延時の対応を明記しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
示談書は、単なる合意書ではなく、不起訴や減刑を目指す上で極めて重要な証拠となる文書のため、作成から提出まで、正確かつ丁寧に対応しなければなりません。
5.検察や裁判所に示談書を提出する
示談が成立したら、弁護士が作成した示談書を検察や裁判所へ提出します。
まだ起訴前の段階であれば、検察官に対して「被害者との示談が成立していること」や「被害者が処罰を望んでいないこと」を正式に伝え、不起訴処分を求めて働きかけます。
検察官は、起訴・不起訴を判断する際に、示談の有無や内容、被害者の処罰感情を重視するため、示談書の提出は不起訴の可能性を高める有力な材料となります。
一方、すでに起訴されている場合でも、示談が成立していれば、裁判官が量刑を判断する際の情状として考慮される可能性があります。
この場合、執行猶予が付く、罰金刑で済むなど、刑罰が軽くなる要因として働くこともあります。
いずれにしても、示談書は加害者にとって大きな意味をもつ重要な証拠です。
速やかに提出し、法的手続きの中で適切に扱ってもらうことが、よりよい結果を引き寄せる一歩となります。
撮影罪(盗撮罪)の示談金相場
盗撮事件の示談金(慰謝料)は、通常10万円~50万円程度が相場とされています。
中間的な金額としては30万円前後が多いとされますが、実際の金額は事件の内容や被害の程度によって大きく異なります。
盗撮の被害態様には幅があり、満員電車内の一時的な撮影から、更衣室・トイレ・職場内での隠し撮り、さらにはデータの保存や第三者への送信まで、行為の内容によって被害者の受ける心理的影響は大きく変わります。
とくに悪質性が高い場合や、被害者の処罰感情が強い場合には、100万円を超える示談金が提示されることもあるでしょう。
また、2023年施行の「性的姿態撮影等処罰法」では、撮影罪に対して3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があると定められました。
ただし、実際に科される罰金刑は30万円前後が多い印象であり、重罰は常習性や画像拡散といった悪質性があって初めて適用されるのが一般的です。
なお、示談金は「相場」だけで機械的に決まるものではなく、被害者と加害者が示談交渉を通じて合意した金額が最終的な額となります。
加害者側の社会的地位や収入の高さ、誠意の有無、再発防止策の提示なども、金額に影響を及ぼすことを覚えておきましょう。
示談金が高額化しやすいケースとは
盗撮事件では、以下のような事情があると、示談金が相場を大きく上回る傾向があります。
- 被害者が未成年だった
- 被害者が強いショックを受けている
- 常習的に盗撮行為をおこなっていた
- 女子トイレや更衣室など、私的空間での盗撮だった
- 盗撮した映像をインターネット上にアップロード・拡散していた
- 盗撮した映像を販売していた
- 住居侵入など、ほかの犯罪も同時に成立している
- 被害者が複数存在していた
なぜなら、これらのケースでは盗撮行為の悪質性が高く、被害者の処罰感情も強くなるためです。
とくに未成年が被害者となった場合は、示談交渉の相手が保護者となり、父母双方の同意が必要になるなど、合意に至るまでのハードルも上がります。
また、インターネットでの拡散や販売など、被害の広がりが不可逆的なケースでは、被害者の精神的苦痛が極めて大きく、社会的非難も強いため、金額面でも厳しい交渉を迫られることが多くなるでしょう。
盗撮事件の対応を弁護士に依頼するメリット
盗撮事件において、前科や社会的信用の喪失を回避するためには、早期に弁護士へ相談・依頼することが重要です。
刑事手続きはスピードが早く、適切な対応ができなければ、示談交渉の機会を逃したり、不利な結果につながるおそれがあります。
ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを5つ解説します。
逮捕直後に本人と面会し、不安を解消できる
逮捕後は家族とも連絡が取れず、本人は強い不安と混乱の中に置かれます。
その点、弁護士であれば速やかに留置場に面会へ行き、今後の見通しや取るべき対応を本人に直接伝えることが可能です。
本人にとっては精神的な支えとなり、家族にとっても現在の状況を正確に把握できるため、混乱を最小限に抑えることができます。
被害者との示談交渉を任せられる
被害者と加害者の直接的な接触は、トラブルの原因になりかねません。
一方、弁護士を通じておこなえば、被害者の感情を尊重しつつ、法的な枠組みの中で冷静かつ適切な交渉が可能になります。
示談金額の提案、謝罪の伝達、再発防止策の提示など、全て弁護士が窓口となって進めることで、示談成立の可能性が高まるでしょう。
逮捕回避や早期釈放を目指せる
事件発覚時点で弁護士に依頼すれば、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す書類や身元引受人の情報を整え、事前に逮捕を防ぐよう警察や検察に対して働きかけることが可能です。
こうした対応は、初動の数日間で結果が分かれることも多く、時間との勝負になります。
また、すでに逮捕されている場合でも、勾留の必要性がないことを主張して裁判所に異議を申し立てたり、検察に対して釈放を求めたりと、身柄拘束の長期化を防ぐための対応を迅速に進めてもらえます。
不起訴獲得の確率を高められる
弁護士をつければ、不起訴処分を獲得できる可能性を大きく高めることが可能です。
盗撮事件では、起訴されると99%以上の確率で有罪となり、前科が付くリスクが極めて高くなります。
そのため、起訴前の段階でいかに適切な対応ができるかが非常に重要です。
たとえば、弁護士が間に入って早期に示談を成立させ、示談書を検察に提出することで、被害者の処罰感情が和らいでいることを証明できます。
さらに、反省文や誓約書、身元引受書などを揃えたうえで、不起訴を求める意見書を提出すれば、検察官に対して加害者に有利な情状をしっかり伝えることが可能です。
家族や職場にバレるリスクを軽減できる
弁護士に頼れば、盗撮事件が家族や職場に知られるリスクを大幅に減らすことが可能です。
逮捕や勾留が長引くと、出勤できない期間が続き、不自然な欠勤を通じて事件が発覚するおそれがあります。
さらに、正式に起訴されて刑事裁判に進んでしまえば、公の記録や報道を通じて外部に知られる可能性も高まります。
こうした事態を避けるには、弁護士による早期対応が重要です。
たとえば、身柄拘束が長引かないよう迅速に釈放を求めることで、職場には病欠や私用といった体裁で説明し、実際の事情を明かさずに済む可能性があります。
また、弁護士が家族への説明役を担ったり、職場対応に関する助言や文面の調整をおこなったりすることで、情報が広がるリスクを最小限に抑えることができます。
さいごに | 盗撮事件の対応はなるべく早く弁護士に依頼を!
盗撮事件は、被害者の処罰感情や社会的影響が大きく、たとえ初犯であっても逮捕・起訴・前科といった深刻な結果につながるおそれがあります。
そして、その後の人生にも大きな影を落としかねません。
しかし、早期に示談交渉を進め、被害者の理解を得ることができれば、不起訴処分となって前科を回避できる可能性が十分にあります。
また、弁護士に依頼すれば、適切な交渉や釈放への働きかけ、家族や職場への対応支援なども含めて、社会的ダメージを最小限にとどめるためのサポートが受けられます。
盗撮事件はスピードが命です。
迷っている間にも、手続きは進行してしまいます。
今できる最善の対応は、できるだけ早く刑事事件に注力している弁護士に相談することです。
再出発のための第一歩を、どうか迅速に踏み出してください。