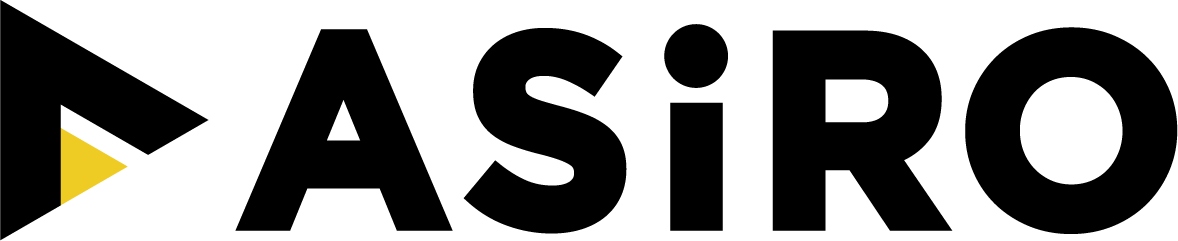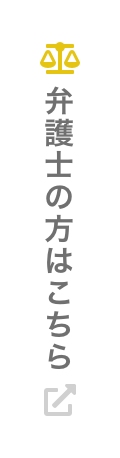自動車を運転中に不注意で人にけがを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪が成立して刑事処分や行政処分などを受ける可能性があります。
事故を起こしてしまった方のなかには「自分にはどのような刑罰が科されるか心配」「減刑のために何かできることはないか」などと、今後が不安な方もいるでしょう。
過失運転致傷罪に問われた場合、懲役刑や罰金刑などが科される可能性がありますが、起訴されずに事件終了となるケースも多くあります。
事故後の対応次第では不起訴や執行猶予などを獲得できることもあり、本記事で過失運転致傷罪や刑事手続きについて押さえておきましょう。
本記事では、過失運転致傷罪が成立するケースや刑罰、逮捕後の流れや減刑獲得のポイントなどを解説します。
過失運転致傷罪とは?
過失運転致傷罪とは、自動車の運転中に必要な注意を怠って人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
以下では、過失の定義や、刑事罰・行政処分の内容などについて解説します。
過失運転致傷罪と「過失」の定義
過失運転致傷罪での「過失」とは、注意義務に違反する行為のことを指します。
運転中の注意義務としては、主に以下のようなものがあります。
- 前方注視義務
- 速度制限遵守義務
- 信号指示遵守義務
- 居眠りしない義務
- 携帯を操作しない義務
- アルコールを摂取しない義務 など
上記のような注意義務を果たさずに事故を起こして人にけがを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪の刑罰
過失運転致傷罪の刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金(自動車運転死傷処罰法第5条)」です。
また、刑事罰だけでなく以下のような行政処分もあり、被害状況や過失の有無などによって科される内容は異なります。
| 事故の区分 | 治療期間 | 加害者側の一方的な過失による事故 | 加害者と被害者の双方に過失がある事故 |
| 重症事故 | 全治3ヵ月以上または後遺障害がある | 13点 | 9点 |
| 全治30日以上3ヵ月未満 | 9点 | 6点 | |
| 軽傷事故 | 全治15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
| 全治15日未満 | 3点 | 2点 |
過去3年間の累積点数がない方でも、全治3ヵ月以上のけがを負わせた場合は13点が加点されて90日間は免許停止となります。
また、過去に交通違反などがあって15点以上になった場合は、免許取り消しとなります。
過失運転致傷罪に似た罪
過失運転致傷罪に似たものとしては「過失運転致死罪」や「危険運転致死傷罪」などがあります。
ここでは、それぞれの違いについて解説します。
過失運転致傷罪と過失運転致死罪の違い
過失運転致死罪とは、自動車の運転中に必要な注意を怠って人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪も過失運転致死罪も「自動車の運転中に必要な注意を怠った」という点は共通していますが、「被害者がけがをしたか死亡したか」という点で異なります。
被害者がけがを負った場合は過失運転致傷罪、被害者が死亡した場合は過失運転致死罪が成立します。
過失運転致死罪の刑罰は、過失運転致傷罪と同じく「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金(自動車運転死傷処罰法第5条)」です。
過失運転致傷罪と危険運転致死傷罪の違い
危険運転致死傷罪とは、危険な状態で自動車を運転して人を負傷・死亡させた場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪とは運転態様の悪質性や刑罰の内容などが異なり、より悪質性や危険性が高い場合は危険運転致死傷罪が成立し、刑罰も重く設定されています。
一例として、危険運転致死傷罪が成立し得るケースとしては以下があります。
- アルコールや薬物などで正常な運転が難しい状態で運転した
- 制御困難なスピードで走行していた
- 運転技能が未熟な状態で走行していた
- ほかの車両の前方で停止して通行を妨害した
通行禁止道路で重大な交通の危険を生じさせるスピードで走行したなど上記のような行為によって人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役が科されるおそれがあります(自動車運転死傷処罰法第2条)。
過失運転致傷罪で逮捕された場合の刑事手続きの流れ
過失運転致傷罪で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進行します。
- 警察に逮捕されて取り調べがおこなわれる
- 検察官によって起訴・不起訴が判断される
- 裁判所で公判手続きがおこなわれる
- 判決が確定して刑が執行される
ここでは、過失運転致傷罪に問われて刑が執行されるまでの流れを解説します。
1.警察に逮捕されて取り調べがおこなわれる
事故を起こして逮捕された場合、留置場に身柄を拘束されて捜査機関による取り調べを受けることになります。
逮捕後の拘束時間は最大72時間ですが、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合は勾留に移行し、さらに最長20日間拘束される可能性もあります。
なお、逃亡などのおそれがなければ「在宅事件」として扱われ、身柄を拘束されずに在宅のまま聞き取りなどの捜査がおこなわれる場合もあります。
過失運転致傷事件の場合、逮捕されずに在宅事件となることも珍しくありません。
2.検察官によって起訴・不起訴が判断される
逮捕・勾留されている場合は逮捕後23日以内に、在宅事件の場合には適宜のタイミングで検察官が起訴するかどうかを判断します。
検察官が下す判断としては「正式起訴」「略式起訴」「不起訴」などがあり、それぞれ以下のような違いがあります。
- 正式起訴:被疑者への処罰を求めて刑事裁判にかけること
- 略式起訴:被疑者への処罰を求めて簡易裁判所に請求すること
- 不起訴:刑事裁判にかけずに事件を終結させること
不起訴になった場合、懲役刑や罰金刑などは科されず、前科もつきません。
事故を起こして過失運転致傷罪が成立していたとしても、罪質が軽微なケースなどでは不起訴処分になることもあります。
3.裁判所で公判手続きがおこなわれる
正式起訴された場合や略式起訴で異議がある場合などは、公判手続きがおこなわれます。
公判手続きでは、検察側は被告人が犯罪を犯していることを立証し、被告側は検察側の主張に対して反論をおこないます。
自分で対応することも可能ではありますが、的確に主張や反論をするためには法律知識などが必要となるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
4.判決が確定して刑が執行される
十分に主張立証が尽くされたところで、裁判官によって判決が下されます。
日本の刑事裁判は有罪率が99%以上と言われており、高い確率で有罪判決が下されます。
過失運転致傷罪の場合は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」が科されることになります。
ただし、有罪となっても量刑が「3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金」であれば、執行猶予が付くこともあります(刑法第25条1項)。
執行猶予付判決となった場合、前科は付いてしまうものの、裁判終了後は身柄を解放されて日常生活に戻ることができます。
過失運転致傷罪で起訴される?起訴されたらどうなる?
事故を起こして逮捕されたとしても、必ずしも起訴されて有罪になるわけではありません。
過失運転致傷事件では不起訴になることもあり、ここでは不起訴率や起訴されやすいケースなどを解説します。
過失運転致傷罪の不起訴率は約75%
2024年版の検察統計調査によると、過失運転致傷事件の総数2万6,734件のうち2万60件が不起訴となっており、不起訴率は約75%にのぼります。
なお、過失運転致死事件での不起訴率は約27%、危険運転致死傷事件での不起訴率は約21%となっており、多くのケースで事故後に起訴されています。
過失運転致傷事件に関しては、事故後速やかに弁護士の的確なサポートなどを受けることで、不起訴処分を獲得できる可能性が十分にあります。
過失運転致傷罪で起訴されやすいケース
刑事事件では、被害状況・犯行の悪質性・被害者の処罰感情などを考慮したうえで起訴不起訴の判断が下されます。
過失運転致傷事件の場合、以下のようなケースでは起訴されるおそれがあります。
- 被害者の負傷の程度が重い場合
- 被害者との示談が成立していない場合
- 過失の程度が大きい場合 など
過失運転致傷罪で起訴されると罰金刑になる可能性が高い
2024年版の検察統計調査によると、過失運転致傷事件での起訴件数4,373件のうち3,884件が略式起訴であり、全体の約89%を占めています。
略式起訴の場合、懲役刑は科されず、罰金や科料の支払いが命じられます。
過失運転致傷事件での罰金額は犯行態様などによって異なりますが、2023年の司法統計では「30万円以上50万円未満」が最多となっています。
| 罰金額 | 人数・割合 |
| 100万円 | 40人(約0.1%) |
| 50万円以上100万円未満 | 6,727人(約19%) |
| 30万円以上50万円未満 | 13,394人(約38%) |
| 20万円以上30万円未満 | 6,853人(約19%) |
| 10万円以上20万円未満 | 8,259人(約23%) |
| 5万円以上10万円未満 | 5人(0.1%以下) |
【参考元】令和5年 司法統計年報 2 刑事編
過失運転致傷罪の判例
ここでは、過失運転致傷事件の裁判例を2つ紹介します。
禁錮1年6ヵ月・執行猶予3年の判決が下されたケース
自動車を運転していた被告人が、横断歩道を歩いていた被害者をはねてしまい、全治1年の重傷を負わせたという事件です。
この事件では、被告人は考えごとをしながら運転していて前方注視義務を怠っており、事故直前まで被害者の存在に気付いていませんでした。
被告人には前科や前歴などがなかったものの、被害者は事故によって自力での外出が困難な状態となっており、被告人に対して厳重な処罰を求めていることなども考慮され、禁錮1年6ヵ月・執行猶予3年の判決が下されました。
禁錮1年2ヵ月・執行猶予3年の判決が下されたケース
普通乗用車を運転していた被告人が車道脇に停車しようとしたところ、ブレーキとアクセルを踏み間違えて歩道に乗り上げてしまい、歩行者8名をはねてけがを負わせたという事件です。
この事件では、被告人はタクシー運転手の仕事をしており、運転に慣れていたにもかかわらず、基本的かつ重要な安全確認などを怠って事故を起こしました。
被告人は全ての事実を認めて「今後は運転しない」という旨を述べており、被告人の妻が今後監督することを約束したものの、被告人の過失の程度は大きく、被害者のうち2名が厳しい処罰を求めていることなども考慮され、禁錮1年2ヵ月・執行猶予3年の判決が下されました。
【参考元】名古屋地裁 令和2年6月3日判決|裁判所
過失運転致傷罪で不起訴や執行猶予を獲得するためのポイント
ここでは、過失運転致傷事件で不起訴や執行猶予を獲得するためのポイントを解説します。
自分で示談交渉をおこなう
過失運転致傷事件などの被害者がいる刑事事件では、「被害者との示談が成立しているかどうか」がひとつのポイントとなります。
被害者と示談交渉をおこなって、被害者に「処罰は望まない」という意向を示してもらうことで、不起訴処分になったり執行猶予が付いたりする可能性があります。
ほかにも、運転免許を自主返納したり社会奉仕活動に参加したりして反省の意思を示すことで、加害者側に有利な事情として考慮されることもあります。
弁護士に相談する
できるだけ重い処分を回避したい場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
刑事事件に強い弁護士なら、状況に適した弁護方針を立ててくれて、被害者との示談交渉や減刑獲得に向けた証拠収集などのサポートをしてくれます。
被害者によっては、加害者に対する処罰感情が強かったりして交渉を拒否されたりすることもありますが、弁護士が間に入ることで応じてくれるケースもあります。
当社が運営する「ベンナビ刑事事件」では、刑事事件の加害者弁護が得意な全国の法律事務所を掲載しています。
相談内容や地域から対応可能な法律事務所を一括検索でき、夜間や休日でもスピーディに対応してくれる事務所なども多くあるので、弁護士を探す際はおすすめです。
弁護士に依頼する場合の費用の目安
弁護士に示談交渉などのサポートを依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。
ただし、弁護士費用は事務所によってもバラつきがあるため、正確な金額が知りたい方は直接事務所に確認しましょう。
| 内訳 | 相場 |
| 相談料 | 30分あたり5,000円程度 ※初回相談無料の法律事務所もある |
| 着手金 | 30万円~50万円程度 |
| 報酬金 | 30万円~50万円程度 |
| 日当(弁護士が事務所を離れた場合に発生) | 3万円~10万円程度 |
| 実費 | 事件内容によって異なる |
さいごに|過失運転致傷罪に問われそうな場合は弁護士に相談
運転者としての注意義務を怠って事故を起こし相手にけがをさせてしまったら、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
過失運転致傷罪では「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」という罰則が定められていますが、不起訴になったり執行猶予が付いたりするケースも多くあります。
できるだけ重い処分を回避するためには、速やかに弁護士に相談して示談交渉や証拠集めなどのサポートを受けることが大切です。
「ベンナビ刑事事件」なら、刑事事件の加害者弁護が得意な弁護士をすぐに探せますので、まずは一度利用してみましょう。