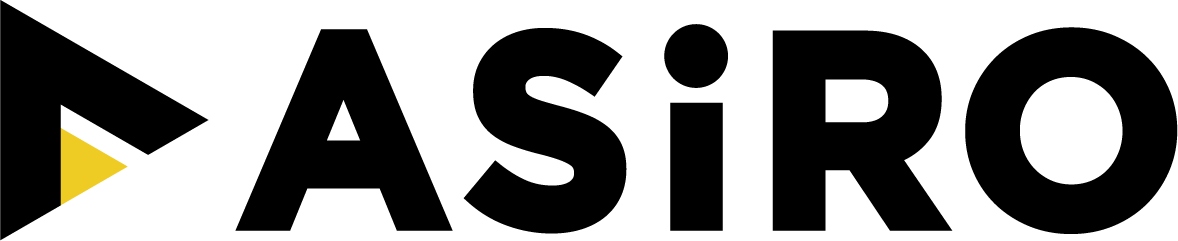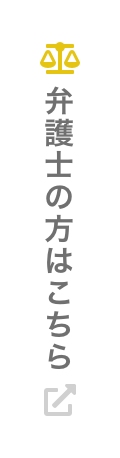20歳未満の者が刑事事件などを起こした場合は、少年事件として取り扱われます。
自分の子どもが少年事件を起こしてしまった場合は、どのような処分を受けることになるのか、どうすれば処分を軽減できるのかと考えるのが親心です。
信頼できる弁護士に依頼すれば、重い処分を避けられるように親身になって対応してもらえるでしょう。
本記事では、少年事件について弁護士ができるサポート、弁護士に依頼するメリット、弁護士の選び方、弁護士費用などを解説します。
少年事件とは?20歳未満の少年が起こした事件のこと
「少年事件」とは、20歳未満の者(=少年)が起こした刑事事件などの総称です。
具体的には、以下のいずれかの場合に少年事件として取り扱われます(少年法3条1項)。
- 少年が罪を犯した場合
- 14歳に満たない少年が、刑罰法令に触れる行為をした場合
- 少年について次に掲げる事由があり、その性格または環境に照らして、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合
- 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
- 正当の理由がなく家庭に寄りつかないこと。
- 犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること。
- 自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
少年事件については原則として、通常の刑事手続き(刑事裁判)ではなく、家庭裁判所の審判(少年審判)によって少年の処遇を決定します。
少年事件で弁護士(付添人)がしてくれる主な活動内容
少年事件の依頼を受けた弁護士は、少年の「付添人」として活動します。付添人として弁護士がしてくれる主な活動内容は、以下のとおりです。
- 少年との面会・アドバイス
- 被害者への謝罪と示談交渉
- 少年審判における弁護活動
- 逆送時の公判手続きにおける弁護活動
- 更生に向けた環境の整備
- 学校や職場とのやり取り
1.少年との面会・アドバイス
付添人となった弁護士は、少年と継続的に面会したうえでその話を聞き、今後の過ごし方や手続きに関する相談相手となります。
どのように更生していくか、少年審判ではどのような結果が見込まれるかなどを弁護士と話すことにより、少年にとっては安心に繋がります。
2.被害者への謝罪と示談交渉
少年の行為によって被害が生じた場合は、被害者に対する謝罪と示談交渉を付添人である弁護士が代行します。
被害者に対して真摯に謝罪して被害弁償をおこなえば、少年が重い処分を受ける可能性は低くなります。
少年本人やその家族が自ら謝罪や示談交渉を試みると、被害者に拒否されるケースも多いです。
弁護士を通じて申入れをおこなえば、スムーズに示談が成立する可能性が高まります。
3.少年審判における弁護活動
少年事件を起こした少年に対する処分は、家庭裁判所の審判(=少年審判)によって決定されます。
弁護士は付添人として、少年の反省や更生環境が整っていることなどを示し、家庭裁判所に対して重い処分を避けるように求めます。
4.逆送時の公判手続きにおける弁護活動
死刑・懲役・禁錮に当たる罪の事件について、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、家庭裁判所は少年事件を検察官に送致しなければならないとされています(少年法20条1項)。
これは「検察官送致」や「逆送」などと呼ばれるものです。
なお、少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合に、その罪を犯したとき16歳以上であったときは、原則として逆送がおこなわれます(少年法20条2項)。
逆送がおこなわれた場合は、検察官によって起訴され、公判手続き(刑事裁判)にかけられる可能性が濃厚です。
弁護士はこの場合、公判手続きにおける弁護人として、被告人である少年に対して重い刑事処分をおこなわないように求めます。
5.更生に向けた環境の整備
弁護士は、少年審判や公判手続きにおいて少年をサポートするだけでなく、少年の更生についてもサポートをおこないます。
具体的には、少年の話を親身になって聞きながら更生の方法を一緒に考えたり、更生をサポートする機関を紹介したりしています。
6.学校や職場とのやり取り
少年が所属している学校や職場とのやり取りについても、弁護士に任せることができます。
少年本人や家族が自らやり取りしなくてよくなるため、精神的なストレスの軽減に繋がるでしょう。
少年事件を弁護士に相談・依頼する5つのメリット
自分の子どもが少年事件を起こした場合に、弁護士へ相談および依頼をすることには、主に以下のメリットがあります。
- 更生の方法を一緒に考えてもらえる
- 違法な取調べへの対策ができる
- 早期に釈放される可能性が高まる
- 不処分・保護観察処分となる可能性が高まる
- 退学処分などを避けられる可能性が高まる
1.更生の方法を一緒に考えてもらえる
事件を起こしてしまった少年がまっすぐ更生していくためには、サポート役となる大人の存在が必要不可欠です。
両親などの親族に加えて、弁護士にもサポート役になってもらえれば、少年の更生にとって大いにプラスとなります。
特に少年事件を豊富に取り扱う弁護士は、法的な専門知識や少年の更生に関する業務上の知見を有しています。
一般の方では持ちづらい視点から客観的なアドバイスを受けられる点は、弁護士に相談する大きなメリットのひとつです。
2.違法な取調べへの対策ができる
警察官による取調べを受ける際には、不適切な言動によって自白を求められることが少なくありません。
弁護士にあらかじめ相談すれば、取調べの流れや心構えなどについてアドバイスを受けられます。
弁護士のアドバイスを踏まえて前提知識を備えておけば、警察官から違法な取調べを受けたとしても、不本意な供述を避けることができるでしょう。
3.早期に釈放される可能性が高まる
弁護士は、少年が重い処分を避けられるように、さまざまな手段を尽くして活動します。
特に少年が身柄を拘束されている場合は、1日も早く身柄が解放されるように、家庭裁判所や検察官に対する働きかけをおこなってもらえます。
子どもの身柄を早期に釈放してもらいたい場合は、速やかに弁護士へ依頼しましょう。
4.不処分・保護観察処分となる可能性が高まる
少年事件における処分には、以下の種類があります。
①不処分
家庭裁判所が、少年に対する処分をおこなわないことを決定します。
②保護処分
保護観察・少年院送致・児童自立支援施設送致の3種類があります。
(a)保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受け、社会の中で更生を目指します。比較的軽微な非行をした少年は、保護観察処分となる可能性があります。
(b)少年院送致
少年院に収容して矯正教育をおこないます。非行の程度が重い場合や、社会の中での更生が難しい場合には、少年院送致が選択される傾向にあります。
(c)児童自立支援施設送致
児童自立支援施設に収容して更生指導をおこないます。低年齢の少年が重大な非行をした場合には、児童自立支援施設送致が選択される傾向にあります。
③検察官送致(逆送)
家庭裁判所が事件を検察官に送致します。
上記のうち、不処分または保護観察処分となれば、少年は自宅に戻る(または自宅で過ごし続ける)ことができます。
弁護士が家庭裁判所に対して、少年の反省や更生環境が整っていることなどを説得的に訴えれば、少年が不処分または保護観察処分となる可能性が高まります。
5.退学処分などを避けられる可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、少年審判などの法的手続きへの対応に加えて、少年が通う学校とのやり取りなども代行してもらえます。
少年が十分に反省していることを学校側に訴えれば、退学処分などの重い処分を避けられる可能性があります。
少年事件の弁護士(私選付添人)を選ぶ際の4つのポイント
少年事件の対応を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目するとよいでしょう。
- 少年事件の対応実績や経験が豊富かどうか
- 少年や家族などへの配慮を重視しているか
- 夜間や土日祝日などでも活動してくれるか
- 相場と比較して弁護士費用が適正かどうか
1.少年事件の対応実績や経験が豊富かどうか
少年と真摯に向き合い、更生や処分の軽減に向けて力を尽くしてもらうことを期待したい場合は、少年事件の対応実績や経験が豊富な弁護士に依頼すべきです。
実績豊富な弁護士に依頼すれば、過去にさまざまな少年と向き合った経験を活かして、本当に少年のためになる過ごし方や対応を考えてもらえます。
少年事件の対応実績や経験は、法律事務所のウェブサイトや弁護士ポータルサイトの事務所紹介ページに掲載されていることがあります。
また、弁護士に法律相談をする中でも、少年事件について受けるアドバイスの内容によって、経験の程度はある程度窺い知ることができるでしょう。
複数の弁護士に相談したうえで、アドバイスの具体性や対応の丁寧さなどを比較することも効果的です。
2.少年や家族などへの配慮を重視しているか
少年事件を取り扱う弁護士には、法律に従って画一的に対応するだけでなく、少年の性格や生い立ちに向き合って更生をサポートすることが求められます。
また、少年の家族も「少年が重い処分を受けるのではないか」「離れて暮らさなければならないのか」などと悩み続けることが多いため、弁護士による精神的ケアが非常に重要です。
少年事件への対応を依頼する弁護士を選ぶ際には、少年本人や家族などに対して十分に配慮する姿勢が見られるかどうかにも着目しましょう。
3.夜間や土日祝日などでも活動してくれるか
少年事件は、少年審判までの期間が通常の刑事事件と比較して短いため、弁護士には迅速な対応が求められます。
方針を速やかに決定し、かつ少年の更生に向けたきめ細かい対応をしてもらうためには、平日の日中だけでなく、夜間や土日祝日にも相談に応じてくれる弁護士に依頼するのがよいでしょう。
少年本人や家族が突然不安に苛まれた際には、いつでも弁護士に相談できる点も大きなメリットです。
4.相場と比較して弁護士費用が適正かどうか
少年事件への対応を依頼する際の弁護士費用は、依頼先の弁護士によって千差万別です。
少年事件の弁護士費用には大まかな目安があるので、目安額からかけ離れていない合理的な費用を提示する弁護士に依頼するのがよいでしょう。
ただし、弁護士費用が安ければ安いほどよいわけではなく、その弁護士が信頼できるかどうかを総合的に判断することが大切です。
少年事件の弁護士費用の相場|事件内容などによって異なる
少年事件の弁護士費用については、事件の複雑さや内容などに応じて、弁護士が個別に見積もりを提示するのが一般的です。
事件が複雑な場合や、非行が重大である場合などには、弁護士費用が高額になる傾向にあります。
日本弁護士連合会の「日本弁護士連合会報酬等基準 」(現在は廃止)を参考にした、少年事件の弁護士費用の目安額を紹介します。
あくまでも目安額に過ぎないので、実際の弁護士費用は相談先の弁護士へ個別にご確認ください。
| 費用項目 | 費用区分 |
| 相談料 | 30分ごとに5,500円~1万1,000円(税込) |
| 着手金 | 22万円~55万円(税込) ※家庭裁判所への送致前・送致後、抗告・再抗告および保護処分の取り消しのそれぞれについて発生(ただし、継続受任の場合は一部の着手金が減額または免除される場合あり) |
| 報酬金 | 22万円~55万円(税込) |
少年事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探せる
少年事件について豊富な経験を有する弁護士を探すには、「ベンナビ刑事事件」を活用するのが便利です。
ベンナビ刑事事件を利用すれば、「少年事件に強い」弁護士を検索できます。
地域に応じてスムーズに弁護士を検索でき、電話やメッセージで直接問い合わせることが可能です。
少年事件を依頼できる弁護士に心当たりがない方は、「ベンナビ刑事事件」をご利用ください。
少年事件の加害者やその家族が知っておくべき3つの制度
ご自身やご家族が少年事件を起こしてしまったときは、以下の制度を利用できる場合があることを知っておきましょう。
- 当番弁護士制度・当番付添人制度|身柄拘束後に1度だけ弁護士を呼べる制度
- 国選付添人制度|国費で少年に弁護士を付けられる制度
- 少年保護事件付添援助制度|日弁連が弁護士費用を負担してくれる制度
1.当番弁護士制度・当番付添人制度|身柄拘束後に1度だけ弁護士を呼べる制度
「当番弁護士」とは、逮捕された被疑者の相談に応じるため、各都道府県の弁護士会に待機している弁護士です。
逮捕された被疑者は、当番弁護士を1度だけ無料で呼ぶことができます。
当番弁護士に相談すれば、逮捕後の手続きの流れや取調べに臨む際の注意点などについてアドバイスを受けられます。
また、少年鑑別所に収容された少年については、1度だけ無料で「当番付添人」である弁護士を呼ぶことができます。
当番付添人は、通常の刑事事件における当番弁護士に相当します。
なお、当番弁護士や当番付添人に事件の対応を正式に依頼することもできますが、初回接見以外の対応は有料となる点にご注意ください。
2.国選付添人制度|国費で少年に弁護士を付けられる制度
「国選付添人」とは、少年事件を起こした少年のために、国費で選任される付添人です。少年やその家族において、国選付添人の費用を負担する必要はありません。
以下のいずれかに該当し、私選付添人が選任されていない場合には、国選付添人が選任されます。
- 死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件において、その非行事実を認定するための審判手続きに検察官が関与する必要があると家庭裁判所が認めるとき(少年法22条の3第1項)
- ①の事件、または14歳未満の少年が①の罪に係る刑罰法令に触れる行為をした事件について、少年鑑別所送致の措置がとられており、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判手続きに弁護士である付添人が関与する必要がある家庭裁判所が認めるとき(少年法22条の3第2項)
- 家庭裁判所が被害者等に少年審判の傍聴を許すとき(少年法22条の5第2項)
【参考】国選弁護人・国選付添人|法テラス
3.少年保護事件付添援助制度|日弁連が弁護士費用を負担してくれる制度
「少年保護事件付添援助制度」とは、少年が希望する場合には、すべての少年事件について弁護士費用の全額を援助する制度です。日本弁護士連合会が運用しています。
たとえば、被疑者段階の国選弁護人が家裁送致後に国選付添人に選任されなかった場合には、少年保護事件付添援助制度を利用すれば、同じ弁護士に引き続き無料でサポートしてもらえます。
また、当番付添人として相談に応じた弁護士に依頼する際にも、少年保護事件付添援助制度を利用可能です。
【参考】
少年保護事件付添援助制度|日本弁護士連合会
弁護士白書2022年版 第3節少年事件における付添人活動 2弁護士付添人拡充のための取組(2)少年保護事件付添援助制度|日本弁護士連合会
少年事件の弁護士に関するよくある質問
少年事件に関する弁護士への依頼について、よくある質問とその回答をまとめました。
- Q.少年事件ではどのタイミングで弁護士に依頼すれば良いか?
- Q.どのような事件の場合に検察官送致になってしまうのか?
Q.少年事件ではどのタイミングで弁護士に依頼すれば良いか?
少年事件について弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほど望ましいです。
早い段階で弁護士に相談すれば、弁護活動の選択肢が増えるため、重い処分を避けられる可能性が高まります。
また、少年事件の当事者となった少年や家族には大きな精神的負荷がかかるため、早期に弁護士のサポートを受けましょう。
Q.どのような事件の場合に検察官送致になってしまうのか?
少年事件が検察官送致(逆送)となるのは、死刑・禁錮・懲役に当たる罪の事件について、罪質・情状に照らして刑事処分が相当であると家庭裁判所が認めた場合です(少年法20条1項)。
特に強盗罪や不同意性交等罪、被害者に重傷を与えた傷害罪などについては、検察官送致となる可能性が高いと考えられます。
また、少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合に、その罪を犯したとき16歳以上であったときは、原則として検察官送致となります(少年法20条2項)。
検察官送致となった場合には、少年に対する処分は通常の刑事裁判(公判手続き)によって審理されます。弁護士と密に相談を重ねて、公判手続きに向けた準備を整えましょう。
さいごに|少年が事件を起こしたらできる限り早く弁護士に相談を
犯罪や非行をした少年に対しては、更生に向けたサポートと精神的なケアが必要不可欠です。
少年の家族にとっても、信頼できるサポート役を得ることが精神的な安定に繋がります。
少年事件を豊富に経験している弁護士に相談すれば、重い処分を避けるためにさまざまな活動をおこなってもらえます。
さらに、少年や家族のよき相談相手として、親身になって話を聞いてもらえるでしょう。
ご自身や子どもが少年事件を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士へご相談ください。