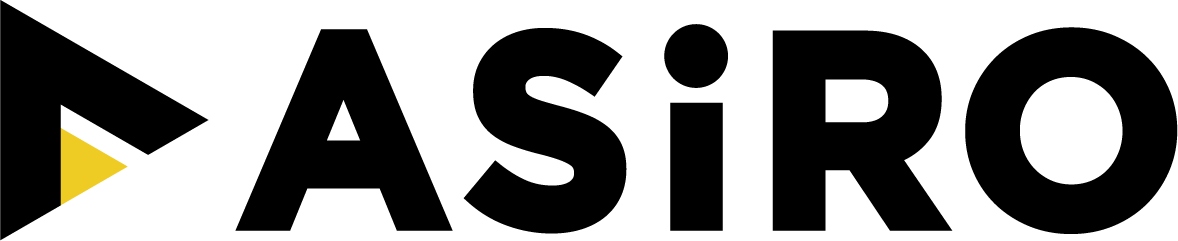窃盗・詐欺・横領などの犯罪については、刑法において「親族相盗例(親族間の犯罪に関する特例)」が設けられています。
被害者と一定の親族関係にある行為者には親族相盗例が適用され、刑の免除などの効果が発生します。
ただし、親族相盗例が適用される被害者の親族は、一定の範囲に限定されています。
また、親族相盗例によって刑事罰を免れたとしても、民事責任(損害賠償責任)は免れない点に注意が必要です。
今回は親族相盗例について、要件・効果・注意点などをまとめました。
親族相盗例(親族間の犯罪に関する特例)とは
「親族相盗例(親族間の犯罪に関する特例)」(刑法244条)とは、親族同士の間でおこなわれた財産犯について刑を免除し、または親告罪として取り扱う旨を定めた特例です。
親族相盗例の趣旨・根拠
親族相盗例が定められているのは、親族間の紛争には国家による介入を控えるという考え方に基づくと解するのが判例の立場です(=政策説)。
最高裁平成20年2月18日決定では、親族相盗例による刑の免除の趣旨を以下のように判示しています。
「刑法255条が準用する同法244条1項は,親族間の一定の財産犯罪については、国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づき、その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず、その犯罪の成立を否定したものではない」
親族相盗例の対象となる犯罪
親族相盗例の適用対象となるのは、以下の犯罪です。
- 窃盗罪(刑法235条)
- 不動産侵奪罪(刑法235条の2)
- 詐欺罪(刑法246条)
- 電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
- 背任罪(刑法247条)
- 準詐欺罪(刑法248条)
- 恐喝罪(刑法249条)
- ①~⑦の各罪の未遂罪(刑法243条、250条)
- 横領罪(刑法252条)
- 業務上横領罪(刑法253条)
- 遺失物等横領罪(刑法254条)
親族相盗例が適用される行為者・適用の効果
親族相盗例が適用される場合の効果は、行為者と被害者の関係性(続柄)によって異なります。
親族相盗例が適用される行為者は、以下のとおりです。
なお、親族でない共犯については、親族相盗例が適用されません(刑法244条3項)。
- 被害者の配偶者・直系血族・同居の親族
- 被害者のその他の親族
被害者の配偶者・直系血族・同居の親族
被害者の配偶者・直系血族・同居の親族が、親族相盗例の対象となる罪を犯した場合、その刑が免除されます(刑法244条1項)。
(a)被害者の配偶者
法律婚である(婚姻届を提出している)必要があります。
内縁の場合、親族相盗例は適用されません(最高裁平成18年8月30日決定)。
また財産を騙し取る手段として婚姻したに過ぎないなど、婚姻が無効とされる場合も、親族相盗例の適用はありません(東京高裁昭和49年6月27日判決)。
(b)被害者の直系血族
被害者の直系尊属(父母、祖父母……)と直系卑属(子、孫……)が該当します。
(c)被害者の同居の親族
「親族」とは、以下の者をいいます(民法725条)。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
配偶者は(a)、直系血族は(b)に該当します。
そのため(c)に該当するのは、被害者と同居している6親等内の傍系血族(兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、いとこ、はとこなど)と、3親等内の姻族(義父母など)です。
なお刑が免除されるとしても、無罪として取り扱われるわけではなく、犯罪の成立自体は認められます(最高裁平成20年2月18日決定など)。
被害者のその他の親族
上記(a)~(c)に該当する者以外の被害者の親族が、親族相盗例の対象となる罪を犯した場合、その犯罪について告訴がなければ、検察官は公訴を提起できません(=親告罪。刑法244条2項)。
具体的には、被害者と同居していない6親等内の傍系血族(兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、いとこ、はとこなど)と、3親等内の姻族(義父母など)による対象犯罪が親告罪となります。
所有者と占有者が異なる場合、親族関係は犯人と誰の間に必要か?
窃盗などの被害に遭った財物の所有者と占有者が異なる場合、親族相盗例を適用するためには、犯人と誰の間に親族関係が存在する必要があるかが問題となります。
この点判例では、窃盗罪について親族相盗例の適用可否が問題となった事案において、所有者および占有者の両方と犯人の間に親族関係が必要と解しています(最高裁平成6年7月19日決定)。
財物の所有者と占有者はどちらも被害者であり、両者の利益を尊重・保護すべきであることから、上記判例の見解は学説上も通説となっています。
親族相盗例が適用される場合でも、民事責任は免れない
親族相盗例が適用されたとしても、刑事責任との関係で刑の免除や親告罪化の効果が生じるに過ぎません。
窃盗などの行為は、被害者に対して違法に損害を与える不法行為(民法709条)に該当します。
したがって、行為者は被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。
親族相盗例に関するQ&A
親族相盗例について、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1 少しでも血縁関係があれば、親族相盗例の対象になるのか?
Q2 親族関係があると勘違いしていた場合、親族相盗例は適用されるのか?
少しでも血縁関係があれば、親族相盗例の対象になるのか?
親族相盗例が適用されるのは、民法725条で定められる「親族」に限られています。
具体的には、被害者の6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族が親族相盗例の適用対象です。
それよりも遠縁の行為者については、親族相盗例が適用されません。
なお前述のとおり、被害者との続柄や同居の有無によって、親族相盗例の効果(刑の免除or親告罪化)が異なる点にご注意ください。
親族関係があると勘違いしていた場合、親族相盗例は適用されるのか?
たとえば、父親の所有物だと思って貴金属を盗んだところ、実は父親が第三者から預かっていたものだったとします。
貴金属が父親の所有物であれば、親族相盗例が適用されて刑が免除されます。
しかし、実際には第三者の所有物を盗んでしまったということです。
このように、犯人が被害者との親族関係について錯誤(=勘違い)に陥っていた場合、どのように取り扱うべきかが問題となります。
この点、最高裁平成20年2月18日決定(前掲)で示された政策説の立場からは、親族関係の錯誤は罪責に影響しないと解されています。
すなわち客観的に親族関係が存在しない以上、「親族間の紛争には国家による介入を控える」という趣旨が妥当しないので、親族相盗例は適用できないということです。
政策説の考え方からは、上記とは反対のケースについても、客観的な親族関係の有無のみを基準に親族相盗例の適用可否が判断されます。
たとえば第三者の所有物であると思って盗んだ物が父親の所有物だった場合には、客観的な親族関係が存在するため、親族相盗例が適用されて刑が免除されます。
刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
捜査機関から犯罪の疑いをかけられたら、速やかに信頼できる弁護士を探して、刑事弁護を依頼することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護を依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
- 取調べについてアドバイスを受けられる
- 被害者との示談交渉を一任できる
- 軽微な犯罪であれば、不起訴の可能性が高まる
- 公判手続きに向けて十分な準備ができる
- 逮捕・勾留されている場合、家族との窓口になってもらえる
取調べについてアドバイスを受けられる
刑事事件の被疑者は、取調べを受ける際の対応について特に気を配る必要があります。
取調べで供述した内容は、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事裁判における審理の重要な参考資料となるからです。
被疑者には黙秘権が保障されており、取調べに対して供述せず黙っていることもできます。
話したいことだけを取捨選択して話しても構いません。
しかし、取調べを担当する警察官や検察官からプレッシャーを受け、不本意な供述をしてしまうケースも散見されます。
弁護士に相談すれば、取調べに臨む際の心構えや注意点についてアドバイスを受けられます。
弁護士の助言を踏まえながら、話すべきこととそうでないことを区別することで、不本意な供述をしてしまうリスクを抑えられます。
被害者との示談交渉を一任できる
被害者がいる犯罪については、示談が成立するかどうかが刑事処分の内容を左右します。
示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
起訴が避けられない場合でも、示談が成立した事実は被告人にとって量刑上有利に働きます。
しかし被害者は、被疑者・被告人と直接示談交渉をすることを嫌うケースが多いです。
また、被疑者・被告人が身柄を拘束されている場合は、自ら示談交渉をおこなうことができません。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を一任できます。
弁護士が建設的に交渉を進めることで、被害感情の悪化を防ぎながら、適正な条件による早期の示談成立を目指せます。
被疑者・被告人が身柄拘束されている状態でも、弁護士の代行により示談交渉が可能となります。
軽微な犯罪であれば、不起訴の可能性が高まる
被疑者が犯した罪が比較的軽微な場合は、検察官の判断により不起訴(起訴猶予)となる可能性があります。
起訴猶予処分が行われるのは、刑罰を科すよりも、社会における更生を促すことがより適当であると検察官が判断した場合です。
被疑者としては、真摯な反省の態度や更生をサポートする人の存在などをアピールすれば、起訴猶予となる可能性が高まるでしょう。
また被害者との示談が成立すれば、刑罰を科す必要性が低下するため、起訴猶予の見込みが広がります。
弁護士に依頼すれば、起訴猶予処分が適当であることを、検察官に対して幅広い角度からアピールしてもらえます。
不起訴によって刑罰を回避したい場合は、そのための弁護活動を弁護士に依頼することをおすすめします。
公判手続きに向けて十分な準備ができる
検察官に起訴された場合は、公判手続き(刑事裁判)に向けた準備を整える必要があります。
罪を認めるか否認するかの方針を決めた上で、検察官立証に対する反論があれば、その主張構成と根拠となる資料を準備しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、刑事訴訟法の規定や事実関係を踏まえて、公判手続きに向けた適切な準備を整えることができます。
逮捕・勾留されている場合、家族との窓口になってもらえる
逮捕されている被疑者は、家族と面会することができません。
逮捕から勾留に移行した後も、家族との面会は短時間に制限されるほか、接見禁止処分により面会できないケースもあります。
これに対して弁護士は、被疑者といつでも面会(接見)することが可能です(=接見交通権)。
接見交通権を活かして、弁護士は被疑者と家族を繋ぐ役割を果たします。
お互いに伝えたいことがあれば、弁護士が接見の際に伝えることができます。
家族が被疑者に差し入れをしたい場合は、弁護士に預ければ代わりに差し入れてもらえます。
弁護士を通じて家族と繋がることは、心身ともに過酷な環境に置かれた被疑者にとって、心の安定に少なからず寄与するでしょう。
刑事弁護を依頼する際の弁護士費用
刑事弁護を弁護士に依頼する際には、主に以下の弁護士費用がかかります。
①相談料
刑事弁護を正式に依頼する前の段階で、法律相談を利用した際に発生することがあります。
②着手金
刑事弁護を正式に依頼する段階で支払います。
③報酬金
刑事弁護の対応が終了した段階で、弁護士による事件処理の結果に応じて発生します。
④日当
刑事弁護の対応に伴い、弁護士が出張した際に発生します。
「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考に、各弁護士費用の目安額(いずれも税込)を紹介します。
実際の弁護士費用は依頼先によって異なるので、弁護士へ個別にご確認ください。
相談料の目安
相談料は、30分当たり5,500円程度に設定している弁護士が多いです。
その一方で、無料相談を受け付けている弁護士も多数存在します。
着手金の目安
刑事弁護の着手金額は、事案の内容や複雑さを考慮して決められるのが一般的です。
<刑事弁護に関する着手金額の目安>
| 起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | 22万円~55万円 |
| 上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 | 22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
報酬金の目安
刑事弁護の報酬金額は、不起訴処分(または略式起訴)となったかどうか、あるいは刑事裁判における判決の内容によって決まるのが一般的です。
<刑事弁護に関する報酬金額の目安>
| 起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | <起訴前> 不起訴:22万円~55万円 求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額
<起訴後> 刑の執行猶予:22万円~55万円 求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額 |
| 上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 | <起訴前> 不起訴:22万円~55万円以上 求略式命令:22万円~55万円以上
<起訴後> 無罪:55万円以上 刑の執行猶予:22万円~55万円以上 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
日当の目安
刑事弁護の日当額は、弁護士が出張した際の拘束時間を基準に決まるのが一般的です。
<刑事弁護に関する日当額の目安>
| 半日(往復2時間超4時間以内) | 3万3,000円以上5万5,000円以下 |
| 一日(往復4時間超) | 5万5,000円以上11万円以下 |
刑事弁護を依頼する弁護士を探すなら「ベンナビ刑事事件」
刑事弁護を依頼できる弁護士に心当たりがない方は、「ベンナビ刑事事件」を活用するのがたいへん便利です。
地域や相談内容に応じて、スムーズに弁護士を検索できます。
「ベンナビ刑事事件」には、刑事弁護について無料相談ができる弁護士も多数登録されています。
メールや電話で弁護士に直接問い合わせることができるので、複数の弁護士を比較して選びたい方や、できるだけ弁護士費用を抑えたい方にもおすすめです。
刑事弁護を弁護士に依頼したい方は、「ベンナビ刑事事件」をご活用ください。