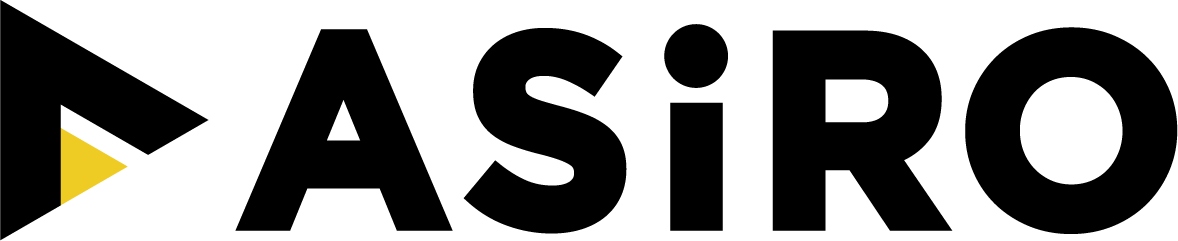「略式起訴」とは、検察官が簡易裁判所に対して、簡略化された手続き(略式手続)による被疑者への科刑を求めることをいいます。
正式起訴に比べて、被疑者が早期に刑事手続きから解放される点などが略式起訴のメリットです。
罰金以下の刑が定められている犯罪につき、嫌疑が固く不起訴処分が期待できない場合には、正式起訴よりも略式起訴のほうが被疑者にとって有利です。
今回は略式起訴について、正式起訴との違い・手続き・注意点などを解説します。
略式起訴で早期に刑事手続きから解放されたいと考えているが、その方法がわからずに困っていませんか?
結論からいうと、略式起訴を目指すためには起訴前の段階での対処が必要です。略式起訴を受けて事件を早急に解決したい場合は、すぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 略式起訴を目指すべきケースかがわかる
- 刑事手続きや取り調べについてのアドバイスがもらえる
- 依頼した場合、被害者との示談交渉などで正式起訴を避けるための弁護活動をしてくれる
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
略式起訴(略式手続)とは
「略式起訴」とは、検察官が簡易裁判所に対して、略式命令により被疑者に刑罰を科すことを求めることをいいます。
法的には「略式命令請求」などと呼称するほうが適切ですが、慣例的に「略式起訴」と呼ばれることが多いです。
検察官が裁判所に対して、公開法廷でおこなわれる通常の公判手続きを求めることを「正式起訴」といいますが、略式起訴は正式起訴と対比される処分と位置付けられます。
略式手続の目的
簡易裁判所が略式命令の内容・可否を審査する手続きを「略式手続」といいます(刑事訴訟法461条以下)。
略式手続の目的は、悪質性の高くない軽微な刑事事件を、簡易迅速な手続きによって処理することにあります。
刑事手続きが長引くと、被疑者・被告人に大きな負担がかかります。
重大な犯罪であれば適正手続きの観点からやむを得ませんが、軽微な犯罪について長期間の公判手続きをおこなうのは、被告人が受ける不利益の大きさを考慮すると不適切な場合があります。
そこで、一定の軽微な犯罪については略式手続による科刑を認めることで、被疑者を早期に刑事手続きから解放する道を用意しているのです。
略式命令によって科すことのできる刑罰
簡易裁判所が略式命令によって科すことができる刑罰は、「100万円以下の罰金または科料」に限られています。また、刑の執行猶予・没収その他の付随処分をおこなうことも可能です(刑事訴訟法461条)。
これに対して、死刑・懲役・禁錮・100万円を超える罰金・拘留については、正式裁判(公判手続き)によらなければ科すことができません。
略式起訴の要件
検察官が被疑者を略式起訴する場合、以下の手続きをおこなう必要があります(刑事訴訟法461条の2)。
- 被疑者に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明する
- 正式裁判による審判を受けることができる旨を告げる
- 略式手続によることについて、被疑者に異議がないことを書面で確認する
もし被疑者が略式手続を拒否すれば、検察官は略式起訴をすることができず、正式裁判を請求することになります。
略式起訴と正式起訴の違い
略式起訴に対して、検察官が裁判所に通常の公判手続き(正式裁判)を請求することを「正式起訴」といいます。
略式起訴と正式起訴の主な違いは、以下のとおりです。
①略式手続は非公開
正式裁判は公開法廷でおこなわれますが、略式手続は非公開でおこなわれます。
②略式手続は書面審査のみ
被告人が出頭しておこなわれる正式裁判とは異なり、略式手続では書面のみによって審査がおこなわれます。
③被告人に反論の機会はない
正式裁判では、被告人は自ら主張をおこない、関連する証拠を裁判所に提出できます。これに対して略式手続では、被告人に反論の機会が与えられません。
④正式裁判では科刑の制限がない
略式手続によって科すことのできる刑罰は「100万円以下の罰金または科料」に限定されていますが、正式裁判では、法定刑の範囲内であれば科刑の制限がありません。
略式起訴の期限
起訴について、特に法律上の期限は設けられていません。
ただし、身柄拘束されている被疑者については通常、起訴前勾留の期間(最長20日間、刑事訴訟法208条)が満了するまでに略式起訴がおこなわれます。
起訴前勾留の期間内に起訴しないと、被疑者を釈放しなければならないためです。
一方、身柄拘束されていない被疑者について略式起訴がおこなわれる場合、その時期は検察官の裁量によって決められます。
略式起訴の手続きの流れ
検察官が被疑者を略式起訴する際には、以下の流れで手続きがおこなわれます。
- 検察官による略式手続の説明・告知
- 被疑者による申述書の提出
- 検察官による略式命令請求
- 簡易裁判所による審査
- 簡易裁判所による略式命令
- 異議がある場合は正式裁判の請求
- 略式命令の確定・罰金or科料の納付
検察官による略式手続の説明・告知
検察官は、まず略式手続とは何かを被疑者に理解させるため、必要な事項の説明をおこないます(刑事訴訟法461条の2)。
被疑者が検察官の説明を理解できない場合は、さらに具体的かつわかりやすく説明するように求めましょう。
また、検察官は被疑者に対して、正式裁判による審判を受けることができる旨を告げる必要があります。
被疑者としては、略式手続のデメリットを考慮し、拒否した上で正式裁判を求めることも選択肢の一つです。
被疑者による申述書の提出
略式手続によることにつき異議がない場合、被疑者は検察官に対してその旨の申述書を提出します。
申述書の様式は事件事務規程に定められています。被疑者は、検察官から交付される様式に沿って、日付・住居・氏名を記載して提出しましょう。
検察官による略式命令請求
被疑者から異議がない旨の申述書が提出された場合、検察官は公訴の提起と同時に、簡易裁判所に対して書面で略式命令の請求をおこないます(刑事訴訟法462条1項)。
略式命令の請求書には、被疑者(被告人)から提出された申述書を添付しなければなりません(同条2項)。
簡易裁判所による審査
簡易裁判所は、以下のいずれかに該当すると判断した場合には、正式裁判による審理をおこなわなければなりません(刑事訴訟法463条1項、2項)。
- 事件が略式命令をすることができないものであるとき
- 事件が略式命令をすることが相当でないものであるとき
- 検察官が略式命令請求に関する手続きに違反したとき
上記に該当しない場合には、簡易裁判所は検察官から提出された書面について審査をおこない、略式命令の内容を決定します。
簡易裁判所による略式命令
簡易裁判所は審査の完了後、被告人に対して略式命令を告知します。
略式命令には、以下の事項を記載しなければなりません(刑事訴訟法464条)。
- 罪となるべき事実
- 適用した法令
- 科すべき刑および附随の処分
- 略式命令の告知があった日から14日以内に正式裁判を請求できる旨
異議がある場合は正式裁判の請求
略式命令に異議がある場合、被告人・検察官は、略式命令の告知日から14日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法465条1項)。
正式裁判の請求は、略式命令をした簡易裁判所に対して書面を提出しておこないます(同条2項)。
正式裁判への移行後も、第一審の判決があるまでは、正式裁判の請求を取り下げることが認められています(刑事訴訟法466条)。取下げがなされた場合、略式命令が確定します(刑事訴訟法470条)。
正式裁判において判決が言い渡された場合、略式命令は失効します(刑事訴訟法469条)。
略式命令の確定・罰金or科料の納付
略式命令は、以下の場合に確定します(刑事訴訟法470条)。
- 正式裁判の請求期間が経過した場合
- 正式裁判の請求が取り下げられた場合
- 正式裁判の請求を棄却する裁判が確定した場合
確定後、被告人は検察庁に対して、略式命令で定められた罰金または科料を納付します。納付方法については、検察庁の徴税事務担当者に確認してください。
なお、罰金・科料を完納できない場合は、労役場留置となります(刑法18条)。
略式起訴を受け入れることのメリット・デメリット
被疑者(被告人)にとって、略式起訴を受け入れることにはメリット・デメリットの両面があります。弁護人と相談した上で、総合的な観点から受け入れるかどうかを決めましょう。
略式起訴のメリット
被告人にとって、略式起訴の主なメリットは以下のとおりです。
- 禁錮以上の刑は科されない
- 短期間で刑事手続きから解放される
- 公開法廷での裁判を回避できる
禁錮以上の刑は科されない
略式手続によって科すことのできる刑は、100万円以下の罰金または科料に限られます。
したがって、略式起訴を受け入れれば禁錮以上の刑は科されず、少なくとも刑務所への収監は回避できます。
短期間で刑事手続きから解放される
被告人にとって、刑事手続きが長引くことは大きな負担になる可能性が高いです。
略式起訴を受け入れれば、書面審理のみによって短期間で手続きが終了するため、被告人にとって負担が軽くなります。
早期に刑事手続きから解放されることにより、その分社会復帰も早まるでしょう。
公開法廷での裁判を回避できる
通常の公判手続きは公開法廷でおこなわれるため、傍聴人の視線に晒されることになります。
特に知名度の高い方は、興味本位の傍聴人から奇異の目を向けられるかもしれません。
略式起訴を受け入れれば、公判手続きはおこなわれないので、公開法廷における審理を回避できます。
略式起訴のデメリット
被告人にとって、略式起訴の主なデメリットは以下のとおりです。
- 無罪を主張することはできない
- 量刑について被告人側の主張が考慮されない
無罪を主張することはできない
略式手続では、被告人が無罪を主張することはできません。
したがって、検察官が提出する証拠に不備がない限り、基本的には有罪判決が言い渡される可能性が高いです。
犯罪について身に覚えがなく、無罪を主張して争いたい場合には、略式手続を拒否して正式裁判を請求しましょう。
量刑について被告人側の主張が考慮されない
略式手続では、被告人に反論する機会が与えられないため、量刑についても被告人側の主張は一切考慮されません。
ただし、略式手続きによって科される刑は軽微な罰金・科料にとどまります。
そのため、犯罪事実に間違いがなければ、早期に刑事手続きから解放されるメリットを考慮して、略式起訴を受け入れることも検討すべきでしょう。
略式起訴に関するQ&A
略式起訴に関して、以下のよくある疑問につき回答をまとめました。
- 略式命令を受けると前科が付くのか?
- 罰金・科料を支払わないとどうなるのか?
- 罰金・科料を準備できない場合はどうすべきか?
- 略式手続を拒否すべきなのは、どのような場合か?
- 正式裁判を請求した場合、どこの裁判所が審理するのか?
略式命令を受けると前科が付くのか?
略式命令が確定した場合は刑事罰が科されるため、被告人には前科が付きます。
前科が付いた場合、再度罪を犯すと量刑が加重される可能性が高いので注意してください。
罰金・科料を支払わないとどうなるのか?
確定した略式命令に基づく罰金・科料を支払えない場合、労役場留置の処分がおこなわれます(刑法18条)。
労役場留置の期間は、以下の期間の範囲内で定められ、略式命令の主文に記載されます。
| 罰金を完納できない場合 | 1日以上2年以下 ※罰金を併科した場合、または罰金と科料を併科した場合は1日以上3年以下 |
| 科料を完納できない場合 | 1日以上30日以下 ※科料を併科した場合は1日以上60日以下 |
一般的には、未納5,000円当たり1日の労役場留置がおこなわれることが多いです。労役場では、懲役刑の受刑者がおこなう刑務作業に準じた軽作業が命じられます。
罰金・科料を準備できない場合はどうすべきか?
罰金・科料をすぐに準備できなくても、検察庁の徴収事務担当者に一部納付または納付延期を申し出れば、労役場留置を回避できる可能性があります。
①一部納付の申出(徴収事務規程16条)
罰金・科料のうち一部を納付する旨の申出です。徴収主任が調査をおこない、合理的な事由があると認めた場合には、一部納付が許可されることがあります。
②納付延期の申出(徴収事務規程17条)
罰金・科料の納付を延期する旨の申出です。徴収主任が調査をおこない、合理的な事由があると認めた場合には、納付延期が許可されることがあります。
略式手続を拒否すべきなのは、どのような場合か?
略式手続では、被告人側の主張を審理に反映させることができません。
たとえば無罪を主張したい場合や、検察官の求刑に不服がある場合には、略式手続を拒否して正式裁判を請求しましょう。
正式裁判を請求した場合、どこの裁判所が審理するのか?
略式手続を拒否して正式裁判を請求した場合や、略式命令を受けた後に正式裁判を請求した場合には、検察官が公訴提起の際に指定した裁判所が正式裁判の審理をおこないます。
略式手続の対象となっている犯罪については、いずれも簡易裁判所が管轄権を有するため(裁判所法33条1項2号)、正式裁判も簡易裁判所が担当するケースが大半です。
なお、正式裁判の一審判決に対して控訴を提起した場合、控訴審の管轄は高等裁判所となります(裁判所法16条1号)。
正式起訴を避けたい場合は弁護士にご相談を
不起訴となるべき場合や無罪を主張して争う場合を除けば、短期間で刑事手続きから解放される略式起訴は、被告人にとってメリットの大きい手続きといえます。
特に、嫌疑が確実で不起訴も期待できない場合には、正式起訴ではなく略式起訴を目指すべきでしょう。
しかし、懲役刑・禁錮刑や100万円を超える罰金刑を科すべきと検察官が判断した場合は、正式起訴がおこなわれてしまいます。
被疑者としては、起訴される前に検察官に対して良い情状をアピールして、求刑を軽いものにとどめるよう働きかけるべきです。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉や検察官とのやり取りを通じて、できる限り正式起訴を避けるための弁護活動をおこなってもらえます。
自身や家族が犯罪捜査の対象となった場合は、すぐに弁護士まで相談してください。
さいごに
略式起訴は、公開法廷での審理を避けつつ短期間で刑事手続きから解放される点で、被疑者(被告人)にとってメリットのある手続きです。
検察官から略式起訴を提案されたら、無罪を主張して争う場合を除けば、基本的には受け入れたほうがよいでしょう。
不起訴または略式起訴によって刑事手続きから解放されるためには、起訴前段階での弁護活動が重要になります。できる限り早期に弁護士へ相談することが、正式裁判や重い刑罰を避けるための重要なポイントです。
弁護士に相談すれば、刑事手続きの見通しや取調べに臨む際の注意点などについてアドバイスを受けられます。プレッシャーのかかる刑事手続きにおいて、弁護士は心強い味方です。
自身や家族が犯罪捜査の対象となってしまった場合は、速やかに弁護士へ相談しましょう。
略式起訴で早期に刑事手続きから解放されたいと考えているが、その方法がわからずに困っていませんか?
結論からいうと、略式起訴を目指すためには起訴前の段階での対処が必要です。略式起訴を受けて事件を早急に解決したい場合は、すぐに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 略式起訴を目指すべきケースかがわかる
- 刑事手続きや取り調べについてのアドバイスがもらえる
- 依頼した場合、被害者との示談交渉などで正式起訴を避けるための弁護活動をしてくれる
当サイトでは、刑事事件解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。