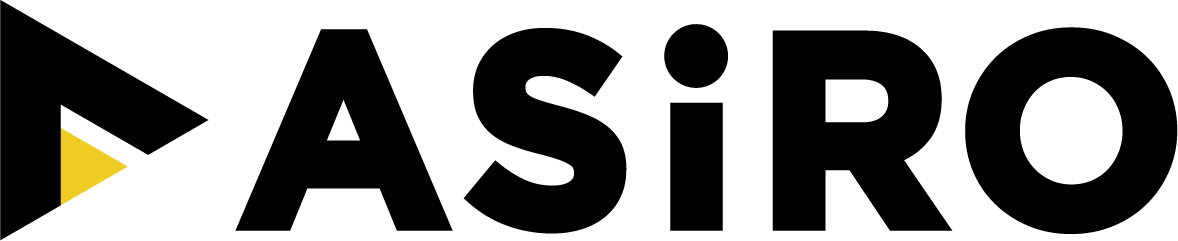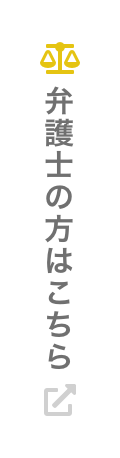「ネット上で脅迫を受けて身の危険を感じた」という方も多いのではないでしょうか?
実際の事件でも事件の前に、ネット上で加害者が被害者に対して脅迫をしていたというケースは少なくありません。
そのため、身の危険を感じるほどの脅迫を受けたら、警察などに相談して然るべき対処をすべきでしょう。
しかし、何も証拠がない状態や、客観的に見て「身の危険があるほどの脅迫」と感じられない内容の場合には、ネットで脅迫を受けても警察が動いてくれるとは限りません。
本記事では、ネットの脅迫で警察が動いてくれるケースと、警察に通報する前にやるべきことについて詳しく解説します。
ネットでの脅迫から事件に繋がってしまう事例も存在するため、ネット上での脅迫に対する適切な対処法を理解しておきましょう。
ネットの脅迫でも警察は動いてくれる!
ネットの脅迫でも内容によっては、警察が動いてくれる可能性があります。
芸能人やスポーツ選手などがネットで脅迫されるようなケースは社会問題化していますし、実際にネットでの脅迫から事件になって事例も数多く存在します。
警察もこのような事態は当然に理解しているため、ネットでの脅迫は「事件につながる行為」と重く考えているでしょう。
また、ネットでの脅迫そのものが犯罪になるケースも少なくありません。
そのため、警察はネットでの脅迫に関する相談を受け付けています。
例えば、大阪府警はネット上の脅迫について以下のようにホームページに明記しています。
脅迫等何らかの犯罪被害にあっているとお考えならば、「1 証拠を保全する」で説明する資料を準備し(中略)あなたの住所地を管轄する警察署に事前に連絡の上相談に行かれてはいかがでしょうか。
(中略)あなたの身に直接危害が及ぶおそれがあり、緊急の場合は、すぐに110番通報してください。
身の危険を脅かすような脅迫を受けた場合、警察へ相談することで事件として警察が動いてくれる可能性があるでしょう。
ネットの脅迫で警察が動いてくれるかは内容次第
ネット上での脅迫を事件として扱い、警察が動いてくれるかどうかは、書き込みや投稿の内容次第というのが実情です。
書き込まれた側が一方的に「これは脅迫だ」と主張しても、警察が脅迫と判断できない場合には動いてくれないこともあるでしょう。
そのため、どのようなケースで警察が動くのか理解しておくことが重要です。
ここでは、ネット上の脅迫被害で警察が動いた事例を紹介します。
ネット上でよくある脅迫被害の例
ネット上でよくある脅迫被害の事例は、主に次の2つのケースです。
- 「殺す」「放火する」などの実際に危害を加える投稿をする
- 「写真」「プライバシー」などを晒すと脅迫される
「殺す」「放火する」などの投稿は、脅迫罪が成立する可能性があります。
例えば「1月10日に会社へ押しかけ、会社にガソリンを撒いて放火する」などの投稿は明らかに脅迫罪が成立し、逮捕者が出る可能性がある投稿です。
日時や場所を指定しているような投稿は、実際に被害が生じないように警察が出動する可能性があるため、それと同時に投稿者が逮捕される可能性があるでしょう。
また、「写真やプライバシーを晒す」などの脅迫も脅迫罪が成立する可能性があります。
SNSなどで知り合った人に裸の写真などを送ってしまい、その写真を晒すことを口実に「会ってくれないなら晒す」などと脅迫される事例は少なくありません。
この他にも個人情報を晒すと脅迫される事例もあり、実際に社会問題化しています。
具体的に「どのような写真を晒して」「どのような個人情報を晒す」のかを示す脅迫であれば、脅迫罪で警察が動く可能性があるでしょう。
ネット上の脅迫で実際に警察が動いた事例
実際にネット上の脅迫で逮捕された事例をいくつか紹介します。
①那覇市長の殺害予告を書き込んだ
(2022年4月12日)県外の行政機関のホームページに城間幹子那覇市長を「殺そうと思っています」などの文章を送ったとして、脅迫の疑いで那覇市の会社員の容疑者(51)を逮捕した。(中略)沖縄県那覇署によると、1月28日から3月4日の間に3回、県外の行政機関ホームページの意見要望投稿フォームに投稿し脅迫した疑い。
②オンラインゲームに負けた腹いせにセガサミー社員を脅迫
ゲーム機大手セガサミーホールディングス(東京都品川区)に脅迫メールを送ったとして、品川署は(2022年3月17日)、愛知県豊川市、会社員の男(54)を脅迫と威力業務妨害容疑で逮捕したと発表した。
男は1月12日~2月2日、同社の問い合わせ窓口に「会社を放火し、社員をぶっ殺してやる」などと書いたメールを12回送信し、従業員を脅迫したほか、同社に警備対策を取らせるなど業務を妨害した疑い。調べに、「オンラインゲームに負けて悔しかった」と容疑を認めている。
実際に暴行などに及んでいなくても、公人に対する脅迫や、複数回にわたる脅迫、また脅迫によって警備対策の強化などの対応をとった場合には、脅迫的な投稿をしたことだけで逮捕される可能性があるでしょう。
ネット上の脅迫で成立し得る主な犯罪と刑事罰
ネット上の脅迫は、実際に傷害などの犯罪に及ばなくても、書き込んだことそのものが犯罪として成立する可能性があります。
ネット上の脅迫で成立する可能性がある犯罪は次の3つです。
- 脅迫罪
- 強要罪
- 威力業務妨害罪
それぞれの罪がどのような投稿で成立する可能性があり、どの程度の刑罰が課されるのか詳しく解説します。
脅迫罪 | 相手の生命・身体や名誉などに害を与えると告知した場合の罪
脅迫罪とは、相手の生命や身体や名誉などに害を与えると告知した場合の罪です。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。引用元:刑法|e-Gov法令検索
脅迫罪で有罪となると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰が課せられます。
「殺す」という投稿は身体に害を加える旨の告知ですし、「写真を晒す」などの投稿は名誉に害を与える告知に該当する可能性があります。
多くの脅迫的な投稿は脅迫罪に該当する可能性があるといえるでしょう。
強要罪 | 脅迫や暴行によって相手に義務のないことをおこなわせる罪
強要罪とは、脅迫や暴行によって相手に義務のないことを実行させる罪です。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。引用元:刑法|e-Gov法令検索
強要罪で有罪になると、3年以下の懲役が刑罰として課されます。
例えば「自分に会わないならネットに写真を晒す」などと強要する行為は、名誉に害を与える旨の告知に該当するため強要罪が成立する可能性があります。
また、3項にて「前二項の罪の未遂は、罰する。」と明記されていることから、実際に強要させなくても「自分に会わないならネットに写真を晒す」と投稿するだけで、強要未遂となる可能性があります。
威力業務妨害罪 | 威力によって相手の業務を妨害した場合
他人の自由意志を抑圧するような、強い力や勢いで相手の業務を妨害する投稿は、威力業務妨害罪になる可能性があります。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。引用元:刑法|e-Gov法令検索
威力業務妨害罪で有罪となると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰が課されます。
例えば「○月○日に店舗を爆破する」などと投稿し、実際に店舗が当日を休業せざるを得なくなった場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ネットの脅迫を警察に通報する前に証拠を確保しよう
ネットの脅迫を警察へ通報する前には、できる限り証拠を保全することに努めましょう。
実際に大阪府警では、ネットで脅迫されたら次のような証拠を集めるように明記しています。
次のものを用意(保存の上、印刷)してください。
- 対象となる掲示板のURLや、コミュニケーションアプリの名前
- 強百内容(脅迫の文言・画像、投稿日時、投稿番号、受信日時、URL)
- 脅迫内容の閲覧方法
- 投稿した人物のIDやアカウント名
- その他、経緯や対応等を明らかにできる記録
このほか、投稿が消される前にスクショを取ったり、該当するページを印刷するなどして証拠を保全しましょう。
また、該当する投稿の前後のやり取りも同時に保全しておくことが重要です。
投稿が脅迫に当たるかどうかは、その投稿に至るまでの前後のやり取りが重要になるためです。
ネットで脅迫されたら、
- スクショを取る
- 前後のやり取りを保存しておく
- URLがわかるようにしておく
3点に注意して証拠を保全しましょう。
警察へ相談する際には、確保した証拠を持参しましょう。
ネットでの脅迫を警察へ通報・相談する場合の窓口
ネットで脅迫されたら警察や通報したり相談したりすることができますが、警察の通報・相談窓口には次のようなものがあります。
- 110番
- 最寄りの警察署
- #9110
- オンライン窓口
それぞれの窓口ごとに緊急性や用途が異なります。
以下では、どのようなタイミングでどの窓口へ相談すべきなのか、詳しく解説します。
緊急性が高い場合は「110番」
「今から殺しに行く」などと投稿され、緊急で身の危険を感じた場合には、すぐに110番通報してください。
爆破予告、殺人予告、自殺予告等の人命に関わる事案は最寄りの警察署に通報(緊急を要するものは110番)してください。
投稿に危険性が認められた場合には、110番通報ですぐに警察が動いてくれる可能性があります。
最寄りの警察署へ行って通報・相談することも可能
すぐに身の危険を感じるような状況ではないが、怖さを感じる場合や、自宅にパトカーが来たら困ると考えている方は、最寄りの警察署へ訪問して相談や通報をすることも可能です。
その場合は、脅迫投稿の証拠などを持参して、最寄りの警察署へ相談に行きましょう。
あなたが、脅迫等何らかの犯罪被害にあっているとお考えならば、「1 証拠を保全する」で説明する資料を準備し、平日(午前9時00分から午後5時45分)にあなたの住所地を管轄する警察署に事前に連絡の上相談に行かれてはいかがでしょうか。
警察署によって相談時間が決まっているほか、すぐに対応してもらえない可能性があるため、緊急時には「パトカーが来たらいやだ」などと考えず、110番通報したほうがよいでしょう。
犯罪にあたるか分からないが相談したい場合は「#9110」
ネットに投稿された内容が脅迫罪などにあたるかわからず、相談したいという方は「#9110」へ電話しましょう。
「#9110」は警察相談専用電話のことで、電話をかけた地域を管轄する警察本部へ繋がります。
投稿の内容を伝え、脅迫罪が成立するかどうかや、適切な対処方法を確認するとよいでしょう。
110番は「いますぐ警察に駆けつけて欲しい」というときに使用しますが、#9110番は相談したいときに利用できます。
緊急性の低い場合や「このまま脅迫的な投稿を放置しても大丈夫なのか?」と相談したい場合には「#9110」を利用するとよいでしょう。
なお「#9110」は、平日の日中しか相談を受け付けていません。各都道府県警察本部の営業時間に合わせて、午前8:30から午後5:15までを対応時間としていることが多いので、詳しくは警察本部のホームページで確認しましょう。
土日など、相談対応時間外に身の危険を感じた場合には、110番に通報することも検討してください。
警察からのアドバイスが欲しい場合はオンライン窓口
警察では、オンラインの相談窓口も設けています。
電話で通報や相談するほどの緊急性はないものの、不安だから適切な対処法を知りたいという方はオンライン窓口も活用するとよいでしょう。
オンライン窓口では、ネット上の脅迫などのサイバー犯罪について相談・情報提供をおこなうことができます。
また、情報提供もおこなえるため、ネット上の脅迫投稿などを見つけたら、警察へ情報を提供することで、犯罪を未然に防ぐことに寄与できる可能性があります。
警察が動いてくれない場合はどうすればいい?
証拠が不十分な場合や警察署の対応によっては、所轄の警察署では動いてくれない場合があります。
このような場合には、次のような方法でネットの上の脅迫に対処してください。
- サイバー犯罪相談窓口にも問い合わせてみる
- 刑事告訴を検討する
- 弁護士に依頼して刑事告訴をしてもらう
- 加害者の身元を特定して慰謝料を請求する
最寄りの警察署が動いてもらえない場合にも、対処方法はいくつもあるため、決して放置せず、適切に対応してください。
それぞれの対処法について、以下で詳しく解説します。
サイバー犯罪相談窓口にも問い合わせてみる
最寄りの警察署が動いてくれない場合には、サイバー犯罪相談窓口にも問い合わせてみましょう。
サイバー犯罪相談窓口では、通報先を選択できるため、「警察本部」を選択して通報や相談をおこなえば、警察本部へ脅迫の内容を相談・通報できます。
最寄りの警察署が動いてくれなくても、最寄りの警察署へ警察本部から連絡が行くことで、警察が動く可能性があるでしょう。
刑事告訴を検討する
警察が動いてくれない場合には、被害者自ら刑事告訴をすることで警察が動かすことができます。
刑事告訴とは、捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
脅迫罪は、被害者自ら被害を訴えなければ犯罪が成立しない親告罪ではありません。しかし、相談しても警察が動かないのであれば刑事告訴をする意味があります。
告訴を受けた捜査機関は、捜査を尽くす義務を負うと解されているためです。
相談しても警察が動かない場合には刑事告訴を検討してください。
弁護士に依頼して刑事告訴をしてもらう
実際に刑事告訴をする際は、弁護士へ依頼しておこなったほうがよいでしょう。
刑事告訴は口頭でも可能ですが、一般的には告訴状を用いて書面でおこなうのが基本です。
そして、告訴状には脅迫投稿のスクショなどの証拠が必要になります。
警察に告訴を受理してもらうためには、適法な刑事告訴である必要があります。
次のような告訴は受理されない可能性が高いでしょう。
- すでに時効が成立している
- 犯罪事実が特定されていない
- 趣旨が判然としない
受理される可能性の高い告訴をしたいのであれば、弁護士へ相談・依頼したほうが無難です。
加害者の身元を特定して慰謝料を請求する
刑事事件として訴えるだけでなく、脅迫的な投稿に対しては民事事件として慰謝料や損害賠償を請求することもできます。
脅迫によって精神的苦痛を感じたのであれば、慰謝料を請求できるほか、威力業務妨害などであれば、妨害によって失った経済的な利益の損害賠償を請求できます。
ネットの投稿の多くが匿名でおこなわれていますが、発信者情報開示請求をおこなうことで、発信者の氏名や住所などの個人情報は特定することが可能です。
弁護士へ依頼すれば、発信者情報開示請求から慰謝料請求までおこなってくれるため、脅迫に対して民事的な責任を問いたい場合にも弁護士へ相談するとよいでしょう。
ネット上の脅迫を警察へ相談・通報する場合によくある質問
ネット上で脅迫され、警察に相談や通報をする際によくある質問を紹介します。
- 「恋人を殺す」と脅迫された場合、本人でない私が告訴しても警察は動いてくれますか?
- 匿名の投稿で脅迫された場合、警察は動いてくれませんか?
本人以外が脅迫されている場合や、投稿者名が特定できない場合でも警察が動いてくれるのか理解しておきましょう。
「恋人を殺す」と脅迫された場合、本人でない私が告訴しても警察は動いてくれますか?
恋人を殺すという脅迫でも、警察が動いてくれる可能性はあります。
脅迫罪や強要罪や威力業務妨害罪は、非親告罪です。
非親告罪とは、被害者が被害を訴えなくても、情報提供を受けた警察が独自の判断で捜査して取り締まる犯罪です。
そのため、恋人や友人が脅迫されている場合には、その旨を警察へ相談することで警察が動いてくれる可能性は十分あるでしょう。
匿名の投稿で脅迫された場合、警察は動いてくれませんか?
匿名の投稿で脅迫されている場合でも、警察は動いてくれる可能性があります。
脅迫罪などは非親告罪ですので、被害者が加害者を特定して被害を訴える必要はありません。
警察が投稿そのものの内容によって捜査が必要であると判断すれば、匿名の投稿での脅迫に対しても捜査をおこないます。
また、匿名投稿でも警察は投稿者の個人情報を特定することができます。
警察には捜査関係事項照会という制度があるため、警察が捜査が必要であると認めた投稿がされているサイトの運営者へIPアドレスの提供を依頼し、IPアドレスからサービスプロバイダへ照会をおこなうことで個人情報を特定できます。
匿名の投稿であっても警察は動いてくれる可能性があるので、脅迫された場合には早めに相談しましょう。
さいごに|警察が動いてくれないネットの脅迫は弁護士へ
ネット上の脅迫は、脅迫罪や強要罪などが成立する可能性があります。
脅迫について警察へ相談することで、警察が動いてくれる可能性があり、実際に逮捕まで至った事例も多数あります。
身の危険を感じるほどの脅迫を受けた場合には、迷わず110番に通報しましょう。
ただし、脅迫の内容や状況によっては警察が動いてくれない場合があります。
警察は刑事告訴をすることで動いてくれる可能性がありますが、警察が受理するような告訴状を一般の方が作成することは困難です。
そのため、ネット上で脅迫を受けていて警察に動いてもらいたい場合は弁護士へ相談するのがおすすめです。
弁護士へは刑事告訴だけでなく、民事事件として慰謝料請求などの相談・依頼も受け付けています。
ネットでの脅迫は、警察が動くかどうかの微妙な事案なので、脅迫された場合には早めに弁護士に相談し、対応方針についてアドバイスを得るとよいでしょう。