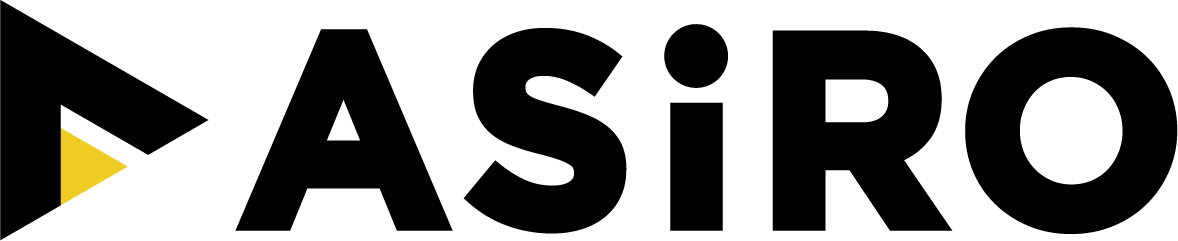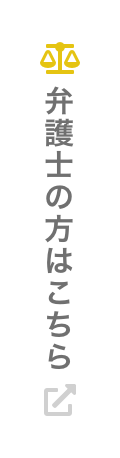SNSで誹謗中傷の書き込みをしてしまい「訴えられたらどうしよう…」と不安になっていませんか?
SNSや掲示板などで他人や会社、店舗などを誹謗中傷すると個人を特定され、損害賠償請求をされたり刑事告訴をされたりする可能性があります。
最近では「ネット上の誹謗中傷に対して名誉毀損などで訴えられる」ということが広く知られているため、あなたの投稿に対して被害者がなんらかの対応をとる可能性は十分考えられるでしょう。
そこで本記事では、SNSで誹謗中傷してしまったときの対処法や、具体的にどのような投稿が誹謗中傷になるのかについて詳しく解説します。
誹謗中傷をしてしまったがどうしたらいいかわからず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
誹謗中傷とは?悪口や噂で相手を否定・攻撃すること
誹謗中傷とは、相手に対して悪口を言ったり、根拠のない噂などを流して、人格や名誉を貶める行為を指します。
どこからが誹謗中傷にあたるのかの明確な区分はありません。
しかし、基本的には「根拠のないこと」や「虚偽の内容」で相手の攻撃したり否定することは誹謗中傷に該当する可能性が極めて高いと考えられます。
また、他人が誰かを誹謗中傷した投稿をリポストしたり、シェアするなどの方法で再投稿する行為も「誹謗中傷をおこなった」と判断される可能性が高いでしょう。
誹謗中傷の内容を見かけても、安易に他人へ共有することがないよう注意してください。
誹謗中傷をすると、名誉毀損などの民事責任が問われるだけでなく、名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事責任を問われる可能性もあります。
誹謗中傷をしてしまったあとに投稿者に起こりうる3つのこと
SNSで誹謗中傷をしてしまった投稿者には、以下の3つのリスクがあります。
- 発信者情報開示請求をされる
- 損害賠償請求をされる
- 刑事告訴をされる
匿名だからといって無責任に誹謗中傷の内容を含む投稿をすると、さまざまなリスクが生じる可能性があります。
以下では、それぞれのリスクについて詳しく解説します。
1.発信者情報開示請求をされる
誹謗中傷の投稿をすると、誹謗中傷された人から発信者情報開示請求がおこなわれる可能性があります。
発信者開示請求とは、インターネット上の匿名投稿で他人の権利が侵害された際に、誹謗中傷された被害者がプロバイダーに対して発信者の情報を開示するように求めるものです。
開示請求手続きは特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法。旧プロバイダ責任制限法)で以下のように定められています。
(発信者情報の開示請求)
第五条
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
発信者開示請求は、サイトの運営元である「コンテンツプロバイダ」へおこなう場合と、携帯キャリアなど、インターネット接続サービスを提供する事業者である「アクセスプロバイダ」へおこなう方法があります。
サイトの運営元が投稿者の個人情報を保有している場合には「コンテンツプロバイダ」へ開示請求をおこなうことで、発信者の氏名や住所などを特定できます。
しかし、匿名のSNSなどでは、サイトの運営元は発信者の情報をもっていないことが多いでしょう。
そのため、まずは「コンテンツプロバイダ」からIPアドレスなどの提供を受けたあとに「アクセスプロバイダ」へ開示請求をおこない、氏名や住所を特定する流れが一般的です。
いくら匿名でアカウント作成しても、誹謗中傷の被害者が発信者開示請求をおこなった場合には、ほぼ確実に個人が特定されてしまうと理解しておきましょう。
2.損害賠償請求をされる
発信者情報開示請求によって個人情報が特定されたあとは、被害者が加害者に向けて損害賠償請求をおこなう可能性が高いでしょう。
インターネット上の誹謗中傷に対して民事裁判で認められる慰謝料・損害賠償額は、投稿内容など、個別の事情により左右されますが、おおむね10万円から100万円に収まることが多いです。
ただし、誹謗中傷の書き込みによって企業の利益を損ねてしまった場合、その損害額に対しても損害賠償請求がおこなわれ、場合によっては数百万円の損害賠償になる可能性もあります。
相手側の弁護士が任意で示談交渉をしてきた場合には、慰謝料を支払って裁判にならずに和解になることもありますが、相手が権利の侵害を訴えて裁判になるケースも多々あります。
また、慰謝料や損害賠償だけでなく、発信者情報開示請求などにかかった弁護士費用の負担も認められる可能性があるため注意してください。
3.刑事告訴をされる
誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性もあるため、場合によっては相手方が刑事告訴する可能性もあります。
インターネット上の誹謗中傷によって刑事告発される可能性がある主な罪は「名誉毀損罪」と「侮辱罪」です。
それぞれ、最悪のケースとして懲役刑又は禁固刑が課される可能性があります。
インターネット上の誹謗中傷は「慰謝料や損害賠償などの民事責任だけを負えばいい」と考えている人も多いですが、相手によっては刑事告発をおこなう可能性も十二分にあります。
刑事告発されてしまうと、刑務所へ行かなければならない可能性もあるため、ネット上の書き込みには責任をもちましょう。
※令和7年6月1日に施行される改正刑法では、懲役刑と禁錮刑が、拘禁刑に一本化されます。
誹謗中傷をしてしまった場合に成立する可能性がある主な犯罪
SNSで誹謗中傷をすると、主に、以下のような罪に問われてしまう可能性があります。
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
それぞれの罪が成立する要件や刑罰について、詳しく見ていきましょう。
1.名誉毀損罪|事実を指摘して他人の社会的地位を低下させた場合に成立する
誹謗中傷の内容によっては、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪が成立する要件は、ざっくり以下のとおりです。
- 「公然と」おこなわれたもの
- 「事実を摘示」したこと
- 同定可能性があること
- 「人の名誉を毀損」したこと(人の社会的評価を低下させる内容を投稿したこと)
- 違法性阻却事由がないこと
ネット上など、誰にでも見える状態で誹謗中傷することは「公然」とおこなわれたことになります。
また、「事実を摘示」とは、具体的な事実内容を投稿したことです。例えば「Aさんは過去に殺人をした」などと投稿することは「事実を摘示」したことに該当します。
同定可能性とは、個人を特定できることです。「山◯一郎」などと伏字を使用していても、文脈等から一般の閲覧者が個人を特定できる内容であれば、同定可能性があると判断される可能性が高いです。
なお、違法性阻却事由とは、以下の3つです。
- 公共の利害に関する事実に係るものであること
- その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- 真実であることの証明があったこと
これらの違法性阻却事由がいずれもあれば、名誉毀損罪の刑事責任は問われません。
名誉毀損罪の刑罰は、以下のように「3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金」と定められています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
2.侮辱罪|事実を指摘せずに他人の社会的地位を低下させた場合に成立する
誹謗中傷は、内容によっては侮辱罪に該当する可能性もあります。
侮辱罪とは公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です。
侮辱罪の成立要件は、「事実を摘示せずに公然と人を侮辱した」ことです。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
事実を摘示して誹謗中傷をおこなった場合には、名誉毀損罪が成立しますが、「バカ」「ブサイク」「ブラック企業」などの事実の摘示がない誹謗中傷を公然とおこなった場合には、侮辱罪が成立する可能性があるのです。
誹謗中傷の対象は個人だけでなく法人も含まれます。会社に対して事実を摘示せず誹謗中傷をおこなった場合も、侮辱罪によって刑事責任が問われる可能性があるでしょう。
なお、侮辱罪の罰則は「1年以下の懲役/禁錮/30万円以下の罰金」と、こちらも懲役刑・禁固刑がある重いものとなっています。
安易に「バカ」や「ブサイク」などと、いわゆる悪口を投稿するだけでも、警察に逮捕されて刑務所へ行く可能性がゼロではないと認識し、インターネット上の投稿は責任をもっておこなう必要があります。
※令和7年6月1日に施行される改正刑法では、懲役刑と禁錮刑が、拘禁刑に一本化されます。
ネット上の誹謗中傷によって起訴された事例2選
ネット上の誹謗中傷は、民事的な慰謝料等の支払いだけでは済まされず、刑事責任が問われる可能性もあります。
ここでは、ネット上の誹謗中傷によって、実際に起訴された事例を紹介します。
1.大学教授を繰り返し誹謗中傷して書類送検された事例
1つ目の事例は、茨城県警本部の男性警部がSNS上で大学教授の女性を誹謗中傷していたとして、書類送検された事例です。
男性警部は「X(旧Twitter)」にて筑波大学の女性教授に対して、女性教授がテレビ番組に出演した際の画像とともに「見た目からしてバケモノかよ」などと投稿していました。
捜査関係者によると男性は2024年6月18日付けで侮辱容疑で書類送検されています。
その後、水戸簡易裁判所が罰金30万円の略式命令を出しています。
本件は、バケモノなどと事実を摘示することなく誹謗中傷したため、侮辱罪が成立すると判断された事例です。
単なる誹謗中傷でも、実際に侮辱罪で刑罰を受ける可能性はあるため注意してください。
【参考】SNSで教授侮辱の罪 県警の警察官に罰金30万円の略式命令|NHK
2.元自衛官の女性を誹謗中傷して略式起訴された事例
2つ目の事例は、複数の隊員から性被害を受けたと訴えた元陸上自衛官を侮辱したとして、41歳の陸上自衛隊の施設学校所属の幹部自衛官が侮辱罪容疑で略式起訴された事例です。
41歳の男性自衛官は、掲示板のサイトに元自衛官の女性を侮辱する内容の投稿をしたとして罪に問われています。
2023年7月、この男性自衛官は神奈川県警から書類送検され、検察庁が13日侮辱の罪で略式起訴しました。
中傷の内容は明らかになっていませんが、侮辱罪ということは、やはり「事実を摘示することなく」中傷したものであると考えられます。
「事実の摘示があれば名誉毀損」「事実の摘示がなければ侮辱罪」が成立する可能性があります。
実際に警察や自衛官といった公的な立場のある人間が侮辱罪で送検されたり起訴されたりしているため、絶対にネット上には誹謗中傷を書き込まないようにしてください。
【参考】防衛大臣記者会見|防衛庁
ネット上で他人を誹謗中傷してしまった場合の3つの対処法
ネット上で他人を誹謗中傷してしまった場合には、以下の3つの方法で対処することが重要です。
- できる限り早く記事や投稿を削除する
- 被害者に対して誠意をもって謝罪をする
- ネットトラブルが得意な弁護士に相談する
以下では、ネット上で誹謗中傷をしてしまった場合にとるべき対処法について詳しく解説します。
1.できる限り早く記事や投稿を削除する
感情的になり、誹謗中傷と判断されるような投稿をしてしまったら、できる限り早く投稿を削除しましょう。
SNSであれば、投稿した内容は自分ですぐに削除や修正ができます。
一方、掲示板であれば投稿した内容を自分で削除できず、管理者に削除依頼をしなければならないケースもあります。
削除依頼をすることに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、誹謗中傷を長時間公開状態にしておけばおくほど、被害は拡大し、慰謝料を請求されたり、刑事罰に問われたりする可能性は高くなります。
自分で削除しても証拠隠滅に問われる心配はありませんので、できる限り早く削除するか、削除依頼をするようにしてください。
2.被害者に対して誠意をもって謝罪をする
被害者が誹謗中傷を訴えてきたら、誠意をもって謝罪することも重要です。
「つい感情的になって投稿してしまったが、自分が間違っていた。申し訳なかった。以後、このような誹謗中傷は絶対にしない」などと誠意をもって謝罪することによって相手の怒りやショックが和らぐ可能性があります。
ネット上の誹謗中傷については、被害者側が警察に相談したり、開示請求をしたりしない限り、罪に問われたり罰金を課されることはまずありません。
そのため、一時の感情で相手の誹謗中傷する投稿をしてしまっても、すぐに削除して相手に謝罪すれば、相手が被害を訴えたり、慰謝料を請求したりする可能性が低くなります。
間違った投稿をしてしまった場合には、できる限り速やかに削除するとともに、相手に対しては誠意をもって謝罪しましょう。
3.ネットトラブルが得意な弁護士に相談する
相手を誹謗中傷するような投稿をしてしまい、削除や謝罪をしても相手の怒りが収まらない場合には、ネットトラブルを得意としている弁護士へ相談してください。
相手から損害賠償請求や慰謝料請求があった場合に適切な法的対処をおこなってくれますし、早めに示談へ持ち込んでもらうことで刑事告訴を回避できる場合もあります。
刑事告訴になってしまったら、住所や氏名が公表されて、勤務している会社をクビになるほか、家族との関係性が破綻してしまうリスクもあります。
リスクを回避するためにも、相手が被害を訴えてきた場合には、できる限り早くネットの誹謗中傷問題に強い弁護士へ相談しましょう。
なお、ベンナビであれば、ネットに強い弁護士を絞り込んで検索できます。
相談無料の弁護士も多数登録されているので、「どの弁護士へ相談したらよいか分からない」という方は、ベンナビを活用してください。
誹謗中傷加害者が弁護士に相談・依頼する3つのメリット
ネット上で誹謗中傷してしまったときに弁護士へ相談・依頼すると、次の3つのメリットを得られます。
- 匿名掲示板でも記事削除ができる可能性がある
- 被害者からの請求や法的な手続きに対応してもらえる
- 早期に示談を成立させることで刑事告訴などを回避できる
弁護士へ依頼することで、刑事的民事的な責任をできる限り軽減することが可能です。
それぞれのメリットについて、以下で詳しく紹介します。
1.匿名掲示板でも記事削除ができる可能性がある
弁護士へ依頼することによって、匿名掲示板でも記事削除ができる可能性があります。
XやFacebookなどのSNSであれば、自分の投稿は自分で自由に削除や編集ができます。
しかし、匿名掲示板の中には投稿した人が投稿の内容を削除したり編集したりできないものがあります。
このような掲示板へ誹謗中傷の投稿をしてしまった場合には、管理者に対して削除依頼をする必要がありますが、一般の方が削除依頼をおこなっても対応してもらえないか時間がかかるケースがほとんどです。
その点、ネットトラブルに強い弁護士へ依頼すれば、過去の事例などから削除する方法がないかを前向きに検討してもらえるでしょう。
自分で削除できない掲示板や口コミサイトなどへ誹謗中傷を投稿してしまった場合は、弁護士へ相談してください。
2.被害者からの請求や法的な手続きに対応してもらえる
誹謗中傷の被害者から慰謝料請求や損害賠償請求があった場合には、適切に対処する必要があります。
基本的には相手方の弁護士や裁判所とのやり取りになるため、一般の方が自分だけで被害者からの請求対応や法的手続きをおこなうことは困難です。
弁護士へ依頼することによって、これらの対応や手続きを全て任せられます。
適切に対応してもらえることはもちろん、相手や相手方の弁護士とのやりとりも任せあれるため、精神的な負担を軽減できる点もメリットです。
弁護士へ相談すると、示談がよいのか、裁判で戦うのがよいのかを過去の判例や経験などをもとに客観的に判断してもらえるので、心強いでしょう。
3.早期に示談を成立させることで刑事告訴などを回避できる
弁護士へ相談することで、早期に示談を成立させることも可能です。
投稿の内容が明らかに誹謗中傷にあたる場合、裁判で戦っても勝ち目がないことがあります。
その場合、早期に示談による和解を目指すことで、慰謝料や損害賠償などの解決金が低くなるのが一般的です。
また、相手が民事だけでなく刑事でも戦う姿勢を示している場合も、早期に示談を成立させることによって、刑事告訴まで発展しない可能性もあります。
刑事告訴されてしまうと、住所や氏名などが特定され、場合によっては実名で報道される可能性があります。
社会的地位や家庭を失ってしまうリスクがあるため、示談によって刑事告訴を回避できる可能性がある点は非常に大きなメリットです。
示談の交渉や相手が納得できる解決金がいくらなのかを個人で把握するのは困難です。
弁護士へ依頼することで、適切な金額での示談交渉を任せられます。
投稿を削除し、相手に誠心誠意謝罪しても相手が納得しない場合には、早期に弁護士へ相談するのがよいでしょう。
さいごに|ベンナビITで弁護士を探して誹謗中傷について相談しよう
誹謗中傷をしてしまうと、慰謝料や損害賠償の支払いなどの金銭的な負担だけでなく、名誉毀損罪や侮辱罪など、刑事罰を科される可能性もあります。
「匿名だから」と軽い気持ちで、他人や会社を誹謗中傷することはNGであるのは当然です。
しかし、もしも一時の感情で誹謗中傷をしてしまったら、すぐに投稿を削除し、相手に対して誠意をもって謝罪しましょう。
投稿が削除できない場合や相手が法的措置をとってきた場合には、できる限り早期に弁護士へ相談する必要があります。
ベンナビITであれば、ネット上のトラブルや誹謗中傷に強い弁護士が多く登録されています。
「どの弁護士へ相談したら良いかわからない」「ネットトラブルに強い弁護士へ相談したい」「相談料無料の弁護士へ依頼したい」このような場合には、ネット問題に強い弁護士が数多く登録しているベンナビITを活用しましょう。